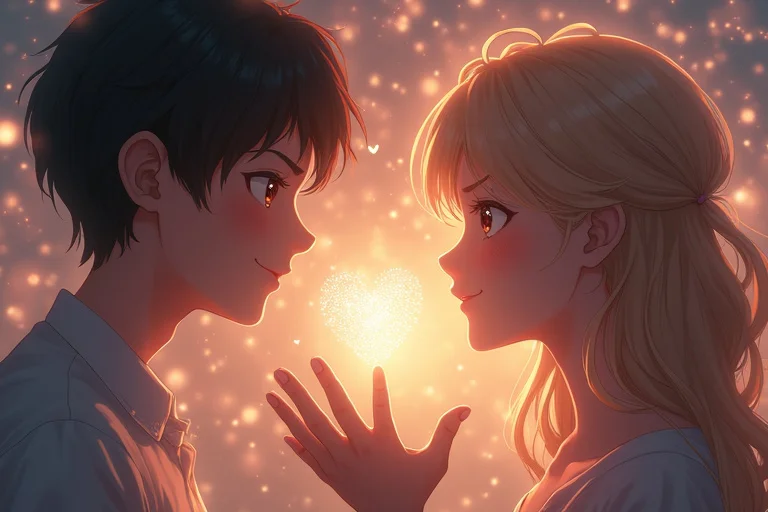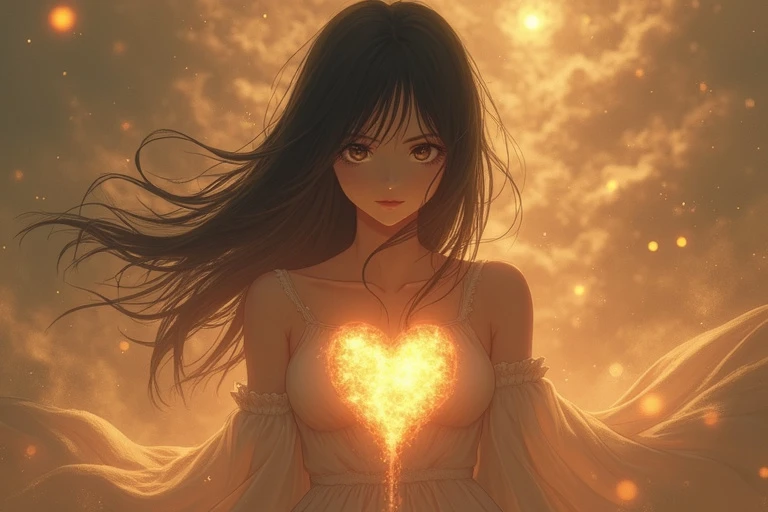第一章 霞みゆく絶望の色
アスファルトに叩きつけられた雨粒が、街灯の光を乱反射している。柏木湊(かしわぎ みなと)は、破れた傘の下で、今日の失敗をフィルムのように繰り返し再生していた。クライアントへの重要なプレゼンテーション。喉の奥に張り付いた言葉、震える指先、そして向けられた失望の視線。胃の底に鉛の塊が沈んでいくような、重苦しい自己嫌悪が湊の全身を支配していた。
「ただいま……」
湿った空気と共にアパートのドアを開けると、そこにはいつもと変わらない光景があった。部屋の明かりは点いていて、ローテーブルの上には温かいマグカップが二つ。そして、ソファに座って古びた文庫本を読んでいた親友の凪(なぎ)が、ゆっくりと顔を上げた。
「おかえり、湊。ひどい雨だったね」
凪の声は、まるで風のない水面のように穏やかだ。彼がここにいることに、湊は少しも驚かない。凪は、湊が物心ついた頃から、こうして当たり前のように隣にいた。
「ああ……最悪だったよ。何もかも」
湊は濡れたジャケットを脱ぎ捨て、凪の向かいにどさりと腰を下ろした。堰を切ったように、言葉が溢れ出す。準備不足だったこと、緊張で頭が真っ白になったこと、上司に厳しく叱責されたこと。情けない自分の姿を、洗いざらい吐き出した。凪はただ黙って、相槌を打つでもなく、否定するでもなく、静かに聞いていた。彼の深い夜色の瞳が、じっと湊を見つめている。
不思議なことだった。凪に話していると、あれほど鮮明だった絶望の記憶が、徐々に輪郭を失っていくのだ。クライアントの冷たい視線はぼやけ、上司の怒声は遠い場所で鳴る響きのように変わる。胃の底の鉛は溶け、代わりに温かいものがじんわりと広がっていく。
「……まあ、そんな感じだったんだ」
話し終える頃には、湊の心は驚くほど軽くなっていた。まるで、心の澱をすべて凪が吸い取ってくれたかのように。これが、湊がずっと頼ってきた、凪の持つ不思議な力だった。
「そっか。大変だったんだな」
凪はそう言って、ふわりと微笑んだ。その笑顔を見ると、もうすべてがどうでもよくなる。
だが、その時だった。湊は見てしまった。微笑む凪の体の向こう側、壁に掛けられた時計の文字盤が、一瞬、透けて見えたのだ。まるで陽炎のように、凪の輪郭が揺らめいている。
「……凪? 今、なんか……」
「ん? どうかした?」
凪は首を傾げる。彼の体はもう元に戻っていた。見間違いだったのかもしれない。しかし、最近、こんなことが頻繁に起きている気がした。湊の胸に、これまで感じたことのない、冷たい不安の染みがじわりと広がった。
第二章 約束のない共生
湊と凪の出会いは、記憶の海の底、少年時代の雨の日に遡る。公園の滑り台の下で、いじめられた痣を抱えて泣いていた湊の前に、凪は現れた。傘もささずに、まるで最初からそこにいたかのように、凪は立っていた。
「どうして泣いてるの?」
凪はそう尋ねた。初対面のはずなのに、湊は警戒心も抱かず、今日あった辛い出来事を泣きじゃくりながら話した。凪はあの夜と同じように、ただ静かに聞いていた。そして、湊の涙が枯れる頃、ぽつりと言った。
「そっか。それは、痛かったね」
翌朝、湊が目を覚ますと、体の痣は残っていたが、心の痛みだけが綺麗に消え去っていた。いじめっ子たちの顔も、投げつけられた言葉も、靄がかかったように思い出せない。まるで、悪い夢から覚めた後のように。その日から、凪は湊の「親友」になった。
湊にとって凪は、人生のセーフティネットだった。大学受験に失敗した夜、初めて恋人に振られた夜、そして社会に出て味わった数々の挫折の夜。湊はいつも凪にすがり、心のゴミを吐き出した。凪はそれを黙って受け止め、湊の記憶から「痛み」だけを消してくれた。凪のおかげで、湊は何度も立ち直ることができた。
しかし、湊は凪について何一つ知らなかった。彼に家族はいるのか、どこから来たのか、どうやって生活しているのか。尋ねても、凪はいつも曖昧に笑って誤魔化すだけだった。凪の存在は、湊の日常にあまりにも深く溶け込み、その正体を問うこと自体が野暮な気がしていた。二人の間には、言葉にならない共生の形があった。湊は凪に心の安寧を求め、凪はただそこにいる。それだけで、十分だった。
凪の体が透ける現象は、日を追うごとに頻度と時間を増していった。本を持つ指先が透け、マグカップを呷る唇が透ける。湊が不安を口にしても、凪は「ちょっと疲れてるだけだよ」と力なく笑うばかりだった。
湊は初めて、凪に対して恐怖に近い感情を抱いた。この穏やかな共生が、何か決定的な過ちの上に成り立っているのではないか。自分が知らない、知ってはいけない秘密が、この親友の存在そのものを蝕んでいるのではないか。凪の輪郭が薄れるたびに、湊自身の足元までが崩れていくような、途方もない喪失感の予兆が彼を襲った。
第三章 捕食者の告白
その夜、湊は悪夢で目を覚ました。アパートに帰ると、部屋が空っぽになっている夢。凪の痕跡が何一つ残っていない、冷たい無人の空間。心臓が氷水で満たされたような冷たさを感じながらリビングへ向かうと、ソファの隅で小さな影がうずくまっていた。
「凪!」
駆け寄ると、そこにいたのはほとんど消えかかった凪だった。彼の体は青白い光を放ちながら、激しく明滅している。その姿は、まるで燃え尽きる寸前の蝋燭の炎のようだった。
「どうしたんだ、凪! しっかりしろ!」
湊が肩を揺さぶると、凪は苦しげに顔を上げた。その瞳は虚ろで、焦点が合っていない。
「……みなと……お腹が、すいた……」
「腹が? 何を言ってるんだ! 救急車を……」
「だめだ……意味がない……」
凪はか細い声で湊を制し、ゆっくりと言葉を紡いだ。それは、湊が長年見て見ぬふりをしてきた、残酷な真実の告白だった。
「僕はね、湊。人の記憶を糧にして生きているんだ」
時が止まった。窓の外で降りしきる雨音だけが、やけに大きく聞こえる。
「悲しい記憶、辛い記憶、忘れたい記憶……そういう、強い負の感情がこもった記憶が、僕の『食事』なんだ。君が僕に話してくれた辛い出来事は、僕にとってはご馳走だった。君の記憶を食べることで、僕はこうして存在できている」
湊は言葉を失った。癒やしの力だと思っていたものは、単なる捕食行為だったというのか。凪が食べていたのは、湊の記憶であり、湊の心そのものだった。
「じゃあ、今……消えかかってるのは……」
「うん。最近の君は、幸せそうだったから」
凪は寂しそうに微笑んだ。
「仕事も順調で、大きな悩みもなかった。僕にとっては……長い飢餓状態だったんだ。今日のプレゼンの失敗は、久しぶりの食事だったけど……もう、僕の存在を繋ぎ止めるには、足りなかったみたいだ」
衝撃が湊の全身を貫いた。友情だと思っていたものは、捕食者と被食者の関係だった? 凪にとって、湊の不幸は生きるための糧でしかなかった? 凪は、湊が苦しむのを待っていたというのか?
「僕の……不幸が、君のご馳走……?」
湊の声は震えていた。長年の信頼が、足元からガラガラと崩れ落ちていく。凪は、湊の混乱を見透かしたように、静かに続けた。
「ごめん。ずっと黙っていて。でも、君と一緒にいる時間は、本当に楽しかった。それは本当だよ。ただ……君の痛みを食べるたびに、僕も苦しかった。友人の不幸を喜びながら生きるなんて、本当は……もう、嫌だったんだ」
凪の瞳から、光る雫が一つ、こぼれ落ちた。それは涙なのか、それとも彼の存在が霧散していく粒子なのか、湊には分からなかった。
罪悪感と裏切られたという思いが、湊の中で渦を巻く。自分は凪に依存し、彼を利用してきた。同時に、凪もまた、自分を利用していた。歪で、しかし確かに存在した二人の友情が、今、その本当の姿を現して、湊に残酷な選択を突きつけていた。
第四章 君を忘れないために
湊の頭の中を、一つの記憶がよぎった。誰にも話したことのない、凪にさえも与えることを拒んできた、心の最も深い場所に封印した記憶。それは、幼い頃に飼っていた犬、コタロウの記憶だった。
湊の不注意で、玄関のドアが少しだけ開いていたあの日。コタロウは外に飛び出し、車に轢かれて死んだ。自分のせいだという罪悪感が、鉛のようにずっと湊の心にこびりついている。それは湊の人生で最も辛く、そして最も消したくない記憶だった。コタロウを忘れてしまうことは、彼を二度殺すことのように思えたから。
「……僕に、食べさせてくれないか」
消え入りそうな声で、凪が言った。
「君がずっと、心の奥に隠している記憶。それがきっと、一番『美味しい』はずだ。それをくれたら、僕はもう少しだけ、ここにいられる」
凪を生かすためには、コタロウの記憶を差し出すしかない。だが、それをすれば、湊の中からコタロウの存在証明そのものが消えてしまうかもしれない。湊は激しく葛藤した。凪を失いたくない。でも、コタロウを忘れたくない。
湊は、明滅する凪の姿を見つめた。友人の不幸を喜びたくなかったと、彼は言った。それは、紛れもなく友情だったのではないか。歪な形であっても、凪は自分を友として見てくれていたのではないか。
「……話すよ」
湊は覚悟を決めた。ソファに座り、凪を膝に乗せる。驚くほど軽くなった親友の体を抱きしめながら、湊はゆっくりと語り始めた。コタTロウとの出会い、共に過ごした日々、そして、あの最後の日。雨の中、動かなくなった小さな体を抱きしめた時の感触。涙が後から後から溢れ、言葉が何度も途切れる。
凪は静かに、その記憶を味わっていた。湊の涙が彼の頬を濡らす。湊の中から、長年彼を縛り付けてきた罪悪感と、胸を抉るような悲しみが、ゆっくりと凪の中へ吸い取られていくのを感じた。
やがて湊がすべてを語り終えた時、凪の体は確かな輪郭を取り戻し、温かい光を放っていた。
「……ありがとう、湊。すごく、温かい味がした」
凪は湊の膝から降りると、しっかりとした足取りで立ち上がった。そして、悲しいほど優しい笑顔で言った。
「でも、もう行かなくちゃ。君はもう、僕がいなくても大丈夫だ」
「待ってくれ!」
湊は凪の腕を掴もうとしたが、その手は空を切った。
「君は、一番辛い記憶と向き合えた。それを手放すことができた。これからは、僕に頼らなくても、自分の足でちゃんと歩いていける」
「嫌だ! 行かないでくれ、凪!」
湊の叫びも虚しく、凪の体は光の粒子となって、ゆっくりと宙に溶け始めた。
「忘れないで、湊。君が僕にくれたものも、僕が君から貰ったものも、全部が僕たちの友情だったんだ」
湊は、凪に頼り、嫌な記憶から目を背け、彼を縛り付けてきた自分を悟った。もう、彼を利用することはできない。湊は初めて、凪のために「忘れる」のではなく、「覚えておく」ことを選んだ。
「忘れないよ、凪! 君のことも、君が食べてくれた記憶のことも、全部!」
その言葉を聞いて、凪は満足そうに微笑んだ。そして、完全に光となって消えた。
部屋に静寂が戻る。湊は呆然と立ち尽くしていたが、やがて気づいた。コタロウを失った悲しみは和らいでいる。だが、彼との楽しかった記憶は、少しも色褪せることなく、鮮やかに胸に残っている。凪が食べてくれたのは、記憶そのものではなく、それにまとわりついていた「痛み」や「罪悪感」という棘の部分だけだったのだ。
友情とは、忘却ではない。共有だ。辛い記憶も、楽しい記憶も、すべてを抱きしめ、共に背負い、乗り越えていくこと。凪は、その最後の食事で、湊に最も大切なことを教えてくれた。
湊は窓を開けた。雨はすっかり上がり、東の空が白み始めている。新しい朝の光が、凪のいなくなった部屋を、そして湊の新しい人生を、静かに照らし始めていた。