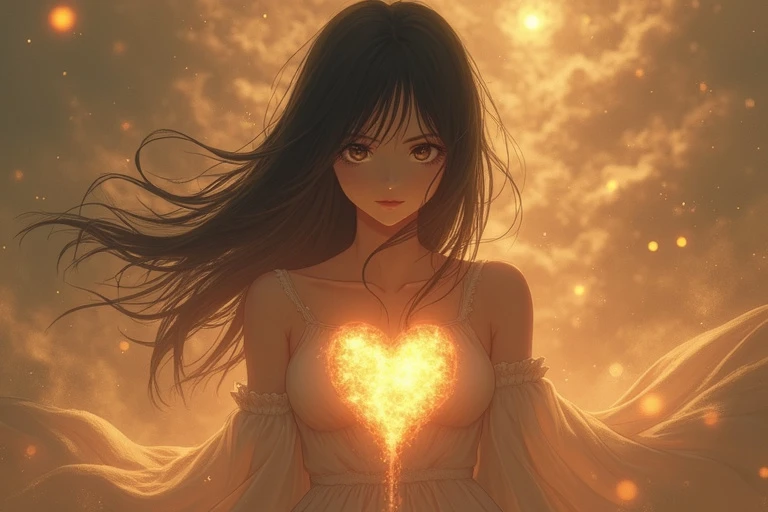第一章 邂逅と錆びたシャッター
潮の香りが、肺の奥まで満たしていく。海辺の街に暮らす僕、桐島カイトにとって、防波堤に座って水平線を眺める時間は、唯一の平穏だった。空っぽのキャンバスを前にした時のような、漠然とした不安から逃れられる唯一の聖域。十七歳の僕の未来は、沖合にかかる海霧のように不確かで、掴みどころがなかった。
その日も、僕は錆びた手すりに背を預け、スケッチブックを開くでもなく、ただ時間をやり過ごしていた。そんな僕の隣に、いつからか一人の男が座っていた。歳の頃は三十代半ばだろうか。着古したネイビーのコートを羽織り、その手には年季の入ったフィルムカメラが握られていた。
「いい光だね」
男は独り言のように呟いた。その声は、低く、落ち着いていて、不思議と耳に馴染んだ。
「……はあ」
僕は曖昧に相槌を打つ。知らない人間に話しかけられるのは苦手だった。男は気にした様子もなく、カシャリ、と乾いたシャッター音を立てた。その音は、僕の心のささくれを優しく撫でるようだった。
「君は、撮らないのかい?」男は僕の足元に置かれたままの、父親から譲り受けた古い一眼レフに目をやった。「いいカメラなのに」
「撮りたいものなんて、別にないんで」
嘘だった。撮りたいものは、描きたいものは、溢れるほどあった。だが、それを形にする才能が自分にあるとは思えなかった。自信のなさが、僕の指をシャッターから遠ざけていた。
男は僕の嘘を見透かしたように、ふっと笑った。その笑い方を知っているような気がして、僕は奇妙な既視感に襲われた。
「そうか。じゃあ、これを貸してあげよう」
男は自分の首から下げていたフィルムカメラを、僕の膝の上にそっと置いた。ずしりと重い金属の感触。使い込まれて角の丸くなったボディが、持ち主の時間を物語っている。
「僕には見えない、君にしか見えないものが、きっとある。それを探してみて」
男はアキと名乗った。それから僕たちは、週に二、三度、この場所で会うようになった。アキさんはいつも僕の話を静かに聞き、僕が撮った拙い写真を、まるで至高の芸術品のように褒めてくれた。彼との出会いが、僕の灰色だった日常を、少しずつ色鮮やかなものに変えていく。僕はまだ、この不思議な友情が、僕自身の時空をも歪める、巨大な渦の中心にあることなど知る由もなかった。
第二章 セピア色の共犯者
アキさんとの時間は、まるで古びた映画のワンシーンのようだった。彼は僕が決して言葉にしない心の澱を、的確に掬い上げてくれた。
「この写真、いいね。光と影の境界線に、君の迷いが写ってる。でも、その奥に強い光を探そうとしてる意志も見える」
現像されたばかりのモノクロ写真を指差しながら、アキさんは言った。それは僕が、美術室の隅で描きかけのキャンバスを前に、筆を持てずにいた日の午後に撮った一枚だった。誰にも話していない僕の葛藤を、アキさんは一枚の写真から読み解いてみせた。
「どうして、わかるんですか……?」
「わかるさ。僕も、君と同じくらいの歳の頃、よくそうやって悩んでいたから」
アキさんは遠い目をして海を眺めた。その横顔には、僕が知らないはずの深い哀愁が刻まれている。僕は彼に、自分の描いた絵を初めて見せた。誰にも見せたことのない、僕だけの世界。震える手で差し出したスケッチブックを、アキさんは宝物のように丁寧にめくった。
「……すごいな、カイト君。君の絵には、魂がある。この色彩、この筆致……僕がずっと前に、失くしてしまったものだ」
彼の瞳が、わずかに潤んでいるように見えた。その言葉は、どんな賞賛よりも僕の心を強く打ち、固く閉ざしていた創作意欲の扉をこじ開けた。僕は夢中でシャッターを切り、無心で絵筆を走らせた。アキさんという唯一の理解者を得て、僕の世界は急速に輪郭を帯びていった。彼のような、静かで、優しく、物事の本質を見抜く力を持った大人になりたい。アキさんは僕にとって、ただの友人ではなく、憧れであり、未来の道標そのものだった。
しかし、友情が深まるにつれて、小さな違和感が僕の中で芽生え始めていた。アキさんは、僕の家族構成や、僕が幼い頃に好きだった絵本のタイトルまで、まるで自分のことのように知っていた。僕が話したことのない、僕だけの記憶の断片を、彼はなぜか共有していた。
「不思議なこともあるもんだね」
僕がそう尋ねるたび、アキさんは決まって寂しそうに笑い、話題を変えるのだった。その笑顔の裏に隠された真実を、僕はまだ恐ろしくて覗き込むことができなかった。僕たちはまるで、セピア色の写真の中に閉じ込められた、秘密を共有する共犯者のようだった。
第三章 未来からの来訪者
その日は、冷たい雨が降っていた。アキさんから「見せたいものがある」と誘われ、僕は初めて彼の住むアパートを訪れた。古い木造アパートの二階、突き当たりの部屋。軋むドアを開けると、インクと古い紙の匂いが僕を包んだ。
部屋は、僕の記憶で埋め尽くされていた。
壁一面に飾られていたのは、僕がこの数ヶ月で撮り溜めた写真たち。夕暮れの防波堤、雨に濡れた紫陽花、教室の窓から見えた飛行機雲。そして、その中に混じって、見覚えのあるものがいくつもあった。小学生の僕がコンクールで入選した海の絵。中学生の時に家族旅行で撮った、ぎこちなく笑う僕の写真。どれも僕の実家にあるはずのものだ。
心臓が氷の塊になったように冷えていく。混乱する僕の視線は、部屋の奥のイーゼルに釘付けになった。そこに置かれていたのは、一枚の未完成の油絵。海辺の公園で、年老いた男が若い少年にカメラを渡している情景。それは、僕とアキさんの出会いの場面そのものだった。だが、僕はこの絵を描いた覚えなど、まったくない。
「……どういう、ことですか、アキさん。これは、一体……」
声が震える。アキさんは、僕の向かいの椅子に静かに腰を下ろし、ゆっくりと口を開いた。その表情は、今まで見たことのないほどに痛々しく、そして穏やかだった。
「驚かせてすまない。……カイト君、いや、カイト。僕はね、未来から来たんだ」
時が止まった。雨音が遠のいていく。
「僕は、君だよ。四十二歳になった、君自身なんだ」
理解が追いつかない。目の前の男が、僕だと? 憧れていたこの人が、未来の僕?
「僕は……夢を、諦めたんだ」アキ、いや、未来の僕の声は、懺悔のように響いた。「二十代の終わりに、大きなコンクールで落選して、心が折れてしまった。絵を描くことをやめ、カメラも手放し、ごく普通の、魂の抜けたような大人になった。毎日、後悔だけを抱えて生きてきた。あの時、もっと自分を信じていれば。あの時、背中を押してくれる誰かがいれば、と」
彼は、僕の目をまっすぐに見つめた。その瞳の奥に揺らめくのは、僕がずっと目を背けてきた、僕自身の弱さだった。
「だから、来たんだ。人生を懸けた最後の賭けとして、未完成のタイムマシンで過去へ飛んだ。僕がなれなかった自分に、君を導くために。僕にとっての、たった一人の希望である君を、救うために」
頭を鈍器で殴られたような衝撃。友情だと思っていたものは、未来の自分からの憐憫だったのか? 憧れの対象は、夢に破れた無様な自分の成れの果てだったのか? 裏切られたような、愚弄されたような感情が、感謝や驚きを遥かに凌駕して、僕の心を黒く塗りつぶしていく。
「ふざけるな!」
僕は叫んでいた。膝に置かれたアキさんのカメラを床に叩きつけ、部屋を飛び出した。雨の中を、僕はあてもなく走り続けた。信じていた世界が、足元から崩れ落ちていく音が聞こえた。
第四章 時を超えた友情
何日も、僕は部屋に閉じこもった。絵筆も、カメラも、見るのも嫌だった。アキこと未来の僕の言葉が、呪いのように頭の中で反響する。憧れは失望に変わり、友情は自己欺瞞に思えた。
だが、嵐のような感情が過ぎ去った後、静かな夜の闇の中で、僕は別の声を聞いた。それは、アキさんが僕の写真や絵を褒めてくれた時の、心からの喜びが滲んだ声だった。彼が僕の才能を語る時、その瞳は確かに輝いていた。あれは、憐憫や同情などではなかった。
あれは、未来の自分が、過去の自分に託した、紛れもない「希望」の光だったのではないか。彼は、僕を救うと言った。それは、僕自身を救うことでもあったのだ。友情が偽物だったわけじゃない。むしろ、これ以上に純粋で、切実な友情があるだろうか。自分自身を「友人」として、時を超えてまで支えようとする、究極の自己愛。
僕は、壊れたカメラを拾い集め、あのアパートへ向かった。ドアは開いていた。部屋はがらんどうで、壁の写真も、イーゼルの絵も、すべて消えていた。まるで、初めから何もなかったかのように。
ベランダに出ると、雨上がりの澄んだ空の下、アキさんが立っていた。その手には、小さなスーツケースが一つ。
「……来てくれたんだな」
彼は穏やかに微笑んだ。その顔には、もうあの深い哀愁はなかった。
「僕の役目は、もう終わった。君はもう、僕がいなくても大丈夫だ。君は、僕とは違う未来を歩む」
僕は何も言えず、ただ頷いた。アキさんは僕に歩み寄り、ポケットから何かを取り出した。それは、僕が床に叩きつけたカメラの、レンズだった。傷一つついていない。
「これは、元々君のものだ。大切にな」
彼はレンズを僕の手に握らせた。その手の温もりが、僕の心の凍てついた部分をゆっくりと溶かしていく。
「ありがとう、カイト」アキさんは言った。「僕の、たった一人の、最高の友人」
その言葉を最後に、彼の身体が徐々に透き通っていく。光の粒子となって、夜明け前の空気に溶けていくように、アキさんは静かに消えた。僕の頬を、一筋の涙が伝った。
それから十年。僕は、画家として生きていた。傍らにはいつも、あの古いフィルムカメラがある。時々、僕はあの海辺の公園を訪れる。もちろん、そこにアキさんの姿はない。でも、僕は知っている。僕の中には、最高の友人が生き続けていることを。未来の僕が救おうとした過去の僕は、今、未来の僕を支えている。僕たちは、時を超えた友情で、固く結ばれているのだ。
僕はファインダーを覗き、昇り始めた太陽にレンズを向ける。カシャリ、と乾いたシャッター音が響く。それは、未来の自分に宛てた、感謝と決意の手紙。僕がこれから紡いでいく、新しい物語の、始まりの合図だった。