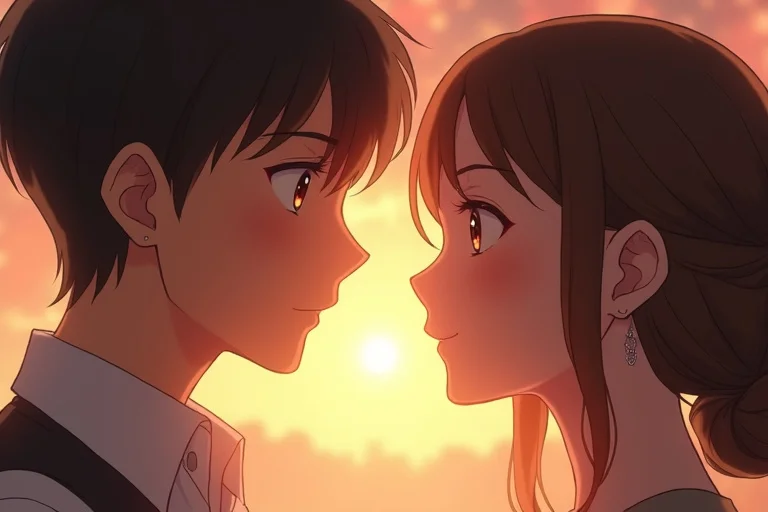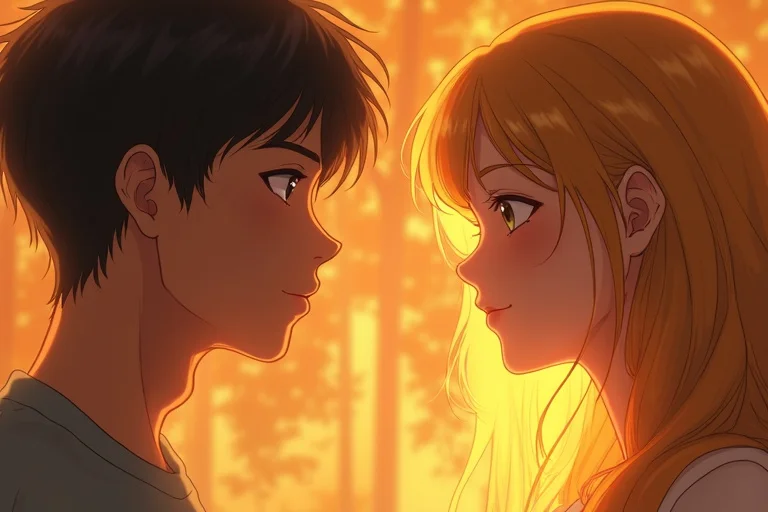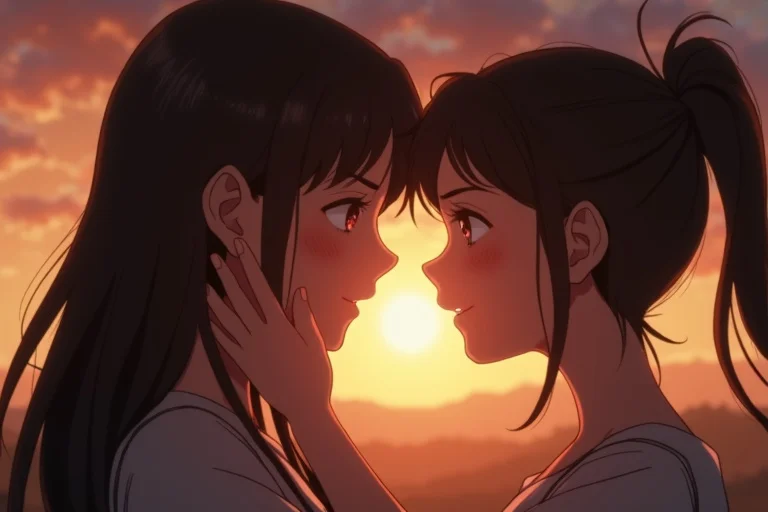第一章 琥珀色の記憶
神保町の片隅に佇む古書店「時雨堂」。その棚に挟まれ、水野蒼(みずの あおい)は息を潜めるようにして生きていた。彼には秘密があった。幼い頃から、物に触れると、その最後の所有者が抱いた強烈な感情が流れ込んでくるのだ。しかし、不思議なことに、彼が感じ取れるのは「愛」という感情だけだった。喜びも、悲しみも、怒りも、彼の感覚を通り抜けていく。ただ、ひたむきで、温かく、時に切ない「愛」の記憶だけが、彼の内に流れ込んでは消えていった。
それは呪いであり、祝福でもあった。他人の幸福な記憶は、彼の孤独な心を慰めてくれる。しかし、あまりに純粋で美しい愛の記憶に触れすぎたせいで、蒼は現実の不器用な人間関係や、自身の淡い恋心さえも、色褪せた模造品のように感じてしまうようになっていた。
その日、店に持ち込まれたのは、銀製の古びた懐中時計だった。埃を払い、そっと手のひらに乗せた瞬間、蒼は息を呑んだ。
経験したことのない、圧倒的な奔流。
それは、一人の男性が、ある女性へ捧げ続けた、何十年にもわたる愛の記憶だった。春の陽光の中で微笑む彼女の姿。夏の夜、線香花火を共に見つめる静かな時間。秋風に舞う落ち葉を踏みしめながら歩いた並木道。冬の朝、冷えた彼女の手にそっと息を吹きかける温もり。そのすべてが、琥珀色の光に包まれた映像となって、蒼の脳裏に焼き付いた。それは情熱というより、もっと深く、静かで、揺るぎない献身。蒼は、その名も知らぬ愛の物語に完全に心を奪われた。時計の裏蓋には、流麗な筆記体で『S.T.へ A.M.より』とだけ刻まれている。
「この愛は、本物だ」
蒼は呟いた。他人の記憶に過ぎないと分かっていながら、その琥珀色の愛は、彼の空虚な心の中で、一つの確固たる理想となった。そして彼は、この「真実の愛」の持ち主を探し出したいという、抑えきれない衝動に駆られたのだった。
第二章 イニシャルの迷路
懐中時計の謎を追う日々が始まった。蒼は仕事の合間を縫って、時計の製造年代や刻印のスタイルから、持ち主の情報を探ろうとしたが、手がかりはあまりに少ない。そんな彼の姿を、静かに見つめる一人の女性がいた。
月島詩織(つきしま しおり)。
時雨堂の常連客で、いつも静かに哲学や詩集の棚を眺めている、どこか儚げな女性だった。彼女は、蒼がカウンターで熱心に古い時計を調べているのに気づき、声をかけた。
「何か、お探しですか?」
彼女の声は、澄んだ湧き水のように蒼の耳に届いた。蒼は戸惑いながらも、懐中時計のこと、そしてそこに宿る美しい愛の記憶について、夢中になって話してしまった。突拍子もない話だ。信じてもらえるはずがない。だが、詩織は眉一つ動かさず、真剣な眼差しで彼の言葉に耳を傾けていた。
「素敵な話ですね。そのイニシャル、何かヒントになるかもしれません。私にも、少しお手伝いさせていただけませんか」
その日から、二人の奇妙な共同調査が始まった。図書館で古い名簿をめくり、昔ながらの時計店を訪ね歩いた。詩織は驚くほど勘が鋭く、蒼が思いつきもしなかったような視点から、次々と調査の糸口を見つけ出した。
古書のインクの匂いが満ちる静かな空間で、二人は少しずつ言葉を交わすようになった。詩織がなぜいつもこの店に来るのか。蒼がなぜ古書に囲まれて生きることを選んだのか。互いの輪郭が、ゆっくりと形を結んでいく。蒼は、詩織といる時の穏やかな心地よさに、戸惑いを覚えていた。彼女に触れたい、もっと知りたいという気持ちが芽生える。だがその度に、あの懐中時計の完璧な愛の記憶が、彼の行く手を阻んだ。
(俺のこの気持ちは、あの琥珀色の愛に比べれば、なんてちっぽけで、不確かで、みすぼらしいんだろう)
詩織の指先が、偶然、資料を指し示す蒼の手に触れた。その瞬間、蒼は何も感じなかった。愛の記憶は、流れ込んでこない。その事実が、彼を安堵させると同時に、深く傷つけた。彼女は、自分に何の愛情も抱いていないのだ。その思い込みが、二人の間に見えない壁を作っていた。
第三章 時の環、愛の環
調査は難航を極めた。諦めかけたある日、詩織が古い写真館の顧客名簿のマイクロフィルムから、決定的な情報を見つけ出した。昭和三十年代、とある記念写真の顧客欄に、こう記されていたのだ。
『撮影依頼主:水野 蒼(みずの あきら)。贈答品(懐中時計)の記念撮影。受取人:月島 聡子(つきしま さとこ)様』
「水野……蒼?」
蒼は自分の名前と同じ響きに凍り付いた。まさか。震える手で、実家のアルバムを保管している箱を開ける。そこにいたのは、若き日の祖父と祖母。写真の中の祖父は、蒼と驚くほど面影が似ていた。そして、その隣で優しく微笑む祖母の名前は、確かに聡子だった。
『S.T.へ A.M.より』——Satoko Tsukishimaへ、Akira Mizunoより。
彼が追い求めていた「真実の愛」は、彼自身の祖父母の物語だったのだ。全身の血が逆流するような衝撃。彼は理想化し、追い求めていたものが、自らの血肉を分けたルーツそのものであったという事実に、立ち尽くすしかなかった。
混乱する頭で、蒼は祖父が遺した書斎の奥深く、開かずの引き出しに手をかけた。そこには、一冊の古びた日記帳が眠っていた。ページをめくると、そこには懐中時計にまつわる物語と、蒼を根底から揺るがす衝撃的な真実が記されていた。
『——私には、生まれつき奇妙な力がある。触れた物から、持ち主の「愛」の記憶だけを読み取ってしまうのだ。この力は、私を孤独にした。だが、聡子と出会い、全てが変わった。私は彼女を愛した。しかし、聡子もまた、私と同じように特異な感受性を持っていた。彼女は、人の強い感情をノイズのように感じ取り、苦しんでいた。私が愛を伝えようとすればするほど、彼女はその強すぎる感情の波に疲弊してしまうのだ。
だから、私は決めた。言葉や直接的な接触で愛を示すのではなく、この懐中時計に、私の愛を、記憶を、少しずつ込めていくことにした。聡子がこの時計に触れるたび、私の愛が、穏やかな記憶として、ゆっくりと彼女に伝わるように。これは、私たち二人だけの、沈黙の愛の対話なのだ——』
蒼は日記を閉じた。祖父も、自分と同じ能力者だった。そして、彼が焦がれた琥珀色の愛は、愛する人を苦しめないために編み出された、究極に優しく、そして切ない愛の形だったのだ。
第四章 沈黙と告白
蒼は、懐中時計と祖父の日記を手に、詩織の元へ向かった。時雨堂の、いつもの席。窓から差し込む午後の光が、舞い上がる埃をきらきらと照らしている。彼は、全てを話した。自分の能力のこと。祖父母の物語のこと。そして、彼女の手に触れても何も感じなかった時の、絶望感を。
話を聞き終えた詩織は、静かに目を伏せた。そして、ゆっくりと顔を上げると、初めて自分のことを語り始めた。
「私も、普通じゃないんです。人の感情が、特に強いものが、うるさい音や、不快な光のように感じられてしまう。だから、人が多い場所が苦手で……いつも静かなこのお店に逃げてきていました」
彼女は蒼を真っ直ぐに見つめた。その瞳は、わずかに潤んでいる。
「あなたの周りだけは、不思議なくらい静かだった。うるさい感情のノイズが、全くしなかった。それが、どうしてなのか、ずっと分からなかった。でも、今、分かりました。あなたは……愛以外の感情を感じないから。あなたの世界は、私が探し求めていた静寂に満ちていたから……」
そして、彼女はこう続けた。
「あなたの手に触れても、あなたが何も感じなかったのは、私があなたに愛情を抱いていないからじゃない。逆です。あなたへの気持ちが強くなりすぎて、どう伝えたらあなたを傷つけずに済むのか、分からなかったから。祖父と祖母がそうであったように、私もあなたにどう触れたらいいのか、臆病になっていただけなんです」
沈黙が落ちる。しかし、それはもはや壁ではなかった。互いの特異性を受け入れ、理解し合った二人の間には、温かく、優しい沈黙が流れていた。
蒼は、そっと詩織の手に自分の手を重ねた。今度は、何も感じ取ろうとしなかった。ただ、目の前にいる女性の、その手の温もりだけを感じようと努めた。
懐中時計の琥ax色の記憶は、確かに美しい。だがそれは、過去の物語。これからは、自分自身の物語を始めなければならない。不器用で、不確かで、ちっぽけかもしれないけれど、詩織と共に、自分たちだけの色をした愛の記憶を、一つひとつ、この手で紡いでいくのだ。
蒼は懐中時計をポケットにしまい、詩織の手を引いた。古書店の扉を開けると、柔らかな陽光が二人を包み込む。カチ、カチ、とポケットの中で時を刻む時計の音が、まるで未来への序曲のように、蒼の心に静かに響いていた。