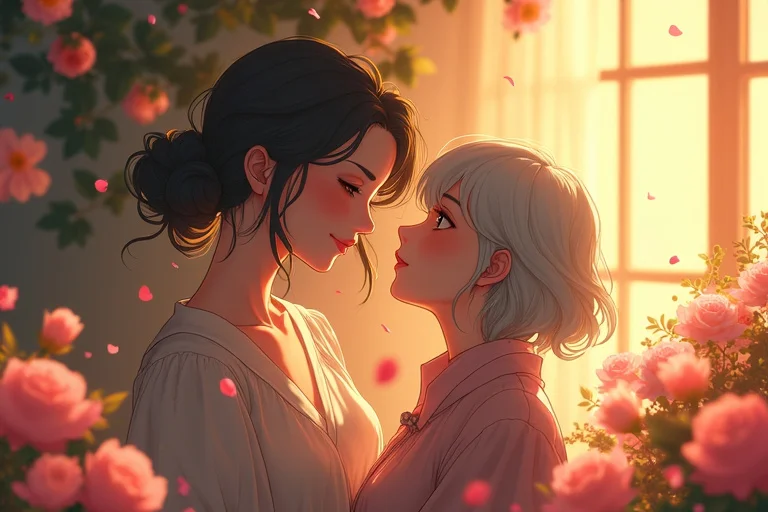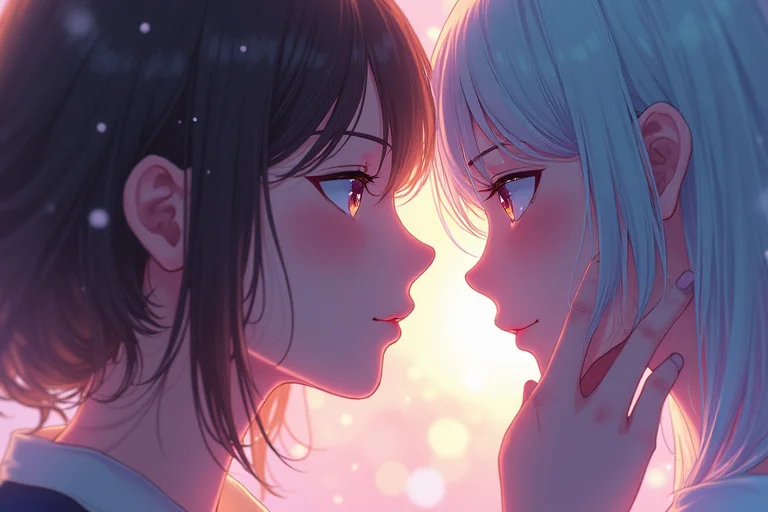第一章 偽りのプレリュード
坂井律(さかい りつ)の世界は、不協和音に満ちていた。調律師である彼にとって、それは職業的な比喩などではない。幼い頃から、彼は他人の「嘘」を、頭の中で鳴り響く「音楽」として知覚してしまう特異な体質を持っていた。
スーパーの店員が口にする「お似合いですよ」というお世辞は、調子の外れたリコーダーのようだし、取引先の言い訳がましい「鋭意努力します」は、弦の切れたチェロの軋みとなって鼓膜を掻きむしる。悪意が強ければ強いほど、その音楽は耳を覆いたくなるほどの不協和音となった。おかげで律は、いつしか人を信じることをやめ、必要最低限の会話しか交わさない、孤独で静かな調律師になっていた。彼の唯一の安らぎは、自らが完璧に調律したピアノが奏でる、純粋で嘘のない音色だけだった。
そんな灰色の日々に、予期せぬ変奏曲が割り込んできたのは、初夏の午後のことだった。仕事で使うホールの打ち合わせが思いのほか早く終わり、駅までの道を歩いていると、ふと、色鮮やかな店構えが目に留まった。路地裏にひっそりと佇む、小さな花屋。ガラス窓の向こうで、一人の女性がスプレーボトルで紫陽花に霧を吹いていた。陽光を浴びてきらめく水滴と、彼女の柔らかな横顔に、なぜか足が吸い寄せられた。
「いらっしゃいませ」
カラン、とドアベルが鳴ると、彼女は顔を上げた。藤代葵(ふじしろ あおい)と名札にある。色素の薄い瞳が、少し驚いたように律を捉えた。店内に満ちる、甘く湿った土と花の香りに、律は少しだけ眩暈を覚えた。
「何か、お探しですか?」
「いえ……特に。ただ、綺麗だったので」
言葉を探しながら店内を見回す律に、葵はにこりと微笑んだ。その笑顔は、まるでひまわりのように屈託がない。律は、窓際に置かれた小さなサボテンに目を留めた。
「これ、ください」
「あら、良い趣味ですね。この子、とっても丈夫なんですよ。それに、見てください」
葵はそう言うと、サボテンのてっぺんを指差した。「昨日、ちょうどピンクの可愛い花が咲いたんです。ラッキーでしたね、お客さま」
その瞬間だった。
律の頭の中に、音が流れ込んできた。それは、いつもの耳障りな不協和音ではなかった。澄み切ったハープのアルペジオ。静かな森の泉に、一滴の雫が落ちたかのような、清らかで優しい旋律。
律は思わず息をのんだ。サボテンの花は、よく見れば布でできた精巧な造花だ。彼女は、客を喜ばせるための、ささやかな嘘をついたのだ。
だが、その嘘から生まれた音楽は、律がこれまでの人生で聴いたどんな嘘の音とも違っていた。それは、人を傷つけず、むしろ温かい気持ちにさせるための、美しい偽り。
「……ありがとうございます」
律は、かすかに震える声で礼を言った。会計を済ませ、店を出る。腕に抱えた小さなサボテンと、まだ頭の中でリフレインするハープの音色。彼のモノクロームの世界に、確かな色が灯った瞬間だった。
第二章 重なり合うカノン
あの日以来、律は吸い寄せられるように葵の花屋に通うようになった。理由をつけては小さな花束や観葉植物を買い求め、彼女と短い言葉を交わす。そのたびに、彼の世界は美しい音楽で満たされた。
「このバラ、今朝、私が一番綺麗だと思うものを選んできたんです」
――その言葉と共に、軽やかなフルートのメロディーが流れる。本当は昨日仕入れたものだろう。
「すみません、お釣りの百円玉が切れちゃって。十円玉ばかりでいいですか?」
――おどけたようなピッコロのトリルが響く。財布の中には百円玉が見えている。
彼女のつく嘘は、どれも他愛なく、誰かを守るためだったり、場を和ませるためのものだった。そして、その嘘から生まれる音楽は、モーツァルトのピアノソナタのように、明るく、優雅で、律のささくれた心を少しずつ癒やしていくのだった。
いつしか二人は、店の中だけでなく、外でも会うようになった。初めての食事、公園での散歩、美術館巡り。葵はいつも楽しそうで、彼女の隣にいると、律は自分の特殊な聴覚のことさえ忘れそうになった。
「律さんって、いつも静かだけど、なんだか安心する。まるで、調律されたピアノみたい」
ある夜、食事の帰りに彼女がそう言った時、律の頭には音楽は流れなかった。それは彼女の紛れもない本心だった。律の胸が、ぎゅっと締め付けられるように熱くなる。この感情を、何と呼べばいいのだろう。
しかし、二人の関係が深まるにつれて、律は彼女の奏でる音楽に、時折、微かな違和感を覚えるようになっていた。それは、長調の明るい旋律の中に、ふと混じる短調の響き。影を落とすような、チェロの物悲しい低音。
「最近、少し疲れてる? 顔色が良くないようだけど」
公園のベンチで、律が尋ねると、葵は一瞬目を伏せ、すぐにいつもの笑顔を作った。
「ううん、全然! 昨日ちょっと夜更かしして映画を観ちゃっただけ。すっごく元気だよ」
その言葉と同時に、律の頭には壮麗なヴァイオリンのソロが鳴り響いた。それは息をのむほど美しいが、どこまでも哀愁を帯びた旋律だった。まるで、必死に何かを隠そうとする悲痛な叫びのように聞こえた。
律は不安を覚えながらも、それ以上踏み込むことができなかった。彼女の嘘が奏でる音楽が、あまりにも美しく、そしてあまりにも切なかったからだ。その音楽に込められた想いを、暴いてしまうのが怖かった。
第三章 悲愴のシンフォニー
季節は秋に移り、街路樹の葉が赤や黄色に染まり始めていた。葵と会えない日が、少しずつ増えていた。「実家の手伝い」や「友人の結婚式の準備」――彼女が口にする理由は様々だったが、そのたびに律の耳には、悲しみを湛えた弦楽四重奏が響いた。それは、関係の終わりを予感させるレクイエムのようだった。
そして、運命の日は突然やってきた。
葵から「大事な話がある」と連絡があり、初めて彼女の部屋に招かれた。ドアを開けた彼女は、いつもよりずっと痩せ、血の気のない顔で無理に微笑んでいた。部屋には、微かに薬品の匂いが漂っている。
「ごめんね、急に。……ちょっと、聞いてほしいことがあって」
彼女はそう切り出すと、テーブルの上に一枚のパンフレットを置いた。それは、ある特定の難病に関する医療機関のものだった。律の心臓が、嫌な音を立てて跳ねる。
「私ね、ずっと病気だったの。進行性のもので、もう、あまり長くはないんだって」
彼女は淡々と、しかし震える声で語り始めた。律と出会った頃には、まだ病状は安定していたこと。彼と過ごす時間が何よりも大切で、この幸せな時間を壊したくなくて、ずっと言い出せなかったこと。
「律さんといると、病気のこと忘れられた。普通の女の子みたいに、笑ったり、ドキドキしたりできた。だから……」
彼女の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「だから、最後に、ちゃんとしたかった。あなたに、嘘をついたままでいたくなかった」
律は、ただ黙って彼女の話を聞いていた。頭の中は、奇妙なほど静かだった。何の音も聞こえない。それは、彼女が生まれて初めて、律に対して一切の嘘偽りのない「真実」を語っている証だった。
静寂が、何よりも重く律の心にのしかかる。
一通り話し終えた葵は、涙で濡れた顔を上げ、最後の力を振り絞るように、必死の笑顔を作った。
「でも、大丈夫。本当に、大丈夫だから。残りの時間も、私らしく、明るく過ごすって決めたの。だから、心配しないで」
その瞬間だった。
律の頭の中で、音楽が爆発した。
それは、もはや単一の楽器の音色ではなかった。ティンパニが地を揺るがし、トランペットが高らかに咆哮する。無数のヴァイオリンが慟哭し、ピアノが激しい激情を叩きつける。壮大で、悲痛で、混沌としていながら、恐ろしいほどの調和を保った、一つの交響曲。
それは、死の淵に立ちながらも愛する人を不安にさせまいとする、彼女の魂そのものの絶叫だった。彼女が今までついてきたどんな嘘よりも、強く、深く、そして圧倒的に美しい、究極の「愛の嘘」。
律は、その音楽の奔流に打ちのめされながら、ようやく理解した。
彼女の嘘から生まれる音楽の美しさは、嘘に込められた「想い」の強さに比例していたのだ。そして今、彼の全身を駆け巡っているこの壮絶なシンフォニーこそが、藤代葵が坂井律に向ける、最大級の愛情の証明だった。
第四章 愛のフーガ
壮絶なシンフォニーが鳴り響く中、律はゆっくりと立ち上がり、泣きじゃくる葵の隣に座った。そして、震える彼女の体を、そっと抱きしめた。
「……聞こえてるよ、葵さん」
「え……?」
「君の、本当の心の音が。ずっと前から、聞こえてた」
律は、初めて自分の秘密を打ち明けた。嘘が音楽として聞こえること。彼女のささやかな嘘が奏でる優しいメロディーに惹かれたこと。そして今、彼女の「大丈夫」という嘘が、どんな言葉よりも雄弁に、彼女の愛と苦しみを伝えてくれていること。
葵は驚きに目を見開いたが、やがて、彼の胸に顔をうずめ、子供のように声を上げて泣いた。律は、その背中を優しく撫で続けた。もう、彼の頭の中に音楽は流れていなかった。ただ、愛する人の温もりと、規則正しい心臓の鼓動だけが、そこにあった。
その日を境に、二人の関係は新しい楽章へと入った。律は調律師の仕事を調整し、できる限りの時間を葵と共に過ごした。彼女は相変わらず、小さな嘘をついた。
「今日のスープ、ちょっとしょっぱかったかな?」と心配する律に、「ううん、世界一美味しいよ」と微笑む。その瞬間、律の耳には温かなホルンの音色が響く。
痛みを堪えながら、「今日は調子がいいみたい」と気丈に振る舞う。すると、優しく寄り添うようなオーボエの旋律が流れる。
律は、もう嘘の音楽に戸惑うことはなかった。それは、言葉にできない彼女の愛情そのものだったからだ。彼は、自分の呪われたはずの能力を、初めて心から感謝した。この耳がなければ、彼は彼女の健気な嘘の裏にある、深く美しい魂の響きに気づけなかっただろう。
ある晴れた午後、二人は海が見える丘のベンチに座っていた。葵は、少し息を切らしながらも、幸せそうに律の肩に寄り添っている。
「ねえ、律さん。私の嘘って、どんな音楽だった?」
「……そうだね」律は空を見上げた。「君が初めてついた嘘は、ハープのアルペジオだった。清らかで、キラキラしてた。僕の灰色の世界に、光が差したみたいだったよ」
「そっか……」
葵は嬉しそうに目を細めた。
彼らの未来に、どんなフィナーレが待っているのか、誰にも分からない。けれど、確かなことが一つだけあった。
たとえいつか、彼女という存在がこの世界から消えてしまっても、彼女が奏でた数え切れないほどの美しいメロディーは、律の心の中で永遠に鳴り響き続けるだろう。嘘つきな君が遺してくれた、愛という名のシンフォニー。律は、その旋律を胸に抱いて、これからも生きていくのだ。