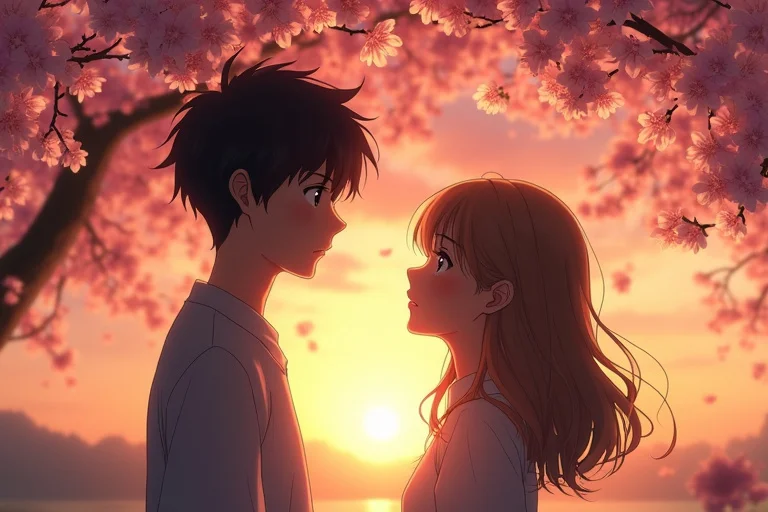第一章 灰色の同居人
坂本修一の日常は、限りなく無色透明に近かった。朝六時半に鳴る電子音で目覚め、焦げ付かないように細心の注意を払ってトーストを焼き、味のしないコーヒーで流し込む。同じ時刻の電車に乗り、いつも同じ車両の同じドアのそばに立つ。車窓を流れる風景は、昨日と寸分違わぬ速度と角度で後方へ消えていく。会社では、数字と格闘し、当たり障りのない会話を交わし、定時になれば誰よりも早くタイムカードを押す。コンビニで買った弁当を、テレビの無機質な笑い声をBGMに掻き込む。これが、修一の世界のすべてだった。
彼にとって、感情はコストだった。喜べば、失った時の落差に苦しむ。怒れば、無用な軋轢を生む。悲しめば、前に進む足が重くなる。だから修一は、心を凪の状態に保つ術を、いつしか身につけていた。まるで、分厚いガラスケースの中に自分の心をしまい込み、外の世界の刺激から守っているかのように。
ただ一つ、彼の無菌室のような日常に、異質なものが存在した。それは「影」だ。
彼の本当の影とは別に、常に修一の三歩後ろに、もう一つの人型の影が佇んでいた。それは陽光の強さや照明の角度に関係なく、常に同じ濃さの黒でそこに在った。輪郭はぼんやりとしていて、性別も年齢も窺い知れない。ただ、人の形をしているということだけが分かった。
物心ついた時から、影はそこにいた。最初は気味悪がったものの、影は決して彼に触れようとも、声をかけようともしない。ただ、いるだけ。まるで風景の一部のように。やがて修一は、それを自分の特異体質か何かだと割り切り、意識の隅に追いやった。日常に害をなさないのであれば、存在しないのと同じだ。彼はその影を「同居人」と、心の中で密かに呼んでいた。
その朝も、いつもと同じだった。はずだった。
玄関で革靴に足を通し、ドアノブに手をかけた瞬間、修一は背後に奇妙な気配を感じて振り返った。三歩後ろにいるはずの影。その、いつもは力なく垂れ下がっているはずの右腕が、ゆっくりと持ち上がっていた。そして、ぼんやりとした指先が、ぴたりと正面のドアを指し示したのだ。
修一は息を呑んだ。心臓が、錆びついたブリキのように軋んだ音を立てる。何十年も、ただそこに「いる」だけだった影が、初めて明確な「意思」のようなものを見せた。それは、彼の無色透明な日常に、一滴の黒いインクが落とされたような、静かで、しかし決定的な出来事だった。
第二章 指先の導き
影の奇妙な行動は、その日を境に始まった。
会社のデスクで、山積みの資料に目を通していると、背後の影がすっと腕を伸ばし、ある一つの契約書ファイルを指さした。修一は無視を決め込んだが、胸のざわめきが収まらない。結局、休憩時間にもう一度そのファイルを確認すると、契約金額に一桁の間違いがあるのを発見した。上司に報告すると、危ないところだったと感謝され、少しだけ株が上がった。だが修一は、手柄を立てた喜びよりも、影の行動に対する不可解さと、薄気味悪さの方が勝っていた。
帰り道、いつもの駅への道を歩いていると、影はふいに、賑やかな商店街とは逆方向の、薄暗い路地を指さした。修一は足を止める。行きたくない。自分の決めたルートを外れることは、平穏な日常のレールから脱線するようで怖かった。しかし、背後でじっと路地を指し続ける影の無言の圧力は、じわじわと彼の心を侵食していく。
「……一度だけだ」
誰に言うでもなく呟き、修一はため息と共におもむろに路地へと足を踏み入れた。黴と湿気の匂いが鼻をつく。数分も歩くと、視界が開け、小さな公園が現れた。錆びついたブランコと、塗装の剥げた滑り台、そして半分砂に埋もれたベンチが一つ。平日の夕暮れ時だというのに、子供の声一つしない、時が止まったような場所だった。
影は、公園の中央でぴたりと動きを止め、指先をゆっくりと下ろした。まるで、ここが目的地だとでも言うように。修一は、意味も分からず錆びたブランコに腰掛けた。ギィ、と低い音が鳴る。なぜ、ここへ? 彼はこの公園に見覚えがなかった。しかし、胸の奥深く、分厚いガラスケースの内側で、何かが微かに震えるのを感じていた。忘れてしまった古い歌のメロディを、ふとした瞬間に思い出しそうになる時のような、もどかしく、切ない感覚。
風が吹き、ブランコの鎖がカランと音を立てた。その乾いた音を聞きながら、修一は無意識に隣に視線を送った。誰もいない、もう一つのブランコ。なぜだろう。そこには、誰かが座っているべきような気がした。小さな、自分とよく似た誰かが。
その考えに自分で驚き、修一は乱暴に立ち上がった。馬鹿馬鹿しい。感傷に浸っている暇はない。彼は公園を背に、早足でいつもの日常へと戻っていった。だが、背中に感じる影の気配は、いつもより少しだけ濃く、重くなっているように思えた。
第三章 忘れられた写真
数週間が過ぎた。影は時折何かを指さしたが、修一はそれをことごとく無視し続けた。公園での一件以来、彼は影の存在を以前にも増して疎ましく感じ、意識的に見ないようにしていた。ガラスケースの壁をさらに厚く塗り固め、心の微かな震えを無理やり押さえつけた。
しかし、ある土曜日の朝、事件は起きた。
リビングでぼんやりとテレビを眺めていると、背後の影が、これまでになく強く、激しく、南の方角を指し示したのだ。その指先は微かに震えているようにさえ見える。南。その方角には、修一が十年以上も帰っていない実家があった。
逃げたい。拒絶したい。だが、影の放つ尋常ならざる気配が、彼の足に অদৃশ্যの鎖を絡ませる。それはもはや単なる指さしではなく、悲痛な叫びのように感じられた。修一は観念した。この黒い同居人と決着をつける時が来たのかもしれない。彼は重い腰を上げ、数年ぶりに帰省の準備を始めた。
新幹線と在来線を乗り継ぎ、実家の最寄り駅に着いた頃には、陽は西に傾いていた。潮の香りが混じる懐かしい風が、彼の心をざわつかせる。重い足取りで実家の門をくぐると、驚いた顔の母が彼を迎えた。「修一かい? まあ、どうしたんだい急に」。母の声は、記憶の中より少しだけ細くなっていた。
ぎこちない会話を交わし、仏壇に手を合わせた後、修一は逃げるように二階の自分の部屋へ向かった。背後の影も、静かについてくる。埃っぽい空気と、色褪せたポスター。何もかもが、時が止まったままだ。影は部屋の中央で立ち止まると、ゆっくりと腕を上げ、勉強机の一番下の引き出しを指さした。
心臓が大きく脈打つ。修一は唾を飲み込み、震える手でその引き出しを開けた。教科書やノートの山。その奥に、手触りの違うものがあった。古びたアルバムだ。ページをめくると、幼い自分の姿が次々と現れる。そして、最後のページに挟まっていた一枚の写真に、彼の視線は釘付けになった。
色褪せた写真の中には、七五三の晴れ着を着た二人の少年が、はにかみながら立っていた。一人は間違いなく自分だ。そして、もう一人。自分と瓜二つの、しかし少しだけやんちゃそうな笑みを浮かべた少年。
その瞬間、雷に打たれたように、記憶のダムが決壊した。
――健二。
脳裏に響いた名。弟。双子の弟。いつも一緒だった。同じ顔で笑い、同じことで泣いた、自分の半身。そうだ、弟が、いた。
忘れていた光景が、濁流のように押し寄せる。公園のブランコを二人で漕いだ日。誕生日にもらったお揃いのミニカー。そして、あの雨の日。道路に転がったボールを追いかけて飛び出した健二。けたたましいブレーキ音。自分の悲鳴。振り向いたトラックの運転手の、真っ青な顔。
「あ……ああ……っ」
声にならない声が漏れた。修一はその場にへたり込み、写真を持つ手がわなわなと震える。そうだ。僕は、見ていたんだ。健二が、僕の目の前で……。
そのあまりの衝撃と罪悪感に、幼い彼の心は耐えきれなかったのだ。健二の存在そのものを、悲しみも、後悔も、愛情も、すべてを記憶の奥底に封じ込め、まるで最初からいなかったかのように、自分の世界から切り離してしまった。
呆然と顔を上げると、目の前にいた影の輪郭が、ゆっくりと変わっていくのが見えた。ぼんやりとした人型が、写真の中の少年――健二の姿に重なっていく。
影は、僕が捨てた記憶。僕が蓋をした感情。忘れられた弟の存在そのものだったのだ。ずっと、ずっと、思い出してほしくて、すぐ後ろで佇んでいたのか。
影は、悲しそうに微笑んだように見えた。
第四章 影が還る場所
「修ちゃん、健二のこと、思い出したのね」
いつの間にか背後に立っていた母が、震える声で言った。その目には、うっすらと涙が浮かんでいる。
「あの子の事故から、あなた、弟の話を一切しなくなった。まるで、健二なんて最初からいなかったみたいに…。お母さん、それがつらかったけど、あなたもつらいんだろうと思って、何も言えなかった…」
母の言葉が、修一の心の最後の壁を打ち砕いた。彼は、子供のように声を上げて泣いた。健二ごめん、ごめん。忘れててごめん。一人にしてごめん。堰を切ったように溢れ出す言葉は、誰にともなく、しかし確かに弟に向けられていた。何十年分もの悲しみと後悔、そして心の底に押し殺していた愛情が、熱い涙となって頬を伝い、古いアルバムの上に染みを作った。
どれくらい泣き続けたのか。涙が枯れ、しゃくりあげる肩がようやく落ち着いた頃、修一はふと、あることに気づいた。
背後に、影の気配がしない。
慌てて振り返るが、そこには誰もいない。ただ、夕日が差し込む埃っぽい部屋があるだけだ。消えた? いや、違う。修一は直感的に理解した。影は消えたのではない。彼が自分の過去と感情を受け入れた瞬間、その役目を終え、本来いるべき場所へと還っていったのだ。修一自身の、心の中へと。
世界が、まるで違って見えた。
部屋の空気の匂い。窓から見える夕焼けの、燃えるような赤。階下から聞こえる母の気配。すべてが、今まで感じたことのない解像度と温度をもって、彼の五感を満たしていく。分厚いガラスケースは粉々に砕け散り、剥き出しになった彼の心は、世界のすべてを敏感に感じ取っていた。それは少しだけ痛みを伴ったが、それ以上に、生きているという確かな実感を与えてくれた。
一週間後、修一は故郷の墓地に来ていた。真新しい花を供え、水をかけた墓石には「坂本家之墓」と並んで、健二の名が刻まれている。彼は静かに手を合わせた。
「健二。遅くなって、本当にごめん。これからは、ずっと一緒だ。もう、忘れたりしないから」
風が吹き、木々がさわさわと葉を揺らす。それが、弟の返事のように聞こえた。
立ち上がった修一の背後に、もうあの黒い影はない。しかし、彼は決して孤独ではなかった。彼の内側には、弟の記憶と、彼を愛したという確かな感情が、温かい光のように宿っていたからだ。
日常は、これからも続いていくだろう。満員電車に揺られ、数字と格闘し、時には味気ない弁当を食べる日もあるかもしれない。だが、その一つ一つは、もはや無色透明ではなかった。喜びも、悲しみも、すべてを抱きしめて生きていく。それが、影が還る場所を見つけた修一の、新しい日常の始まりだった。