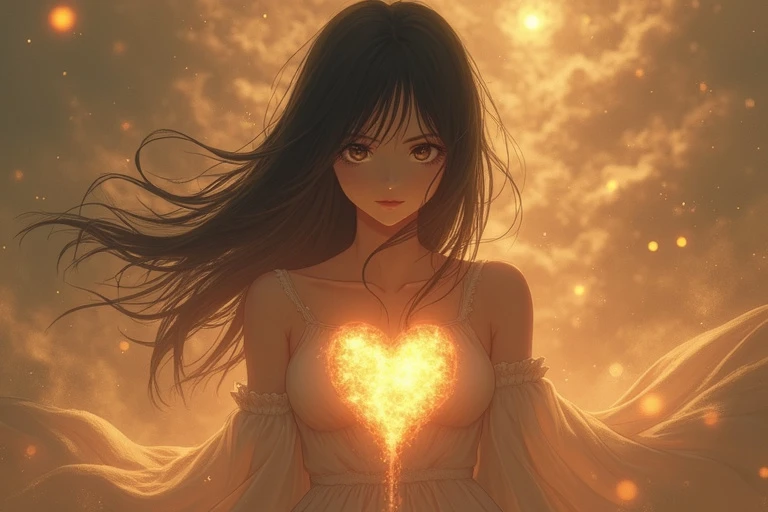第一章 掌の破片
僕の左手には、友人の心が宿る。
正確に言えば、その破片だ。誰かとの絆が軋む音を立てるたび、あるいは深い絶望が友人の心を抉るたび、僕の掌には小さな結晶が自動的に生成される。鋭く尖ったそれは、硝子の破片のように冷たく、指先でなぞれば、その持ち主の痛みが微かな電流となって僕の胸を刺す。だから僕は、この能力を呪っていた。
世界は「共有された記憶」でできている。誰かと深く心を交わすうち、互いの記憶の一部は混ざり合い、分かちがたい繋がりとなる。幼馴染のリオとは、特に多くの記憶を共有していた。僕の脳裏には、彼が初めて自転車に乗れた日の、誇らしげな笑顔が焼き付いている。彼の記憶には、僕が川で溺れかけた時の、水の冷たさが染み込んでいるはずだ。僕たちは、互いの人生の一部を生きることで、一人ではなかった。
ある雨の日の午後、些細なことでリオと口論になった。僕の言葉が彼のプライドを傷つけたと気づいた瞬間、左の掌にちりちりとした熱が走る。見れば、乳白色の歪な結晶が生まれていた。指でそっと触れると、リオの悔しさと悲しみが、湿った雨の匂いと共に流れ込んできた。
「ごめん」
図書館の軒下で雨宿りをしていた彼に駆け寄り、僕は掌の結晶を見せた。彼は一瞬目を見開いたが、すぐに苦笑して僕の頭をくしゃりと撫でた。
「お前には、隠し事ができないな」
彼のその一言で、掌の結晶は砂のようにさらさらと崩れ、指の間から消えていった。絆が修復された証だ。雨上がりのアスファルトの匂いが、僕たちの間に漂う。共有された記憶が、また一つ温かい色を帯びた瞬間だった。
第二章 空白の肖像
その異変は、街の噂話のように、静かに始まった。
「大切な友人のことを、思い出せないんだ」
カフェで聞こえてきた囁き。学校の廊下で交わされる戸惑いの声。「忘却の霧」とは違う、もっと絶対的な喪失。関係が途絶えた時の、記憶が曖昧になる現象ではない。まるで、その存在自体が初めから人生になかったかのように、綺麗にくり抜かれているのだという。ぽっかりと空いた穴は、誰にも認識できない「空白の絵画」となって、人々の心に掛けられているらしかった。
その日の夜、僕の掌に、これまでとは全く異なる結晶が現れた。
それは、完璧な円形をしていた。どこにも継ぎ目のない、透明な玻璃の球。これまでの欠片が宿していた感情の熱も、ざらついた手触りもない。氷のように冷たく、驚くほど滑らかで、まるでこの世のものではないような非現実的な存在感を放っていた。僕はその結晶を握りしめ、言いようのない不安に襲われた。誰の心なのだろう。この完全な無感情は、一体何を意味しているのだろう。
翌日から、その円形の結晶は、一つ、また一つと、僕の掌に増え続けた。
街からは、人々の笑い声が少しずつ減っていく。誰もが、自分の心のどこかに空いた穴の存在に気づかぬまま、漠然とした喪失感を抱えて歩いているように見えた。
第三章 褪せる色彩
恐怖は、じわじわと僕の日常を侵食してきた。
ある日、僕とリオの共通の友人であるアヤが、僕に尋ねた。
「ねえ、カイ。私、昔バイオリンを習ってたんだけど、誰に勧められたんだっけ?」
彼女の記憶では、それは「誰か大切な人」だったはずなのに、その顔も名前も思い出せないのだという。彼女の人生という名の絵画から、一人の人物が、背景ごと綺麗に消し去られていた。その夜、僕の掌にまた一つ、完璧な円形の結晶が生まれた。
リオとの間にも、見えない壁が生まれ始めていた。彼もまた、街に漂う静かな喪失感を感じ取っているようだった。
「なんだか、最近変だよな。みんな、何か大事なものを忘れているような顔をしてる」
夕暮れの公園で、ブランコに揺られながら彼が呟く。茜色の光が彼の横顔を染め、共有された記憶が作り上げたその輪郭を、僕は失うことを想像して怖くなった。この掌の円い結晶が、いつかリオとの記憶の代償になるのではないか。そんな考えが頭をよぎり、僕は彼の腕を強く掴んでいた。
「僕たちは、大丈夫だよな?」
声が震える。リオは驚いた顔をしたが、やがて優しく微笑んだ。
「当たり前だろ。俺たちだぞ」
その言葉が、僕を繋ぎとめる唯一の錨だった。しかし、その錨でさえ、静かに進行する記憶の侵食の前では、あまりにも脆いものに思えた。
第四章 調律師の囁き
朝、目が覚めた時、世界は変わっていた。
部屋に満ちる朝の光も、窓の外でさえずる鳥の声も昨日と同じだ。だが、決定的に何かが欠けていた。隣の部屋から聞こえてくるはずの、リオが朝食の準備をする物音がしない。そもそも、僕の隣に、誰かが住んでいただろうか。
思考が空転する。頭の中には、親友と過ごしたはずの場所が、ぽっかりと穴の空いたキャンバスとして存在している。彼がいたはずの席、彼が笑ったはずの道、彼の声が響いたはずの空間。全てが、完璧な空白だった。
絶望が全身を駆け巡る。僕は自分の左手を見た。そこには、これまでで最も大きく、そして透明に輝く、完璧な円形の結晶が一つ、静かに鎮座していた。
その時、背後に人の気配がした。
「それが、君と彼の絆の、最も美しい形だ」
振り返ると、深いフードを目深にかぶった男が立っていた。いつからそこにいたのか、まるで影が人の形をとったかのようだ。
「お前は、誰だ……リオを、どこへやった!」
「私は『調律師』。私は、友情を救っているのだよ」男は静かに言った。「友情は、必ず終わりを迎える。裏切り、すれ違い、そして死。共有された記憶は濁り、やがては苦痛に変わる。私は、その苦しみから人々を解放している。友情が最も輝かしい瞬間に、その記憶だけを完全な形で凍結保存し、他の全ての関係性の記憶からその存在を消し去る。永遠に色褪せない、完璧な肖像画としてね」
彼の言葉は、冷たい刃のように僕の心を切り裂いた。これは救済だと? 輝かしい瞬間だけを切り取ることが、本当に救いになるというのか。
第五章 円環の真実
僕は調律師に掴みかかろうとした。だが彼の体は、まるで陽炎のように揺らめき、僕の手は空を切る。
「無駄だ。君には私を止められない」
「ふざけるな!」
僕は掌の円い結晶を、部屋に差し込む朝日にかざした。すると、信じられない光景が目の前に広がった。透明な球体の中に、映像が浮かび上がったのだ。リオと二人で屋上で見た、満点の星空。喧嘩の後に並んで食べた、アイスキャンディーの味。僕が忘れてしまった、彼とのかけがえのない瞬間が、万華鏡のように次々と映し出されては消えていく。
「なぜ……なぜこんなことを!」
涙で視界が滲む。その時、調律師がゆっくりとフードを外した。
そこに立っていたのは、僕だった。
歳を重ね、深い悲しみと後悔が刻まれた、紛れもない未来の僕の顔だった。
「私は……未来の君だ」彼は苦しげに告白した。「私は、リオを失った。事故だった。あまりにも突然で、受け入れられなかった。彼との記憶は、共有されていたが故に、彼の死と共に濁り始め、やがて耐え難い苦痛へと変わった。だから、私はこのシステムを創った。友情の終わりという絶望から、全ての人を救うために。最も美しい記憶だけを、永遠の宝石として残すために」
未来の僕は、僕に手を差し伸べた。
「過去の私よ。共に、この世界を悲しみから救おう。もう誰も、大切な友を失う痛みを知らずに済むのだ」
彼の瞳は、狂信的な光を宿していた。それは、あまりにも深い愛と絶望が生み出した、歪んだ理想の形だった。
第六章 瑕疵ある絆を
永遠に輝く、完璧な友情。終わりのない、美しい記憶。それは、かつての僕が夢見た理想郷かもしれない。だが、今ならわかる。
「違う」僕は首を横に振った。「それは、救いじゃない」
僕の脳裏に、リオと交わした最後の言葉が蘇る。『当たり前だろ。俺たちだぞ』。あの言葉の温もりは、完璧な結晶の中にはない。喧嘩した時の痛みも、仲直りした時の安堵も、全てが混ざり合って、僕たちの絆を形作っていたのだ。
「たとえ終わりが来て、記憶が霧に霞んでもいい。傷ついて、悲しくて、どうしようもなくなっても……それが、僕たちが確かに一緒に生きた証なんだ。完璧な絵画なんていらない。僕は、不格好で、色褪せていくかもしれない、本物の記憶が欲しい!」
僕が叫ぶと、掌の円形の結晶が眩い光を放ち始めた。未来の僕が作り上げたシステムが、過去の僕自身の意志によって拒絶され、崩壊を始めていた。
「そうか……君は、そちらを選ぶのだな」
未来の僕は、どこか安堵したような、寂しげな微笑みを浮かべていた。彼の姿は光の粒子となって、少しずつ掻き消えていく。
「ならば、一つだけ。これだけは、君に」
システムが完全に崩壊する直前、僕の掌に残っていた一つの結晶だけが、未来の僕の手によって守られた。そして、世界は元の色を取り戻し始めた。リオの記憶は戻らない。彼の存在は、僕の人生から完全に消え去ったままだ。
けれど、手の中には、最後の結晶が残されていた。
僕はそれを、震える手で光にかざす。そこに映し出されたのは、僕の知らないリオの笑顔だった。それは、僕が出会うはずだった、事故で失われる未来で、彼が僕に見せてくれるはずだった、幸せに満ちた笑顔だった。
涙が、頬を伝って結晶の上に落ちる。
完璧な友情など、どこにもない。けれど、この痛みも、喜びも、そしてこの永遠に得られることのなかった未来の笑顔も、全てが僕とリオの、かけがえのない絆そのものなのだ。僕はその小さな円環を、壊れないように、そっと胸に抱きしめた。