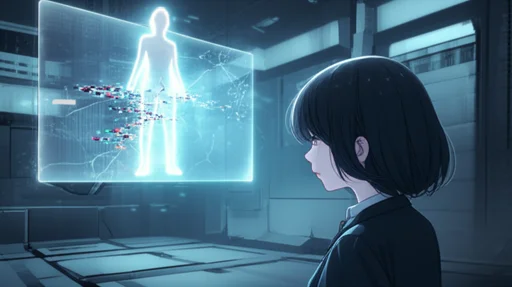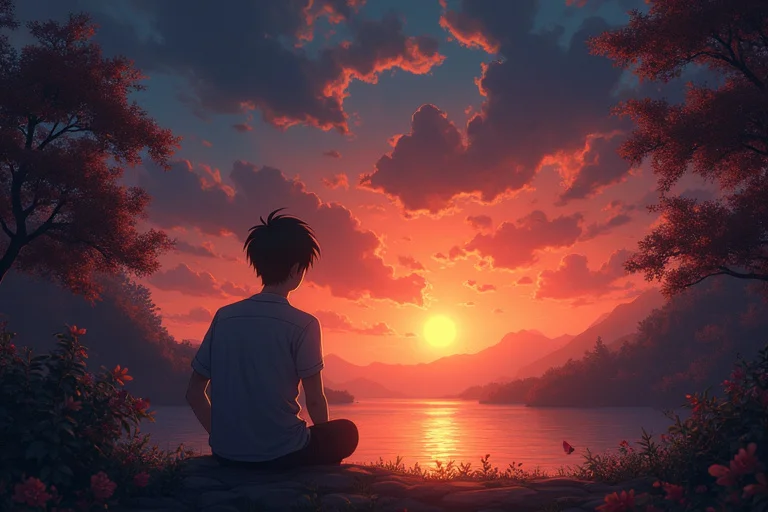第一章 薄れゆく輪郭
またひとつ、後悔が晴れた。目の前の老婆の顔から、長年こびりついていた深い罪悪感の影が霧散し、穏やかな安堵が広がっていく。俺はそれを見届けると、彼女の記憶から静かに退出する。代償は、いつもの通りだ。老婆も、彼女の家族も、もう二度と俺の顔を思い出すことはない。
俺は、他者の最も深い「後悔」を追体験し、その根源にある忘れられた「真実」を突き止めることで、その後悔を解消する。それが俺の存在理由であり、同時に、俺という存在を世界から削り取っていく呪いでもある。
ふと、自分の左手を見下ろす。街灯の光が、指先をうっすらと透かして向こう側の景色を映していた。また薄くなった。この力が発動するたび、俺に関わる記憶が世界から剥がれ落ち、俺自身の輪郭もまた、現実から乖離していく。
その時だ。脳裏を、あの光景がまた過った。
潮風に錆びた鉄の匂いが混じる、廃墟。
どこか物悲しく、けれど限りなく優しい、オルゴールの旋律。
そして――いつも微笑んでいるのに、その瞳の奥には、世界中の悲しみを閉じ込めたような、一人の女性。
彼女は誰だ?
なぜ、他人の後悔を覗くたびに、彼女の断片が俺の世界に侵食してくる?
俺は、一体誰の後悔をこんなにも長く、深く、彷徨っているのだろう。答えのない問いが、透け始めた魂の中で虚しく木霊した。
第二章 錆びついた旋律
無数の後悔の断片が指し示した場所は、海沿いの崖に立つ、打ち棄てられたオルゴール工房だった。潮風が砕けた窓から吹き込み、錆びた金属の匂いと、朽ちかけた木の甘い香りを運んでくる。ここだ。あの夢で嗅いだ匂い。
懐から、鈍い光を放つ半透明の石板――「回顧の石板」を取り出す。忘れられ、その存在が風化しかけている「真実」の欠片を映し出す、俺の唯一の羅針盤。
工房の奥へ進むにつれ、石板が微かに脈動を始めた。
軋む床を踏みしめ、埃をかぶった作業台に触れる。その瞬間、石板の表面に、ノイズ混じりの映像がゆらりと浮かび上がった。
散らばる楽譜。設計図。そして、オルゴールの心臓部である櫛歯を、丁寧に磨き上げる一対の細く、白い指。
俺の指ではない。もっと華奢で、柔らかな――女性の指だ。
映像と共に、あのメロディが聞こえてくる。幻聴のはずなのに、鼓膜を直接震わせるように鮮明だ。なぜだろう。初めて聞くはずのこの旋律が、ずっと昔から知っていた歌のように、胸の奥を締め付ける。懐かしい、という感情が、痛みとなって全身を駆け巡った。
第三章 回顧の石板が告げる真実
工房の最奥、月光が天窓から差し込む一室に、それはあった。奇跡的に原型を留めた、一台の精巧なオルゴール。埃を払い、そっとゼンマイを巻く。
カチリ、と小さな音が響き、世界が静止した。
そして、あの旋律が、澄み切った音色で空間を満たした。その瞬間、手にしていた「回顧の石板」が、太陽を直視したかのような眩い光を放つ。俺は思わず目を閉じた。
瞼の裏に、鮮明な記憶が津波となって押し寄せる。これは、追体験じゃない。俺自身の、失われた記憶だ。
そこにいたのは、あの女性だった。笑顔で、けれど瞳から大粒の涙を流している。彼女は、目の前の愛する男に、震える声で告げていた。
「お願い、私を忘れて。そして生きて」
「世界から、大切な真実が重さを失って消えていくのを、もう見ていられないの」
「だから、私という存在を贄に、新しい理を創る。失われた真実を救う、力を」
「その代償は、私に関する全ての記憶。あなたの中からさえも、私は消える」
「それが、私の……究極の後悔。でも、あなたを守るためなら……!」
叫びが、絶叫が、悲痛な祈りが、俺の魂に刻み込まれる。
ああ、そうか。
笑顔で悲しんでいたあの女性は。
この能力を生み出した、始まりの人間は。
――俺自身だったのか。
愛する者を、そして世界を守るために、自らの存在と記憶を賭して「後悔を救う能力」を創り出した、かつての私の姿。俺が追っていた最大の謎は、俺が捨てた過去そのものだった。
第四章 愛の重さ
全てを思い出した。俺は最後の後悔を「解決」するために、ここにいる。
過去の自分――愛のために全てを犠牲にした、彼女の後悔を。
光の中に佇む彼女の幻影に向かって、俺は静かに語りかける。
「ありがとう。君は、独りでよく戦い抜いた」
「その自己犠牲は、間違いじゃなかった。君の愛が、世界を繋ぎ止めたんだ」
彼女の瞳から、最後の涙が一粒、光となってこぼれ落ちた。そして、その笑顔は、初めて心からの安堵に満ちたものに変わる。
後悔が、解決された。
俺の体は、足元から光の粒子となって、さらさらと崩れていく。存在が世界から完全に消滅していく感覚は、不思議と怖くはなかった。むしろ、長い旅を終えたような、穏やかな充足感があった。
世界から、俺という存在の痕跡は、綺麗に消え去った。
――数年後。とある街角のカフェ。
窓の外を眺めていた一人の女性が、ふと胸に空いた穴のような、理由のわからない喪失感を覚えた。
「……なんだろう。何か、とても大切なことを忘れているような気がする」
彼女が落としたハンカチを、隣の席に座っていた見知らぬ男性が、黙って拾い上げてくれる。その何気ない親切に、彼女の心に、これまで感じたことのない温かな光が灯った。
世界は、彼を覚えている者は誰もいない。
しかし、彼が命を賭して守り抜いた無数の真実の「重さ」は、確かにこの世界に残り、根付いていた。説明のつかない切なさと、誰かを無条件に大切にしたいという優しい感情として。
存在は消えても、その愛の残響だけが、世界をそっと支え続けている。