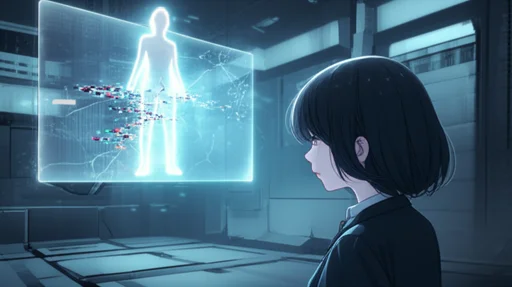第一章 死者からの星図
古書の修復師である相馬蒼(そうま あおい)の世界は、埃とインク、そして悠久の時を吸い込んだ紙の匂いで満たされていた。彼の指先は、脆くなった頁(ページ)の僅かな断裂を感じ取り、失われた文字の痕跡を寸分違わず復元できる。すべては論理と経験則に基づいた、確かな手仕事。曖昧な感情や、非科学的な偶然が入り込む余地など、彼の人生には存在しなかった。少なくとも、あの日までは。
親友の訃報は、一本の無機質な電話によってもたらされた。天文学者の星野航(ほしの わたる)が、自宅の天文台で遺体で発見されたという。警察の見解は、観測中に誤ってドームの足場から転落したことによる「事故死」。現場に争った形跡はなく、他殺を疑う要素は何一つないと断定された。
蒼は、その結論を受け入れられなかった。航は、誰よりも慎重な男だった。子供の頃から、石橋を叩いて渡るどころか、叩きすぎて破壊してしまうような性格だ。そんな彼が、慣れ親しんだ場所で足を滑らせるなど、論理的にあり得ない。しかし、蒼にはそれを覆す証拠も、感情的に訴える術もなかった。ただ、冷たい事実だけが彼の胸に突き刺さる。友はもういない。その事実が、彼の整然とした世界に初めて不協和音を響かせた。
葬儀から三日後の夜。蒼のPCが、静かに通知音を鳴らした。差出人は「星野航」。心臓が氷の指で鷲掴みにされたような衝撃が走る。それは、生前に設定された予約投稿メールだった。
『蒼へ。このメールが君に届いたということは、僕の身に何かあったということだ。警察は事故だと言うかもしれない。でも、もし君が少しでも腑に落ちないと感じるなら、僕からの最後の挑戦を受けてほしい』
息を詰めて画面をスクロールする。そこには、意味不明な数字の羅列と、一つの星図データが添付されていた。
『僕を殺した犯人は、僕らが愛した星空の中にいる。これは、死んだ僕から君への、最初で最後のメッセージだ。どうか、真実を見つけてくれ。君の論理と、僕のロマンを信じている。』
蒼は、震える手でマウスを握りしめた。死者からのメッセージ。非科学的で、情緒的で、彼が最も嫌う類のものだ。犯人だと? 事故ではなかったというのか?
頭では馬鹿げていると一蹴しながらも、心の奥底で燻っていた疑念の炎が、航の言葉によって激しく燃え上がった。彼の整然とした世界は、音を立てて崩れ始める。蒼は、航が遺した星屑の暗号を解読することを決意した。それは、親友の死の謎を追うためであり、そして何より、バラバラになった自身の世界を再構築するための、孤独な戦いの始まりだった。
第二章 論理の迷宮
航の天文台は、主を失い、ひっそりと静まり返っていた。許可を得て足を踏み入れた蒼を、冷たい金属と潤滑油の匂い、そして微かな夜の草いきれの匂いが迎える。巨大な望遠鏡が、まるで墓標のように夜空を指したまま沈黙している。
蒼は、添付されていた星図と数字の羅列をプリントアウトし、航の研究室のデスクに広げた。数字は、星の座標、等級、スペクトル型……天文学の知識を総動員しても、それらは無関係な星々のデータの寄せ集めにしか見えなかった。
「犯人は、星空の中にいる……」
航の言葉が頭の中で反響する。比喩か、それとも物理的な意味を持つのか。蒼は、航の研究ノートを片っ端からめくっていった。几帳面な文字で埋め尽くされたページには、未知の変光星に関する膨大な観測データが記されている。その研究は、航が学会で発表を予定していた、彼のキャリアの集大成となるはずのものだった。
調査を進めるうちに、容疑者として二人の人物が浮かび上がった。一人は、航と同じ大学に籍を置く准教授、高遠。彼は航の才能を公然と妬み、研究テーマが似ていたことから、しばしば対立していた。もう一人は、航の研究成果を狙っていたとされる技術開発企業のスカウト、三上だ。三上は航に執拗に接触し、データの買い取りを持ちかけていたという。
蒼は二人と会った。高遠は航の死を悼む素振りも見せず、「これでポストが一つ空いた」と冷笑を浮かべた。三上は「惜しい才能を亡くした」と芝居がかった口調で言い、航の研究データの行方をそれとなく探ってきた。どちらも怪しい。だが、彼らが航を殺害したという直接的な証拠はない。そもそも、警察は「事故」と結論づけているのだ。
蒼は焦燥感に駆られた。人の嘘や嫉妬、欲望といった不確定な要素が、彼の論理的な思考を掻き乱す。まるで霧の中の迷宮を彷徨っているようだ。彼はただ、事実という名の光を求めていた。
その夜、蒼は自分の工房に戻り、修復途中の古い天球儀に目をやった。航が子供の頃、蚤の市で見つけてきて、「二人で宇宙の謎を解こう」と笑った、思い出の品だ。その球体に刻まれた星座の一つに、ふと目が留まる。琴座。航が一番好きだと言っていた星座だ。
その瞬間、脳内で何かが繋がった。添付されていた星図。それは特定の領域を切り取ったものではなかったか。そして、あの無秩序な数字の羅列。あれは、バラバラの星々を繋ぐための「楽譜」だったのではないか。
航は言った。「君の論理と、僕のロマンを信じている」。
ロマン――音楽、物語、そして、星座。
蒼は、航が遺した暗号が、単なるデータの集合体ではなく、一つの「物語」を指し示している可能性に気づいた。冷たい論理の迷宮に、初めて微かな光が差し込んだ気がした。
第三章 琴座の告白
蒼の思考は、かつてない速度で回転を始めた。航の暗号は、琴座を構成する星々を、特定の順番で、特定の「明るさ(等級)」で見えるように並べ替えるための指示書だったのだ。それはまるで、星を使った演奏のスコアのようだった。
彼は再び天文台へ向かった。巨大なドームの制御パネルには、手動で座標を入力するテンキーが備え付けられている。蒼は、解読した順番通りに、星々の座標と等級に対応する数値を打ち込んでいった。それは、航と二人で夜空を見上げた、ある夏の夜の、琴座の配列そのものだった。
最後の一桁を打ち込み、エンターキーを押す。
カチリ、と小さな金属音が響いた。音の出所は、壁に埋め込まれた書棚の一角。そこには巧妙に隠された、小さな金庫の扉が現れていた。
「これか……!」
蒼は息を呑んだ。この中に、犯人を示す決定的な証拠が……。しかし、震える手で扉を開けた彼の目に映ったのは、がらんどうの空間だけだった。何もない。空っぽだ。
全身から力が抜けていく。絶望が蒼を打ちのめした。暗号を解いた先は、行き止まりだったのか。航は、自分をからかっただけなのか。
その時、蒼の足元に落ちていた一枚の紙片が目に留まった。航の観測日誌の破れたページだった。そこには、走り書きのような文字でこう記されていた。
『新星発見。座標XXX.XX、YYY.YY。――蒼、君がいなければ、僕はここまで来られなかった。この星に、君の名を贈る』
蒼は、雷に打たれたように立ち尽くした。
航の目的は、犯人の告発ではなかった。
彼は、蒼に自分の発見を託したかったのだ。そして、その発見を誰かが――高遠か、三上か――狙っていることに気づいていた。だから、データを守るために、この二重三重のロックをかけたのだ。
「犯人は、星空の中にいる」。
その言葉の本当の意味が、ようやく分かった。犯人は、航が発見した「新星」を狙う者。
では、航の死は?
蒼は、事故現場をもう一度検証した。足場には、不自然な擦過痕が残っている。そして、床の隅に、見慣れない土が付着していた。航の靴のものではない。第三者のものだ。
蒼の頭の中で、すべてのピースが嵌っていく。
航はあの日、新星の最終観測のためにドームの屋根に登っていた。そこへ、データを盗むために侵入者が現れた。おそらく高遠だろう。彼は航に気づかれ、揉み合いになったのではない。いや、違う。航は争うような人間じゃない。侵入者に驚き、バランスを崩したのだ。殺意のない、しかし致命的な結末。
航の死は、警察の言う通り「事故死」だった。しかし、その引き金を引いた「侵入者」がいた。航は、自分の死が単なる事故として処理され、侵入者の罪が見逃され、そして何より、命を懸けた発見が闇に葬られることを恐れた。だから、蒼に「犯人」という強い言葉を使って、この星屑のパズルを託したのだ。
金庫は空だったが、もう問題ではなかった。航が蒼に託したかったのは、物理的なデータではない。彼の夢そのものだったのだ。そして、その夢を証明できるのは、航が最も信頼した男、天才的な記憶力と論理的思考を持つ、相馬蒼だけだった。
第四章 盟友の光
蒼は、警察にすべてを話した。彼の推理と、天文台に残された第三者の痕跡から、高遠准教授が窃盗未遂と過失致死の容疑で逮捕された。高遠は、航の死後、再び天文台に忍び込み、金庫からデータを盗み出していたことも自供した。事件は、法的には解決した。
しかし、蒼の物語はまだ終わっていなかった。彼は自らの工房に籠もり、航が残した日誌の断片、そして何よりも、航と交わした無数の会話の記憶を手繰り寄せた。航が語った新星の周期、スペクトルの特徴、夜空における微かな揺らぎ。それらの情報を、自身の記憶の宮殿から引き出し、一つ一つ数式に落とし込んでいく。それは、修復師としての緻密な作業と、天文学者としての論理的な思考の融合だった。
数週間後、蒼は一枚の論文を完成させた。それは、航の観測データがなくても、理論的にその新星の存在を証明するものだった。彼はその論文を、航と自分の連名で、国際天文学連合に提出した。
季節が巡り、冬の夜。蒼は一人、丘の上に立っていた。吐く息が白く凍り、夜空の星々はダイヤモンドのように鋭く輝いている。
数日前、一通の通知が届いた。新星は正式に承認され、「S-Aoi(蒼)」という仮符号が与えられたという。航が望んだ通り、蒼の名前が星になったのだ。
しかし、蒼は論文と共に、一つの要望書を提出していた。
その星の正式名称を、「アルラ」としてほしい、と。
アラビア語で「盟友」を意味する言葉。
蒼は、ポケットから小さな双眼鏡を取り出し、夜空にかざした。論文に記した座標の先に、肉眼では到底見えない、微かな光を探す。それは、簡単には見つからない。しかし、蒼はもう焦らなかった。
論理と事実だけを信じて生きてきた。目に見えないものは、不確かで、価値がないとさえ思っていた。だが今は違う。航が遺した想い、二人の間にあった友情。それらは、どんな数式よりも確かな「事実」として、蒼の心に刻まれている。
その光は見えなくても、そこにある。友が、星になって自分を見守ってくれている。
その温かい確信が、冷たい夜気の中で、蒼の心を静かに満たしていく。彼はもう、整然としているが孤独な世界の住人ではなかった。星屑のパラドックスを解き明かした先に見つけたのは、犯人ではなく、永遠に消えない友情の光だった。
蒼は、静かに空を見上げ続けた。その瞳には、盟友の星が、確かに映っているかのように、穏やかな輝きが宿っていた。