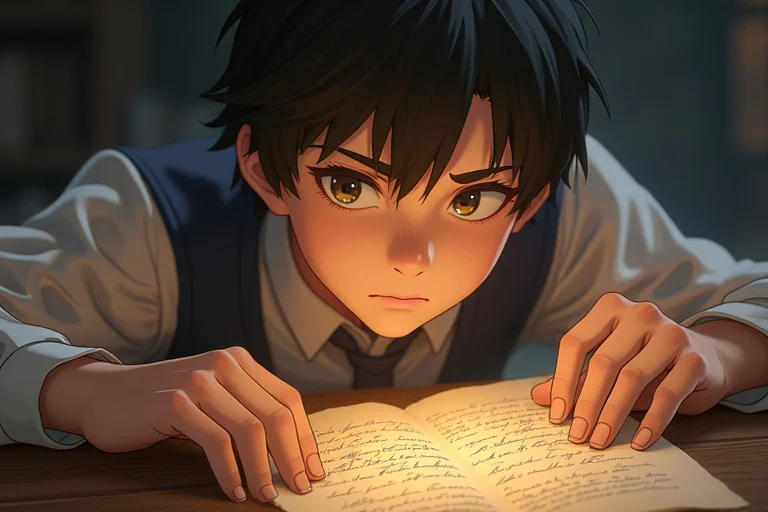第一章 陶片に宿る沈黙の叫び
時任湊(ときとう みなと)の仕事場は、死んだ時間の匂いがした。国立歴史編纂局・地下三階。特殊記録課、通称「物語修復師」の部屋は、埃と古紙、そしてかすかな防腐剤の匂いが混じり合い、まるで巨大な石棺の内部にいるようだった。彼の仕事は、歴史の闇に葬られた名もなき人々の「物語」を、遺された断片から掬い上げ、再構築すること。遺物に触れることで、そこに込められた残留思念を読み取るという、科学では説明のつかない能力を持つ彼だからこそ可能な、孤独な作業だった。
その日、湊のデスクに置かれたのは、桐の箱に収められた、手のひらほどの大きさの陶器の欠片だった。五世紀頃のものとされる、何の変哲もない土師器(はじき)の一部。依頼書には「身元不明の陶工。反逆罪により処刑されたとの伝承あり」とだけ、無機質な明朝体で記されていた。
「反逆者、か」。湊は呟き、白い手袋をはめた指でそっと陶片に触れた。歴史は常に勝者が記述する。敗者や反逆者の物語は、歪められ、あるいは抹消されるのが常だ。彼の仕事は、その歪みを正し、沈黙させられた魂に声を与えることにある。
目を閉じ、意識を集中させる。指先から冷たい何かが逆流し、心臓を直接鷲掴みにされるような衝撃が走った。
「っ……!」
思わず声が漏れる。これは、尋常ではない。普段感じる思念は、霧のように朧げで、時間をかけてその輪郭を捉えていくものだ。しかし、この陶片から流れ込んできたのは、奔流だった。声にならない絶叫、胸を張り裂くような悲嘆、そして、何かを、あるいは誰かを守ろうとする、燃え盛る炎のような強烈な意志。ビジョンは嵐のように断片的で、意味をなさなかった。燃え盛る窯。闇夜に煌めく無数の星。小さな子供の手を握る、ごつごつとした土くれの手。そして、すべてを絶望で塗りつぶす、冷たい刃のきらめき。
湊は弾かれたように陶片から手を離した。額には汗が滲み、呼吸が荒くなる。なんだ、これは。ただの陶工ではない。この陶片には、歴史の記録が完全に黙殺した、巨大な物語が封じ込められている。彼の冷めきっていたはずの探究心に、静かだが確かな火が灯った。この沈黙の叫びの正体を、突き止めなければならない。
第二章 記録と感情の乖離
調査は難航を極めた。陶片が出土したのは、かつて「葦原郷(あしはらのさと)」と呼ばれた山間の集落跡。古文書をいくら紐解いても、この陶工に関する記述は、依頼書にあった「時の国造(くにのみやつこ)に逆らい、一族もろとも処罰された」という、数行の曖昧な伝承しか見つからなかった。歴史の表舞台において、彼は存在しないも同然だった。
湊は方針を変え、同じ地層から出土した他の遺物に触れてみることにした。それはまるで、主役のいない舞台のセットから、物語の核心を探るような作業だった。炭化した家の柱、錆びた鋤の先、そして、小さな子供が作ったであろう歪な土の人形。
柱に触れれば、家が焼かれる瞬間の村人たちの恐怖と混乱が津波のように押し寄せる。鋤に触れれば、豊かな実りを願い、黙々と土を耕す日々の穏やかな営みが伝わってきた。そして、土の人形。そこから感じ取れたのは、陶工の腕に抱かれて空を見上げる、幼い娘の純粋な愛情と、父親への絶対的な信頼だった。
「どういうことだ……」
湊は眉を寄せた。伝承が示す「反逆者」のイメージと、遺物から伝わる「家族を愛し、村人に慕われた男」の人物像が、どうしても結びつかない。彼の残留思念は、確かに強烈な怒りと抵抗の意志を示している。だがそれは、私利私欲のための反逆ではなく、もっと根源的で、守るべきもののための悲痛な叫びのように感じられた。
湊は自室の壁一面に貼った巨大な地図と年表に、新たに得た情報を書き込んでいく。事実と、感情。記録と、記憶。二つの異なる歴史が、彼の目の前で乖離していく。彼は「物語修復師」として、客観的な事実に基づき、論理的に物語を再構築することを信条としてきた。感情はあくまで補助的な情報であり、それに流されてはならない。だが、この陶工の事件に限っては、むしろ感情の側にこそ、無視できない「真実」の核が隠されているように思えてならなかった。
焦燥感が募る。パズルのピースは散らばっているのに、それらを繋ぐ絵柄が見えない。このままでは、彼を「悲劇の反逆者」というありきたりの型に押し込めて報告書を書き上げるしかない。それは、あの沈黙の叫びに対する裏切りだ。湊は、最後の望みを託し、もう一度あの陶片と向き合うことに決めた。何かを見落としている。必ず、何かがあるはずだ。
第三章 星辰の暗号
深夜、静まり返った資料室で、湊は再び陶片をデスクライトの下に置いた。以前は気づかなかったが、表面に刻まれた無数の細かい線刻が、不規則な文様のように見えていた。だが、本当に不規則だろうか? 湊はルーペを取り出し、食い入るように表面を観察した。
線と、点。それらは、ある一定の法則性を持って配置されているように見えた。もしかして、これは単なる装飾ではない。一種の記号、あるいは、暗号なのではないか。
彼は古代の文字や文様に関する資料を片っ端から調べ始めた。そして、数時間が経った頃、ある天文学の古文書に描かれた図を見て、息を呑んだ。
「まさか……」
陶片に刻まれた点と線は、夜空の星の配置図だった。しかも、それは当時の人々が知るはずのない、極めて正確な星辰図。そして、その中心に描かれているのは、太陽と月が重なり合う、皆既日食のシンボルだった。
湊は震える手で、古代の暦と天体の運行記録を照合する。そして、ついに特定した。陶片が作られたと推定される年代。その二年後、この葦原郷一帯で、記録的な規模の皆既日食が起こっていたのだ。
すべてのピースが、音を立てて嵌っていく。
彼は再び陶片に触れた。今度は、躊躇わない。真実を知る覚悟を決めて、深く意識を沈めていく。
ビジョンが、今度は鮮明な物語となって流れ込んできた。
陶工は、夜ごと空を見上げ、星の動きを記録していた。彼は、代々受け継がれてきた密かな知識によって、天体の運行を読み解く術を知る、類稀なる天文学者だったのだ。彼は、やがて訪れる「太陽が喰われる日」を正確に予見する。そして、それに伴い、この土地を大規模な天災――おそらくは豪雨や洪水――が襲うであろうことも。
彼は村人たちを守るため、時の権力者である国造に進言した。しかし、国造は彼の知識を理解できず、むしろ「日食という凶兆を口にし、民を惑わす妖術使い」と断じた。為政者にとって、自らの権威を揺るがしかねない未知の知識は、反逆と同義だった。
陶工は捕らえられ、処刑される運命を悟る。彼に残された時間はわずかだった。彼は最後の力を振り絞り、窯に向かった。未来の誰かが、この真実を掘り起こしてくれることを信じて。自分の知識が、いつか子孫の役に立つことを願って。彼は、星の配置図と日食の警告を、永遠に残る陶器に刻みつけたのだ。それが、彼にできた唯一の、そして最大の「抵抗」だった。
ビジョンの中で、陶工が振り返る。その顔を見た瞬間、湊は全身の血が凍りつくような衝撃を受けた。深い皺、厳しいながらも慈愛に満ちた眼差し。それは、幼い頃に亡くなった、自分の祖父の顔に生き写しだった。
――守りたかった。未来に続く、我らの血を。
声ではない声が、魂に直接響く。湊は、自分が修復していた物語が、単なる赤の他人の過去ではなく、自分自身の血の源流、遥かなる祖先の物語であったことを悟り、言葉を失った。冷徹な傍観者でいるはずだった彼は、当事者として、歴史の渦の中心に立たされていた。
第四章 時を超えた対話
湊が書き上げた報告書は、これまでの彼の仕事とは全く異質のものだった。それは、淡々とした事実の列挙ではなく、一人の人間の魂の軌跡を克明に描いた、一篇の叙事詩のようだった。
「名もなき陶工、その正体は、民を救わんとした孤高の天文学者なり。彼の反逆とは、無知という名の権力に対する、知識人の静かなる抵抗であった」
彼は、客観的な証拠として星辰図の解析結果を添付し、そして、これまで避けてきた主観的な「想い」――遺物から感じ取った家族への愛、村人への慈しみ、そして未来への願いを、余すところなく記述した。歴史とは無味乾燥な事実の集合体ではない。それは、無数の人々の感情と意志が織りなす、生きたタペストリーなのだ。そのことを、彼は祖先の魂から教えられた。
報告書を提出し、自室に戻った湊は、桐箱に納められた陶片をそっと手に取った。もう、あの胸を抉るような悲しみや怒りは感じなかった。代わりに、穏やかで温かい、陽だまりのような感謝の念が、じんわりと心に広がっていく。まるで、遥かなる時を超えて、祖先が「ありがとう」と微笑みかけてくれているようだった。
湊は、窓の外を見上げた。コンクリートのジャングルを隔てても、空には変わらず星が瞬いている。千五百年前、彼の祖先が見上げたであろう星々。あの陶工は、この星空に未来を託し、絶望の中で希望を刻んだ。その想いが、時空を超えて、今、ここにいる自分に届いた。自分は、歴史という巨大な川の流れの中に浮かぶ、ちっぽけな存在ではない。自分もまた、この流れを未来へと繋いでいく、確かな一部なのだ。
彼の仕事は、これからも続くだろう。だが、その意味合いは根底から変わった。それはもはや、死んだ時間を整理する作業ではない。沈黙した魂と対話し、その想いを未来へと受け渡す、神聖な儀式となった。
湊は、指先にかすかに残る土の感触を確かめながら、静かに目を閉じた。彼の心には、千五百年の時を超えて結ばれた、血の系譜の確かな温もりが満ちていた。歴史は記録されるものではなく、受け継がれていくものなのだ。その真実に辿り着いた彼の顔には、夜明け前の空のような、静謐な光が差していた。