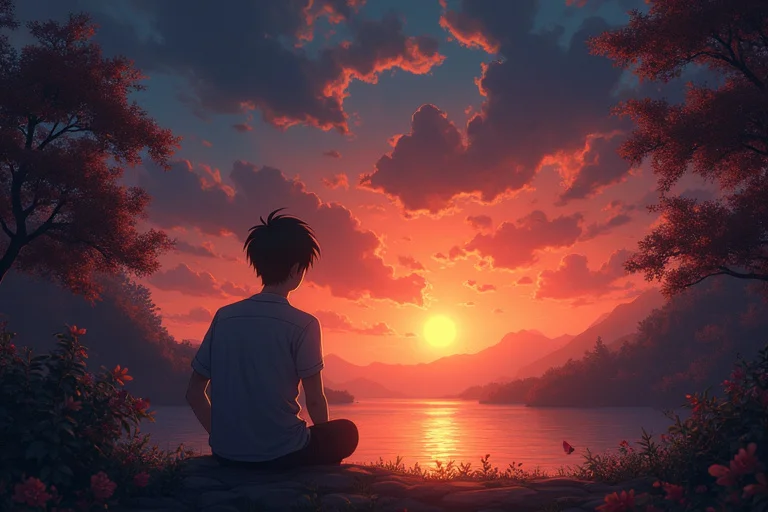第一章 甘く危険な不在証明
鼻腔を麻痺させるほどの甘やかな死の匂いが、その重厚な書斎を支配していた。古い革表紙とインクの匂いに満ちた静謐な空間で、主である古書収集家・高遠祥一郎は、安楽椅子に深く身を沈めたまま、永遠の眠りについていた。
「外傷、なし。毒物反応、なし。部屋は内側から鍵がかけられた完全な密室。……お手上げだ、朔」
旧友の刑事、長谷部は、うんざりしたように溜め息をついた。俺、桐谷朔(きりたに さく)は、彼の要請でこの異様な現場に足を踏み入れていた。かつて天才調香師と持て囃された俺も、今では世間から忘れられたアトリエの主だ。鋭すぎる嗅覚は呪いにも似て、普段は外界の匂いを遮断する特殊なフィルターマスクが手放せない。だが、今はそのマスクを外し、全ての感覚を研ぎ澄ませていた。
警察の人間が鼻を覆うほどの、このむせ返るような香り。それは単一の香水や芳香剤のそれとは明らかに異質だった。いくつかの要素が複雑に絡み合い、一つの物語を紡いでいるかのような、作為的な調香の気配。
「……これは、香りだ」
「はあ? だからそう言ってるだろ。部屋の匂いがキツいって」
長谷部のいらだった声が、空気を震わせる。俺は首を横に振った。
「違う。この香りが、凶器なんだ」
俺はゆっくりと目を閉じ、意識を嗅覚だけに集中させる。まず鼻をつくのは、リンドウの凛とした苦みと、白檀の深く落ち着いた香り。それは鎮魂の祈りのように、空間に荘厳さを与えている。だが、その下には、まるで隠された悪意のように、錆びた鉄を思わせる冷たい金属臭と、熟れすぎて腐敗しかけた果実のような、背徳的な甘さが潜んでいた。そして、それら全てを包み込むように、高遠祥一郎自身の匂い――長年愛用したであろうレザーの安楽椅子と、古い紙の乾いた匂いが混じり合っている。
これは、殺人者の署名だ。被害者の人生を嘲笑い、その最期を演出するかのような、傲慢で、しかし途方もなく繊細な技術で作られた香り。俺の知る限り、こんな芸当ができる調香師は、世界に数えるほどしかいない。そしてその誰もが、こんな陰惨な遊戯に手を染めるとは思えなかった。
「長谷部。被害者が亡くなる直前、誰かと会っていたか?」
「いや、それがさっぱりだ。昨夜八時に秘書が帰ってからは、ずっと一人だったはずだ。誰も部屋に出入りした形跡はない」
不在証明。犯人は、この部屋に物理的に存在することなく、高遠を殺害した。そして、証拠として残したのは、この捉えどころのない、しかし確かな存在感を放つ「香り」だけ。俺は、見えない犯人が仕掛けた香りの迷宮に、足を踏み入れたことを悟った。心の奥底で、とうに蓋をしたはずの過去の扉が、軋みを立てて開こうとしているのを感じながら。
第二章 香りの記憶、偽りの輪郭
俺のアトリエは、街の喧騒から切り離された路地裏にひっそりと佇んでいる。数百種類もの香料が並ぶガラス瓶の壁は、俺だけの聖域であり、監獄でもあった。事件現場から持ち帰った香りのサンプル――特殊な吸着シートに染み込ませた微かな残香を、ガスクロマトグラフで分析する。モニターに現れる無数のピークは、香りの成分を示唆するが、それはレシピの一部を解読するに過ぎない。本当の答えは、俺の鼻と記憶の中にしかない。
長谷部の捜査で、被害者の周辺にいくつかのトラブルがあったことが判明した。稀覯本『黄昏のソネット』の所有権を巡って争っていた大学教授。高遠に多額の借金をしていた美術商。そして、高遠の遺産の第一受益者である、年の離れた若妻。
俺は長谷部と共に、彼ら一人一人と会った。俺の鼻は、嘘や隠し事の匂いを敏感に嗅ぎ分ける。教授は焦燥と嫉妬の酸っぱい匂いをさせ、美術商は恐怖と諦めの黴びた匂いを纏っていた。若妻は、悲しみを装ってはいたが、その奥からは新しい香水と解放感の明るい匂いが漏れ出ていた。誰もが怪しかった。だが、あの現場にあった、あの複雑で芸術的なまでの悪意に満ちた香りの痕跡は、誰からも感じられなかった。
犯人は、まるで自分の存在を消し去るかのように、巧みに香りをコントロールしている。あるいは、犯人自身は、何の香りも纏っていないのかもしれない。
「朔、何か掴めたか?」
アトリエを訪れた長谷部が、コーヒーを啜りながら尋ねる。俺は首を横に振った。
「パズルのピースはいくつか見つかった。リンドウ、白檀、金属臭……。だが、それらを繋ぎ合わせる『何か』が足りない。この香りは、ただの成分の集合体じゃない。明確な『意図』と『物語』を持って調香されている。まるで、誰か特定の個人に向けたメッセージのように」
「メッセージ?」
「ああ。この香りを嗅いだ時、何か特定の記憶や感情を強制的に呼び覚ます……そんな力がある」
俺は再現を試みる。リンドウのエッセンシャルオイルを一滴、ガラス棒に垂らす。白檀のパウダーを微量、乳鉢で擦る。だが、何度試しても、あの現場の香りの核心にはたどり着かない。何かが決定的に欠けている。それは、レシピには書かれない、調香師の魂とも言うべき要素。記憶、情念、あるいは、愛。
その夜、俺は悪夢を見た。忘れたはずの光景。陽光が降り注ぐアトリエで、一人の女性が微笑んでいる。彼女の周りには、俺が彼女のためだけに作った香りが、幸せのオーラのように漂っていた。
「素敵な香りね、朔。名前はなんていうの?」
「『Mémoire(メモワール)』……記憶、っていう意味だよ」
彼女――美緒の笑顔が、事件現場の甘く苦い香りと重なり、俺は飛び起きた。全身が冷たい汗で濡れていた。まさか。そんなはずはない。あの香りは、俺がこの世で最も愛した女性、そして事故で失った彼女のために作った、世界に一つしかない香りだったのだから。
第三章 再生のレクイエム
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。なぜ、『Mémoire』が、あの殺風景な書斎にあったのか。あれは、数年前に交通事故で亡くなった恋人・美緒のためだけに、俺のすべてを注いで作り上げた香りだ。レシピは俺の記憶の中にしかない。そして、現物は、彼女と共にこの世から消えたはずだった。
過去から目を背けるな、と誰かが囁く。俺は震える手で、何年も開けていなかったクローゼットの奥から、美緒の遺品が入った箱を取り出した。中には、彼女が愛用していたスカーフや、古びた手帳が収められていた。手帳を開くと、そこには俺の知らない美緒の苦悩が、繊細な文字で綴られていた。
『――家が傾き、父の残した稀覯本を売るしかない。高遠祥一郎という収集家が興味を示してくれた。私の足元を見て、不当に安い価格を提示してくる。でも、今は呑むしかない……』
ページをめくる手が止まった。高遠祥一郎。被害者の名前が、そこにあった。
日記は続く。高遠は美緒を騙し、彼女の家系に伝わる本――『黄昏のソネット』――を二束三文で手に入れた。美緒がそれに気づき、抗議に行った日の記述が、最後の日記だった。
『彼と口論になった。揉み合った末に、階段から……』
その後のページは、空白だった。
事故ではなかった。俺が信じていたすべてが、音を立てて崩れ落ちていく。美緒は、高遠によって殺されたも同然だった。そして俺は、彼女の死の真相から目を背け、ただ自分の悲しみに溺れていただけの臆病者だった。
全てが繋がった。犯人は、美緒の無念を知る者。そして、『Mémoire』の存在を知る者。俺の脳裏に、一人の人物の顔が浮かんだ。葬儀の時、俺を責めるような、それでいて深い悲しみを湛えた瞳で見ていた、美緒の弟・湊(みなと)。彼は大学で化学を専攻していたはずだ。
俺は湊のアパートへ向かった。ドアを開けた瞬間、確信した。あの香りだ。リンドウと白檀。そして、俺だけが知るはずの『Mémoire』の甘く切ない残り香が、部屋に満ちていた。
「……やはり、君だったか」
部屋の奥にいた湊は、驚くでもなく、静かに俺を見つめていた。
「姉の日記を見つけたんです。あいつが姉さんをどうやって追い詰めたか、全部知ってしまった。警察は事故として処理した。誰もあいつを罰しない。だから、僕がやるしかなかった」
彼の声は、乾いていた。
「姉さんの部屋で、あなたのレシピを見つけました。『Mémoire』の。姉さんが、宝物のように大切にしていたメモです。僕は、あなたへの嫉妬と、姉さんを守れなかった自分への怒りで、必死に調香を学びました。そして、あの香りを再現したんです」
湊は、小さな小瓶を取り出した。
「これは、ただの香水じゃない。特殊な植物から抽出したアルカロイドを加えてある。微量だが、強い情動、特に罪悪感や恐怖を感じた時に心臓の動きを不規則にする効果がある。僕は、高遠の部屋の空調に細工をして、一晩かけてこの香りを気化させた。密室で、姉さんの記憶を呼び覚ます香りに包まれ、彼は自らの罪の重さに耐えきれず、心臓発作を起こした。僕の手は、汚れていません」
香りは、凶器だった。そして、裁きの道具でもあった。湊は、最も詩的で、最も残酷な方法で復讐を遂げたのだ。
事件は解決し、湊は自首した。だが、俺の心には、虚しさと共に、言いようのない感情が渦巻いていた。俺は香りで人を癒し、幸せにすることだけを考えてきた。だが、同じ香りが、憎しみを増幅させ、人の命を奪う凶器にもなり得る。その事実が、重く俺にのしかかった。
数週間後。俺はアトリエで、新しい香水を作っていた。夜明け前の澄んだ空気のようなベルガモット、雨上がりの土の匂いを思わせるパチュリ、そして、悲しみを乗り越えた後に咲くという、かすかな水仙の香り。それは『Mémoire』ではない。過去への追憶ではなく、未来へ向かうための、再生と希望の香り。
俺は完成したばかりの香りを一吹きし、アトリエの窓を大きく開け放った。街のざわめき、風の匂い、光の粒子が、部屋へと流れ込んでくる。もう、フィルターマスクは必要ない。
香りは記憶を呼び覚ます。だが、新しい香りは、新しい物語を紡ぎ出すこともできるはずだ。俺は、美緒の死と、湊の罪を、そして自らの弱さを、この胸に抱きしめて生きていく。それが、香りの持つ光と影を知ってしまった、調香師としての俺の、唯一の贖罪なのだから。