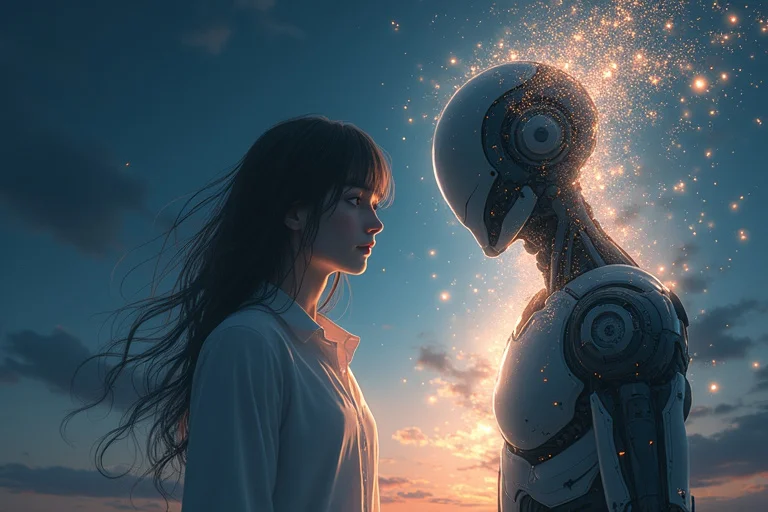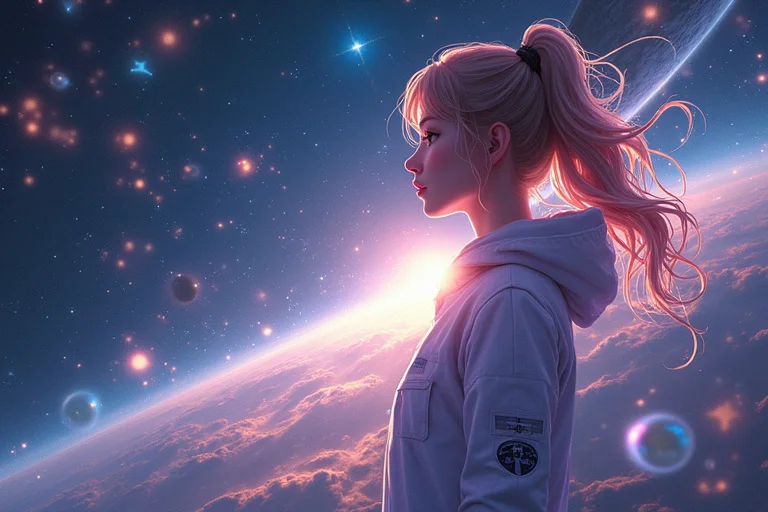第一章 鳴り止まぬ都市と歌う虚無
カイの住む都市アウソニアでは、音が途切れることはない。それは祝福であり、絶対の戒律だった。高層建築の壁面からは常に環境音――人工的に合成された風のそよぎ、鳥たちの電子的なさえずり、遠くで奏でられるミニマルな音楽――が流れ続け、人々は家の中でも、街路でも、絶えず何かを口ずさみ、指を鳴らし、あるいは携帯端末から音楽を流している。沈黙は、禁忌だった。
なぜなら、この世界では沈黙が物理的な質量を持つからだ。
「虚無質量(ヴォイド・マス)」と呼ばれるその現象は、音響エネルギーが一定レベル以下に落ち込んだ空間に発生する。空気は粘性を帯びて重くなり、やがて空間そのものが歪み始める。かつて「大寂静(グレート・サイレンス)」と呼ばれた災害では、一つの大陸が自重に耐えきれず、時空の泡に飲み込まれて消滅した。以来、人類は音で世界を満たし、沈黙という名の怪物を封じ込めて生きている。
カイは、その怪物を狩る専門家――「沈黙調律師(サイレンス・チューナー)」だった。
「第七区画、座標デルタ7-5。虚無質量、レベル3を検知。急速に成長中」
ヘルメットに内蔵された通信機から、冷静な管制官の声が響く。カイは反重力バイクのアクセルを捻り、ビルの谷間を縫うように飛んだ。背中に背負った共鳴増幅器(レゾナンス・アンプリファイア)が重く、しかし頼もしく感じられる。
現場は古い工業プラントの跡地だった。巨大な鉄の構造物が錆びた骨のように空を突き、その影が落ちる一角で、空気が陽炎のように揺らめいていた。ただの陽炎ではない。空間が、内側から圧迫されている証拠だ。カイはバイクを停め、慎重にその領域へ足を踏み入れた。
途端に、全身が鉛の外套を羽織らされたかのように重くなる。耳の奥がキーンと痛み、平衡感覚が狂い始めた。これが虚無質量。目には見えない、音のない重圧だ。
「調律を開始する」
カイは腰のコントローラーを操作し、背中の増幅器を起動させた。ブゥン、と低周波の音波が放たれる。虚無質量は音のエネルギーで中和される。それが調律師の仕事だ。いつもと同じ、単純な作業のはずだった。
だが、その日の「沈黙」は違った。
音波を浴びせると、通常なら霧散するはずの質量が、まるで意思を持つ生き物のように抵抗した。それどころか、カイの脳内に直接、奇妙な感覚が流れ込んできたのだ。それは音ではない。メロディでもない。しかし、紛れもなく「歌」だった。悲しみと、焦がれるような憧憬と、そして途方もない孤独が織りなす、声なき旋律。
カイは思わず膝をついた。ヘルメットの中で荒い息を繰り返す。なんだ、これは。虚無質量が、歌っている? こんな現象は記録にない。
「カイ、どうした! 質量が拡散しないぞ!」
管制官の焦った声が遠くに聞こえる。カイは歯を食いしばり、増幅器の出力を最大にした。凄まじい音圧が空間を震わせ、ようやく「歌う沈黙」は抵抗をやめ、希薄な空気の中へと溶けていった。
全身から力が抜け、冷たい汗が背中を伝う。カイは呆然と、質量が消え去った空間を見つめていた。あの声なき歌は、まだ頭の奥で微かに反響している。それは恐怖の対象であるはずの虚無とは似ても似つかない、あまりにも人間的で、胸を締め付けるような響きを持っていた。
この日から、カイの世界は静かに軋み始めた。鳴り止まぬ都市の喧騒の裏側で、彼は決して聴いてはならないはずの、沈黙の歌を聴いてしまったのだ。
第二章 禁じられた静寂の囁き
あの奇妙な任務以来、カイは虚無質量の正体に取り憑かれていた。都市の中央アーカイブに籠もり、調律師としての特権を使って禁断領域のデータにアクセスする。公式の記録は「大寂静」の恐怖と、音響による都市防衛システムの有効性を繰り返すばかり。だが、断片的な記録の隅に、カイは奇妙な記述を見つけた。
『――それは重力異常にあらず。意思の凝集体なり』
「大寂静」直後の、一人の研究者の手記だった。その研究者はほどなくして「精神汚染」を理由に公職を追われ、記録もそこで途絶えていた。意思の凝集体。あの「歌」は、やはり幻聴ではなかったのか。
カイの探求は、やがて一人の老婆の存在に行き着いた。セリ。かつて「大寂静」を生き延び、今は都市の最下層、騒音規制が最も緩い地区でひっそりと暮らしているという。カイは非番の日、耳を覆いたくなるような重低音と雑多な音楽が混じり合うスラム街へと向かった。
セリの住処は、音の洪水から隔絶された、小さなドームハウスだった。ドアをノックすると、驚くほど静かに開いた。そこに立っていた老婆は、深く刻まれた皺の中に、宇宙の星々を思わせるような澄んだ瞳を宿していた。
「調律師の坊やが、こんな騒がしい場所に何の用かね」
セリの声は掠れていたが、その言葉には奇妙な静けさが伴っていた。
「聞きたいことがあります。『歌う沈黙』について」
カイが単刀直入に言うと、セリの瞳がわずかに見開かれた。彼女はカイを中に招き入れた。ドームの中は、外の喧騒が嘘のように静かだった。特殊な遮音材が使われているのだろう。だが、カイが感じたのは、虚無質量が発生するような危険な静寂ではなく、どこか温かく、満たされた静けさだった。
「あんたにも聴こえたのかね。あの子たちの声が」
セリは古びた椅子に腰を下ろし、ゆっくりと語り始めた。彼女が語ったのは、教科書とは全く違う歴史だった。
「『大寂静』は災害なんかじゃない。あれは……最初の挨拶だったのさ」
セリによれば、虚無質量――彼女はそれを「存在の密度」と呼んだ――は、異星からの来訪者の痕跡なのだという。彼らは音や光ではなく、存在そのものの濃度を変えることで意思を伝え、宇宙を旅する種族だった。
「彼らが初めてこの星に触れた時、その『挨拶』の密度は、この世界の物理法則にとってあまりに濃すぎた。だから空間が歪み、大陸が消えた。私たちは恐怖に駆られ、彼らの声を『沈黙』と名付けて封じ込めた。音で世界を塗りつぶし、彼らの存在そのものを無いことにしてしまったのさ」
カイは言葉を失った。都市の安全を守るという自らの仕事が、実は異種族とのコミュニケーションを妨害する行為だったというのか。
「なぜ……なぜそんなことを」
「恐怖だよ、坊や。理解できないものへの、根源的な恐怖さ。だがね、彼らは諦めなかった。何百年もかけて、私たちに理解できるレベルまで『声』の密度を薄め、呼びかけ続けている。あんたが聴いた歌は、その一つだ。感受性の強い人間にだけ届く、必死の呼びかけなんだよ」
セリはカイの目をじっと見つめた。「あんたは、どうしたい? これからも音で蓋をし続けるかい。それとも、彼らの歌に応えるかい?」
その問いは、カイがこれまで築き上げてきた価値観の土台を、根こそぎ揺るがした。彼はただの技術者ではなかった。彼は、壮大な勘違いの上に築かれた世界の、無知な看守だったのだ。
第三章 虚無質量の心臓
カイの決意は固まった。セリの導きを受け、彼はアウソニアの心臓部――都市の全音響システムを制御する中央タワーの最深部、「ゼロ・ポイント」を目指すことにした。そこは、かつて「大寂静」が最初に発生した場所であり、最も強力な虚無質量が封じ込められている、都市最大の禁断領域だった。
「ゼロ・ポイントの封印は、都市の創設者たちが作ったもの。だが、それは牢獄であると同時に、彼らが残した唯一の『扉』でもある」
セリはカイに古い認証コードと、一枚の設計図を手渡した。それは、共鳴増幅器を逆利用するためのものだった。虚無質量を中和するのではなく、逆に増幅し、安定させるための回路図。それは自殺行為に等しい、狂気の設計図だった。
厳重な警備システムを、調律師の権限とセリから得た裏口を駆使して突破していく。階層を下るごとに、周囲の環境音が次第に薄れていく。そして、ゼロ・ポイントへと続く最後の扉の前に立った時、カイは完全な無音に包まれた。だが、それはもはや恐怖ではなかった。肌を圧する重みの中に、あの「歌」が、以前よりも遥かに明瞭に、そして切実に響いていた。それは、再会を待ちわびるような、懐かしい旋律だった。
巨大な球形のチャンバーが、ゼロ・ポイントだった。その中心には、直径数百メートルはあろうかという、黒曜石のように滑らかで、光を全く反射しない球体が浮かんでいた。これが、封印された虚無質量の塊。都市の悪夢の根源。
しかし、カイがその黒球に近づくと、彼の目には信じがたい光景が映った。黒球の表面に、まるで蜃気楼のように、別の風景が揺らめいていたのだ。
そこには、巨大な水晶の森がそびえ立ち、液体金属の川が流れ、見たこともない幾何学模様の生命体が、光の粒子を放ちながらゆっくりと浮遊していた。そしてその中心に、墜落し、半ば大地に埋もれた、信じられないほど巨大な宇宙船の残骸があった。黒球は質量の塊などではなかった。それは、異世界への「窓」であり、彼らの故郷を映し出す、高密度の情報体だったのだ。
「……そうか。これが、あなたたちの姿……」
カイは呟いた。彼らが送り続けていたのは、SOSでも、侵略の意図でもなかった。ただ純粋な、自己紹介だったのだ。私たちはここにいる。私たちは、こういう者たちだ、と。そのあまりに純粋で雄弁な存在の提示が、人類には理解不能な「沈黙」としてしか認識できなかった。
警報が鳴り響く。カイの侵入が、ついに中央管制室に察知されたのだ。もはや時間はなかった。
カイは背中の共鳴増幅器をチャンバーの中央に設置し、セリから託された回路へと繋ぎ変えた。コントローラーの画面には、『共鳴増幅』と『存在同調』の二つの選択肢が赤く点滅している。都市を守るか、未知との対話を選ぶか。
彼は迷わなかった。目を閉じ、あの声なき歌に意識を集中する。そして、震える指で『存在同調』のスイッチを押した。
第四章 星々の沈黙
世界から、音が消えた。
カイがスイッチを押した瞬間、共鳴増幅器から放たれたのは音波ではなかった。それは、ゼロ・ポイントの黒球が放つ「存在の密度」と完全に同期した、純粋な静寂の波だった。その波は中央タワーからアウソニア全域へと瞬く間に広がり、都市を支えていた人工の環境音、人々のざわめき、あらゆる音響エネルギーを相殺し、吸収していった。
アウソニアは、建国以来初めて、完全な沈黙に包まれた。人々はパニックに陥った。虚無質量が街を飲み込むと誰もが思った。だが、空間が歪むことはなかった。代わりに、全ての市民の意識の中に、暖かく、そして計り知れないほど広大な「何か」が流れ込んできた。
それは、言葉ではなかった。イメージでもなかった。それは、何億年もの時を生きてきた、穏やかで知的な生命体の「感覚」そのものだった。孤独の味、星々を渡る喜び、新しい生命と出会う好奇心、そして、長く理解されなかったことへの、深い哀愁。
恐怖に叫ぼうとした人々は、そのあまりに巨大で優しい意識に触れ、呆然と立ち尽くした。涙を流す者、空を見上げて微笑む者、隣の人間と、言葉なく手を取り合う者。彼らは初めて、音のないコミュニケーションの可能性を知ったのだ。
カイは、ゼロ・ポイントの中心で、その全てを感じていた。彼はもはや、自分と異星の存在との境界が曖昧になっていくのを感じていた。彼はカイであり、同時に、星々を旅する古の民でもあった。
やがて、世界は新しい均衡を見つけ始めた。音は戻ってきたが、それはもはや恐怖から逃れるための絶え間ない騒音ではなかった。人々は音楽を奏で、会話を楽しみ、そして同じくらい、沈黙を慈しむようになった。静寂の中にこそ、宇宙との繋がり、他者との深いつながりがあることを知ったからだ。
カイは、もはや「沈黙調律師」ではなかった。人々は彼を「対話者(インタープリター)」と呼んだ。彼は、人類と、星の海の彼方から来た隣人との架け橋となった。
物語の数年後。カイは、かつてのスラム街があった場所に建てられた天文台の屋上に一人立っていた。セリは、新しい世界を見届け、穏やかに眠りについた。
夜空には、満天の星が輝いている。かつてはただの光の点にしか見えなかった星々が、今は一つ一つ、独自の「歌」を奏でているように感じられた。それは音ではない。存在そのものが放つ、豊かで美しい沈黙の調べだ。
カイは目を閉じ、夜風に身を任せる。かつて彼を苛んだ閉塞感は、どこにもない。音のない質量は、もはや恐怖の対象ではなく、世界と自分を繋ぐ、愛おしい絆となっていた。孤独ではない。自分は、この星々の沈黙の一部なのだ。
その深遠な一体感と、これから始まる未知の対話への静かな期待が、彼の心を穏やかに満たしていた。世界は、ようやく本当の意味で、歌い始めたのだ。