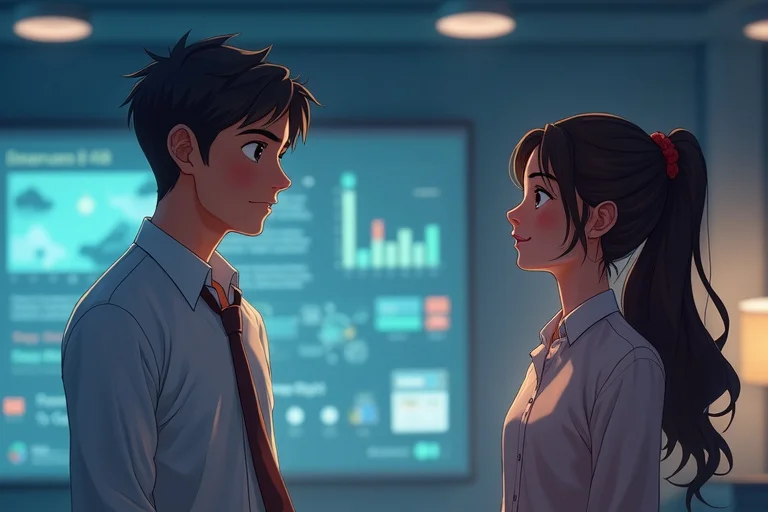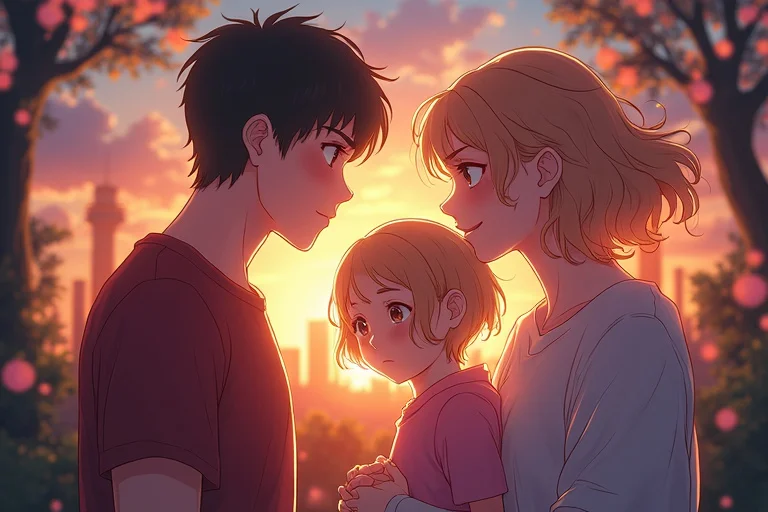第一章 ユーモア指数狂騒曲
佐藤健人(さとうけんと)、三十四歳、独身。彼の人生は、寸分の狂いもなく設計された精密機械のようだった。毎朝六時半に起床し、きっちり八分間トーストを焼き、同じ車両の同じドアから電車に乗る。変化を嫌い、予定調和を愛する彼にとって、世界は退屈だが安全な場所だった。その日までは。
異変は、月曜の朝、満員電車の中で始まった。目の前に立つ、いつも不機損な顔をしている上司の頭上に、ふわりとネオンピンクの数字が浮かんでいたのだ。『8』。健人は目を擦った。寝不足だろうか。しかし、視線を隣に移すと、スマホゲームに夢中な女子高生の頭上にはエメラルドグリーンの『72』が、吊り革を握る疲れた顔のサラリーマンにはくすんだ黄色の『13』が、それぞれ踊っている。
パニックに陥りかけた健人の脳裏に、天啓のように一つの仮説が閃いた。これは、まさか「ユーモア指数」ではないだろうか。
その日から、健人の灰色だった世界は、突如としてフルカラーの採点会場へと変貌した。彼は憑かれたように、人々の頭上の数字を観察し始めた。会社の同僚たちは大体二桁台で、たまに冗談を言っては場を白けさせることで有名な経理の田中課長は、案の定『3』という絶望的な数値を叩き出していた。逆に、いつも明るくムードメーカーの新人、高橋さんは『85』と高得点だ。健人は確信した。この指数は、その人物が内包する「面白さ」の総量を可視化したものなのだ、と。
「俺の人生に足りなかったのは、これだ!」
健人は、退屈な日常からの脱却を誓った。最高のユーモアを持つ人間を見つけ出し、そのエッセンスを吸収すれば、自分の灰色の日々もきっと輝き出すに違いない。彼は週末になると街へ繰り出し、高得点者を探し始めた。繁華街の客引きは『110』、テレビ局の前で出待ちしているファンは『95』。それなりの数値には出会えるが、心が震えるほどの「面白さ」にはまだ出会えない。彼らのジョークはどこか上滑りしていて、健人の生真面目な心をこじ開けるには至らなかった。
そんなある日、彼はいつもの公園のベンチで、ついにそれを見つけた。穏やかな陽光の中、静かに鳩に餌をやっている一人の老人の頭上に、それは神々しく輝いていた。プラチナホワイトに光り輝く、驚異的な数値。
『999』。
カンストしている。健人は息を呑んだ。この老人こそ、自分が探し求めていたユーモアの頂点に立つ人間、現代のソクラテスにしてお笑い界の救世主に違いない。見た目は枯れ木のような老人だが、その内に秘めたユーモアのマグマは、きっと地球を揺るがすほどの熱量を持っているはずだ。健人の心臓は、予定調和を破って激しく高鳴っていた。彼は震える足で立ち上がると、その沈黙のコメディアンへと向かって、ゆっくりと歩き出した。
第二章 沈黙のコメディアン
「あの、弟子にしてください!」
健人は、老人の前で九十度に腰を折った。鳩が驚いて一斉に飛び立つ。老人はゆっくりと顔を上げ、深い皺の刻まれた目尻をほんの少しだけ下げた。彼の頭上の『999』が、午後の光を反射してきらめく。
「……弟子? わしはただの年金暮らしじゃが」
「ご謙遜を! 俺には分かるんです。あなたの内には、世界を震撼させるほどのユーモアが眠っている!」
健人のあまりの熱量に、老人は少し呆気にとられたようだったが、やがて「ふむ」と一つ頷くと、「古川と申します。まあ、好きになさい」とあっさり承諾した。
こうして、健人の奇妙な弟子入り生活が始まった。彼は来る日も来る日も古川老人の元へ通ったが、予想していたような爆笑の渦や、珠玉のギャグが飛び出すことは一切なかった。古川が健人に課した「修行」は、およそお笑いとはかけ離れたものばかりだった。
最初の修行は「石を褒める」ことだった。公園に転がっている、ごく普通の石ころを指差し、古川は言った。
「この石の、素晴らしいところを十個、言ってみなさい」
「はあ……? 石、ですか?」
「そうじゃ。ほれ、早く」
健人は戸惑いながらも、「ええと、形が丸くて……色が灰色で……」と捻り出すが、三つも言うと息が詰まった。古川はそんな健人を見て、ただ静かに微笑むだけだった。
次の修行は「雨漏りの音を聞く」ことだった。古川の住む古い木造アパートの一室で、天井の染みからぽたん、ぽたんと規則的に落ちる水滴の音を、ただひたすら二人で聞く。沈黙が部屋を満たす。健人は何か面白い一言を期待したが、古川は目を閉じ、まるで偉大な交響曲に耳を傾けるかのように、その音に集中しているだけだった。
健人の不満は募っていった。この老人は本当に『999』の実力者なのだろうか。もしかしたら、俺の能力の方がおかしいのかもしれない。苛立ちと失望が、彼の心をじわじわと蝕んでいく。彼は、高得点者にありがちな、難解なユーモアを自分に試しているのだと思い込もうとしたが、それにしては手応えがなさすぎた。
「師匠! いつになったら本当のユーモアを教えてくださるんですか! 石を褒めても、雨漏りを聞いても、誰も笑いませんよ!」
ある日、ついに我慢の限界に達した健人がそう詰め寄ると、古川はゆっくりと茶をすすり、静かに言った。
「佐藤くん。君は、なぜ笑いたいんじゃ?」
「え……? それは、人生が楽しくなるからです。退屈から解放されたいんです」
「そうか」
古川はそれ以上何も言わなかった。ただ、その横顔はひどく寂しげで、窓から差し込む夕日が、彼の深い皺を一層濃く映し出していた。健人はその時、老人の頭上に輝く『999』の光が、まるで救いを求める悲鳴のように見えた気がした。
第三章 ペーソスの涙
決定的な出来事が起きたのは、冷たい雨が降りしきる火曜日の夜だった。健人は、会社帰りに古川のアパートを訪ねた。修行という名目で、ただ一緒に夕食を食べるだけの約束だったが、呼び鈴を鳴らしても応答がない。ドアには鍵がかかっておらず、心配になった健人は、そっと中へ入った。
部屋の奥、雨漏りのバケツの隣で、古川は一人、小さなちゃぶ台に突っ伏していた。背中が小さく震えている。健人は息を殺して近づいた。古川の肩にそっと手を置くと、老人はびくりと体を揺らし、ゆっくりと顔を上げた。その顔は、涙と雨で濡れた窓ガラスのように、ぐしゃぐしゃに歪んでいた。彼の頭上の『999』が、弱々しい電灯の光を浴びて、悲しく揺らめいていた。
「師匠……?」
古川はしばらく何も言わず、ただ嗚咽を漏らしていたが、やがて途切れ途切れに語り始めた。その日は、三年前に亡くなった彼の妻、千代さんの命日だった。
「わしはな、あいつがいないと、どうやって笑ったらいいのかも分からんようになってしもうてな……」
古川は、千代さんとの思い出を語った。二人で見た映画、一緒に食べたおにぎりの味、些細なことで笑い合った日々。彼女を失ってから、世界から色が消え、音が消え、喜びが消えた。絶望の淵で、彼はただ死ぬことだけを考えていたという。
「そんな時、ふと思い出したんじゃ。あいつがよく言っておった。『どんなにつまらない日でも、一つだけ面白いことを見つけてから寝なさい』ってな。だから、わしは始めたんじゃよ。道端の石の面白い形を探したり、雨漏りの音を楽器だと思ってみたり……。必死でな。そうでもせんことには、悲しみに飲み込まれてしまいそうでのう」
健人は、雷に打たれたような衝撃を受けていた。全身の血が逆流するような感覚。
「佐藤くん。君に見えているその数字はな、『ユーモア指数』なんぞじゃない」
古川は、健人の目を見つめて、はっきりと言った。
「それは、『ペーソス指数』じゃ。その人間が抱える心の痛みを、どれだけの力で笑いに変えようと藻掻いているか……その、悲しい力の大きさを示す指数なんじゃよ」
ペーソス指数。哀愁の指数。
健人の頭の中で、これまでの光景がフラッシュバックした。上滑りなジョークを連発していた客引きの『110』。彼は生活の苦しみを、必死に笑顔で覆い隠していたのかもしれない。いつも明るかった新人、高橋さんの『85』。彼女もまた、見えない場所で何かと戦っていたのかもしれない。そして、退屈だと思っていた田中課長の『3』という数値は、彼が誰よりも満たされ、平穏な心で生きている証だったのだ。
健人は、自分がどれほど傲慢で、無神経だったかを思い知った。彼は人々の「面白さ」を値踏みしていたつもりで、実はその「痛み」の大きさを無邪気に測っていたのだ。そして、目の前のこの老人の『999』という数値は、ユーモアの極致などではない。それは、最愛の人を失った、耐え難いほどの巨大な悲しみの現れだった。世界で一番面白い人だと思っていた男は、世界で一番、悲しみを乗り越えようと戦っている男だったのだ。
健人の目から、熱いものが込み上げてきた。それは、自分の愚かさへの涙であり、古川の痛みに触れた共感の涙だった。
第四章 優しさの単位
世界の見え方が、完全に変わった。健人が今まで追い求めていたネオンカラーの数字は、今や痛々しい傷跡のように見えた。彼はもう、高得点者を探して街をさまようことはなくなった。代わりに、彼は人々の指数が示す、声なき声に耳を澄ませるようになった。
翌日、健人は古川のアパートを訪ねた。何も言わず、彼の隣に座り、一緒に雨漏りの音を聞いた。ぽたん、ぽたん。以前は退屈でしかなかったその音は、今や古川が奏でる魂の鎮魂歌のように聞こえた。
「師匠」健人は言った。「俺、石を褒める修行の続きがしたいです。今日は、あの角の、ちょっと平べったい石に挑戦させてください」
古川は驚いたように健人を見た後、ふっと、本当に嬉しそうに笑った。その瞬間、彼の頭上の『999』が、ほんの少しだけ、温かい色に変わったように見えた。
それから数週間、健人は古川と共に、日常に隠された小さな「素敵」を探す日々を送った。夕焼け雲の形を龍に見立てたり、道端の雑草の力強さを讃えたり。それはお笑いの修行ではなかったが、健人の乾いた心は、ゆっくりと潤いを取り戻していった。誰かを笑わせるのではなく、誰かの痛みに寄り添うこと。そこに、彼が本当に求めていた豊かさがあった。
ある朝、健人は出勤前に、ふと鏡で自分の姿を見た。今まで気にしたこともなかったが、自分の頭上にも指数はあるのだろうか。恐る恐る目を凝らすと、そこには、か細く、しかし確かに、淡い水色の数字が浮かんでいた。
『1』。
それは、ほとんどゼロに等しい、小さな小さな数値だった。しかし、健人はその数字を見て、胸が熱くなるのを感じた。以前の彼なら、測定不能の『0』だったに違いない。この『1』は、彼が初めて誰かの痛みに寄り添い、ほんの少しだけ世界を優しく見つめられるようになった証なのだ。それはユーモアの単位ではなく、優しさの単位だった。
会社に着くと、彼は廊下で新人、高橋さんとすれ違った。彼女の頭上には、相変わらず『85』が輝いている。以前の彼なら「高橋さん、今日も面白いね!」と声をかけていただろう。だが、今の健人は違った。彼は立ち止まり、彼女が身につけている小さなブローチに目を留めた。
「高橋さん。そのブローチ、鳥の形なんだね。すごく素敵だね」
高橋さんは一瞬きょとんとした顔をしたが、すぐに、はにかむような、心からの笑顔を見せた。
「……ありがとうございます、佐藤さん」
その笑顔は、どんな爆笑よりも、健人の心に温かく響いた。
世界は、必ずしも笑いで満ちているわけではない。誰もが、それぞれのペーソスを抱えて生きている。でも、ほんの少しの優しさで、世界は温かくなる。健人は、かつて自分が憎んだ退屈な日常が、今は愛おしいものに感じられることに気づいた。彼はもう、指数に振り回されることはないだろう。ただ、目の前の人の小さな「素敵」を見つけるために、明日も生きていく。空は灰色かもしれない。でも、その向こうにはきっと、優しい光が満ちている。健人は、静かにそう信じられるようになっていた。