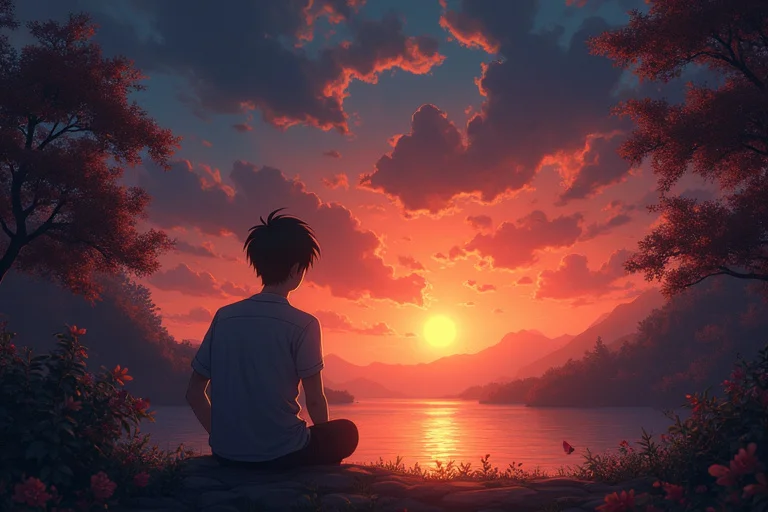第一章 錆びついた真実
世界は、腐りかけたシチューの味がする。
雨の日は特に酷い。
湿ったアスファルトから立ち昇る埃っぽさが、舌の根にへばりつくカビのような不快感に変わるからだ。
僕はキッチンで、銀色のシートから小さな錠剤を押し出した。
味覚遮断薬。
この白い粒だけが、僕の過敏すぎる舌を麻痺させ、世界を「無味」という安息で満たしてくれる。
だが、その錠剤を口に運ぶ手は、不意に止まった。
玄関の向こう。
ドアの隙間から、強烈な「気配」が侵入してきたからだ。
鉄錆。
古びた血。
そして、鼻の奥をツンと刺す、冷たいホルマリンの刺激臭。
僕は錠剤をシンクに弾き飛ばし、ドアを開けた。
そこには差出人のない小包が一つ、雨に濡れて置かれていた。
震える指で封を切る。
黒いベルベットのクッション。
その中央に、親指大の灰色の結晶が鎮座している。
『感情石』。
人が死ぬ瞬間に結晶化する、魂の残滓。
これが僕の元に届いた。
意味するところは一つしかない。
「リサ……」
視界が歪む。
脳裏に、彼女の笑顔がフラッシュバックした。
大学の帰り道、二人で分け合った肉まんの湯気。
「アオイの舌は特別なんでしょ? じゃあ、この幸せな味も、二倍に感じるのかな」
そう言って笑った彼女からは、春の陽だまりのような、温かいホットミルクの匂いがした。
なのに。
目の前の石から漂うのは、吐き気を催すほどの悪臭だ。
僕は躊躇い、けれど確かめずにはいられなかった。
石をつまみ上げ、その冷たい先端を、恐る恐る舌に乗せる。
刹那。
脳髄を直接殴られたような衝撃。
「ぐ、ぁああああ……ッ!」
ドロリとした汚泥が口内を蹂躙する。
内臓が裏返るような腐臭。
何万本の錆びた釘を飲み込んだような、喉を引き裂く激痛。
絶望。憎悪。孤独。
世界への呪詛が、味となって僕の神経を焼き尽くす。
僕は床に崩れ落ち、胃液を吐き出した。
違う。
こんなドブのような味が、あのリサの感情であるはずがない。
彼女は誰よりも世界を愛していた。
誰よりも、僕のこの呪われた能力を「才能」だと肯定してくれた。
「はぁ、はぁ……」
痺れる舌を袖口で拭う。
口の中に残る残滓。
腐った魚、泥、鉄錆。
その奥に――微かだが、決定的な違和感があった。
舌の先チリチリと焦がす、無機質な酸味。
それは感情の味ではない。
化学薬品だ。
高濃度のエーテルと、焦げた回路基板のような人工的な苦味。
誰かが、手を加えた?
リサの純粋な感情の上に、汚らわしい絶望をコーティングしたのか?
怒りが、身体の芯で熱い塊になった。
その熱が、麻痺しかけた四肢を無理やり突き動かす。
僕はよろめきながら立ち上がり、雨の降る街へと飛び出した。
第二章 連鎖する苦味
場末のバーの扉を開けると、紫煙と共に安いバーボンの甘ったるい匂いが漂ってきた。
カウンターの隅。
私立探偵の相馬が、氷の溶けたグラスを揺らしている。
「酷い顔だ。死人が歩いているのかと思ったぞ」
相馬は僕を一瞥し、眉間の皺を深くした。
「リサの石が届いた」
僕は隣のスツールに座り込むこともせず、カウンターに両手をついた。
「味が違うんだ、相馬。表面は絶望で塗り固められているが、核にある味が違う。あれは……作為的に作られた毒だ」
相馬は黙ってグラスを呷る。
その所作から、焦げたカラメルのような「諦念」の味がした。
彼は懐から一枚の写真を取り出し、カウンターに滑らせる。
最近多発している、原因不明の失踪者リストだ。
「警察は自殺で処理した。遺体は見つからず、遺族に石だけが送られてくる。『自動転送』のルール通りにな」
「僕もそう思った。でも、調べたんだ」
僕はポケットから、しわくちゃになったメモを取り出す。
この数時間、リストにある遺族の元を駆けずり回った記録だ。
「三件、回らせてもらった。遺族にお願いして、彼らに届いた石を舐めたよ」
相馬が目を見開く。
「正気か? 他人の絶望を舐めるなんざ、脳が焼き切れるぞ」
「焼き切れそうだったさ。でも、分かったんだ」
口の中に蘇る、幾重にも重なった他人の悲鳴。
だが、それら全ての底に、共通する「署名」が刻まれていた。
「全員、同じ味がした」
僕は乾いた唇を舐める。
「微量だが、確実に残っていた。特異なオゾン臭と、古い実験室の埃の味。そして何より……あの独特なミントタブレットの刺激臭」
相馬の表情が変わる。
彼もまた、その味に心当たりがあるのだ。
「……カイトか」
その名を口にした瞬間、舌の奥で苦い薬の味が弾けた。
天才的な脳科学者であり、かつて僕やリサと共に大学で過ごした男。
彼はいつも、強烈なミントタブレットを噛み砕きながら、世界の不完全さを嘆いていた。
『感情こそがバグだ。修正しなければならない』
彼の口癖が、薬品臭と共に蘇る。
「奴の研究室があった場所……湾岸の廃棄プラント跡か」
相馬が上着を掴んで立ち上がろうとするのを、僕は手で制した。
「一人で行く。これは僕と、リサと、あいつの問題だ」
「死ぬ気か」
「生きるために行くんだ。本当の味を取り戻しに」
相馬は短く息を吐き、座り直した。
「……勘定はツケとくぞ。必ず払いに来い」
背中に感じる相馬の味は、心配という名の、少し渋いお茶のような味だった。
第三章 希望のレシピ
廃棄プラントの鉄扉を押し開ける。
途端に、鼻をつくような金属臭と、張り詰めた電気の味が空気を支配した。
広大なホールの中心。
天井まで届く巨大なガラスシリンダーが鎮座している。
その内部では、虹色の流体が脈動し、不気味な心音のような重低音を響かせていた。
シリンダーの前、制御コンソールを操作する痩せた背中があった。
白衣は薄汚れ、床には空になった栄養剤のチューブが散乱している。
「……来たね、アオイ」
カイトが振り返る。
その瞳は充血し、焦点が定まっていない。
だが、彼から発せられる「味」に、僕は戦慄した。
狂気特有の腐敗臭ではない。
恐ろしいほどに純粋で、透明な、人工甘味料のような甘さ。
歪みきった正義の味だ。
「リサはどこだ」
カイトは愛おしそうにシリンダーを見上げた。
「そこにいるよ。世界を救うための、最も美しい核となってね」
僕はシリンダーを見上げる。
虹色の光の渦。
その中心に、胎児のように丸まり、眠っているリサのシルエットが透けて見えた。
「なんてことを……!」
「感じただろう? 君に送った石の味を」
カイトは恍惚とした表情で両手を広げる。
「あれは燃料の搾りかすだ。世界中から集めた『絶望』を凝縮し、その反動エネルギーで極大の『希望』を生成する。振り子と同じさ。大きく後ろに引くほど、前への推進力は増す」
彼はコンソールを叩く。
モニターに映し出される数値が、危険域へと跳ね上がっていく。
「だが、絶望を希望へと反転させるには、強靭な触媒が必要だった。純粋で、無垢で、誰よりも他者を想う魂がね」
「それが、リサだと?」
「彼女は志願したんだ」
カイトの声が、甘い毒のように鼓膜に絡みつく。
「彼女は泣いていたよ。君が、他人の汚い感情を味わうたびに削られていくのを見て。君を救うためなら、自分はどうなってもいいと。だから、このシステムの一部になった」
足元の床が抜けるような感覚。
リサが、僕のために?
あの、腐り落ちるような絶望の味の石は、彼女が僕をここへ導くために残した、最後のメッセージだったのか。
「完成まであと少しだ。この『希望の感情石』が発動すれば、世界中の負の感情は中和される。君の舌を苦しめる味も消え失せる。素晴らしい世界だと思わないか?」
「ふざけるな……!」
「ふざけてなどいない! 僕は君たちのために――」
カイトの叫び声が、工場の反響音にかき消される。
シリンダーの光が激しさを増し、虹色の流体が暴れ始めた。
リサが、目覚めようとしている。
最終章 琥珀色の選択
僕はカイトを無視し、シリンダーへと駆け寄った。
分厚いガラスに掌を押し当てる。
熱い。
ガラス越しでも伝わってくる、魂の震動。
僕は額をガラスに押し付け、そして、そっと舐めた。
舌先に広がる味。
それは、さっきの石とは似ても似つかぬものだった。
熟れすぎた桃の果汁。
雨上がりの森の匂い。
二人で海を見に行った時の、潮風の塩辛さ。
そして、古い図書館のページを捲る時の、静かで落ち着いた香り。
「……あぁ」
涙が溢れ出した。
これはリサだ。
紛れもない、僕が愛したリサの味だ。
カイトの言うような『希望』なんていう概念じゃない。
これは、もっと個人的で、切実で、どうしようもなく人間臭い『愛』の味だ。
脳内に、直接声が響く。
『アオイ、ごめんね』
謝らないでくれ。
君の味が、僕の身体中の毒を洗い流していく。
『このまま発動させて。そうすれば、あなたはもう苦しまなくて済む』
リサの意志が、シリンダーのエネルギーを解放しようとしている。
だが、僕は味覚で理解していた。
このエネルギーが解放されれば、触媒である彼女の魂は完全に燃え尽きる。
そして、彼女の愛に同調している僕の存在も、この光の中に溶けて消えるだろう。
それでもいい。
君のいない、泥のような味の世界で生き続けるくらいなら。
「カイト、お前の実験は失敗だ」
僕は振り返らずに言った。
背後でカイトが何か喚いているが、もうその声は遠い。
「これは『希望』なんかで制御できる代物じゃない。……二人分の『魂』だ」
僕はシリンダーの緊急排出レバーに手をかけた。
錆びついた冷たい鉄の感触。
だが、今の僕の手は熱く燃えている。
『アオイ……?』
「一緒に行こう、リサ。これ以上、君を一人にはさせない」
レバーを一気に引き下ろす。
轟音。
世界が白一色に染まる。
カイトの絶叫も、工場の軋みも、すべてが光の奔流に飲み込まれていく。
僕の身体が、指先から粒子となって解けていく感覚。
痛みはない。
あるのは、口いっぱいに広がる、懐かしくて泣きたくなるような甘さだけ。
初めてキスをした夜の、ミントの味。
喧嘩をした翌朝の、焦げたトーストと苦いコーヒー。
そして、最後に彼女が作ってくれた、少し塩辛いスープの味。
走馬灯のように駆け巡る味の記憶が、僕の意識を優しく包み込んでいく。
視界が消え、重力が消え、自分という輪郭が世界に溶け出した。
舌に残った最期の味は、きっと永遠に消えない。
それは、どこまでも澄み渡った、琥珀色の「ありがとう」の味だった。