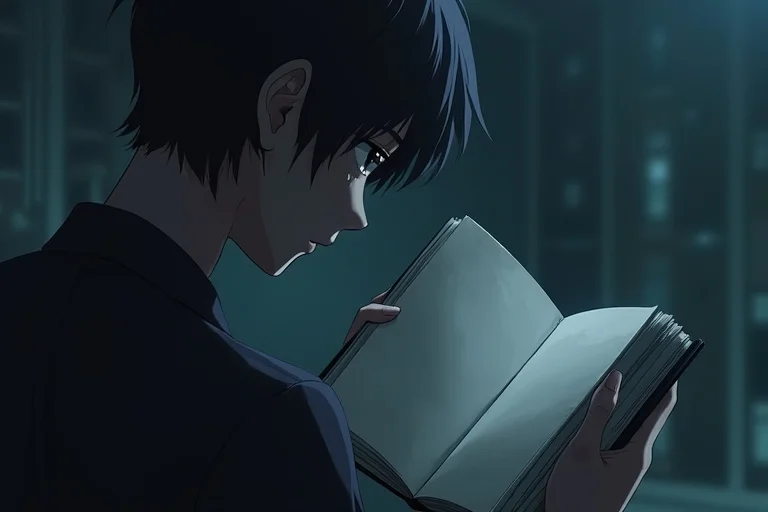第一章 空白からの手紙
三年前のあの日から、俺、倉田樹(くらた いつき)の世界には、ぽっかりと巨大な穴が空いている。転落事故。それが原因で失われたのは、二十歳から二十五歳までの、人生で最も輝いていたはずの五年間の記憶。鏡に映る二十八歳の自分の顔には、見覚えのない細かな皺が刻まれている。まるで、他人の人生を途中から引き継いだような、奇妙な浮遊感が常にまとわりついていた。
実家に戻り、両親の気遣いに甘えながら送る穏やかすぎる日々。だが、その静けさは、記憶という土台を失った建物の、危うい静けさに似ていた。空白の五年間に、俺は誰を愛し、誰に憎まれ、どんな罪を犯したのか。その恐怖が、夜ごと冷たい霧のように寝室に立ち込める。
季節が三度目の秋を迎えた日の午後だった。亡くなった祖母の部屋を片付けていた時、クローゼットの奥深くで、古びた桐の小箱を見つけた。埃を払い、錆びついた留め金を外すと、ふわりと古い紙の匂いがした。中に入っていたのは、十数通の封筒の束。どれも同じ、上質なクリーム色の便箋に、見慣れているはずなのに、どこか知らない他人のもののような、流麗な万年筆の文字で宛名が書かれていた。
『未来の倉田樹へ』
心臓が氷の塊を飲み込んだように冷たく、重くなった。差出人の名はない。だが、その筆跡は、紛れもなく俺自身のものだった。記憶を失う前の、俺が。
震える指で一番上の封筒を手に取る。封蝋(ふうろう)はなく、ただ糊付けされているだけだ。裏には小さな文字で『まず、これを』と書かれている。息を止め、封を切った。
一枚の便箋に綴られた、短い文章。
『これを読んでいるということは、お前は記憶を失くしたんだな。
それでいい。いや、それがいいのかもしれない。
だが、一つだけ思い出してほしいことがある。
僕が犯した、罪の記憶を。
僕が、誰を、どれほど深く傷つけたのかを。
これから送る追憶の旅が、その答えに導くだろう。
恐れるな。これは罰ではなく、お前がもう一度、本当のお前になるための儀式なのだから』
罪。その一文字が、胸の奥で鈍い音を立てて破裂した。やはり、そうだったのか。俺は忘却という安寧の陰で、許されざる過去から目を背けていただけなのだ。便箋を握りしめる手に、じっとりと汗が滲む。箱の底には、日付が記された残りの封筒が、まるで時限爆弾のように静かに横たわっていた。最初の指示は、三日後。俺は、過去の自分自身が仕掛けた、この残酷なミステリーの迷宮に、足を踏み入れるしかなかった。
第二章 追憶のコンパス
三日後、俺は最初の手紙に示された場所、海沿いの小さな街にあるジャズ喫茶『マイルス』の扉を開けた。カラン、とドアベルが乾いた音を立てる。午後の柔らかな光が差し込む店内には、燻された珈琲豆の香りと、サックスの低い音色が満ちていた。手紙には『いつもの席で、カフェ・グラッセを』とだけ書かれていた。
「いつもの席」がどこか分かるはずもない。だが、身体が覚えているかのように、足は自然と窓際の、港が一望できる二人掛けのテーブルへと向かった。注文したカフェ・グラッセが運ばれてくる。二層に分かれた黒と白のコントラストが、光と影を抱える今の俺の心象風景のようだった。
グラスを傾けた瞬間、脳裏を閃光がよぎった。
――陽光に透ける黒髪。笑うと細くなる目。グラスの水滴を指でなぞる、白く長い指先。
「樹くんの設計する家って、きっと陽だまりみたいに暖かいんだろうね」
鈴を転がすような、優しい声の残響。
頭が割れるように痛んだ。誰だ? 今のは、誰なんだ? 記憶の扉が軋み、ほんの少しだけ開いた隙間から、見知らぬ女性の幻影が漏れ出したかのようだった。
次の手紙が俺を導いたのは、プラネタリウムだった。暗闇の中、無数の星々が頭上に降り注ぐ。解説員の穏やかな声が、星座の神話を語っていた。その声が、不意に遠のいていく。
――『あの星、ベガっていうんだって。織姫星』
隣から聞こえる、ささやき声。見上げると、星の光を映した彼女の瞳が、宇宙よりも深く、澄んでいた。
――『じゃあ、僕はアルタイルだ。離れていても、君をずっと見ている』
そう囁いたのは、間違いなく俺の声だった。気障なセリフに、彼女がくすくすと笑う。その笑い声が、胸の奥深くにしまい忘れていた宝物のように、甘く切なく響いた。
手紙は、まるで追憶のコンパスだった。カフェ、プラネタリウム、古書店、建築事務所の跡地。訪れるたびに、俺はパズルのピースを拾い集めていく。ピースはどれも、同じ一人の女性の姿をかたどっていた。笹川美月(ささかわ みつき)。それが彼女の名前だと、なぜか確信できた。俺は彼女を深く愛していた。そして、手紙が示唆する「罪」とは、きっとこの愛しい女性に向けられたものなのだ。
俺は彼女を裏切ったのか? それとも、心ない言葉で傷つけたのか? ピースが集まるほどに彼女への愛しさが募り、それと同時に、罪の意識が鉛のように心を蝕んでいった。最後の目的地を示す手紙を開けるのが、怖かった。そこには、俺が最も知りたくない、残酷な真実が待っている気がしてならなかった。
第三章 星の降る場所
最後の手紙に記されていたのは、丘の上に立つ、建設途中で放棄されたビルの住所だった。三年前、俺が転落事故に遭った、因縁の場所。夕暮れの茜色が、コンクリートの無機質な骨組みを、物悲しく染め上げていた。風が吹き抜け、鉄骨が寂しげな音を立てて鳴いている。
指定されたフロアに上がると、そこに彼女はいた。
笹川美月。
記憶の中の幻影よりも少しだけ痩せて、どこか儚げな雰囲気をまとっていたが、あの優しい眼差しは変わっていなかった。三年間、彼女はどこで何をしていたのだろう。俺の目の前に現れた理由は何だ?
「樹くん」
懐かしい声が、俺の名前を呼ぶ。
「どうして、今になって……。手紙は、君が?」
「ううん。手紙は、あの頃の樹くんが書いたものよ。私が、お願いしたの」
彼女は静かに語り始めた。その言葉は、俺が組み立てていた悲劇のパズルを、根底から覆すものだった。
「樹くんの罪なんて、どこにもない。罪があるとしたら、それは私の方」
美月は、遺伝性の難病を患っていた。身体の自由が少しずつ奪われ、長くは生きられないという宣告を、事故の半年前に受けていたのだという。
「私は、絶望した。でも、樹くんは違った。私の全部を受け入れて、プロポーズしてくれた。『残りの時間を、世界で一番幸せな時間にしてみせる』って」
このビルは、その言葉の結晶だった。車椅子でも暮らしやすく、窓からは彼女が好きな港が見える。寝たきりになっても星空が見えるように、天井には天窓を。俺は、彼女のための「終の棲家」を、全身全霊で設計していたのだ。
「でも、私は怖くなった。あなたの未来を、私のせいで縛り付けてしまうのが。だから……この場所で、あなたに別れを告げたの」
あの日、彼女の言葉に逆上した俺は、「そんなことはさせない」と彼女の腕を掴んだ。それを振り払おうとした彼女がよろめき、庇おうとした俺が、足場から滑り落ちた。それが、転落の真相だった。
「手紙はね、保険だったの」と美月は涙を浮かべて微笑んだ。「もし、樹くんが記憶を失ったら……辛い事故の記憶も、私の病気のことも、全部忘れて、新しい人生を生きてほしかった。もし、思い出そうとして苦しむのなら、せめて、私があなたを恨んでいないこと、あなたのせいじゃないってことだけは、伝えたくて」
「僕の罪を思い出してくれ」
あの言葉の意味が、稲妻のように身体を貫いた。
それは、加害の記憶ではなかった。愛する人を、その腕で幸せにすることができなかった。守り切れなかった。過去の俺が背負おうとしたのは、そのどうしようもない「無力さ」という名の罪だったのだ。
手紙は、罰などではなかった。記憶を失った俺への、過去の俺からの、深すぎる愛と優しさの証明だった。俺は、その場に崩れ落ち、声を上げて泣いた。
第四章 忘却のポスト
涙が枯れる頃には、空には一番星が瞬いていた。俺は、記憶が戻らない頭で、しかし心の奥深くで燃え盛るような感情に突き動かされ、美月の前に立った。記憶という名のフィルムは、今も空白のままだ。だが、魂が、この身体が、目の前の女性を愛していると叫んでいた。
「美月さん」
俺は初めて彼女の名前を呼んだ。
「俺は、過去の俺じゃない。君と過ごした五年間の記憶もない。でも、一つだけ分かる。俺は、君を愛してる。記憶がないからこそ、過去の苦しみも、しがらみも、何もない。ゼロから、もう一度君を愛せる」
俺は彼女の冷たい手を、両手で包み込んだ。
「だから、お願いだ。君の残りの時間を、今度は今の俺にください。幸せにするとか、そんな大それた約束はできないかもしれない。でも、最期の一瞬まで、君の隣で笑っていたい」
美月の瞳から、大粒の涙がいくつもこぼれ落ちた。彼女は何も言わず、ただ何度も、強く頷いた。
後日、俺は実家の自室で、古い図面ケースを開いた。中には、記憶を失う前の自分が描いた、美月のための家の設計図が眠っていた。美しい曲線で描かれた間取り、光を取り込むための大きな窓、そして、天井の天窓。そこには、彼女への愛が、技術という名の言葉でびっしりと書き込まれていた。
俺は鉛筆を手に取り、その設計図の上に、新たな線を一本、書き加えた。
記憶は失われた。だが、愛する人を想い、それを形にするための知識と技術は、この指先に、確かに宿っていた。
過去の俺からの手紙が届くポストは、もう空っぽだ。
これからは、俺が未来を描く番だ。美月と共に歩む、新しい未来を。
忘却は、罰ではなかった。それはきっと、愛をもう一度、最も純粋な形で始めるために神様がくれた、残酷で、そして優しい贈り物だったのだ。