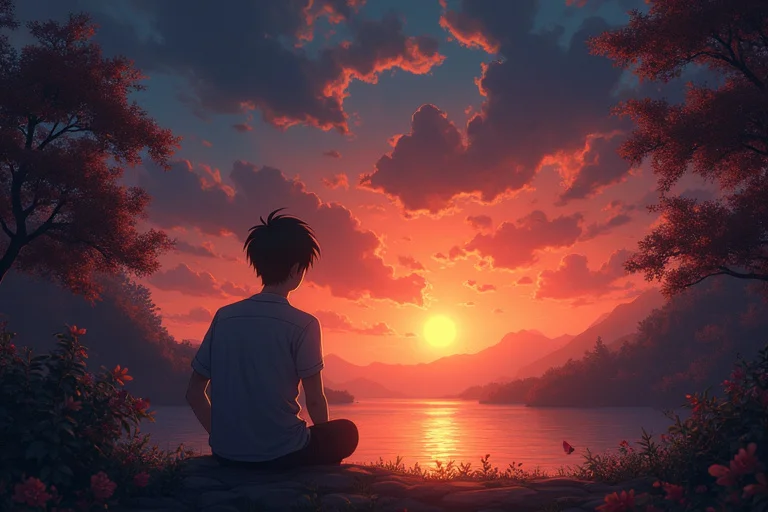第一章 濁色の弔辞
響野律(きょうの りつ)の世界は、常にくすんだ黄土色に汚されていた。それは共感覚の一種であり、彼にだけ見える特殊な色だった。人が嘘をつく瞬間、その言葉は濁った黄土色のオーラを纏って律の目に映るのだ。まるで、真実を覆い隠す泥水のように。この能力のせいで、律は幼い頃から人間という存在に絶望し、いつしか他人と深く関わることを諦めていた。古書の修復師という仕事は、そんな彼にとって天職だった。死んだ作家の言葉は嘘をつかない。静寂な工房で、ひび割れた革の背表紙や、インクの染みが滲んだページと向き合う時間だけが、彼に安らぎを与えてくれた。
その安らぎを根底から覆す報せが届いたのは、冷たい雨がアスファルトを濡らす火曜日の午後だった。律にとって唯一の友人であり、彼の秘密を知る数少ない理解者、古物商『有馬堂』の店主・有馬宗助が亡くなったという。警察からの電話は事務的で、発見時の状況から病による突然死と判断された、と告げた。享年七十八。老齢ではあったが、一週間前に会った時の有馬は、いつものように冗談を飛ばし、新しい骨董品の自慢をしていた。その矍鑠とした姿が、律の脳裏から離れなかった。
数日後、律は有馬堂で営まれたささやかな弔問に足を運んだ。線香の香りが、古い木の柱や埃っぽい調度品の匂いと混じり合い、独特の鎮魂の空気を作り出している。有馬の遠縁だという中年女性が、涙ながらに律に語りかけた。
「あんなにお元気だったのに…。本当に、突然のことで…」
その言葉が、律の目にはっきりと見えた。濃い黄土色の靄が、彼女の口元からゆらりと立ち上る。律は無言で会釈を返した。まただ。なぜ、人は死者の前でさえ、こうも平然と嘘を重ねるのか。
有馬の商売敵だったという男は、「惜しい人を亡くした。この界隈の灯火が一つ消えたようだ」と沈痛な面持ちで言った。その言葉もまた、濁った色に染まっていた。有馬に借金があったという若い男は、「本当にお世話になりました。恩返しもできないままなんて…」と俯いた。彼の言葉からは、これまで見た中で最も濃く、粘りつくような黄土色の煙が立ち上っていた。
誰もが悲しみの仮面を被り、その下で嘘を吐いている。律の胸に、冷たい疑念が芽生えた。警察は病死と結論づけた。だが、この店に渦巻く澱んだ嘘の色は、まるで単純な死ではないと訴えかけているようだった。有馬宗助は、本当に安らかに逝ったのだろうか。それとも、この濁色の嘘の向こうに、誰にも知られていない醜い真実が隠されているのだろうか。律は、閉ざしていたはずの心の扉が、軋みを立てて開くのを感じていた。友の死の真相を、この忌まわしい能力を使ってでも、突き止めなければならない。そう強く決意した。
第二章 虚飾の万華鏡
律の調査は、有馬の死を取り巻く人々の嘘を一つずつ剥がしていくことから始まった。それはまるで、無数の嘘が乱反射する万華鏡を覗き込むような、眩暈のする作業だった。
まず、最初に話を聞いたのは、有馬の孫娘だという大学生の女性だった。彼女は祖父の死を悲しみながらも、「おじいちゃん、最近少し物忘れがひどくて…。持病の薬も飲み忘れることがあったみたいなんです」と語った。その言葉は真実だった。色は見えない。だが、律が「何か変わったことはありませんでしたか?例えば、誰かと揉めていたとか」と尋ねると、彼女は一瞬目を伏せ、そして言った。「いえ、特に…。おじいちゃんは誰からも好かれていましたから」。嘘だ。彼女の言葉は、淡いが確かな黄土色を帯びていた。彼女は何かを知っている。あるいは、何かを隠している。
次に訪ねたのは、有馬の商売敵だった男の店だ。男は律の来訪を訝しげに迎えながらも、「有馬の旦那には、一度だけしてやられたことがある」と苦々しく語り始めた。ある希少な万年筆の競売で、有馬が巧妙な駆け引きの末に競り落としたのだという。「だが、それは商売上のこと。恨みなんてないさ」。その言葉に嘘の色はなかった。しかし、律が「有馬さんが亡くなる直前、彼が何か特別なものを探していたという話は聞きませんでしたか?」と核心に近づくと、男は急に口を閉ざし、「さあな。俺の知ったことじゃない」と吐き捨てた。濁った黄土色が、彼の全身を覆うように見えた。
誰もが何かを隠している。借金をしていた若い男は、律が訪ねると露骨に怯え、震える声で「俺じゃない!俺は何もしていない!」と叫んだ。彼の言葉は激しく嘘の色を放っていたが、それは殺人を否定する嘘なのか、それとも別の何かを隠すための嘘なのか、律には判別できなかった。
能力は、嘘の存在を教えてはくれるが、嘘の理由までは教えてくれない。律は苛立ちと無力感に苛まれた。人々が吐く嘘は、悪意、保身、嫉妬、虚栄心、様々な感情が混じり合った濁流となり、律を飲み込もうとしていた。嘘が見えれば見えるほど、真実は遠のいていく。人々はなぜこうも複雑なのだろう。なぜ、ありのままを語れないのだろう。彼の人間不信は、確信へと変わりつつあった。世界は、やはり救いようのない嘘で出来ているのだ。
調査の過程で、律は有馬の工房の片隅に、鍵のかかった古い木箱を見つけた。孫娘に頼み、鍵を開けてもらうと、中には律が修復した古書と、数本のインク瓶、そして一冊の真新しい日記帳が入っていた。日記の最後のページには、走り書きのような文字があった。
『幻影のインクは、遂に見つからず。だが、律、君になら、最後の謎が解けるはずだ』
幻影のインク。そして、最後の謎。それは、友が律に遺した挑戦状のように思えた。
第三章 幻影インクの告白
「幻影のインク」。その言葉を手がかりに、律は古書やインクの専門家を訪ね歩いた。そして、ある老いたインク職人から、その正体を聞き出すことができた。それは、かつて欧州の密使たちが用いたとされる特殊なインクで、二種類の液体から成るという。第一のインクで書かれた文字は、時間が経つと消えてしまう。しかし、そこに第二のインクを塗布すると、全く別の、予め仕込まれていたメッセージが浮かび上がるのだという。まさに幻影の名にふさわしい代物だった。
律は有馬の遺した日記帳を手に、自身の工房へ戻った。日記はほとんど白紙だったが、最後のページに例の走り書きがあるだけだ。もしや、と思い、律は紫外線ランプを取り出した。特殊なインクの中には、紫外線に反応するものがある。ランプの紫光を日記帳に当てた瞬間、律は息を呑んだ。
何も書かれていなかったはずのページに、青白い光を放つ文字がびっしりと浮かび上がっていたのだ。それは紛れもなく、有馬の筆跡だった。律は震える手でページをめくった。そこに綴られていたのは、事件の真相などではなかった。それは、律に向けた、有馬宗助の最後の告白だった。
『親愛なる律へ。この手紙を読んでいるということは、君は私の死の謎を追ってくれているのだろう。すまない。君をこんな形で巻き込んでしまって。だが、どうしても君に伝えたいことがあったんだ』
日記には、有馬が自身の癌を知り、余命宣告を受けていたことが記されていた。彼は自らの死期を悟っていたのだ。
『君の持つ力は、君から多くのものを奪った。人の温もり、信じる心、穏やかな日常。私はずっと、それがたまらなく悔しかった。君に、もう一度世界を信じてほしかった。だから、私は最後の賭けをすることにした。私の死を、君への最後の贈り物にしようと決めたんだ』
律は、心臓を鷲掴みにされたような衝撃に襲われた。ページを繰る指が止まらない。
『私は、私の死後に関わるであろう人々に、あるお願いをした。孫娘には、私の物忘れがひどかったと嘘をついてくれと。商売敵の彼には、私が探していたインクについて知らないふりをしてくれと。そして、借金のあったあの青年には、金のことで私と揉めていたかのように振る舞ってくれと。皆、最初は戸惑っていたが、私の最後の我儘だと伝えると、固い約束を交わしてくれた。彼らは皆、君に嘘をつくだろう。君は、その嘘の色を見るだろう。だがな、律。よく見てほしい。彼らのつく嘘は、悪意から生まれたものではない。それは、死にゆく老人との約束を守るための、誠実で、不器用で、そして優しい嘘なのだと』
事件など、どこにも存在しなかった。律が追いかけていたのは、殺人犯の影ではなく、友が仕掛けた壮大なフィナーレだったのだ。孫娘は、祖父の死が病による穏やかなものだったという事実を隠すために。商売敵は、有馬が律のために「謎」を用意しているという計画を守るために。借金の青年は、有馬から「この金は返さなくていい。その代わり、俺の友人のために一芝居打ってくれ」と頼まれた恩義に報いるために。
彼らのついていた嘘は、すべて有馬を想う心から生まれたものだった。律が忌み嫌い、絶望の象徴として見ていたあの濁った黄土色は、友情や、誠実さや、優しさの色でもあったのだ。律は、日記帳の上に突っ伏した。嗚咽が漏れる。頬を伝う熱い雫が、インクの文字を滲ませていった。
第四章 嘘の向こう側
数日後、律は有馬の墓前に立っていた。雨上がりの空はどこまでも青く澄み渡り、墓石を濡らした雫が陽光を反射してきらきらと輝いている。律は、買ってきた花を供え、静かに手を合わせた。
「有馬さん、あなたの勝ちですよ」
律はそっと呟いた。声は、不思議なほど穏やかだった。
彼の目には、今も世界が嘘の色に満ちて見えている。新聞を読む政治家の言葉も、テレビで微笑むタレントの笑顔も、街ですれ違う人々の他愛ない会話も、相変わらず黄土色に汚れている。だが、その色の見え方が、以前とは決定的に違っていた。
あれは、単なる「嘘」の色ではなかったのだ。それは、様々な感情が混じり合った、複雑な人間の心そのものの色だった。自分を良く見せたいという見栄。相手を傷つけまいとする配慮。苦しい現実から目を背けたいという弱さ。そして、友との約束を守り抜こうとする、不器用な優しさ。黄土色の中に、赤や青や緑の、微かな感情のグラデーションが見えるような気がした。
律は、ゆっくりと顔を上げた。有馬が遺してくれた最後の謎解きは、事件を解決するためではなく、律自身の凝り固まった心を解きほぐすためのものだった。彼は、律に「嘘」そのものではなく、「嘘の向こう側」にあるものを見てほしかったのだ。
人間不信が完全に消えたわけではない。世界は依然として複雑で、不可解なままだ。しかし、律はもう、ただ絶望するだけではなかった。この忌まわしいと思っていた能力で、嘘の奥にある、時に温かく、時に切ない真実を探してみよう。そう思えるようになっていた。
工房に戻る道すがら、律はカフェのテラス席に座るカップルを見かけた。
「君の作る料理が、世界で一番好きだよ」
男の言葉が、鮮やかな黄土色を放った。以前の律なら、心の中で嘲笑していただろう。だが今の彼には、その色が、恋人を喜ばせたいという愛しい見栄の色に見えた。
律は、小さく笑みを浮かべた。空は青く、風は心地よい。有馬宗助という男が愛した世界は、思っていたよりも、ずっと豊かで、愛おしいのかもしれない。彼のレクイエムは、決して悲しみの歌ではなかった。それは、孤独だった友の心に、新しい光を灯すための、希望の歌だったのだ。