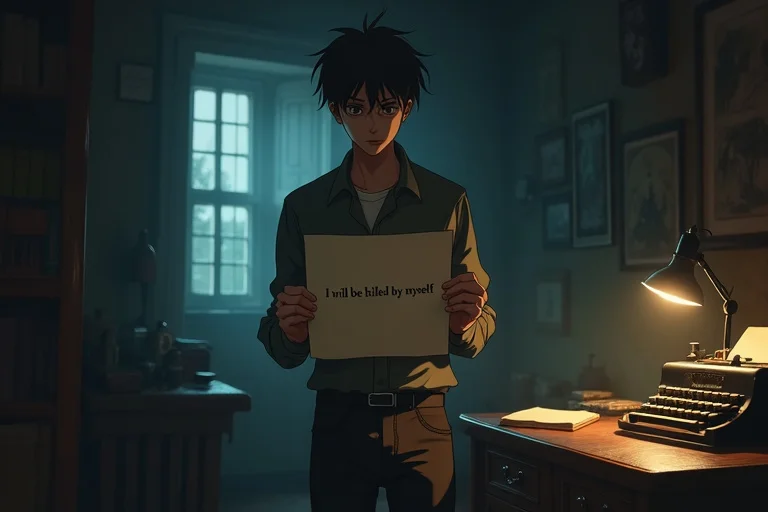第一章 錆びついた心臓の音
時枝陽(ときえだ あきら)の仕事場は、埃とオイルの匂いが混じり合う、静かな時間の澱の中にある。彼は古物修復師だった。傷ついた家具や動かなくなった玩具に触れ、その指先で過去の記憶をなぞる。彼の指は、ただの修復師のものではなかった。
机上の、脚が一本折れた木馬。陽がそっとその滑らかな背に触れると、視界の端が陽炎のように揺らめいた。楽しげな子供の笑い声、陽だまりの匂い、そして次の瞬間、粗大ゴミとして打ち捨てられる冷たい雨の日の光景が、脳裏を閃光のように過る。彼には、時間が逆行している物体――本来の時間の流れに逆らって朽ちていくもの、忘れ去られようとしているもの――に触れると、その物体がたどるはずだった、最も可能性の高い「未来」を幻視する能力があった。それは呪いにも似た祝福だった。
「陽くん、いる?」
扉が軋み、茅野栞(かやの しおり)が顔を覗かせた。彼女は大学で時間残滓を研究する物理学者で、この静かな工房の数少ない訪問者だった。その手には、鈍い光を放つ真鍮製の物体が握られている。
「面白いものを見つけたの」
栞がテーブルに置いたのは、古びた懐中時計だった。だが、文字盤には針が一本もなく、滑らかな真鍮の円盤があるだけだ。陽が眉をひそめると、栞は悪戯っぽく笑った。
「開けてみて」
蓋を開けると、複雑な歯車が剥き出しになっていた。それらは止まることなく、まるで生命を宿した虫のように、不規則かつ微細な振動を続けている。カタカタ、というよりは、キーンという微かな高周波に近い音が、陽の鼓膜を震わせた。
陽はごくりと喉を鳴らし、震える指先でその時計に触れた。
瞬間、世界が反転した。
轟音。無数の悲鳴。ガラスの割れる音。そして、全ての色と音を飲み込む、巨大な白い光。それは未来の幻視だった。だが、今まで見てきたどんなものよりも鮮烈で、暴力的で、そして――絶望的だった。彼は弾かれたように手を離し、激しく咳き込む。心臓が、まるでこの時計の歯車のように、不規則に胸を打っていた。
第二章 地図にない一点
「残滓酔いだわ。大丈夫?」
栞が差し出した水を飲み干し、陽はようやく呼吸を整えた。彼女の瞳には、心配の色と共に、抑えきれない知的好奇心が燃えている。
栞は研究室のホログラムディスプレイを起動させた。無数の光点が地球儀の表面を覆い、その全てがゆっくりと、だが確実に、太平洋上の一点へと収束していく様が映し出される。
「一週間前から、世界中の時間残滓観測装置が、この一点を指し示し始めたの。まるで、全ての過去が、この場所に吸い込まれていくみたいに」
その座標は、既存のいかなる地図にも存在しない、完全な「空白」だった。
「この異常現象と、その懐中時計は繋がっている。私はそう確信してる」
陽は再び、テーブルの上の懐中時計に目をやった。先ほどの幻視の残滓が、網膜に焼き付いて離れない。あの白い光は、一体何だったのか。
「この時計…生きているみたいだ」
「ええ。そして、何かに反応している」
栞が言う通り、時計の内部の歯車は、先ほどよりも明らかに振動を増していた。キーンという金属音が、工房の静寂を切り裂くように響いている。まるで、遠いどこかからの呼び声に、必死に答えようとしているかのように。それは道標であり、同時に、破滅へのカウントダウンのようにも聞こえた。
第三章 揺らぐ聖域
懐中時計の微細な振動は、コンパスの針のように、陽と栞を導いた。二人がたどり着いたのは、街の外れに打ち捨てられた古い教会だった。蔦に覆われた石壁、割れたステンドグラスから差し込む光が、床に積もった厚い埃の上に、幻想的な模様を描き出している。ここは時間残滓が異常なほど濃密に渦巻く場所だった。
陽が教会の中心に足を踏み入れた途端、懐中時計が激しく震えだした。
「すごい…共鳴しているわ!」
栞が息をのむ。陽が時計を祭壇にかざすと、歯車の振動は最高潮に達し、甲高い共鳴音が空間そのものを震わせた。目の前の空間が、水面のようにぐにゃりと歪む。石造りの壁の向こうに、一瞬だけ、あり得ない風景が映し出された。どこまでも続く白い砂浜、ターコイズブルーの穏やかな海、そして空には、二つの太陽が浮かんでいた。
「あれが…空白の座標…?」
だが、その光景を認識する間もなく、陽は強烈な残滓酔いに襲われた。木馬から感じた子供の笑い声、時計が見せた破滅の光景、そしてこの教会で祈りを捧げたであろう無数の人々の喜びと悲しみが、奔流となって彼の意識に流れ込んでくる。現実と記憶の境界が溶けていく。彼は膝から崩れ落ちた。
第四章 最後の僕からの警告
「陽くん、しっかりして!」
栞の叫び声が、混濁する意識の彼方から聞こえる。陽は朦朧としながら、何かを探すように床に手を這わせた。指先に、冷たく、硬い感触が触れた。祭壇から零れ落ち、床の冷たさで固まった一滴の蝋。それは、溶けて固まるという順行の時間ではなく、床から祭壇へとその姿を遡るかのように、僅かに逆行の気を帯びていた。
彼は、無意識にそれを握りしめた。
そして、究極の幻視が、彼を呑み込んだ。
そこは、見覚えのある、しかし完全に荒廃した研究室だった。窓の外は、全てが色を失った灰色の世界が広がっている。そして、巨大な装置の前に立つ、一人の老人。深く刻まれた皺、疲れ果てた瞳。だが、その顔は紛れもなく、未来の自分自身だった。
老いた陽は、震える手で、あの「無時針の懐中時計」を握りしめている。彼はゆっくりと装置の起動スイッチに指をかけ、過去へと語りかけるように、静かに呟いた。
「これで、やり直せる。……頼む、気づいてくれ」
スイッチが押される。装置が眩い光を放ち、世界中のあらゆる物体から、時間残滓が糸のように引き抜かれ、光の中へと吸い込まれていく。過去が消えていく。記憶が、歴史が、人々の生きた証が、全て無に帰していく。
これが、世界の時間的な崩壊、「大消失」。
そして、その光が全てを飲み込む寸前、老いた陽は、過去を見つめるように、真っ直ぐに幻視の中の陽を見つめ、哀しげに微笑んだ。
第五章 時間収束点の真実
幻視から引き戻された陽は、ぜえぜえと肩で息をしていた。涙が頬を伝っている。栞が心配そうに彼の顔を覗き込んでいるが、言葉が出てこない。
パズルのピースが、恐ろしい形で組み上がっていく。
「空白の座標」は、自然にできたものではない。未来の僕が、意図的に作り出した「時間収束点」だったのだ。
いずれ訪れる「大消失」。全ての時間残滓が消滅し、過去も未来も、意味をなさなくなる世界の終わり。それを回避するため、未来の自分は、最後の手段に出た。世界が完全に崩壊する前に、全ての時間残滓を強制的に一点へと集約させ、時空に巨大な歪みを作る。
それは、過去の自分――今の陽――に世界の危機を知らせるための、未来からの"警告"。
そして、その歪みの中心へと自分を導くための、未来の自分が最後に残した"道標"。
あの懐中時計は、未来の陽が、過去の自分に残した唯一の手がかり。時空を超えて送られた、バトンだったのだ。
第六章 二つの未来
「…どういうことなの?何が見えたの?」
栞の問いに、陽はゆっくりと顔を上げた。彼の瞳には、先ほどまでの混乱はなく、嵐の後のような静けさと、あまりにも重い覚悟が宿っていた。
彼は、幻視した全てを栞に語った。大消失の未来、老いた自分の最後の選択、そして、この世界に与えられた猶予が、もういくばくもないことを。
「僕が行かなければならない。あの座標へ」
「行って、どうするの?未来のあなたと同じことを繰り返すの?」栞の声が震える。
「分からない」陽は正直に答えた。「でも、何もしなければ、全ての過去が消える。人々が生きてきた証、愛した記憶、過ちから学んだ教訓、その全てが…。それだけは、駄目だ」
未来の陽は、過去を守るために、全ての時間残滓を一点に封じ込めた。だがそれは、人々が過去の記憶にアクセスする術を永遠に失うことを意味する。それは本当に救済なのだろうか。それとも、別の形の喪失に過ぎないのではないか。
幻視は、最も可能性の高い未来。だが、決して確定した未来ではない。
まだ、変えられるかもしれない。
別の道があるかもしれない。
「一つだけ、分かっていることがある」
陽は立ち上がり、栞の目を真っ直ぐに見つめた。
「未来の僕は、僕に託したんだ。この世界の、過去と未来の全てを」
第七章 夜明けのコンパス
夜が明けようとしていた。東の空が、深い藍色から、柔らかな乳白色へと変わり始めている。廃教会の外の空気は、夜の名残でひどく冷たかった。
陽は、旅の支度を終えていた。背負ったリュックは重くない。必要なものは、もう全て持っているからだ。
彼の手の中には、あの「無時針の懐中時計」が握られている。その振動は、今はもう穏やかだった。だが、確かな意志を持って、一つの方向を指し示している。空白の座標へ続く、まだ誰も知らない道を。
「本当に、一人で行くの?」
栞が、不安を隠しきれない声で言った。
「ああ」陽は頷く。「これは、僕自身の過去と未来に関わる問題だから」
彼は微笑んだ。それは、未来の自分が最後に見せた、あの哀しい微笑みとは違う、どこか吹っ切れたような、穏やかな笑みだった。
「大丈夫。僕は過去を消させはしない。でも、未来の可能性も、諦めない」
それがどんなに困難な選択を強いる道であろうとも。
陽は栞に背を向け、歩き出した。夜明けの光が、彼の進む道を、細く、長く照らし出している。
彼の手の中にあるコンパスには、針がない。だが、その微かな振動だけが、彼が守ろうとしている過去と、これから彼が創り出すべき未来の、両方を指し示しているようだった。その旅の果てに何が待っているのか、今はまだ、誰にも分からない。