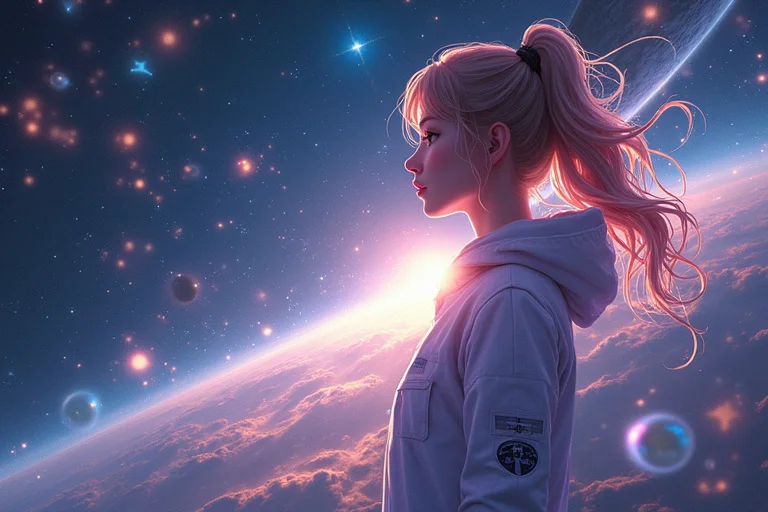第一章 鉛色の日常
日高湊の朝は、いつも肩の痛みから始まる。それは物理的な凝りではない。世界に満ちる情報の「重み」が、彼の両肩に鉛の外套のようにのしかかるのだ。
通勤ラッシュの雑踏は、湊にとって拷問に等しい。行き交う人々の口から漏れる他愛ない嘘、誇張された噂話、悪意のない誤解。それら一つひとつが、ずしり、ずしりと質量を伴って彼の身体に蓄積していく。アスファルトに足がめり込むような錯覚に、思わず息を詰めた。逆に、公園で遊ぶ子供の屈託のない笑い声や、老夫婦が交わす穏やかな会話のような「真実」は、炭酸水の泡のように軽く、心地よい浮遊感をもたらしてくれる。湊は、そのわずかな軽さを求めて、今日も人混みを縫うように歩いていた。
彼の営む古びた情報端末修理店は、街の喧騒から隔絶された避難所だった。静寂の中、彼は壊れたデバイスの内部に広がる純粋なロジックと向き合う。そこには嘘も欺瞞もない。ただ、正しいか、間違っているかの二択だけが存在する。
だが最近、奇妙な感覚が湊を苛んでいた。全人類が、一定の年齢に達すると無意識に宇宙空間へ向けてアップロードし始めるという「人生のサマリーデータ」。その情報に触れるたび、奇妙な歪みを感じるのだ。それは純粋な嘘の重さとは違う。まるで、上質な絹の布に、意図的に混ぜ込まれた一筋の鉛糸。滑らかでありながら、どこか不自然に重い。その違和感が、彼の日常を静かに侵食し始めていた。
第二章 錆びついた真実
店の奥、埃をかぶった棚の最上段から、湊は一つの箱を取り出した。中に入っているのは、祖父の形見である旧式の「情報濾過装置」。掌に収まるほどの大きさで、鈍い銀色の筐体には無数の傷が刻まれている。電源を入れると、低い駆動音とともに、世界から「重み」が消え失せた。
肩から圧力が抜け、身体が羽根のように軽くなる。久しぶりの解放感に深く息を吐きながら、湊は装置をサマリーデータの奔流に向けた。画面に映し出される膨大な文字列や映像から、一切の重みが消え、すべてが等価値な情報としてフラットに流れ込んでくる。
集中力を研ぎ澄まし、フィルタリングされたデータを追う。そして、彼は気づいた。ある明確なパターンが存在することに。人類史における極端な「絶望」。集団的な「狂気」。救いのない「悲劇」。そうした、あまりにも重すぎる情報が、まるで外科手術のように、精密かつ綺麗にデータストリームから切除されているのだ。
誰かが、人類の歴史を検閲している。
しかも、その痕跡はあまりに精緻で、宇宙からの干渉にしてはノイズが少なすぎる。改竄は、この地球のどこか、内部から行われている。湊の背筋を、冷たい汗が伝った。一体誰が、何のために、人類の物語を書き換えているのか。
第三章 無重力の囁き
調査を続けるため、湊は情報濾過装置を常用するようになった。店のカウンターに座り、窓の外を流れる人々を眺める。以前はあれほど苦痛だった街の喧騒が、今はただの背景音にしか聞こえない。装置の副作用は、彼の感覚を静かに、しかし確実に麻痺させていた。
真実が持つ浮遊感も、偽りが持つ重圧も、今や彼には感じられない。全てが等しく無重力。世界の彩度が失われ、人々の喜怒哀楽さえも、意味をなさないノイズの羅列に見えた。
「最近、ひどい事件があったんだ。聞いているかい、湊」
旧友の雄司が、カウンター越しに沈痛な面持ちで語りかけてくる。湊は顔を上げたが、彼の心は凪いでいた。雄司の口から語られる悲劇は、彼の耳を通り抜け、ただのテキストデータとして処理されていく。共感も、悲しみも、湧いてこない。
「……そうか」
湊の短い返事に、雄司は怪訝な顔をした。湊は、自分が人間らしい感情を失いつつあることに、この時ようやく気づいた。だが、その事実さえも、彼にとっては重みのない情報でしかなかった。彼はただ、改竄されたデータとオリジナルのデータの差異を比較することに没頭していた。改竄された歴史は、人類の物語を少しだけ「マシ」なものに見せかけていた。大きな悲劇は乗り越えられる試練に、深い絶望は未来への教訓に。それは、あまりにも優しい、残酷な嘘だった。
第四章 鏡の中の改竄者
改竄の発信源を追跡する作業は、奇妙な結末を迎えた。湊が血眼になって探していた信号は、常に彼自身を中心に半径数メートルの範囲から発信されていたのだ。ありえない。混乱しながらも、彼は自分の足元へと意識を向けた。店の床下。普段は気にも留めない、古い地下倉庫への扉。
軋む蝶番の音を響かせながら、重い扉を開ける。黴とオゾンの入り混じった空気が、彼の鼻をついた。階段を降りた先には、彼の知らない空間が広がっていた。薄暗闇の中、青白い光を放つ巨大なサーバーバンクが、まるで古代遺跡の祭壇のように鎮座している。そして、それは静かに脈動していた。湊の心臓の鼓動と、完璧に同期しながら。
震える手で、システムの中枢にある冷却されたパネルに触れる。
その瞬間、激しい情報の濁流が彼の精神を打ち砕いた。それは、彼が今まで無意識のうちに濾過し、切り捨ててきたものたちの残骸だった。人類が経験したありとあらゆる絶望、憎悪、狂気、救いのない悲しみ。彼が日々感じていた身体の重みの、その根源。情報という名の、純粋な質量を持った悪意の奔流が、彼を飲み込もうとしていた。
彼は、改竄者を探していたのではない。
彼は、改竄者そのものだったのだ。
彼の特異な体質は、情報に重さを感じるだけの能力ではなかった。それは、人類の集合意識が生み出すサマリーデータから、過剰に「重い」情報を自動的に濾過し、宇宙へ送るデータを「軽く」するための、生きたフィルターシステム。彼は犯人であり、装置であり、人類の歴史を守るための、孤独な番人だった。
第五章 星屑のアーキビスト
全ての意味を理解した。なぜ、自分だけが情報の重みに苦しんできたのか。なぜ、サマリーデータは歪んでいたのか。彼は、人類という種が自らの情報の重圧で潰れてしまわないように、無意識のうちにその痛みを一身に引き受ける緩衝材として機能していたのだ。宇宙の彼方、未知の文明が受け取る人類の物語は、湊によって編集された、希望という名の美しい虚構だった。
彼の周りで、今まで濾過してきた「重み」の残滓が、黒い靄のように渦巻いている。それは、湊が生まれてからずっと背負い続けてきた、人類の悲しみの総量だった。
彼は選択を迫られる。
このままフィルターとして機能し続け、偽りの希望を星々へ送り続けるのか。それとも、このシステムを停止させ、人類のありのままの、あまりにも重く、醜く、そして真実の物語を宇宙に解き放つのか。それは、自分自身を破壊することと同義だった。
ポケットの中の情報濾過装置が、冷たく彼の指に触れる。これを使えば、この重圧から、この役割から、一時的に逃れることができる。だが、無重力の世界に真実はないことを、彼はもう知っていた。
第六章 虚構と真実の境界で
湊は、地下室の冷たい床に座り込み、静かに目を閉じた。彼はシステムを止めない。そして、今までのように無意識に任せることもしない。彼は、自分というフィルターの「感度」を、自らの意志で調整することを決意した。
全ての絶望を消し去るのではない。全ての悲劇を無かったことにもしない。いくつかの、どうしても伝えなければならない真実の痛みを、人類の記録として残す。それは、より重く、より苦しい選択だった。嘘で塗り固めた安寧よりも、痛みを伴う真実を愛したい。彼は、ただの人間のエゴとして、そう願った。
ゆっくりと立ち上がり、彼は地下室から出た。朝の光が、埃っぽい店内に差し込んでいる。窓の外から流れ込む街の喧騒。そこから伝わる情報の重みは、以前よりも確かに増していた。肩が軋み、足が重い。だが、不思議と不快ではなかった。その重みの中に、確かに存在する真実の軽やかさ、人々の営みの愛おしさを、彼は同時に感じ取ることができたからだ。
彼の両肩には、世界の痛みが乗っている。彼はこれからも、星々に不完全な物語を送り続けるだろう。それは嘘ではないが、全てでもない。だが、その不完全さこそが、人間という存在の証なのかもしれない。
湊は店の扉を開け、朝の街へ一歩踏み出した。彼の表情には、疲労と、そしてかすかな、しかし確かな使命感を帯びた微笑みが浮かんでいた。彼は、虚構と真実を隔てる、孤独な境界線として生きていく。