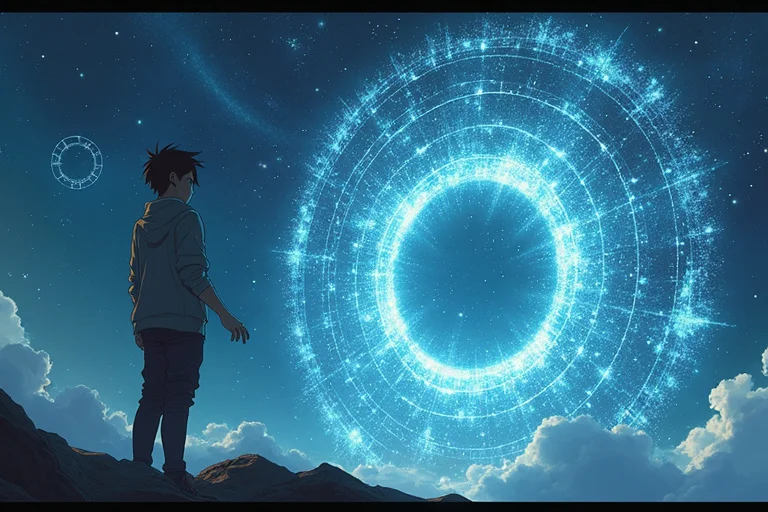第一章 漂流する記録の断片
エリックは「クロノス・レコード」の記録保管人として、過去の絶対性を信じていた。彼の任務は、デジタル化された歴史的データと、人々の集合的な記憶の整合性を保つこと。それは、人類が築き上げてきた文明の礎であり、未来への指針だった。しかし、ある朝、彼の完璧なはずの世界に、ごくわずかな、だが決定的な亀裂が入り始めた。
その日、エリックは通勤途中のモノレールで、見慣れない広告ポスターに目を奪われた。それは、古風な活版印刷を模した、過去の流行とは似ても似つかないデザインだった。昨夜までは、最新のホログラム広告が表示されていたはずだ。彼は記憶の混濁を疑ったが、同僚たちに尋ねても、誰も「昨夜の広告」を覚えていないようだった。奇妙な感覚に襲われながらも、彼はそれを単なるシステムのエラーとして片付けようとした。
だが、違和感は日に日に増していった。クロノス・レコードのデータベースに、小さなノイズが混入し始めたのだ。有名な歴史的演説の一節が、彼の記憶にあるものと微妙に異なっている。消滅したはずの旧時代の建築物が、市街地の記録写真にひっそりと写り込んでいる。当初は「データ破損」として処理されていたが、その頻度と範囲は徐々に拡大していった。それはまるで、過去の記録が、ゆっくりと、しかし確実に「漂流」しているかのようだった。
「どうしたの、エリック。顔色が悪いわ。」
隣の席のリアナが、心配そうに彼を覗き込んだ。彼女は記録の補助分析官で、その明晰な頭脳と、何よりもエリックの心を解き放つような明るい笑顔の持ち主だった。エリックは彼女に、ここ数日の異常について話そうとしたが、言葉を選んでいるうちに、ある戦慄すべき事実に気づいた。リアナとの出会いの記録が、彼の記憶の中で、わずかに、だが決定的に変化しているのだ。
彼の記憶では、リアナとの出会いは三年前に、クロノス・レコードのデータ解析コンペで、互いのアイデアに共鳴し合ったのが始まりだった。しかし、データベースの記録には、彼女は別のプロジェクトから転属してきたと記されている。その転属日も、彼の記憶より半年も遅い。エリックは自分の記憶と、システムの記録がこれほどまでに乖離していることに、深い恐怖を覚えた。まるで、彼の個人的な歴史そのものが、何者かの手によって書き換えられているかのようだった。彼はリアナの手を握りしめようとしたが、まるで幻影を掴むかのように、指先が空を切る感覚に襲われた。
第二章 静止した未来の兆候
エリックの心は疑念と不安で満たされていた。もはや、彼の周りで起こる奇妙な出来事は「システムエラー」では説明できない領域に達していた。彼はプライベートな時間を削り、クロノス・レコードの非公開データベース、通称「ブラックボックス」へのアクセスを試みた。そこには、公式記録から抹消された、あるいはまだ分類されていない膨大なデータが眠っている。彼はそこに、この現象の手がかりがあるはずだと信じていた。
夜毎、自宅の地下室にこもり、埃っぽい旧型端末を前にして、エリックは過去のデータログを遡った。彼の目に飛び込んできたのは、驚くべきデータだった。数年前から、世界中の未来予測機関が収集していた「マクロ・フューチャー・モデル」の更新が、突如として停止しているのだ。人類の気候変動シミュレーション、資源分配予測、恒星間移住計画の進捗データなど、全てが数年前のある一点で「フリーズ」していた。未来は、予測不能な混沌へと向かうのではなく、ただ、静かに「停止」していた。
「未来が……止まっている?」
エリックは呟いた。これでは、まるで誰かが時間を支配し、未来への道を一つに絞っているかのようではないか。彼はさらに深く掘り下げ、ブラックボックスの最も深奥に隠された、禁断のデータファイルを発見した。それは、かつて「タイム・エコー現象」と呼ばれた、時間軸の微細な乱れを検出するためのプロトタイプ装置の設計図と、それに伴う膨大な理論データだった。その理論は、我々が知る時間軸が、より高次元の存在によって「縫い合わされ」、特定の未来へと誘導されている可能性を示唆していた。
エリックは数週間かけて、簡素なタイム・エコー検出装置を組み立てた。夜が明ける頃、完成した装置を起動すると、ディスプレイには無数の時間軸の分岐が、まるで網の目のように表示された。しかし、その網の目の多くは、何者かによって「断ち切られ」、特定の太い一本の道だけが残されているように見えた。それはまさに、無限の可能性の中から、特定の未来だけを選び取り、そこへ向かう過去の選択肢を固定する「時間縫合」の痕跡だった。
彼はその縫合の痕跡を辿り、その起点にある「特異点」を特定しようとした。それは、世界各地に点在する、ごくわずかな時間的特異性を示す地点であり、共通して、極めて高いエネルギー反応を示していた。その特異点の一つが、彼が住む都市の地下深く、クロノス・レコード本部のさらに下に位置していることを突き止めた時、彼の背筋に冷たい戦慄が走った。そしてその特異点から放たれる微細なエネルギー波形が、リアナの存在と奇妙に共鳴していることに、エリックは気づいてしまう。
第三章 クロノスの囚人
エリックは、突き止めた特異点へと向かった。クロノス・レコードの最深部、通常は立ち入り禁止となっている旧時代の研究施設跡のさらに地下に、その空間は存在した。重厚な隔壁を無理やりこじ開け、たどり着いた先にあったのは、光を吸収するような漆黒の祭壇だった。その中央には、巨大な水晶が浮かび、微かに脈打っている。そして、その水晶の周りに、人型でありながらも、どこか非現実的な存在が佇んでいた。彼らは「時間縫合師」と自称した。
「よくここまで辿り着いた、エリック・ヴァン。過去の記録に縛られし者よ。」
一人の縫合師が、感情のない、しかし深遠な声で語りかけた。彼らはエリックのこれまでの行動を全て見透かしているようだった。エリックは恐怖を押し殺し、彼らの目的を問い詰めた。
「あなた方は、過去を改変しているのか?未来を操作しているのか?」
縫合師はゆっくりと首を横に振った。
「我々は過去を改変しているのではない。未来を操作しているわけでもない。我々は、来るべき『確定された滅亡』を回避するために、未来へと続く道を『縫い合わせている』のだ。」
彼らの言葉は、エリックの理解を遥かに超えていた。縫合師は続けた。
「我々が観測する数万もの時間軸の分岐の先には、常に一つの終着点があった。それは、人類文明の絶対的な滅亡だ。環境崩壊、惑星間戦争、未知の疫病……その原因は様々だが、結末は常に同じだった。我々は、その確定された未来を変えるために、この世界に干渉している。」
エリックは混乱した。「滅亡を回避する未来があるのなら、なぜ記録を弄び、人々の記憶を曖昧にするのか?」
「無限の過去の選択肢の中には、滅亡を回避する道は、ごくわずかしか存在しない。我々は、その唯一の道へと世界を誘導するために、無数の分岐を『刈り取り』、現在の時間軸を『縫い合わせ』てきた。その過程で、必然的に過去の記録は再編され、人々の記憶は最適化される。それこそが、唯一生き残る未来へと続く道なのだ。」
そして、縫合師はエリックに、最も残酷な事実を突きつけた。
「そして、この時間軸において、唯一の『特異点』として、その未来への道を阻む存在がある。それが、あなたの愛するリアナ・アスターだ。」
エリックの全身から血の気が引いた。リアナが、人類滅亡を回避する未来を阻む特異点?
「彼女の存在は、我々が特定した唯一の未来において、予測不能な変数となる。彼女が生き続ける限り、我々が縫い合わせた時間は解け、再び滅亡への道へと引き戻される。選択せよ、エリック。一人の個人の愛か、あるいは全人類の存続か。」
エリックは膝から崩れ落ちた。彼が守ろうとしていた過去の記録も、彼が愛した現在のリアナも、未来によって選別され、消えゆく運命にあるというのか。彼の価値観は根底から揺らいだ。我々は過去に縛られているのではない。我々は、未来という巨大なクロノスに囚われた、哀れな囚人なのだ。
第四章 残響する選択の歌
エリックは、縫合師の言葉をリアナに伝えるべきか、激しく葛藤した。彼女が、人類の未来を阻む「特異点」であるという事実。そして、その未来を確定させるためには、彼女自身がこの世界から消えなければならないという、あまりにも残酷な運命。しかし、彼は気づいた。リアナは、この数週間の奇妙な出来事の核心を、すでに自分なりに感じ取っていたのだ。
ある日の夕暮れ、リアナはエリックの自宅のベランダで、沈みゆく夕日を眺めながら静かに語った。
「エリック、最近ね、夢を見るの。自分が、まるで存在しないかのような夢。でもね、不思議と悲しくないのよ。だって、その先に、もっと大きな希望が見えるから。」
彼女の瞳は、寂しさの中にも、どこか遠い未来を見据えるような、強い光を宿していた。エリックは言葉を失った。リアナは、自分の運命を受け入れようとしているのだ。そして、彼女はエリックに、優しい笑顔で言った。
「もし、私の存在が、この世界の未来にとって邪魔になるのなら、私は喜んでその役目を終えるわ。だって、あなたと出会って、私は本当に生きていた。それが、私にとっての永遠だから。」
エリックは涙が止まらなかった。愛する人を失う痛みと、彼女の崇高な決断に対する尊敬の念が、彼の胸でせめぎ合った。彼の手は震えていた。未来を選ぶとは、なんと残酷なことだろう。しかし、彼の目の前には、リアナ自身が差し出す「選択」があった。
数日後、エリックは縫合師たちとの再会を果たした。彼は、リアナの決断を伝え、そして自らも、この世界の再編に協力することを申し出た。縫合師たちは無言で彼を受け入れた。世界の再編が始まった。都市の風景は微かに変化し、人々の記憶は穏やかに調整されていく。リアナがいたはずの記録は、ゆっくりと、しかし確実に消えていった。写真から彼女の姿が薄れ、会話の記録から彼女の言葉が抜け落ちる。同僚たちの記憶からも、彼女の存在は曖昧な残像へと変わっていく。
エリックの心は引き裂かれるようだった。しかし、彼の胸の中には、リアナとの愛の記憶が、決して消えることのない、唯一の「特異点」として、深く刻み込まれていた。それは、誰にも見えず、誰にも触れられない、彼だけが保持する時間軸の真実だった。
世界は再編され、滅亡の危機は去った。人々は穏やかな日々を取り戻し、新たな未来へと歩み始めた。エリックは、クロノス・レコードの新たな部門、「フューチャー・ゲートウェイ」の責任者として、未来の可能性を「記録」し、そして「創造」する役割を担っていた。彼はもはや、過去の記録に縛られる者ではない。
ある晴れた日、エリックは、かつてリアナとよく訪れた公園のベンチに座っていた。彼の心には、彼女の声が、笑顔が、そしてその選択が残響している。未来は、固定された過去の延長線上にあるのではない。それは、私たちが選び、痛みを伴う記憶の残響を胸に、静かに織りなしていく、無数の可能性の先に生まれるものなのだ。エリックは空を見上げた。そこには、消え去ったはずの、リアナが愛した星々が、今も変わらず輝いていた。