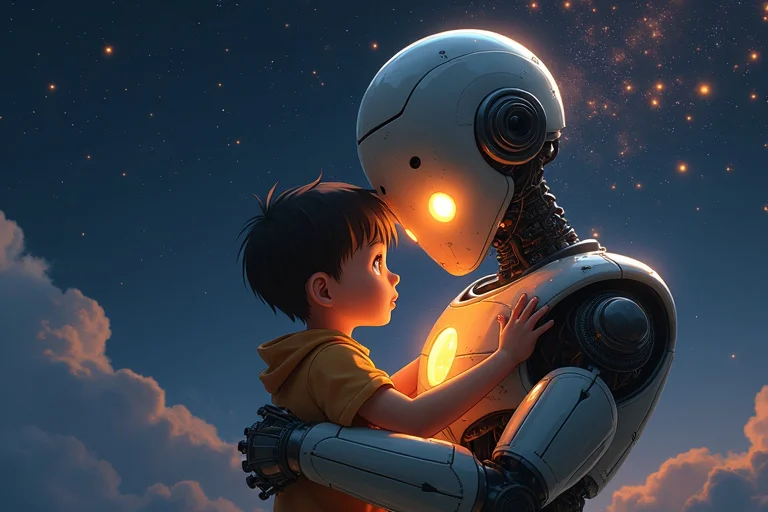第一章 囁くオーロラ
惑星アウロラは、人類の誇りだった。赤茶けた不毛の星を、緑と水の惑星へと生まれ変わらせたテラフォーミング技術の結晶。俺、ミナト・リョウは、その心臓部である大気調整プラントの主任エンジニアだ。俺の仕事は、この星の空気を完璧な数値に保ち、入植者たちが快適に暮らせる環境を維持すること。感情や憶測を排し、データと効率だけを信じる。それが俺の信条だった。
アウロラの空には、常にオーロラが揺らめいていた。地球のそれとは違い、プラントから排出される大気安定用の微粒子に太陽風が干渉して生まれる、人工の絶景だ。入植者たちはそれを「アウロラの祝福」と呼び、詩や歌にしたが、俺にとっては単なる物理現象に過ぎなかった。美しいが、それは計算され尽くした結果の美しさだ。
異変が始まったのは、入植開始から三年目のことだった。最初は酒場での与太話程度だった。「昨夜、奇妙な夢を見た」「お前もか? まるで詩のような…」。その噂は、霧のようにコロニー全体に広がっていった。誰もが口を揃えて、同じような夢について語るのだ。悲しみに満ちた、美しい言葉が流れる夢。液体のように身体を通り抜けていく、言いようのない喪失感の夢。人々はそれを「囁くオーロラ」と呼ぶようになった。
「主任、この集団夢現象、どう思われますか?」
助手のユミが、心配そうな顔で俺に尋ねた。俺はモニターから目を離さずに答える。
「ストレスによる集団ヒステリーの一種だろう。新しい環境への不適応が、潜在意識下で繋がっただけだ。プラントのデータに異常はない。俺たちの仕事は空気を管理することであって、夢の中身まで管理することじゃない」
冷たく言い放つと、ユミは黙って自分のコンソールに戻った。俺は、非科学的な噂に惑わされる彼女の感傷性が理解できなかった。夢は脳が見せる幻だ。そこに意味などない。
だが、その夜。俺も、その夢を見た。
果てしない硝子の平原に、俺は一人で立っていた。空からは、オーロラと同じ色彩の光の雨が、音もなく降り注いでいる。雨粒が肌に触れるたび、誰かの嘆きが直接心に流れ込んでくる。それは言葉ではなかった。もっと根源的な、存在が引き裂かれるような悲しみの波動だった。
――わたしの息が、灼ける。
――わたしの肌が、裂ける。
――わたしの涙が、涸れる。
声なき声が、俺の意識を満たしていく。息が詰まるような哀切に全身が縛られ、金縛りにあったように動けない。ただ、空の美しさと、大地から伝わる絶望的なまでの痛みの間で、俺は為す術もなく立ち尽くしていた。
第二章 不協和音の詩
悪夢から叩き起こされるように目を覚ました。シーツは汗でじっとりと濡れ、心臓が警鐘のように鳴り響いていた。あの感覚。夢の中の悲痛な手触りが、まだ全身の皮膚に残っているようだった。俺はそれを疲労のせいだと無理やり結論づけた。連日のプラント管理で、神経が過敏になっているだけだ、と。
しかし、その日を境に、俺の世界は静かに軋み始めた。プラントの制御室で見るオーロラの輝きが、以前とは違って見えた。あの美しい光のカーテンの裏側に、夢で感じた巨大な悲しみが潜んでいるような気がしてならなかった。モニターに並ぶ完璧な数値の羅列が、何か重大なことを見落としているのではないかという、根拠のない不安が胸をざわつかせた。
「リョウ、少し話があるの」
声をかけてきたのは、コロニーの植物学者、サキだった。彼女は俺とは正反対の人間で、植物の声を聞き、土の匂いで天候を読むような、直感と感性を何よりも重んじる女性だった。
「例の集団夢のことよ。私は、あれが単なるヒステリーだとは思えない」
サキはタブレットを取り出し、一枚の画像を見せた。それは惑星固有種である「涙滴草(るいてきそう)」という植物の写真だった。青い雫のような形をしたその植物は、コロニーのあちこちで枯れ始めているという。
「涙滴草は、大気中の特殊なイオンバランスに非常に敏感なの。そして、この植物が枯れ始めた時期と、集団夢の報告が増え始めた時期が、奇妙に一致する」
「相関関係と因果関係は違う。何かの病原菌かもしれないだろう」
俺は即座に反論した。だが、サキは静かに首を振った。
「夢を見た人たちに聞き取り調査をしたわ。みんな、共通して『引き裂かれるような痛み』や『呼吸が苦しい』感覚を訴えている。まるで、この星そのものが苦しんでいるみたいに…」
「星が苦しむだと? サキ、それは詩人の台詞だ。科学者の言葉じゃない」
俺は苛立ちを隠せなかった。データに基づかない、あまりにも情緒的な仮説。だが、彼女の言葉は、俺が夢の中で感じたあのリアルな痛みを的確に言い当てていた。俺は動揺を悟られまいと、ことさら冷淡な声で言った。
「プラントは完璧に機能している。大気成分に異常値はない。それ以上の議論は無意味だ」
席を立ち、俺はサキから逃げるようにその場を去った。だが、自室に戻っても、彼女の言葉が、そして夢の残滓が、俺の心を蝕んでいた。俺は、自分の信じてきた合理性の足元が、静かに崩れていく音を聞いていた。
第三章 大気の告白
運命の日は、唐突に訪れた。コロニー全域にけたたましいアラートが鳴り響く。
「主任! プラントの主冷却システムが機能停止! 原因不明、制御不能です!」
ユミの悲鳴のような報告を受け、俺は制御室に駆け込んだ。メインスクリーンには、見たこともないエラーコードが無数に点滅している。プラントの中枢機能が、まるで外部から攻撃されたかのように、次々とシャットダウンしていく。このままでは大気循環が停止し、数時間後にはコロニーは呼吸困難に陥る。
「手動制御に切り替えろ! バックアップを起動させろ!」
俺は怒鳴りながらコンソールを叩くが、システムは一切の命令を受け付けない。まるで、巨大な何者かに乗っ取られたかのようだった。パニックに陥るスタッフたちの中で、俺は一つの可能性に思い至り、背筋が凍るのを感じた。
「…ユミ、大気中の微粒子センサーの全ログを、脳波スキャンデータと同期させて表示しろ。特にシータ波、夢を見ている時の脳波だ!」
「主任? 何を言って…」
「いいから早くやれ!」
ユ-ミは戸惑いながらも、俺の指示通りにデータを表示した。スクリーンに、複雑な波形グラフが二つ現れる。一つは大気微粒子のエネルギー分布。もう一つは、コロニー住民の睡眠時の平均脳波データ。そして、俺は息を呑んだ。
二つの波形が、不気味なほど完璧にシンクロしていたのだ。
微粒子のエネルギーパターンが変化するたびに、脳波もそれに追従するように形を変えている。まるで、巨大な楽器が奏でる音楽に、無数の小さな弦が共鳴しているかのようだ。
「そんな…馬鹿な…」
俺は愕然とした。俺たちが大気を安定させるために散布していた微粒子。それが、この星の大気と、俺たち入植者の意識を繋ぐ媒介になっていたのだ。
そして、システムダウン。これは事故などではない。
サキの言葉が脳裏に蘇る。「まるで、この星そのものが苦しんでいるみたいに…」。
そうだ。この星の大気は、単なる気体の集合体ではなかった。それは、惑星全体を覆う、一つの巨大な意識体だったのだ。
俺たちが「祝福」と呼んでいたオーロラは、その意識体が流す苦痛の光だった。プラントが吐き出す排気は、その巨大な生命体の肺を灼き、肌を裂く猛毒だった。そして、あの集団夢は、耐えきれなくなった大気が発した、悲鳴であり、最後の警告だったのだ。
システムダウンは、攻撃ではない。自らの命を守るために、毒の源泉であるプラントを拒絶した、この星の最後の自衛手段だった。
俺は膝から崩れ落ちた。足元の床が、いや、この惑星そのものが、俺の罪を告発するように震えている気がした。俺たちが「開拓」と呼んでいた行為は、ただの身勝手な破壊だった。効率と数字だけを信じ、俺は、生きて嘆き悲しむ存在の声を、ただのノイズとして切り捨ててきたのだ。
「…ああ」
声にならない声が、喉から漏れた。
「俺たちは…なんてことを…」
制御室のガラスの向こうで、オーロラがこれまでになく激しく、そして悲しげに揺らめいていた。それはまるで、断末魔の叫びのように見えた。
第四章 新しい夜明け
俺に残された選択肢は多くなかった。プラントを再起動させ、大気の意識を完全に殺すか。それとも、人類の都合を捨て、この星の声に耳を傾けるか。答えは、もう決まっていた。
俺は全コロニーに向けて、緊急放送を行った。制御不能に陥ったプラントの現状、そして俺がたどり着いた信じ難い真実…この星が、巨大な意識を持つ生命体であるということを、すべて話した。
「私たちは、この星を傷つけてきました。私たちが『快適な環境』と呼んでいたものは、この星の犠牲の上に成り立っていたのです。囁くオーロラは、この星の悲鳴でした」
人々は混乱し、反発する者もいた。だが、誰もが心のどこかで感じていたのだ。あの夢の切実な痛みを。サキをはじめとする研究者たちが、俺の仮説を裏付けるデータを次々と提示し、コロニーの空気は徐々に変わっていった。これは、生存をかけた選択なのだと。
俺たちは、決断した。プラントの再起動は、大気の循環を維持する最小限の機能に留める。それは、人類にとって決して快適とは言えない環境になることを意味した。薄い空気に息苦しさを覚え、厳しい気候変動に耐えなければならないだろう。だが、それが俺たちにできる唯一の贖罪だった。
数週間後、俺は久しぶりに外に出た。プラントの出力が抑えられたアウロラの空は、以前の華やかさを失っていた。空を覆っていた壮麗なオーロラは、今は地平線の彼方に、淡い緑色の光の帯として、かろうじてその姿を残しているだけだ。まるで、重い病から回復しつつある者の、静かな寝息のようだった。
もう、人々はあの悲しい夢を見ることはない。だが、代わりに、私たちは新しい「声」を聞くようになった。風が草を揺らす音に、岩を洗う水のせせらぎに、夜空の星々の瞬きに。そのすべてに、この惑星の穏やかな意志が宿っているのを感じるのだ。
俺は空を見上げ、深く息を吸った。少し冷たく、薄い空気だったが、そこには確かに生命の匂いがした。夢の中で感じたような、引き裂かれる痛みはもうない。代わりに、静かで、広大で、そしてどこか慈愛に満ちた何かが、俺の身体を通り抜けていった。
科学と効率だけが世界を構築するのではない。目に見えないもの、数字にできないものの中にこそ、本当の真実があるのかもしれない。俺はまだ、その答えを見つけたわけじゃない。だが、この静かになった空の下で、俺たち人類は、ようやく本当の意味で、この星の一員としての第一歩を踏み出したのだ。
淡い光を放つ地平線を見つめながら、俺は心の中でそっと呟いた。もう嘆きの歌ではない。いつか、お前と共に、喜びの歌を奏でられる日が来るだろうか。その問いに答えるかのように、優しい風が俺の頬を撫でていった。