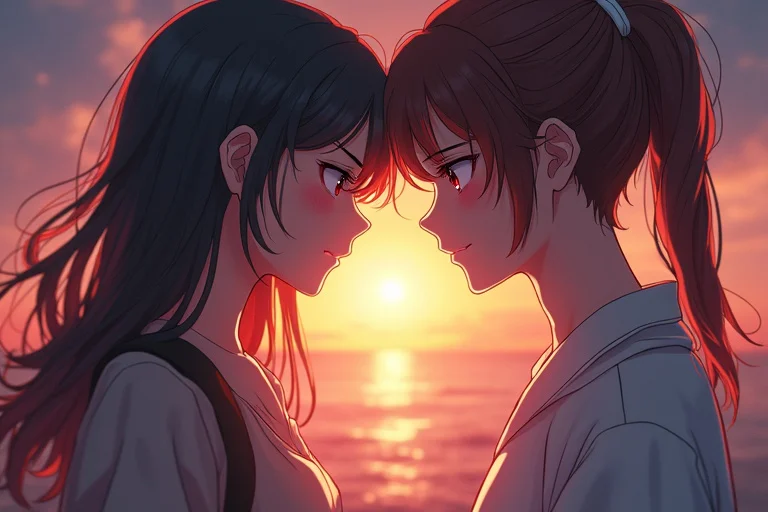タイトル: あなたの言葉を、もう一度味わう
-----
第一章 完熟した桃と蜂蜜の味
水瀬楓(みずせかえで)の世界は、味で満ちていた。それは比喩ではない。彼女は、言葉に味を感じる特殊な共感覚――味覚性語彙共感覚の持ち主だった。
幼い頃から、母の優しい「おはよう」は温かいミルクの味がしたし、父の無骨な「がんばれ」は少し塩辛い煎餅の味がした。成長するにつれ、その能力はより鮮明になり、他人の感情の機微まで舌で感じ取れるようになった。お世辞は後味の悪い人工甘味料の味、隠された悪意は腐った卵の味、そして嘘は、舌が痺れるような化学薬品の味がした。
この能力のせいで、楓は人間関係に深く踏み込むことを恐れていた。誰も彼もが発する言葉の裏に潜む不純な味にうんざりし、いつしか心に分厚い壁を築いていた。恋愛なんて、もってのほかだ。甘い言葉の裏に隠された打算や下心の味を想像するだけで、吐き気がした。
だから、あの日、あのカフェで彼の言葉を「味わった」時の衝撃は、楓の人生を根底から揺るがすものだった。
その日、楓は仕事で使う資料を探して古書店街を歩き回り、疲れ果てていた。ふと目に留まった、蔦の絡まる小さなカフェ。吸い寄せられるようにドアを開けると、珈琲の香ばしい匂いと共に、穏やかな声が楓を迎えた。
「いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ」
その声が耳に届いた瞬間、楓は息を呑んだ。舌の上に、信じられないほどの甘美な味が広がったのだ。それは、太陽の光をいっぱいに浴びて完熟した桃を、黄金色の蜂蜜に漬け込んだような、芳醇で、どこまでも優しく、純粋な味だった。雑味も、えぐみも、人工的な甘さも一切ない。完璧な、天然の甘露。
楓は呆然と声の主を見つめた。カウンターの中に立つ、柔らかな栗色の髪をした青年。名札には「桐谷」と書かれている。彼が他の客と交わす何気ない会話――「ご注文はお決まりですか」「少々お待ちください」――その一つひとつが、極上のデザートのように楓の心を蕩かした。
それから楓は、まるで中毒者のようにそのカフェに通い詰めた。桐谷陽(きりやよう)という名の彼の言葉を味わうためだけに。彼の口から紡がれるすべての言葉が、楓にとって至福のご馳走だった。「ありがとう」は上質な和三盆の味。「またどうぞ」は爽やかなミントの香りを含んだ冷たい湧き水の味。
やがて二人は言葉を交わすようになり、カフェの外で会うようになった。植物学者を目指す大学院生であること、古い映画が好きなこと、猫舌であること。彼を知るほどに、彼の言葉の味はより深く、豊かになっていった。楓は、生まれて初めて、人の言葉を心から美味しいと感じ、その言葉を発する人間そのものを、どうしようもなく愛おしいと思っていた。
ある雨上がりの公園で、陽は少し照れながら楓に向き直った。
「楓さん。あなたのことが、好きです」
その瞬間、楓の世界は爆発的な喜びに包まれた。舌の上で、これまで味わったどんなものとも比較にならない、奇跡のような味がした。それはまるで、幾千もの星屑を溶かし込んだ夜空の雫のようであり、夜明けの光を浴びて輝く朝露のようでもあった。楓は涙を流しながら、何度も頷いた。この味を、永遠に失いたくない。心からそう願った。
第二章 味のない炭酸水
陽との日々は、楓にとって夢のような時間だった。彼の言葉は、もはや楓の生命維持に必要な栄養素そのものだった。朝の「おはよう」で目覚め、夜の「おやすみ」で眠りにつく。彼の「愛してる」という言葉は、どんな高級料理よりも楓の心と体を満たしてくれた。
楓は、自分の共感覚について陽に打ち明けるべきか、ずっと悩んでいた。この不思議な幸福が、もし真実を知られたら壊れてしまうのではないか。彼が、自分の言葉が「味」として消費されていると知ったら、どう思うだろう。楓は怖かった。そして、陽自身ではなく、彼の言葉がもたらす「味」に依存しているのではないかという罪悪感にも苛まれていた。
「楓は、どうしてそんなに俺の言葉を聞きたがるの?」
ある日、陽が悪戯っぽく尋ねた。楓はどきりとして、「だって、陽くんの言葉は、とても綺麗だから」と答えるのが精一杯だった。嘘ではない。けれど、すべてでもない。その言葉は、楓の舌に、ほんの少しだけ、ざらりとした後味を残した。
それでも、幸せな日々は続いた。季節が巡り、二人が付き合い始めてから一年が経とうとしていた、ある秋の日のことだった。楓のスマートフォンが、けたたましい着信音を鳴らしたのは。
それは、警察からの電話だった。陽が、交差点で信号無視の車にはねられ、病院に救急搬送されたという、信じがたい知らせだった。
血の気が引くのを感じながら、楓は病院へ走った。手術室のランプが消え、医師から告げられたのは、「命に別状はないが、頭を強く打っており、記憶に障害が残る可能性がある」という残酷な事実だった。
数日後、陽は目を覚ました。楓が恐る恐る病室に入ると、陽はぼんやりとした目で彼女を見た。
「……ああ、楓さん」
その声を聞いた瞬間、楓は自分の世界が崩壊する音を聞いた。
味が、しない。
あれほどまでに楓を魅了した、完熟した桃も、蜂蜜も、星屑の雫も、すべてが跡形もなく消え去っていた。彼の声は、まるで気の抜けた、味のない炭酸水のように、ただ舌の上を虚しく滑っていくだけだった。
「ごめん、なんだか、頭が霞んでて……。僕たち、どういう関係だったっけ?」
陽の言葉は、無味無臭のまま楓の鼓膜を震わせた。絶望が、冷たい水のように楓の全身を満たしていく。記憶の一部が、楓と過ごした幸せな記憶が、抜け落ちてしまっている。そして、それと共に、彼の言葉から魔法のような「味」も奪い去られてしまったのだ。
楓は、自分が愛していたのは、陽という人間だったのか、それとも、彼の言葉が生み出す、あの奇跡の味だったのか、分からなくなった。答えの出ない問いが、鉛のように心を重くする。味のない言葉を発する陽を前にして、どうしようもない空虚感と、そんな自分への激しい嫌悪感に襲われ、楓はただ立ち尽くすことしかできなかった。
第三章 土の匂いと焼き芋の甘さ
陽は退院したが、二人の関係はぎこちないものになっていた。陽は失われた記憶の断片を埋めようと必死だったが、彼の言葉は相変わらず無味乾燥なままだった。彼は楓に気を遣い、以前のように優しくしようと努めたが、その言葉はどこか表層的で、楓の舌には届かなかった。
楓は、陽と会うのが辛くなっていた。彼の顔を見るたびに、失われた味を思い出して胸が締め付けられた。かつてはご馳走だった会話の時間が、今では味気ない苦行に変わってしまった。彼女は次第に陽からの連絡を避けるようになり、二人の間には、修復不可能なほど深い溝ができていった。
「もう、終わりにしよう」
そう切り出そうと思った日、陽から「話がある」と連絡が来た。楓は覚悟を決めて、思い出のカフェで彼と会った。
「別れ話をしに来たんだろうなって、思ってた」
席に着くなり、陽が力なく笑った。彼の言葉は、やはり味のない炭酸水のままだった。
「記憶が戻らなくて、君の知ってる俺じゃなくなって、申し訳ないと思ってる。でも、どうしても、もう一度ちゃんと話したかった」
陽は、リハビリを兼ねて、以前から好きだった植物園に通っていると話した。そして、楓に「最後になるかもしれないけど、一度だけ、一緒に行ってくれないか」と頼んだ。楓は、断ることができなかった。
数日後、二人は植物園を歩いていた。温室の中は、湿った土と青々とした葉の匂いで満ちている。会話は途切れ途切れで、気まずい沈黙が流れた。
陽は、名も知らぬ熱帯植物の大きな葉を、そっと指でなぞりながら、ぽつりと呟いた。
「記憶はないんだ。君とここでどんな話をしたのか、どんな顔で笑っていたのか、全然思い出せない。でも……不思議なんだ。君と一緒にここにいると、なぜだか、心がすごく落ち着く」
彼は楓の方に向き直った。その瞳は、不安げに揺れている。
「今の俺は、きっと君をがっかりさせることしか言えない。昔みたいに、気の利いた言葉なんて、ひとつも出てこない。……それでも、俺は、また君のことを知りたい。もう一度、君と始めたい。……だめかな」
訥々と、不器用に紡がれる言葉。それは、かつてのような華やかさも、心を蕩かすような甘さもない。だが、その言葉が楓の耳に届いた瞬間、彼女の舌の上に、微かで、しかし確かな「味」が生まれた。
それは、雨上がりの土の匂いが混じった、素朴な味。そして、寒い日に掌で包み込んだ、焼きたての石焼き芋のような、ほっこりとした温かい甘さだった。
派手さはない。けれど、滋味深く、心にじんわりと染み渡る、生命力に満ちた味。楓は、はっと息を呑んだ。
第四章 これからの味
涙が、楓の頬を伝った。それは悲しみの涙ではなかった。
「……味が、する」
楓は、ほとんど無意識に呟いていた。
「え?」
きょとんとする陽に、楓は初めて自分の秘密を打ち明けた。言葉に味を感じる共感覚のこと。彼の言葉が、どれほど特別で、素晴らしい味がしたか。そして、事故の後、その味が消えてしまい、どれほど絶望したか。
「私は、あなたの言葉の『味』に恋をしていただけなのかもしれないって、ずっと苦しかった。あなた自身じゃなくて、あなたがくれる快楽だけを求めていたんじゃないかって……」
一気に話終えた楓に、陽は驚いた顔をしていたが、やがて、その表情は柔らかなものに変わった。彼は楓の濡れた頬にそっと手を伸ばし、親指で涙を拭った。
「そっか。俺の言葉、そんなに美味しかったんだ。……光栄だな」
彼の言葉は、やはり温かい焼き芋の味がした。
「昔の味は、もう分からないや。でも、君が今、俺の言葉に新しい味を感じてくれたなら……。それは、記憶を失った、今の俺自身の味ってことなのかな」
楓は、ようやく気づいたのだ。
愛とは、完璧で不変の味を求めることではない。相手が変わり、自分が変わり、関係性が変化していく中で、その時々に生まれる新しい味を、共に慈しみ、味わっていくことなのだ。失われた完熟の桃の味を追い求めるのではなく、今ここにある、土の香りのする焼き芋の甘さを受け入れること。それこそが、本当の愛なのではないか。
楓は、涙で濡れた笑顔で陽を見つめた。
「うん。あなたの、今の味。……すごく、温かくて、優しい味がする」
陽は、心から安堵したように微笑んだ。その笑顔から発せられた無言の言葉は、楓の舌の上で、まるで淹れたての温かいほうじ茶のように、香ばしく広がった。
二人は、ゆっくりと歩き始めた。手はまだ繋いでいない。けれど、その間にある距離は、もはや絶望的な溝ではなかった。これから二人がどんな会話を交わし、その言葉がどんな味を紡いでいくのか、それは誰にも分からない。時には苦い味や、しょっぱい味がすることもあるだろう。
けれど、楓はもうそれを恐れなかった。変化していくすべての味を、愛おしい記憶として、陽と共に味わい尽くしていこう。そう心に決めながら、楓は隣を歩く陽に、新しい最初の一言を、どの言葉で伝えようかと考えていた。その一言が、きっと、二人の未来の味の始まりになるのだから。