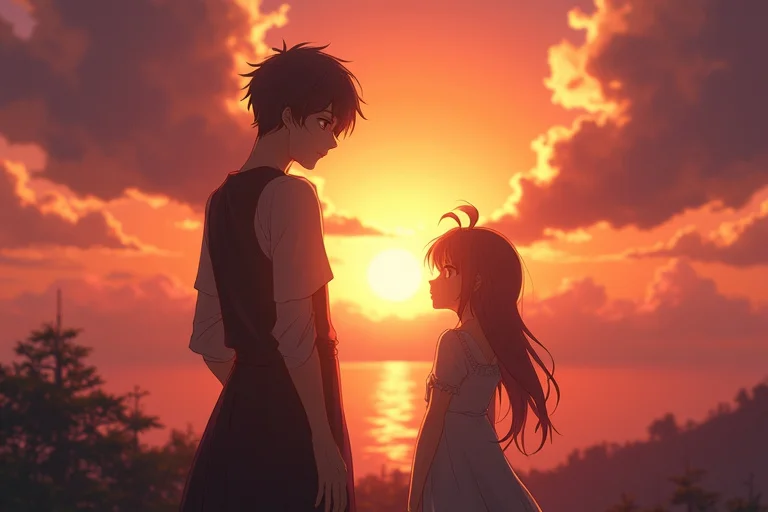第一章 虹色の来訪者
リヒトの仕事場は、死んだ感情の匂いがした。埃と乾燥したインク、そして微かに金属が錆びるような匂い。壁一面の棚には、様々な色と形をした『感情結晶』が、分類ラベルを貼られた小箱の中で静かに眠っている。喜びは太陽のように黄金色に輝き、純粋な悲しみは冬の湖のように青く透き通る。リヒトは、それらを鑑定し、値段をつけ、市場に流す鑑定士見習いだった。
彼自身が結晶を産み出すことは、もう何年もなかった。感情を昂らせると、胸の奥で何かが軋むような痛みを感じる。だからリヒトは、心を凪いだ水面のように保つ術を覚えていた。他人の感情の残骸を扱うのに、自分の感情は邪魔なだけだ。
その日、工房の扉が軋みながら開いたときも、リヒトは拡大鏡を覗き込み、持ち込まれた『嫉妬』の結晶の不純物を調べているところだった。緑色の結晶に混じる黒い澱。持ち主の自己嫌悪の現れだ。値はつかないだろう。
「ごめんください」
か細い、鈴を転がすような声だった。顔を上げると、そこに立っていたのは、ぼろぼろのワンピースをまとった一人の少女だった。年は十歳くらいだろうか。大きな瞳は虚ろで、自分がどこにいるのかさえ分かっていないようだった。その少女が、まるで壊れ物を扱うように、大切に胸に抱えているものに、リヒトは息を呑んだ。
それは、今まで見たこともないほど巨大な結晶だった。
赤子の頭ほどの大きさがあり、形は歪な涙滴。そして何より異様なのは、その色だ。透明な結晶の内部で、赤、青、黄、緑、紫…あらゆる色が、オーロラのように揺らめき、混じり合い、明滅している。それは単なる色の集合体ではなかった。まるで、幾千もの魂がその中で囁き合っているかのような、圧倒的な存在感があった。
「これを…見て、ください」
少女はか細い声で言うと、おずおずと結晶をカウンターに置いた。ゴトリ、と重い音が響く。リヒトは無意識に立ち上がり、それに近づいた。結晶に触れる寸前、指先にピリリとした静電気のような感覚が走る。
「これは…一体?」
「わかりません。気づいたら、これを持っていました。私の名前も、どこから来たのかも…何も」
記憶喪失。珍しいことではない。大きな衝撃や悲しみを受けた人間は、その感情を結晶として排出した後、原因となった記憶を失うことがある。だが、これほどの結晶を産み出すには、どれほどの感情が必要だというのか。国家の存亡に関わるような絶望か、あるいは神々に届くほどの歓喜か。
リヒトは師匠から借り受けた最高級の鑑定用レンズを覗き込んだ。結晶の内部は、万華鏡のように刻一刻と表情を変えている。喜びの光が生まれたかと思えば、次の瞬間には深い悲しみの青に沈み、燃えるような怒りの赤が迸る。単一の感情ではない。これは…まるで、一人の人間の全生涯が凝縮されたような代物だ。
リヒトの指が、吸い寄せられるように結晶に触れた。その瞬間、脳内に激流が流れ込んできた。
──桜並木を駆ける少女の笑い声。暖かい陽光。母親に手を引かれる安心感。初めての恋の甘酸っぱい痛み。友との決別の苦味。燃え盛る家。黒い煙。誰かを呼ぶ、悲痛な叫び声──
「うっ…!」
リヒトは思わず手を引いた。心臓が激しく鼓動している。他人の結晶に触れて、これほど鮮明な感覚が流れ込んできたのは初めてだった。これはただの感情結晶ではない。もっと根源的な、魂の記録のようなものだ。
少女は不安げにリヒトを見つめている。その瞳には、これから自分がどうなるのかという怯えだけが映っていた。リヒトは、久しぶりに胸の奥で何かが軋むのを感じながら、深呼吸を一つした。
日常が、この虹色の涙滴によって静かに、しかし決定的に侵食され始めたことを、彼はまだ知らなかった。
第二章 沈黙の心とささやく結晶
少女には名前がなかったため、リヒトは仮に「アリア」と名付けた。工房の屋根裏部屋を彼女に与え、師匠の許可のもと、奇妙な共同生活が始まった。結晶の正体が判明するまで、という条件付きだったが、その期限は見えなかった。
アリアは、リヒトとは正反対の存在だった。些細なことで笑い、小さなことで涙ぐんだ。彼女の感情は、隠しようもなくその全身から溢れ出ていた。陽だまりで猫が喉を鳴らすのを見れば、彼女の指先から朝日を閉じ込めたような小さな『慈愛』の結晶が生まれ、リヒトが作った少し焦げたスープを飲めば、「美味しい」という言葉と共に、食卓に蜂蜜色の『満足』の結晶がコロンと転がり落ちた。
リヒトは、そんな彼女を最初は戸惑いながら見ていた。自分がいかに感情を殺して生きてきたかを、まざまざと見せつけられているようだったからだ。アリアが産み出す無垢な結晶に触れるたび、彼の心は微かに温められ、同時に、忘れていたはずの何かが疼いた。
「リヒトは、結晶を産まないの?」
ある晩、アリアが不思議そうに尋ねた。リヒトは本を読んでいた視線を上げずに答える。
「必要ないからだ。感情は厄介なだけだよ。人を惑わせ、判断を誤らせる」
「でも、キラキラして、きれいだよ。それに、あったかい」
アリアは、昼間に生まれたばかりの小さな『喜び』の結晶をリヒトの手に乗せた。太陽の欠片のような温もりが、彼の冷えた指先にじんわりと染み込んでいく。その温かさが、胸の奥の古い傷に触れた気がして、リヒトは咄嗟に手を引っ込めた。
一方、あの虹色の結晶──リヒトが密かに『虹涙晶(こうるいしょう)』と名付けたそれの鑑定は、全く進まなかった。どんな文献にも該当する記述はない。ただ、それに触れるたびに流れ込んでくる断片的な記憶は、少しずつ鮮明になっていった。それは、どうやら一人の女性の人生のようだった。幸せな幼少期、情熱的な青春、そして、何かからの逃避。彼女は誰かに追われ、何かを守ろうとしていた。
リヒトは、その記憶の断片に、奇妙な既視感を覚え始めていた。知らないはずの風景なのに、なぜか懐かしい。聞こえるはずのない声なのに、鼓膜の奥で微かに共鳴する。この感覚は、彼を苛立たせ、同時にどうしようもなく惹きつけた。
そんなある日、工房に豪奢な身なりの男が訪れた。街一番の収集家として知られる、バルダス伯爵だ。彼は威圧的な態度でカウンターに金貨の袋を置くと、低い声で言った。
「噂は聞いている。虹色の涙の結晶がここにあるとな。言い値で買おう」
「申し訳ありませんが、あれは売り物では…」
「鑑定中の品だ。持ち主の許可なく手放すことはできない」
リヒトが毅然と断ると、伯爵の目が眇められた。彼はアリアに一瞥をくれると、鼻で笑った。
「持ち主とは、その記憶もない小娘か?好都合だ。小娘ごと買い取ってもいいのだぞ?」
その侮辱的な言葉に、リヒトの腹の底で黒い炎のようなものが揺らめいた。彼自身、なぜこれほどまでに感情が波立ったのか分からなかった。ただ、アリアを、そしてあの結晶を守らなければならないという強い衝動に駆られた。
「お引き取りください。何度来られても、答えは同じです」
リヒトの冷たい声に、伯爵は不快げに顔を歪めたが、やがて不気味な笑みを浮かべて立ち上がった。「まあ、よかろう。だが、覚えておけ。本当に価値あるものは、力ずくで手に入れるのが世の常だ」と言い残し、彼は去っていった。
その夜、リヒトは眠れずに『虹涙晶』の前に座っていた。なぜ、自分はあれを守ろうとするのか。ただの鑑定対象のはずだ。だが、それに触れると、胸の痛みが和らぐ気がした。まるで、失った半身を取り戻すかのように。
彼はそっと結晶に手を伸ばした。流れ込んできたのは、夜空の記憶。無数の星が輝く下で、幼い少年と少女が指切りをしている。
『ずっと、一緒だよ』
その声は、紛れもなく、彼自身の幼い頃の声だった。
第三章 砕かれた沈黙と真実の在処
嵐は、予告通りやってきた。数日後の深夜、工房の扉が乱暴に蹴破られる音でリヒトは目を覚ました。バルダス伯爵が、屈強な傭兵たちを引き連れて押し入ってきたのだ。
「言ったはずだ、小僧。力ずくで手に入れると!」
伯爵の目は、欲望にぎらついていた。『虹涙晶』に向けられたその視線は、もはや収集家のそれではなく、狂信者のそれに近かった。リヒトはアリアを背後にかばい、必死に抵抗しようとしたが、多勢に無勢だった。傭兵の一人がリヒトを突き飛ばし、もう一人がアリアの腕を掴んだ。
「やめて!」
アリアの悲鳴が響き渡る。その瞬間、信じられないことが起こった。
カウンターに置かれた『虹涙晶』が、心臓のように、ゴクン、と一度大きく脈動したのだ。そして、眩いばかりの虹色の光を放ち始めた。工房内の空気が震え、壁の棚に並べられた感情結晶が一斉に共鳴してカタカタと鳴り出す。
「な、なんだこれは…!?」
傭兵たちが怯んだ隙に、光はさらに勢いを増し、工房の外へと溢れ出した。窓の外で、人々の短い悲鳴がいくつか聞こえたかと思うと、やがて不気味な静寂が訪れた。
伯爵は狂喜の声を上げた。「そうだ、これだ!伝説の『創世の涙』の力!世界の感情を支配する至宝よ!」
だが、その表情はすぐに恐怖に変わった。結晶の光に触れた傭兵たちが、次々とその場に崩れ落ちていく。彼らは死んだわけではない。ただ、瞳から一切の光が消え、まるで魂を抜かれた人形のように、虚空を見つめているだけだった。
『虹涙晶』が、周囲の人間の感情を無差別に吸い上げ始めたのだ。
「アリア、逃げろ!」
リヒトは叫んだが、アリアはその場から動けなかった。彼女の体は、結晶から放たれる光と細い糸のようなもので繋がっているように見えた。光が強まるにつれて、アリアの体が少しずつ透けていく。
リヒトは、突き飛ばされた痛みも忘れ、必死にアリアのもとへ這い寄った。その時、暴走する結晶から、これまでとは比べ物にならないほど膨大な記憶の奔流が、彼の脳髄を焼き尽くさんばかりの勢いで流れ込んできた。
──双子の兄妹がいた。兄の名はリヒト。妹の名は、リナ。二人はいつも一緒だった。兄は物静かで、妹は太陽のように笑った。ある夜、家に火事が起きた。リヒトは煙に巻かれ、意識を失いかけた。リナは、幼いながらに悟った。二人で助かることはできない、と。彼女は、最後の力を振り絞り、兄への想いのすべてを込めて祈った。『お兄ちゃんが生きてくれますように。私の喜びも、悲しみも、未来も、全部あげるから』。その祈りは、彼女の全生涯の感情と共に、一つの巨大な結晶となった。燃え盛る梁が落ちてくる寸前、結晶はリヒトを光で包み、守った。そしてリナは、炎の中に消えた──
「ああ…あ…」
リヒトの口から、声にならない声が漏れた。忘れていた。いや、守られるために、忘れさせられていたのだ。この結晶は、伝説の宝などではない。これは、リナの『遺晶』。彼を救うために、命と引き換えに遺した、妹の魂そのものだった。
そして、目の前で消えかけている少女、アリア。彼女は、人間ではなかった。リナの遺晶が、兄に会いたい、もう一度話したいと願い続けて、長い年月をかけて生み出した、感情の化身だったのだ。彼女の記憶喪失は、リナ自身の記憶が不完全だったから。彼女が抱いていた巨大な結晶は、彼女自身だったのだ。
「リナ…」
リヒトが掠れた声でその名を呼ぶと、アリアの、いや、リナの幻影の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
第四章 彩なす心、響き合う涙
世界の真実を前に、リヒトは立ち尽くしていた。長年彼を苛んできた胸の痛みと空虚感の正体は、失われた半身である妹の不在そのものだった。彼は妹に守られた罪悪感と、彼女を失った悲しみのあまりに、自分の感情ごと記憶の奥底に蓋をしていたのだ。
暴走する『虹涙晶』は、街の感情を吸い尽くさんとばかりに、その輝きを増していく。このままでは、街中の人々が感情を失った抜け殻になってしまう。そして、力を使い果たした結晶も、アリアの姿も、完全に消滅してしまうだろう。
止めなければ。
リヒトは、ふらつく足で立ち上がった。結晶を止められる者がいるとすれば、それは本来この感情を受け取るはずだった、自分しかいない。
彼は、震える手で自らの胸を掴んだ。心の蓋を、こじ開ける。何年も無視し続けてきた感情の奔流が、堰を切ったように溢れ出した。
リナを失った、魂が引き裂かれるような悲しみ。守れなかった自分への激しい怒り。守ってくれたことへの、言葉に尽くせない感謝。たった一人の家族だった彼女への、深い、深い愛情。そして、再会できたことへの、切ないほどの喜び。
それら全てが、彼の内で混ざり合い、一つの巨大なうねりとなった。
「リナ…!ごめん…!ありがとう…!」
リヒトの瞳から、生まれて初めて、大粒の涙がいくつも零れ落ちた。それはもはや単なる塩水ではなかった。床に落ちた涙は、チリン、と澄んだ音を立て、虹色に輝く小さな結晶へと姿を変えた。彼の全感情が凝縮された、初めての結晶だった。
リヒトは、その生まれたばかりの温かい結晶を手に、暴走する『虹涙晶』へと歩み寄った。そして、祈るように、そっと二つの結晶を触れ合わせた。
瞬間、世界から音が消えた。
虹色の光は、リヒトの結晶に吸い込まれるように収束していく。街へと伸びていた光の触手は消え、人々の感情を吸い上げるのも止まった。暴走していた『虹涙晶』は、まるで役目を終えたかのように、その脈動を静かに緩めていった。
光が完全に収まると、アリアの姿はほとんど透き通り、輪郭だけがかろうじてそこに留まっていた。彼女は、穏やかな、本当に穏やかな笑みを浮かべてリヒトを見ていた。
「…ありがとう、お兄ちゃん。やっと、会えたね」
その声は、記憶の中のリナの声と寸分違わず重なった。
「ずっと、寂しかった。でも、お兄ちゃんが無事でよかった」
「リナ…俺は…!」
「ううん、いいの。私の感情は、ちゃんと届いたから。お兄ちゃんの心に、届いたから」
アリアの姿が、きらきらと輝く光の粒子となって、ゆっくりとほどけていく。リヒトは、消えゆく妹に手を伸ばすが、その指は空を切るだけだった。
「生きて。私の分まで、たくさん笑って、たくさん泣いて。それが、私のいちばんの喜びだから」
最後にそう言い残し、彼女は完全に光となって、工房の空気の中に溶けて消えた。
後には、輝きを失い、ただの乳白色の石のようになった『遺晶』と、リヒトが流した涙から生まれた、温かい虹色の結晶だけが残されていた。
数年後。街の一角に、一風変わった鑑定士の工房があった。主の名はリヒト。彼は、どんなに小さな、あるいは歪な感情結晶でも、その背景にある物語を丁寧に読み解き、その本当の価値を見出すことで知られていた。
彼の工房の最も目立つ場所には、二つの結晶が並べて飾られている。一つは、全ての輝きを失った乳白色の石。もう一つは、それほど大きくはないが、複雑な虹色の光を内包し、静かに輝き続ける涙滴の結晶。
「結晶の価値はね、その輝きや大きさだけじゃないんですよ」
リヒトは、訪れた客に穏やかに語りかける。その顔には、かつての冷たい仮面はなく、悲しみを知る人間だけが持つことのできる、深い優しさが湛えられていた。
「どんな感情も、喜びも悲しみも、怒りさえも、その人が生きた証なんです。それらは全て、等しく貴い」
彼の心はもう、沈黙してはいない。失われたものと得られたもの、その両方を抱きしめ、彼は今日も、誰かの心の欠片に、そっと耳を澄ませるのだった。