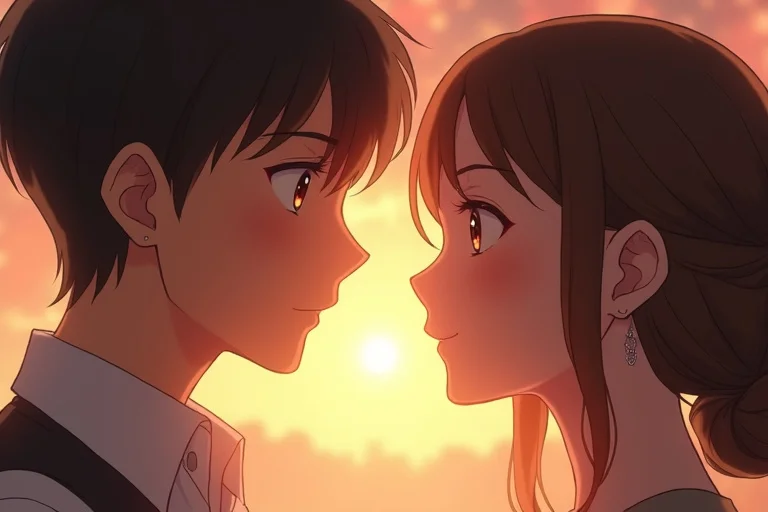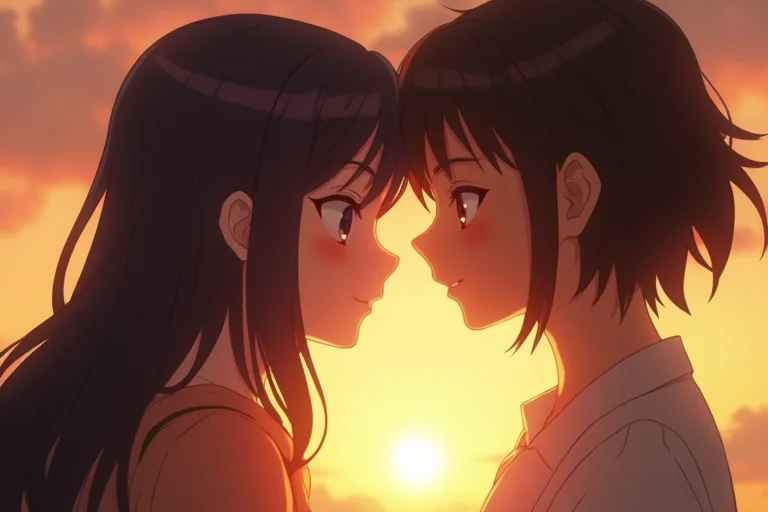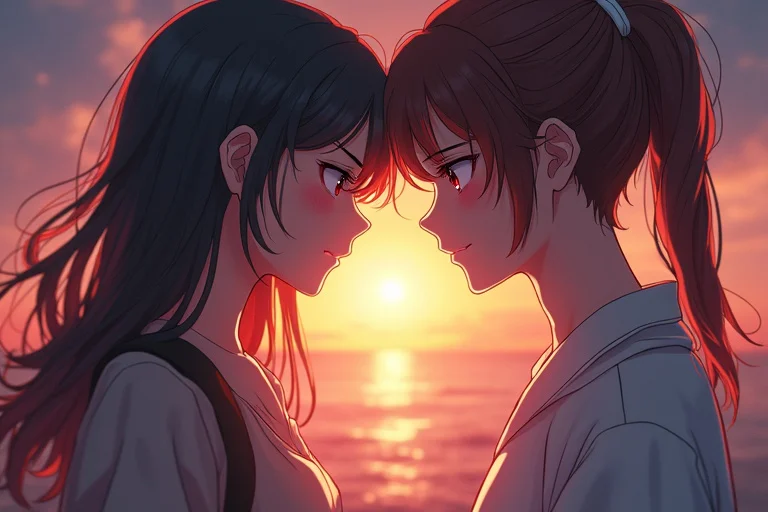第一章 無色の訪問者
私の世界は、いつからか色で溢れすぎていた。人の心、とりわけ誰かを想う気持ちが、オーラのようにその人の輪郭を縁取るのだ。街を歩けば、生まれたばかりの恋心を示す淡い桜色、燃え上がるような情熱の緋色、そして穏やかな信頼を表す空色が、まるでネオンサインのように明滅している。それは美しい光景であると同時に、絶え間ない情報の洪水でもあった。だから私は、古書のインクと紙の匂いが満ちる静かな場所で、世界の色彩から逃れるように息をしていた。
神保町の路地裏にひっそりと佇む「月読堂」が、私の職場であり、聖域だった。高い天井まで届く書架に囲まれ、積年の埃が光に舞うこの場所では、人々の感情の色彩もどこか和らいで見える。
その日、彼はふらりと現れた。古い木製のドアが軋む音と共に、午後の柔らかな光を背負って入ってきた青年。ごく普通の、清潔感のあるシャツを着た、物静かな印象の青年だった。だが、私は息を呑んだ。彼だけが、この色彩過多の世界で、まるでモノクロ映画から抜け出してきたかのように、全くの「無色」だったからだ。
彼の周りには、どんな感情の色も見えない。喜びも、悲しみも、もちろん恋心の色も。それはまるで、彼の周りだけ時が止まり、音が消え、色が抜き取られてしまったかのようだった。私の能力が、初めて機能しない人間。私はカウンターの奥で、埃を払うふりをしながら、彼の姿を盗み見た。彼は迷うことなく人文書の棚へ向かい、一冊の哲学書を手に取ると、窓際の読書席に腰を下ろした。
それから、彼は店の常連になった。週に二、三度、決まって平日の午後にやってきては、数時間、静かに本を読んで帰っていく。私たちは、本の貸し借りを通じて、少しずつ言葉を交わすようになった。彼の名前は月島陽向(つきしま ひなた)といった。
「この作家、お好きなんですか?」
ある日、彼が差し出した本を見て、私は思わず尋ねていた。それは、私も愛読している、今はもう忘れ去られた作家の短編集だった。
「ええ。言葉が静かで、でも、その奥にすごく強い光を感じるんです」
陽向さんはそう言って、少しだけ微笑んだ。その笑顔にすら、色は灯らない。彼の声は、澄んだ湧き水のように穏やかで、私の心を静かに満たしていく。彼と話している時だけは、街の喧騒や、他人の感情の洪水から解放されるような気がした。
私は、日に日に彼に惹かれていった。彼の選ぶ本の趣味、ページをめくる指先のしなやかさ、時折、窓の外を眺める横顔の憂い。そのすべてが、私の心を捉えて離さない。しかし、彼に近づけば近づくほど、「無色」の謎は深まるばかりだった。感情がないのだろうか。それとも、私にだけ心を閉ざしているのだろうか。
この気持ちは、きっと恋だ。そう自覚した時、私は初めて自分の能力を呪った。他人の恋心は嫌というほど見えるのに、肝心な彼の心は何も見えない。そして、私自身の胸に灯ったこの感情が、一体どんな色をしているのかも、私には知る由もなかった。
第二章 色褪せた記憶の栞
季節が移ろい、街路樹の葉が赤や黄色に染まり始めた頃。その日の東京は、朝から冷たい雨が降り続いていた。店内の古びた白熱灯が、いつもより温かく感じられる。陽向さんは、珍しく閉店間際にやってきた。濡れた髪をタオルで拭きながら、彼は申し訳なさそうに言った。
「すみません、雨宿りさせてもらってもいいですか」
「もちろんです。温かいお茶でも淹れますね」
私たちは、カウンター越しに他愛もない話をした。雨音だけが、静かな店内に響いている。やがて雨脚が弱まり、彼は名残惜しそうに立ち上がった。
「長居してしまいました。ありがとうございます」
そう言って店を出ていった彼の背中を見送り、私はふと、彼が座っていた読書席に一冊の本が置き忘れられていることに気づいた。慌てて手に取ると、それは彼がいつも読んでいた古い詩集だった。
本をパラパラとめくっていると、中ほどから一枚の押し花の栞がはらりと落ちた。小さな勿忘草(わすれなぐさ)が、時の重みで琥珀色に変色している。その裏には、震えるような、けれど丁寧な筆跡で、たった一言、こう書かれていた。
『忘れないで』
その栞に指が触れた瞬間、私は確かに感じた。陽向さんの周りを漂っていた静寂の膜が、ほんの僅かに揺らぎ、そこから深い悲しみを帯びた灰色が滲み出すのを。それは恋心の色ではない。けれど、私が彼の内側から感じ取った、初めての「色」だった。それは、まるで冷たい雨に濡れたアスファルトのような、救いのない色だった。
翌日、店を訪れた陽向さんに、私は詩集と栞を差し出した。
「これ、昨日の…」
「あ…すみません、すっかり忘れていました」
彼は栞を受け取ると、その小さな勿忘草を、壊れ物を扱うようにそっと撫でた。その指先が、微かに震えているように見えた。
「大切なもの、なんですか?」
私は、聞くべきではないと分かりながらも、口にしていた。彼は一瞬、遠い目をして、それから諦めたように小さく息を吐いた。
「…昔、大切な人がいたんです。僕より先に、遠くへ行ってしまった」
彼の声は、いつものように穏やかだったが、その奥底には、決して癒えることのない痛みが横たわっているのが分かった。
「彼女が最後にくれたものなんです。僕は…悲しみに呑み込まれるのが怖くて、いつの間にか、自分の気持ちに蓋をすることに慣れてしまった。感じないようにすれば、傷つくこともない、と」
彼の告白は、私の胸に重くのしかかった。彼が無色なのは、感情がないからではなかった。あまりにも深い悲しみを、その身に封じ込めているからだったのだ。私は、彼の心の深淵に触れてしまったような畏れと、同時に、彼のことをもっと知りたいという抗えない衝動に駆られていた。
第三章 透明な虹彩
数日後、私は決意を固めていた。自分の秘密を、彼に打ち明けようと。それは賭けだった。気味悪がられて、二度と会えなくなるかもしれない。それでも、彼との間に見えない壁があるまま、こうして曖昧な関係を続けることには耐えられなかった。
陽向さんがいつもの席で本を読んでいる。私は深呼吸を一つして、彼の向かいの椅子に静かに腰掛けた。
「陽向さん、少し、お話があります」
彼は本から顔を上げ、不思議そうな顔で私を見た。
「私には…少し、変わったところがあって。人の、誰かを好きだと思う気持ちが、色になって見えるんです」
私は、言葉を選びながら、ゆっくりと語り始めた。街がどれだけ色彩に溢れているか。その中で、彼だけが唯一、無色だったこと。だからこそ、彼の存在がどれほど特別に感じられたか。
陽向さんは、ただ黙って私の話を聞いていた。その表情からは、何も読み取れない。拒絶されることへの恐怖で、心臓が氷のように冷たくなっていく。
「だから…あなたの周りには、色が見えないんです。あなたが何を考えているのか、私には少しも分からない」
声が震える。俯いた私の視界に、彼の手がそっと伸びてきた。驚いて顔を上げると、彼は今まで見たことがないほど真剣な眼差しで、私を見つめていた。
「驚いた…。君も、そうだったんだ」
「え…?」
「僕も、昔は人の感情が聞こえたんだ。音として」
予想もしなかった言葉に、私は思考が停止した。
「喜びは軽やかなメロディに、怒りは不協和音に。そして、悲しみは…途切れることのない低いチェロの音色に聞こえた。でも、彼女を失った時、世界中の悲しみの音が、津波のように僕に押し寄せてきた。耐えきれなかった。だから、僕は自分の耳を閉ざしたんだ。もう何も聞こえないように、何も感じないように」
彼が無色だった本当の理由。それは、感情がないからではない。感情の奔流を、その身一つで必死に堰き止めていたからだったのだ。私の能力が効かなかったのは、彼の「感じないようにする」という強い意志が、私の視界から色を奪っていたからに他ならない。
「音葉さん」
彼は、初めて私の名前を呼んだ。
「君が僕を特別だと言ってくれたように、僕にとっても、君は特別だった。君といると、世界を覆っていた分厚い無音の壁に、少しだけ隙間ができる気がしたんだ。そこから、君の静かな声が聞こえてくる。それが心地よかった」
私は、堰を切ったように涙が溢れるのを感じた。理解されないと諦めていたこの世界で、同じ痛みを抱える人に出会えた奇跡に。
「あなたの色が、見たい」
涙声で、私は願った。心の底からの、純粋な願いだった。
「あなたの本当の気持ちを、この目で見たいんです」
陽向さんは戸惑うように目を伏せたが、やがて意を決したように、私の頬にそっと触れた。
その瞬間、世界が変わった。
彼の身体から、眩いばかりの光が溢れ出したのだ。それは、私が今まで見たどんな色とも違っていた。悲しみの深い藍、後悔の滲む灰色、失われた日々への愛惜を示す金色、そして、私への戸惑いと優しさが溶け合った柔らかな光。それら全ての色が混じり合い、乱反射し、まるで透明な虹のようにきらめいていた。それは、彼の心のありのままの姿。傷つき、それでもなお、誰かを想おうとする魂の色彩だった。
第四章 名前のない私たち
陽向さんの放つ透明な虹彩に見惚れていた私は、ふと、自分自身の胸の内に、小さな温かい光が灯っていることに気づいた。それは、今まで見たことのない、名付けようのない色だった。金色でもあり、桜色でもあり、そして陽向さんの虹を映したように、いくつもの光が混じり合って揺らめいている。
これが、私の色。
初めて自覚した自分自身の感情の輝きは、他人の色を見るよりもずっと、温かく、確かだった。色を見るこの能力は、もう他人の心を無遠慮に覗き見るための呪いではない。誰かを深く理解し、その痛みに寄り添い、愛するための道標だったのだ。
私たちは、互いの全てを完全に理解し合えるわけではないことを知っている。陽向さんの悲しみが、明日すぐに消えるわけではない。私もまた、街に溢れる無数の色彩に、これからも戸惑い続けるだろう。
それでも、私たちは手を取り合った。固く閉ざされていた彼の世界に、私が差し込む一筋の光となり、色彩の洪水に溺れていた私の世界に、彼という名の静かな安息の場所が生まれた。
「この気持ちに、まだ名前はつけられないかもしれない」
陽向さんが、私の手を取りながら、少し照れたように言った。
「でも、君と一緒に、その名前を探していきたい」
「はい」
私は、涙で濡れた顔のまま、力強く頷いた。
名前のない感情に、二人でゆっくりと「愛」という名前をつけていけばいい。不確かで、時に傷つけ合うかもしれない未来を、それでも二人で歩いていく。
店を出ると、雨上がりの空には、本物の虹が架かっていた。世界は今日も、数え切れない色と、まだ聞こえない無数の音に満ちている。けれど、私の隣には、透明な虹を宿した、世界でただ一人の人がいる。もう、私たちは色彩や音に惑わされたりしない。互いの手の温もりだけが、確かな真実だと知っているから。