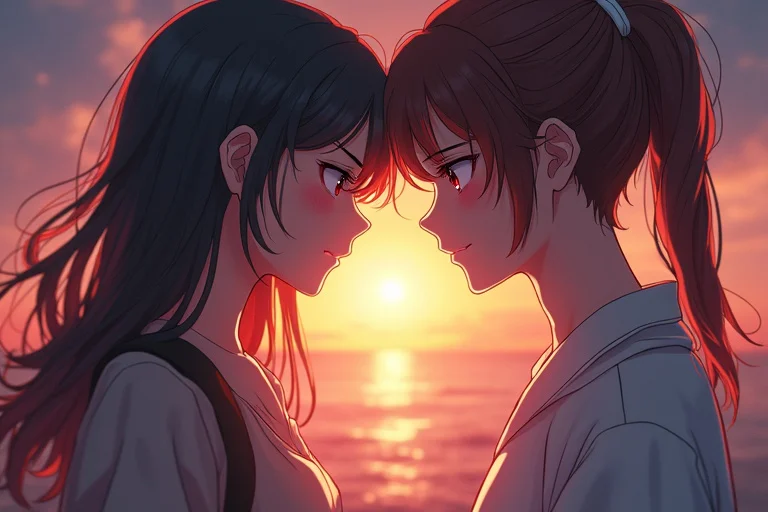第一章 始まりの不在
朝の光が薄いカーテンを透かして、アキトの寝室に白い帯を落としていた。アラームの電子音と共に、ぼんやりとした意識が浮上する。目を開けると、まず目に飛び込んできたのは、ベッドサイドテーブルに不自然に置かれた一枚の写真だった。淡い桜色の背景に、柔らかな笑顔を浮かべた女性。見慣れない顔だ。写真の傍には、達筆とは言えない手書きのメモ。「初めて恋に落ちた日」。
誰だ、これ?
指先でそっと写真をなぞる。ひどく懐かしいような、それでいて全く覚えのない感覚が、胸の奥をざわつかせた。昨日まで、いや、一昨日まで、ここにこんな写真はなかったはずだ。そして、この女性と「恋に落ちた」記憶など、微塵もない。なのに、メモ書きの文字は確かにアキト自身の筆跡だった。
「…夢、だったのか?」
思わず呟くが、答えはない。ただ、胸に巣食うのは、甘く、しかし、取り返しのつかない喪失感だった。まるではるか昔に経験した、大切な何かを置き忘れてきたような。そんな漠然とした感情を抱えながら、アキトは重い体を起こした。
新しい職場での初日だ。出版社で編集者としてのキャリアをスタートさせる。心機一転、新たな環境に飛び込む高揚感が、わずかな不安と混じり合う。
オフィスは活気とインクの匂いに満ちていた。案内されたデスクは窓際で、都会の喧騒が遠く聞こえる。隣の席に座っていたのは、ショートヘアの快活な女性だった。
「こんにちは!私、ユイです。アキトさんですよね?今日からよろしくお願いします!」
彼女は明るく笑い、差し出された手のひらは、驚くほど温かかった。ユイの瞳は深い茶色で、そこに宿る好奇心と親しみやすさが、アキトの緊張を少しだけ和らげた。
「アキトです。よろしくお願いします、ユイさん。」
そう答えるアキトの脳裏には、まだ朝の女性の笑顔が、ぼんやりとした輪郭で貼り付いていた。ユイと話していると、その残像は次第に薄れていく。新しい出会いの新鮮さが、彼の記憶の不確かさを覆い隠していくようだった。
数週間が過ぎ、アキトは仕事に慣れ、ユイとの会話も増えていった。ユイは常に新しいアイデアに満ちていて、その情熱は周囲を巻き込む力があった。アキトはそんなユイに、少しずつ惹かれ始めていることを自覚した。彼女の笑い声は、オフィスに差し込む午後の陽光のように暖かく、アキトの心に柔らかな波紋を広げた。
ある日、休憩中にユイが不意に尋ねた。
「アキトさんって、前にどんな恋愛してたんですか?」
アキトの心臓が、微かに跳ねた。
「え…?ああ、まぁ、いくつか…」
曖昧な返事しかできない。ユイは首を傾げた。
「何か含みのある言い方ですね。秘密ですか?」
「いや、そういうわけじゃ…ただ、あまり昔のことは思い出せなくて」
笑顔でごまかすアキトに、ユイは不思議そうな顔をしたまま、それ以上は詮索しなかった。
しかし、アキトの心にはまた、あの朝の漠然とした喪失感が蘇っていた。写真の女性。彼女との「初めての恋」。なぜ、その記憶だけが、これほどまでに曖昧なのだろう。彼の人生のどこかに、ぽっかりと穴が開いているような感覚。アキトは、その穴の正体を知ることを、無意識に恐れていた。
第二章 記憶の欠片と、芽生える旋律
ユイとの関係は、急速に深まっていった。仕事の合間の休憩時間、終業後の飲み会、そして週末のデート。二人の時間は、まるで春の陽光に誘われる花々のように、自然と咲き誇った。ユイはアキトが提案するどんなデートにも、目を輝かせて付き合ってくれた。古い映画館でレトロな映画を観たり、人気のない裏通りのカフェで何時間も語り合ったり、美術館で抽象画の前でそれぞれの解釈を述べ合ったり。彼女の感性は豊かで、アキトの心の奥底に眠っていた情熱を呼び覚ますようだった。
アキトは、ユイとの一瞬一瞬を大切にしようとした。スマホのカメラロールは、ユイの笑顔で埋め尽くされ、日記帳には、彼女との会話や、感じたことが詳細に綴られていった。まるで、このかけがえのない時間を、何かの力から守ろうとするかのように。しかし、心のどこかで、アキトは常に一抹の不安を抱えていた。まるで、掴んだ砂が指の隙間からこぼれ落ちていくような感覚。
ユイもまた、アキトのどこか影のある部分に気づき始めていた。
「アキトさんって、昔の話をする時、いつもちょっと寂しそうな顔をしますね」
ある日、帰り道でユイがアキトの顔を覗き込むように言った。
「そうかな?」
アキトは苦笑いを浮かべた。
「うん。なんか、大切なものをどこかに置いてきちゃったみたいに。私には話せないこと、なのかな?」
ユイの眼差しは、心配と優しさに満ちていた。アキトは、そんな彼女に、自分の抱える秘密を打ち明けたい衝動に駆られた。しかし、それはあまりにも非現実的で、そして恐ろしい話だった。
過去の恋の記憶が、曖昧なだけでなく、まるで上書きされたかのように消えていくこと。ある日突然、誰かの顔が思い出せなくなったり、かつて恋人と訪れた場所が、ただの風景にしか見えなくなったりすること。アキトはこれを、自分の脳の欠陥か、あるいは心の病だと密かに思っていた。だからこそ、ユイに話す勇気が持てなかった。彼女に、自分を異質な存在だと思われたくなかった。
それでも、ユイへの思いは募るばかりだった。彼女の存在は、アキトの人生に鮮やかな色彩を与えてくれた。彼女の隣にいると、失われた過去の空白など、どうでも良いとさえ思えるほどだった。アキトは、記憶の不確かさよりも、今この瞬間の幸福を選ぶことを決意した。彼の心は、ユイという新しい旋律を奏で始めていた。過去の不協和音をかき消すかのように、力強く、そして美しく。
第三章 上書きされた真実
ユイとの関係は、やがて恋人へと発展した。初めて手をつないだ夜、カフェの喧騒の中で彼女の指がアキトの指に触れた瞬間、電流のような衝撃が走った。そして、初めてキスを交わした夜、アキトは自分が今まで経験したことのない深い安らぎと、燃えるような情熱に包まれるのを感じた。ユイの柔らかな唇が自分の唇に触れたその刹那、アキトの頭の中で、まるで古いフィルムが破れるような、奇妙な音が響いた。
翌朝、目覚めたアキトは、部屋の違和感に気づいた。いつも置いてあるはずの、小学校の頃から大切にしていた、年季の入った地球儀が見当たらない。代わりに、ユイが誕生日にくれた、新しいデスクライトが置かれている。さらに、学生時代に苦心して作った、初めての詩集が収められていたはずの棚には、別の本が並んでいた。
「あれ…?」
心臓が締め付けられるような不安に襲われる。スマホを手に取り、かつて頻繁に連絡を取っていたはずの、小学校からの親友の名前を検索した。しかし、連絡先はおろか、その親友との思い出が全く、と言っていいほど、思い出せない。名前も、顔も、声も、全てが霧の中だった。
アキトは震える手で、日記帳を開いた。そこには、ユイとの日々に加えて、過去の恋愛の記録も綴られていた。しかし、数ページをめくると、ある時期からの記述が、完全に空白になっていることに気づいた。そして、その空白の直前のページには、あの朝、写真で見た女性との恋が、熱く綴られていた。
「嘘だ…」
アキトは愕然とした。恋に落ちるたびに、過去の恋の記憶が上書きされて消える。それは漠然とした不安ではなく、彼の確固たる現実だった。そして、今回消えたのは、かつての恋の記憶だけではなかった。親友との思い出。大切にしていた物。そして、自分の半生を形成していたはずの、ごく個人的な記憶の数々。
アキトの体質は、新しい恋に落ちるたびに「最も古い恋の記憶」を消去するだけでなく、その「恋の記憶」と強く結びついていた「他の大切な記憶」まで巻き添えにして消去していく、という恐ろしいものだったのだ。まるで、コンピュータのデータが、関連ファイルごと削除されていくように。
ユイとの愛によって、アキトはかけがえのない幸福を手に入れた。しかし、それは同時に、彼の一部を蝕む毒でもあった。過去の自分を構成するピースが、また一つ、永遠に失われたのだ。彼は喜びと喪失が同時に押し寄せる感情の濁流に飲まれ、自分が一体何者なのか、その存在意義さえ揺らぐような深い混乱に陥った。ユイへの愛が深まるほどに、自分という人間が、削り取られていく。この残酷な真実に、アキトはただ、絶望するしかなかった。
第四章 忘却の果て、愛の調べ
アキトは憔悴しきっていた。目の前のユイは眩しいほどに輝いているのに、アキトの心は深い闇の底に沈んでいた。ユイへの愛が、彼の過去を、彼自身の輪郭を、少しずつ消し去っていく。このまま愛し続ければ、いずれアキトという存在は、ただの「空白」になってしまうのではないか。
ユイもアキトの異変に気づいていた。アキトは笑顔が少なくなり、食事も喉を通らないようだった。ある夜、ユイはアキトを抱きしめ、優しく囁いた。
「アキトさん、何かあったんでしょう?私には話せない?」
その優しい声が、アキトの心のダムを決壊させた。彼は震える声で、自分の体質の全てをユイに打ち明けた。過去の恋が消えること。そして、今回、親友や幼い頃の記憶まで失われたこと。ユイは、アキトの言葉を聞くうちに、その瞳に驚きと悲しみが広がっていくのが見て取れた。
しばらくの沈黙の後、ユイはゆっくりと顔を上げた。
「…信じられない話だけど、アキトさんがそんなに苦しんでいるなら、本当のことなんだね」
彼女の表情は、どこか遠くを見つめているようだった。アキトは恐怖に震えた。彼女はきっと、自分から離れていくだろう。この不気味な体質の人間を、誰も愛し続けることはできない。
しかし、ユイは静かにアキトの手を握りしめた。その手は、初めて出会った時と同じように、温かかった。
「アキトさん、あなたは今、私を愛してくれている。その記憶は、今、ここにある。それが、何よりも大切なことなんじゃない?」
ユイの言葉は、アキトの凍りついた心に、一筋の光を灯した。
「でも…僕があなたとの記憶すら、いつか失ってしまうかもしれない。そして、もっと大切なものを、未来の愛と引き換えに失うかもしれないんだ…」
アキトの声は震え、恐怖がにじんでいた。
「それでも、私はあなたを愛したい」
ユイはまっすぐにアキトの瞳を見つめた。
「記憶は消えても、今の感情は消えない。あなたが私と出会って、私を愛したという事実は、誰にも消せない。それに…もし、あなたが私との記憶を失ったとしても、私が、あなたに何度でも、私との『初めての恋』を教えてあげる。何度でも、あなたを私に恋させる」
アキトは息を呑んだ。ユイの言葉は、彼の心の奥底に響き渡る、忘れていた旋律のようだった。記憶は、過去の記録かもしれない。しかし、愛は、今この瞬間に生まれ、未来へと続いていく、生きた感情だ。記憶が消えても、愛が消えるわけではない。むしろ、記憶の喪失と引き換えに、今ここにある愛の尊さが、より鮮やかに浮き彫りになるのではないか。
アキトは、ユイの温かい手を取り、深く頷いた。記憶を失うことへの恐怖は完全に消えたわけではない。しかし、ユイの言葉が、その恐怖を包み込む柔らかな光になった。彼は悟った。愛とは、記憶の積み重ねだけで構築されるものではない。それは、たとえ過去が曖昧になろうとも、今この瞬間を全身で感じ、未来へと歩み続ける、揺るぎない「選択」なのだと。
二人はそれから、より一層、一日一日を大切に生きるようになった。写真は撮り続け、日記も書き続けた。それは、記憶を留めるためだけでなく、愛が確かにここにあったという証を、未来の自分たちに残すためだった。
いつか、アキトの記憶が全て消え去り、彼が「アキト」でなくなる日が来るのかもしれない。しかし、その時、ユイが隣で、彼に何度でも「私たちが出会った日」を語りかけるだろう。何度でも、彼を自分に恋させるだろう。記憶の海に沈む航海士のように、アキトはユイという確かな愛だけを羅針盤に、未来へと進んでいく。失われた旋律の代わりに、二人の愛が奏でる、新しい調べが、静かに世界に響き渡っていた。