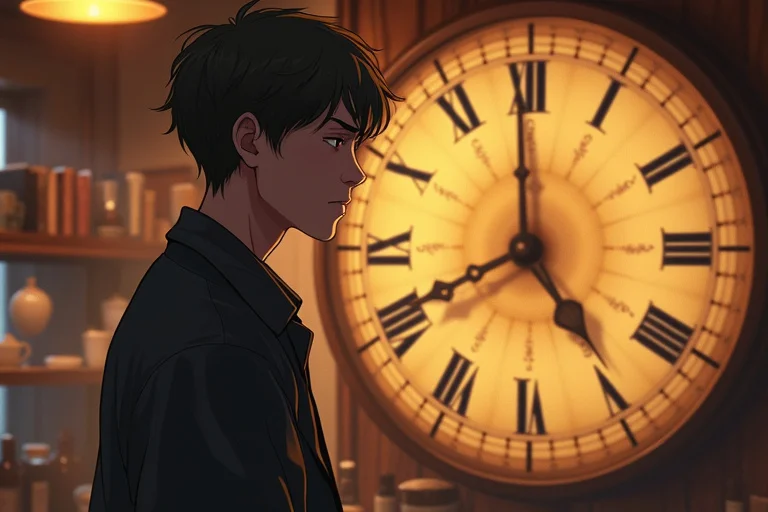第一章 二重写しの影
水島湊(みずしまみなと)にとって、世界は常に少しだけ歪んでいた。それは視力の問題ではない。彼の目に映る世界は、他の人間が認識するものに、一つの余計な情報――嘘の可視化――が加わっているからだ。人が嘘をつくと、その足元の影が、まるで焦点の合わない写真のように、わずかにブレて二重になる。湊がこの奇妙な現象に気づいたのは、サンタクロースはいないのだと悟った、まだ幼い冬の日だった。
以来、彼の日常は影の観察と共にあった。「今日の夕飯は湊の好きなハンバーグよ」と微笑む母の影は一つ。「この企画なら必ず通る」と豪語する上司の影は二つ。「愛してる」と囁いた恋人の影は、ある日を境に、常に揺らめき続けた。些細な見栄、相手を傷つけないための配慮、悪意に満ちた欺瞞。あらゆる嘘が、影の二重奏となって彼の目に映り、湊は次第に人を信じる術を失っていった。
人間関係に疲れ果てた湊が安住の地として選んだのは、神保町の路地裏にひっそりと佇む古書店『彷徨書房』だった。古紙とインクの香りが満ちる静寂の中、言葉を尽くしても嘘をつくことのない本に囲まれる時間は、彼にとって唯一の救いだった。店長の田中さんは人の好い老人で、「腰が痛くてねえ」と言いながら矍鑠(かくしゃく)と重い本棚を動かす時くらいしか、影を二重にすることはなかった。
そんな湊の灰色だった日常に、予期せぬ色彩がもたらされたのは、木犀の香りが街角に漂い始めた秋のことだった。
一人の女性が、ふらりと店に現れた。歳は湊と同じくらいだろうか。陽だまりをそのまま切り取って織り上げたような、柔らかな栗色の髪。彼女は店に入ると、嬉しそうに息を吸い込み、「わあ、いい匂い」と呟いた。その声は、乾いた湊の心に染み渡る清らかな水音のようだった。
彼女は小夜子(さよこ)と名乗った。それから毎日、同じ時間に店を訪れては、一冊の本を熱心に選び、窓際の席で静かに読んでいくのが日課になった。湊はカウンターの奥から、彼女の姿を盗み見るようになった。彼女が笑うと、埃っぽい店内の空気がきらきらと輝くように感じられた。
そして何より、湊を驚かせたのは、彼女の影だった。窓から差し込む西日が、彼女の足元にくっきりとした影を落とす。それはただの一本の、揺らぐことのない、完璧な影だった。
「この本、面白いですか?」
ある日、湊は勇気を出して話しかけた。小夜子が読んでいたのは、彼が特に好きな、忘れられた作家の短編集だった。
「ええ、すごく。言葉の一つ一つが、宝物みたい」
彼女は顔を上げ、花が綻ぶように笑った。その影は、やはり静かな単線を保っている。
この人は、嘘をつかない。
その事実は、湊にとって奇跡のように思えた。彼の歪んだ世界の中で、唯一、歪みのない存在。湊の心に、何年も前に枯れてしまったはずの泉から、再び水が湧き上がるような感覚が芽生えていた。
第二章 陽だまりの単旋律
小夜子と過ごす時間は、湊の世界から影の揺らめきを消し去った。二人は急速に親しくなり、古書店の定休日には、公園を散歩したり、小さなカフェで他愛のない話をしたりして過ごした。
「湊さんは、どうして古本屋さんで働いているの?」
珈琲の湯気が立ち上る中、小夜子が尋ねた。
「……本が好きだから。本は、正直だからかな」
湊は言葉を選びながら答えた。自分の能力のことは、もちろん言えない。この安らかな時間を壊したくなかった。
「正直、か。わかる気がする。ページをめくると、そこに書かれていることが全てだものね。行間はあるけど、裏切りはない」
小夜子は納得したように頷き、その影は静かなままだった。
彼女といると、湊は自分が普通の人間に戻れたような気がした。人の顔色を窺い、言葉の裏を探り、影の揺れに怯える必要がない。小夜子の発する言葉は、彼女の心と完全に一致しているように思えた。彼女が「楽しい」と言えば、世界は本当に楽しくなった。「美味しい」と言えば、味気ないサンドイッチさえもご馳走に感じられた。
ある雨の日、二人は映画を観に行った。上映が終わり、エンドロールが流れる薄闇の中、小夜子の指がそっと湊の手に触れた。驚いて彼女の方を見ると、スクリーンのかすかな光がその横顔を照らしている。彼女はまっすぐ前を見つめたまま、微かに微笑んでいた。湊は、おそるおそるその指を握り返した。温かく、柔らかな感触。心臓が大きく高鳴り、全身の血が熱を帯びるのがわかった。この幸福が、永遠に続けばいい。彼は心からそう願った。
湊は変わり始めていた。これまで人間関係を「嘘か真実か」の二元論でしか見られず、影の揺れを断罪の証拠として切り捨ててきた。だが、小夜子という嘘のない存在を前にして、初めて人を信じるという、温かくも心許ない感覚を味わっていた。この能力を持って生まれてきた意味も、もしかしたら、この人と出会うためにあったのかもしれない。そんな夢想さえ抱くようになっていた。
彼の日常は、もはや灰色ではなかった。小夜子という太陽が、彼の世界を鮮やかに照らし、全ての影を本来あるべき一つの姿に戻してくれていた。
第三章 砕け散る陽光
季節は冬に移り、街路樹の葉はすっかり落ちて、冷たい風が吹き抜けるようになった。湊と小夜子の関係は、誰が見ても恋人同士と呼べるほどに深まっていた。その日、二人は初めて湊の部屋で過ごしていた。古書店で買った古いレコードに針を落とし、温かいココアを飲みながら、窓の外で舞い始めた雪を眺めていた。
部屋は、湊が長年かけて築き上げた、他人を寄せ付けないための静かな要塞だった。その場所に、小夜子がいる。彼女の穏やかな呼吸が、部屋の空気を優しく震わせている。それは、湊にとって信じられないような光景だった。
「湊さんといると、本当に、本当に楽しい」
小夜子が、窓の外に視線を向けたまま、ぽつりと呟いた。その声は、心の底からの響きを伴っているように聞こえた。
「僕もだよ」
湊は答えた。幸福が胸いっぱいに満ち、息が詰まりそうだった。この瞬間を永遠に焼き付けたい。そう思いながら、彼は何気なく、床に落ちる彼女の影に目をやった。
そして、凍りついた。
ストーブのオレンジ色の光に照らされた小夜子の影が、くっきりと、残酷なほど明確に、二重に揺れていた。
時が止まった。レコードの音楽も、窓の外で舞う雪も、遠い世界の出来事になった。湊の耳には、自分の心臓が砕け散る音だけが響いていた。
嘘だ。
今、彼女が言った「楽しい」という言葉は、嘘だった。
頭が真っ白になった。なぜ?どうして?何が嘘なんだ?この温かい時間も、穏やかな笑顔も、全てが偽りだったというのか?信じていた世界が、足元から音を立てて崩壊していく。ガラスの城が粉々に砕け散るように、湊が小夜子と共に築き上げてきた幸福な日々が、一瞬にして瓦礫と化した。
「……どうか、したの?」
湊の異変に気づいた小夜子が、心配そうに顔を覗き込む。その表情には一点の曇りもない。だが、その足元の影は、依然として不吉に揺らめき続けている。
「……いや、なんでもない」
湊は、声を絞り出すのがやっとだった。喉が渇き、指先が氷のように冷たい。
彼は小夜子を直視できなかった。彼女の顔を見れば、その裏側にある欺瞞を暴いてしまいそうだった。これまで嫌というほど見てきた、揺らめく影。それは今、彼が世界で最も信じていたはずの女性の足元で、嘲笑うかのように踊っている。
その日、湊は体調が悪いと嘘をつき、小夜子を帰した。一人きりになった部屋で、彼はただ呆然と立ち尽くすしかなかった。陽だまりは、幻だったのだ。
第四章 きみがくれた真実
それから数日、湊は小夜子を避け続けた。店に彼女が来ても、田中さんに接客を任せ、自分は倉庫の奥に閉じこもった。電話にも出ず、メッセージにも返信しなかった。心は千々に乱れていた。彼女の何が嘘だったのか。自分との時間そのものが苦痛だったのか。それとも、他に好きな人がいるのか。あらゆる可能性が、毒虫のように彼の思考を蝕んでいった。
このままではいけない。苦悩の末、湊は一つの結論に達した。たとえどれほど残酷な真実が待っていようと、彼女と向き合わなければならない。この能力から逃げ続けてきた人生に、今度こそ終止符を打つのだ。
湊は、小夜子をいつもの公園に呼び出した。枯れ木が寒々と空に枝を伸ばす、冬の公園。ベンチに座る彼女の姿は、小さく、儚げに見えた。
「話があるんだ」
湊は切り出した。心臓が嫌な音を立てている。
「僕には……昔から、人にはないものが見える。人が嘘をつくと、その人の影が、二重に見えるんだ」
小夜子の目が、驚きに見開かれる。湊は構わず続けた。
「君と出会って、初めて世界が普通に見えた。君の影は、いつも一つだったから。だから、君だけは信じられると思った。でも……この間、僕の部屋で、『楽しい』と言った時、君の影は二重に見えた。どうしてなんだ、小夜子。何が嘘だったんだ?」
彼の言葉に、小夜子は俯いた。長い沈黙が、冷たい空気の中に落ちる。やがて、彼女の肩が小さく震え始めた。ぽつ、ぽつ、と乾いた地面に涙の染みができていく。
「……ごめんなさい」
か細い声が、ようやく紡がれた。
「嘘じゃ、ないの。湊さんといる時間は、本当に楽しくて、幸せで……生まれてきてよかったって、心から思える。でも……」
彼女は顔を上げ、涙に濡れた瞳で湊を見つめた。
「でも、その度に思ってしまうの。『この幸せは、長くは続かない』って。『私は、もうすぐこの人の前からいなくなってしまうんだ』って」
小夜子は、静かに自分のことを語り始めた。彼女は重い病を患っており、残された時間は決して多くないこと。治療法はなく、ただ穏やかに最期の日々を過ごすことしかできないこと。
「『楽しい』って思う気持ちは、本当なの。でも、その気持ちと同時に、あなたを一人残していくことになるっていう、どうしようもない罪悪感と悲しみが、胸を締め付けるの。私の『楽しい』には、いつも『ごめんなさい』がくっついている。言葉にできなかった、私のもう一つの気持ち……それが、あなたの言う『嘘』だったのかもしれない」
湊は、息を飲んだ。
そうか。影が映し出していたのは、単純な「偽り」ではなかったのか。
それは、言葉にできない想い。隠された痛み。相手を深く想うが故に生まれる、心の矛盾。喜びと悲しみが分かちがたく結びついた、複雑な感情のグラデーションそのものだったのだ。
彼は、この能力を呪い、人を白か黒かで断罪する道具として使ってきた。影が揺らげば「嘘つき」、揺らがなければ「正直者」。なんと浅はかで、傲慢な見方だったのだろう。
小夜子の二重の影は、彼女の欺瞞の証ではなかった。それは、彼女の深い愛情と、悲痛な叫びの証だったのだ。
湊は、震える手で小夜子の手を握った。涙で滲む視界の中で、彼女の足元の影がどうなっているかなど、もうどうでもよかった。
「気づいてあげられなくて、ごめん」
彼の声も、震えていた。
「君の嘘ごと、君の痛みごと、全部僕にください。君がくれるものなら、それがどんな真実だって受け止めるから」
小夜子は、堰を切ったように泣きじゃくった。湊は、その小さな体を強く抱きしめた。
彼の目に、もう影の揺らめきは映らない。ただ、腕の中にいる愛おしい人の温もりと、鼓動だけが、確かな真実としてそこにあった。
二人の間に言葉はなかった。しかし、その沈黙は、これまでのどんな言葉よりも雄弁に、互いの心を繋いでいた。冬の空はどこまでも高く澄み渡り、二人の影を、ただ静かに、一つだけ地面に映し出していた。それは、これから始まる、短くも、かけがえのない時間の、始まりの影だった。