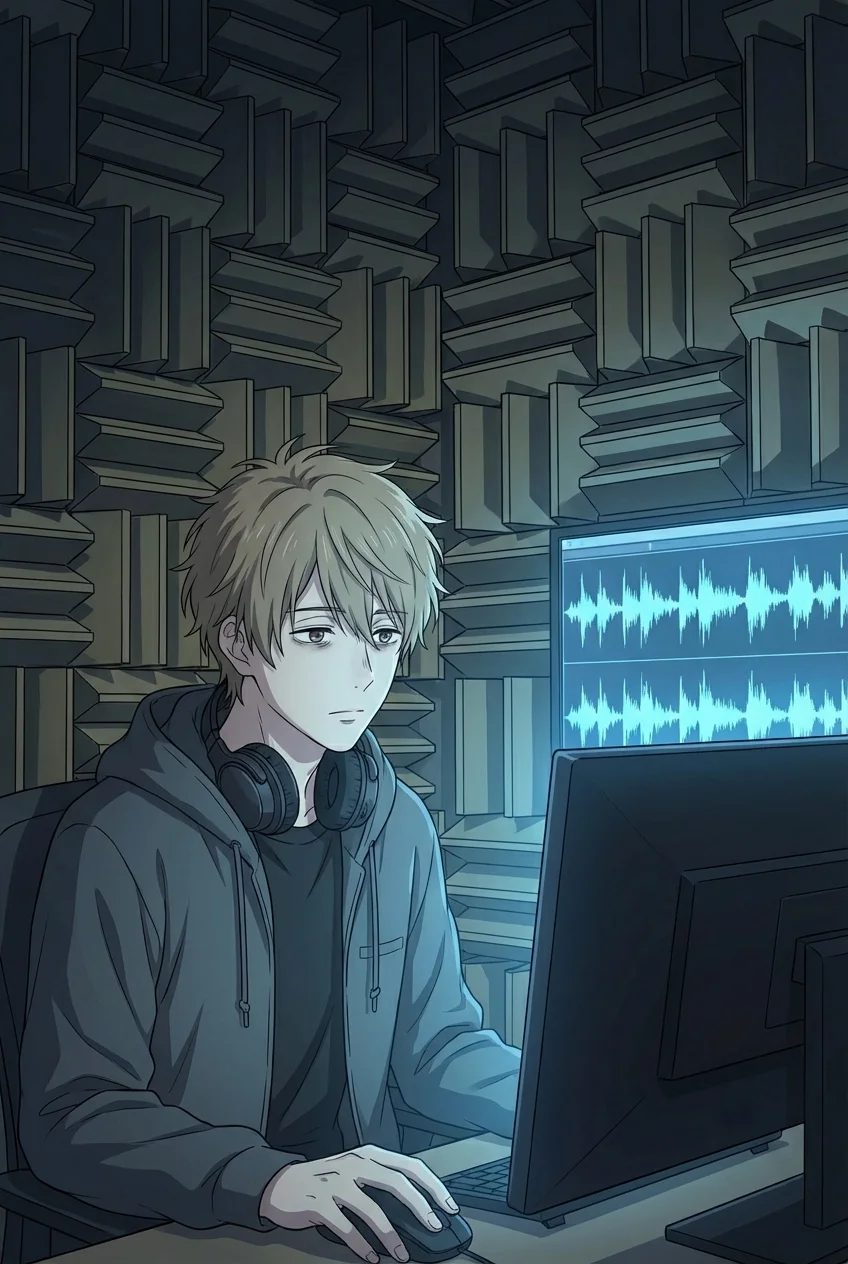第一章 灰色のノイズ
古書店『時雨堂』の空気は、いつも同じ匂いがした。古い紙の乾いた甘さと、微かな黴、そして主人が淹れる深煎り珈琲の香ばしさが混じり合った、静かな匂いだ。俺、水無月湊は、そのカウンターの奥で分厚い革装丁の本を修繕しながら、壁の一点をぼんやりと見つめていた。
壁の、天井に近い部分にある雨漏りのシミ。昨日と寸分違わぬはずのそのシミが、俺の目にはほんのわずかに、くすんだセピア色に傾いて見えた。それは他の誰にも知覚できない、ごく微細な色の変化。俺はそれを、子供の頃から「時間のノイズ」として認識していた。世界がほんの少しだけ疲れて、その色合いを変える瞬間。バスの窓から見える街路樹の葉が刹那的に彩度を失ったり、毎日使うマグカップの縁の光沢が、昨日より鈍く見えたり。それは日常に溶け込んだ、俺だけの秘密だった。
「湊くん、そろそろ閉めるよ」
店主の優しい声に我に返る。時計の針は、とっくに閉店時間を示していた。古書の修繕に没頭すると、いつもこうだ。礼を言って店を出ると、六月の湿った夜気が肌を撫でた。アスファルトを濡らす街灯の光も、今夜は心なしか黄色が強い。世界のあちこちで、人々がいつものルーティンを少しだけ崩したのだろう。その小さな揺らぎが集合して、時間の流れに微細な歪みを生む。俺にはそれが、色のノイズとして見えるだけだ。
自室に戻り、机の引き出しからくたびれた日記帳を取り出す。万年筆を手に取り、インク瓶の蓋を開けた。濃紺の、静かな夜の色。今日の出来事を書き留めるのは、もう十年以上続く習慣だ。けれど、書き終えた文字に目を落とした俺は、微かに眉をひそめた。インクの色が、昨日書いた文字よりも、ほんの少しだけ赤みを帯びている。まるで、乾ききらないうちに、誰かが指でそっと滲ませたかのように。
第二章 揺らぐインク
翌日から、俺は意識的に日記の文字色を観察するようになった。気のせいではなかった。月曜のインクは冴えた青に近づき、火曜は赤みが差し、水曜は緑がかった黒に見える。まるで、曜日ごとに異なるインクを使っているかのようだ。だが、俺が使っているインクは、十年近く愛用している『夜の海』という名の、ただ一種類の濃紺色だけだった。
これは、ただの「ノイズ」とは違う。
壁のシミや街路樹の葉が見せる不規則な色の変化とは、明らかに異質だった。日記の色の変化には、ある種の規則性と、そして……意図が感じられた。
ある日の午後、店番をしながらぼんやりと考えていた。人々の「習慣」の集合的な揺らぎが、その地域の時間を周囲から少しだけ『借りる』。その結果、どこか別の場所で時間の流れが歪む。電車が数秒遅延しただけで、遠い国のカフェでは珈琲が冷めるまでの時間がコンマ数秒速くなる、というような現象が、世界中で無数に起きている。俺はそれを、色の変化として見ているに過ぎない。
だが、俺の日記だけが、毎日規則的に色を変えている。
それはつまり、誰かが意図的に、俺の『日常』という安定した時間から、毎日決まった量を『借りて』いるということではないか。俺の、古書店とアパートを往復するだけの、代わり映えのしない、けれど揺らぐことのないこの日常を。その行為の痕跡が、インクの色のズレとして残っている。
背筋に冷たいものが走った。一体、誰が。何のために。俺の時間を盗んでいるのは。
第三章 褪せた約束
俺は過去の日記をすべて引っ張り出し、机の上に広げた。十年分の日記帳が、小さな塔のように積み上がる。ページをめくるたびに、インクの微細な色の変化が目に飛び込んできた。セピア、藍、深緑、赤銅……まるで、感情のパレットのようだ。しかし、その法則性は掴めない。
何日もかけて色の変化をノートに記録していく中で、俺はひとつの奇妙な事実に突き当たった。たった一日だけ、インクの色が全く変化していないページがあったのだ。
五年前の、十月二十七日。
その日付を見た瞬間、胸が詰まった。忘れるはずもない。親友の雄介が、事故で死んだ日だ。その日の日記には、たった一行だけ、こう書かれていた。
『忘れない。お前との約束も、お前のことも』
その文字だけが、発売されたばかりのインクで書いたかのように、一点の曇りもない、完璧な『夜の海』の色を保っていた。俺の強い想いが、時間の借り入れを拒絶したのだろうか。この揺るがない一日が、全ての基準点になるのかもしれない。
俺はこの日を基点として、前後のページの色変化を再分析し始めた。色のズレを数値化し、波形のようにグラフに落とし込む。すると、バラバラに見えた色の羅列が、意味のあるパターンを描き始めたことに気づいた。それは、まるで誰かが送ってくる、不器用な信号のようだった。俺の平穏な日常のすぐ足元で、何かが静かに、しかし確実に進行している。その予感が、心臓を冷たく締め付けた。
第四章 未来からの警告
解読は困難を極めた。だが、色の三原色の比率を数列に置き換え、さらにそれを文字コードに変換するという方法を試した時、ついに意味のある言葉が浮かび上がった。それは、途切れ途切れの、悲鳴のようなメッセージだった。
『モウ時間ガナイ』
『世界ガ崩レル』
『シズカナ日常ヲ守レ』
心臓が大きく脈打った。これは、未来からの警告だ。俺の時間を借りているのは、未来の誰かなのだ。そして、その人物は、来るべき『日常の破綻』を俺に伝えようとしている。
ページをめくり、最近の日付に近づくほど、メッセージは切迫したものになっていく。そして、昨日の日付のページ。そこに記されていた色のズレが示した言葉に、俺は息を呑んだ。
『明日、彼女に会うな』
明日。俺には、約束があった。大学時代の友人で、ずっと心の片隅で想い続けていた女性、早瀬沙耶と、五年ぶりに会う約束が。偶然街で再会し、食事でもしないかと誘われたのだ。ここ数週間、その約束だけを支えに生きてきたと言っても過言ではなかった。
なぜ、沙耶に会ってはいけない?
彼女に会うことが、なぜ世界の崩壊に繋がる?
頭が混乱する。汗がこめかみを伝い、床に落ちた。その時、ふと気づいた。俺の日常の時間を、これほど正確に、継続的に借りることができる存在。俺の思考や感情が時間に与える影響を、完璧に理解している存在。
そんなことができるのは、世界にただ一人しかいない。
未来の、俺自身だ。
第五章 選択のパレット
未来の俺が、過去の俺の時間を借りている。来るべき世界の崩壊を防ぐために、過去の安定した日常からエネルギーを少しずつ引き出しているのだ。そして、その崩壊のトリガーが、明日、俺が沙耶に会うこと……。
馬鹿げている。でも、日記のインクが示す警告は、疑いようもなくそこにあった。俺と沙耶が再会し、もし、万が一、新しい関係が始まったら? 俺の人生は大きく変わるだろう。古書店を辞めるかもしれない。この街を出るかもしれない。俺の『静かで安定した日常』は、完全に失われる。未来の俺がエネルギー源としていた、この揺るぎない時間が。
俺は、どうすればいい。
何年も胸に秘めてきた想いを遂げるチャンスを捨てるのか? 世界の危機なんていう、荒唐無稽な警告のために?
いや、荒唐無稽ではない。俺は毎日、この目で世界の歪みを見てきた。時間の貸し借りが現実に存在することを知っている。
窓の外は、どす黒い雲が垂れ込めていた。雨粒が窓ガラスを叩き始める。その音を聞きながら、俺は今日のページを開いた。そこには、まだ何も書かれていない。だが、その真っ白な紙面は、今まで見たこともないほど深く、濁ったセピア色に染まっていた。それはまるで、遠い未来で誰かが流している、血の涙の色のように見えた。未来の俺が、必死に叫んでいる。頼むから、踏みとどまってくれ、と。
選択の時は、迫っていた。
俺だけの、静かな日常。
それとも、沙耶との、まだ見ぬ未来。
天秤にかけられているのは、俺個人の幸せと、世界の運命だった。
第六章 僕が貸した時間
約束の喫茶店が見える、通りの向かい側に俺は立っていた。傘もささずに、冷たい雨に打たれながら。ガラス窓の向こう、柔らかな光の中に、沙耶の姿が見えた。少しだけ髪が伸びて、大人びた横顔。彼女は時々、心配そうに入り口に目をやっている。
胸が張り裂けそうだった。今すぐ駆け寄って、謝って、笑い合いたい。だが、俺の足はアスファルトに縫い付けられたように動かなかった。
俺はポケットからスマートフォンを取り出し、震える指でメッセージを打つ。『ごめん。急にどうしても外せない用事ができた。埋め合わせは必ずする』。嘘だ。埋め合わせなんて、きっとできない。
送信ボタンを押した瞬間、ふっと、世界から音が消えたような錯覚に陥った。
そして、視界の隅にあったショーウィンドウのガラスの色が、雨に濡れた街灯の光が、世界中の全ての色が、すうっと本来の落ち着きを取り戻していくのが分かった。まるで、張り詰めていた弦が緩んだかのように、世界の緊張が解けていく。
喫茶店の中から、沙耶がスマートフォンを見て、悲しそうに顔を伏せるのが見えた。すぐに立ち上がり、彼女は店を出ていく。俺とは逆の方向へ。その小さな背中が、雑踏に消えていくのを、俺はただ見ていることしかできなかった。
自室に戻り、日記帳を開く。
新しいインクで、今日のページに書き込んだ。
『今日、僕は大切な約束を破った』
その文字は、一点のズレもない、深く、鮮やかな黒だった。
俺は、未来の自分に『時間』を貸したのだ。沙耶との未来を諦めることで、俺の日常という名の『安定』を、最大の担保として差し出すことで。未来の俺は、俺が今日貸したこの膨大な時間を使って、今この瞬間も、世界の崩壊と戦っているのだろう。
失ったものの大きさは計り知れない。けれど、後悔はなかった。窓の外では、雨上がりの夕日が、いつもと同じ、優しいオレンジ色で街を照らしていた。このありふれた日常を、名もなき一日を、守ったのは紛れもなく俺なのだ。
俺はこれからも、この日記を書き続けるだろう。
決して会うことのない、未来で戦うもう一人の自分へ。
そして、いつかこの日常を守り抜いた彼が、過去の俺の選択を赦してくれる日が来ることを、静かに祈りながら。