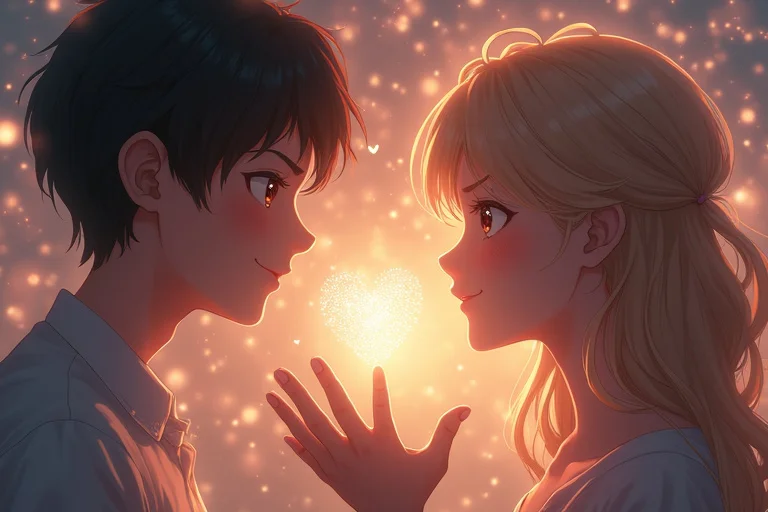第一章 見知らぬデジャヴ
柏木湊(かしわぎ みなと)の日常に最初の亀裂が入ったのは、梅雨入りを間近に控えた湿度の高い日のことだった。大学から帰宅し、愛用のデジタルカメラのデータを整理していると、見慣れない一枚の写真が目に飛び込んできたのだ。
それは、鮮やかな夏の日差しを浴びた海辺で、白いワンピースを着た幼い少女が屈託なく笑っている写真だった。古びた灯台を背景に、波が彼女の足元で白く泡立っている。構図も、光の捉え方も、紛れもなく自分の撮り方だ。だが、湊にはこの少女にも、この風景にも、一切の記憶がなかった。
不気味なのは、それだけではなかった。その写真を見つめていると、脳裏に奇妙な感覚が蘇る。頬を撫でる潮風の生暖かさ、裸足の裏に感じる湿った砂の粒子、そして遠くで鳴くウミネコの声。まるで自分がその場にいたかのような、鮮明すぎるデジャヴ。湊は混乱し、背筋に冷たい汗が伝うのを感じた。ハッキングか、あるいは自分の記憶がおかしくなってしまったのか。考えれば考えるほど、沼に足を取られるような不安に襲われた。結局、その写真は不気味な謎として、彼の心の片隅に澱のように沈殿した。
数日後、湊の前にその少女の面影を持つ人物が現れた。陽向悠(ひなた はるか)。大学の一般教養の講義で、偶然隣の席になった彼女は、太陽をそのまま人の形にしたような存在だった。色素の薄い髪は光を弾き、大きな瞳は常に好奇心で輝いている。人との間に見えない壁を築き、ファインダー越しに世界を観察することで安心感を得ていた湊とは、まさに正反対。
「それ、君が撮ったの?」
悠は、湊がノートパソコンで開いていた写真のポートフォリオを、何のてらいもなく覗き込んできた。彼女の距離感の近さに、湊は思わず体をこわばらせる。
「……ああ、まあ」
「すごい! なんだか、すごく優しい写真だね。世界と少しだけ距離を置いて、でも、その全部を愛おしそうに見てる感じがする」
核心を突く言葉に、湊は息を呑んだ。誰にも理解されたことのない、自分だけの感覚。それを、出会ったばかりの彼女がいとも簡単に見抜いてみせた。悠は屈託なく笑い、悪戯っぽく片目を瞑った。
「ねえ、今度私を撮ってよ。君のファインダー越しに、私がどう見えるのか知りたいな」
その申し出は、湊にとって日常を覆す挑戦状のように響いた。断る理由を探しているうちに、彼女の真っ直ぐな瞳に射抜かれ、気づけば小さく頷いていた。この時、湊はまだ知らなかった。陽向悠という存在が、自分の世界の輪郭を溶かし、根底から揺るがすことになるということを。そして、あの見知らぬ写真に隠された謎の鍵を、彼女が握っているということも。
第二章 侵食する色彩
悠との時間は、湊の世界を鮮やかな色彩で染め上げていった。最初はぎこちなかった撮影も、回数を重ねるうちに自然なものになっていく。公園のベンチで、夕暮れの河川敷で、雑踏の片隅で、湊は悠を撮り続けた。悠は天性の被写体だった。彼女はファインダーの前で泣き、笑い、怒り、そして静かに物思いに耽った。その全てが絵になり、湊の心を捉えて離さなかった。
二人は急速に親しくなった。講義の合間も、休日も、共に過ごす時間が増えていく。他人と深く関わることを避けてきた湊にとって、それは初めての経験だった。心を許せる友人がいることの温かさを、彼は知った。しかし、その温かさと同時に、奇妙で、そして少し不気味な現象が彼の身に起こり始めた。
「子供の頃、お祭りの夜店で金魚すくいをしたんだけど、一枚もすくえなくてさ。悔しくて大泣きしてたら、お店のおじさんが一匹おまけしてくれたんだよね」
カフェで悠が語る幼い日の思い出。それを聞いているうちに、湊の脳裏にありありとその光景が浮かび上がった。揺れる提灯の赤い光、水飴の甘い匂い、そしてポイが破れた時の、あの絶望的な感触。まるで自分の体験であるかのように、感情までが流れ込んでくる。
「……その話、なんだか知ってる気がする」
「え? もしかして湊も同じ経験したことあるの?」
「いや、そうじゃなくて……」
言葉を濁す湊に、悠は不思議そうな顔をするだけだった。こんなことは一度や二度ではない。湊が苦手だったはずのパクチーを、悠が好きだからという理由で平然と食べている自分に気づいた日。読んだこともない小説の結末を、なぜか知っていた日。悠が口ずさむマイナーなバンドの曲のメロディーを、初めて聴いたはずなのに懐かしく感じた日。
湊の嗜好、記憶、感情が、少しずつ悠のものに上書きされていくような感覚。友情という心地よい響きの裏側で、自分の輪郭がゆっくりと溶けていくような、得体の知れない恐怖が忍び寄っていた。彼は、自分の世界に鮮やかな色彩をもたらしてくれた悠という存在に、言い知れぬ畏怖を抱き始めていた。
ある雨の日、現像した写真の束を眺めていた湊は、一枚の写真に釘付けになった。それは、雨に濡れた紫陽花を撮ったものだった。しかし、そのアングル、その色合いは、明らかに悠が好みそうな、情緒的で感傷的なものだった。自分の作風ではない。いつ、こんな写真を撮った? 記憶にない。混乱する湊の脳裏に、ふいに声が響いた。それは悠の声だった。
『雨の日は、世界の色が濃くなるから好き』
いつか彼女が言っていた言葉。その言葉と共に、雨に濡れた土の匂い、葉を打つ雨音の記憶が、奔流のように流れ込んでくる。湊は愕然とした。これは、自分の記憶じゃない。これは、悠の記憶だ。
友情が深まるほどに、自己が侵食されていく。このままでは、自分は自分でなくなってしまうのではないか。その恐怖は、湊の中で確かな形を取り始め、彼を苛んだ。温かかったはずの友情は、今や冷たい鎖となって、彼の心を縛り付けていた。
第三章 共鳴の真実
恐怖は、やがて湊の行動を支配した。彼は悠からの連絡を無視し、大学でも彼女の姿を見つけると、無意識に身を隠すようになった。理由は言えない。どう説明すればいいのか、彼自身にも分からなかったからだ。ただ、これ以上彼女と関われば、柏木湊という存在が完全に消えてしまうという、根源的な恐怖に突き動かされていた。
突然の拒絶に、悠はひどく戸惑い、傷ついているようだった。遠くから見かける彼女の表情は、いつも悲しげに曇っていた。その姿を見るたびに、湊の胸はナイフで抉られるように痛んだ。だが、彼はどうすることもできなかった。
そんなある夜、事件は起きた。湊はベッドの中で、激しい頭痛に襲われた。まるで頭蓋骨の内側から、誰かが力任せに扉をこじ開けようとしているような痛み。そして、暗闇の中で鮮烈なイメージがフラッシュバックした。
―――雨の夜道。車のヘッドライトが乱反射する。急ブレーキの甲高い軋み音。体に突き刺さるような衝撃。そして、隣に座っていた両親の、驚きと愛情が混じった最後の眼差し。温かいものが頬を伝う感覚。それは血の匂いと、絶望の味だった―――
「うわっ!」
湊は叫び声を上げて跳ね起きた。全身は汗でぐっしょりと濡れ、心臓が警鐘のように鳴り響いていた。今の記憶はなんだ? あれは、自分の記憶では断じてない。あまりにも生々しい悲しみと、骨身に沁みる孤独感。それは、陽向悠が心の奥底に封じ込めていた、幼い頃の事故の記憶だった。彼女が両親を一度に失った、あの日の記憶。
その痛みと絶望が、まるで自分の体験のように湊の心を支配し、彼はその場に蹲って嗚咽を漏らした。なぜ、自分が彼女の記憶を追体験している? この現象の正体は何だ?
突き動かされるように、湊は立ち上がった。答えは一つしかない。あの写真の場所へ行くんだ。あの、見知らぬ少女が笑っていた海辺の町。悠の故郷へ。
夜行バスに飛び乗り、揺られること数時間。湊が辿り着いたのは、古びた灯台がシンボルの、小さな港町だった。潮の香りが、あのデジャヴの記憶を呼び覚ます。湊は、悠の実家だという住所を頼りに、一軒の古い家を訪ねた。出てきたのは、悠によく似た、穏やかな目をした老婆だった。悠の祖母だ。
湊が事情を話すと、祖母は全てを察したかのように、静かに語り始めた。
「あの子は、あなたに心を許してしまったんだね……」
祖母の口から語られたのは、信じがたい事実だった。陽向の一族には、代々「共鳴者」と呼ばれる特異な体質の者が生まれるという。共鳴者は、心から信頼し、深く愛した相手と、記憶や感情、時には五感までも共有してしまうのだと。
「それは、祝福であり、呪いでもある。悠の両親も共鳴者同士だった。だから、あの子の父親が事故で亡くなった時、母親は共有された絶望と悲しみに耐えきれず……数日後に、後を追うように衰弱して亡くなってしまった」
だから悠は、誰かと深く関わることを極端に恐れていたのだ。自分の持つ悲しい記憶で相手を苦しませたくない。そして、相手に依存し、二度と境界線が引けなくなることを恐れていた。しかし、湊の写真が持つ、世界との絶妙な距離感と、その奥に潜む底知れない優しさに、彼女は生まれて初めて本気で誰かと繋がりたいと願ってしまった。
「あの子は、君を傷つけることを何よりも怖がっている。君が君でなくなることを、自分のこと以上に恐れているんだよ」
祖母の言葉が、湊の胸に深く突き刺さった。恐怖の正体、悠の苦悩、そして彼女が自分に向けていた想いの深さ。その全てが、一つの線として繋がった。自分はとんでもない勘違いをしていた。悠は自分を侵食していたのではない。彼女は、自分の全てを懸けて、湊と繋がろうとしてくれていたのだ。
第四章 君と僕の境界線
湊は、嵐のような感情に突き動かされ、東京へととんぼ返りした。大学のキャンパスを探し回り、夕暮れの光が差し込む図書館の片隅で、窓の外をぼんやりと眺めている悠の姿を見つけた。その背中は、ひどく小さく、脆く見えた。
「悠」
湊が声をかけると、彼女の肩がびくりと震えた。ゆっくりと振り返ったその瞳には、驚きと、悲しみと、そして諦めが混じり合った複雑な色が浮かんでいた。
「……どうして」
「話があるんだ。全部、聞いたよ。君の故郷で」
その言葉に、悠の表情から血の気が引いていくのが分かった。彼女はか細い声で言った。
「ごめんなさい。私といると、湊が湊でなくなってしまう。あなたの記憶も、あなたの好きなものも、全部私の色で汚してしまう。それが怖かった……」
突き放そうとする彼女の言葉を、湊は静かに遮った。彼はもう、以前の彼ではなかった。他人との間に壁を作り、安全な距離から世界を傍観するだけだった臆病な青年は、もうどこにもいない。彼は、初めて本気で他者と向き合い、その痛みごと受け入れる覚悟を決めていた。
「君の悲しみも、苦しみも、もう僕の記憶の一部だ。あの事故の日の雨の匂いも、アスファルトの冷たさも、僕は知っている」
湊は一歩踏み出し、震える悠の肩にそっと手を置いた。
「それなら、僕の喜びも、君の記憶の一部にしてほしい。一人で抱えるにはあまりにも辛い記憶なら、二人で半分こにすればいいじゃないか。僕の撮る写真の楽しさも、くだらないことで笑う時間も、全部君にあげる。僕たちは、きっと、そうやって生きていける唯一の二人なんだ」
悠の瞳から、大粒の涙がとめどなく溢れ出した。それは、長年彼女を縛り付けてきた孤独と恐怖が、雪解け水のように流れ出していく音だった。
数週間後、二人は再びあの海辺に立っていた。湊が撮った、あの見知らぬ少女の写真と全く同じ場所に。白いワンピースを着た悠は、あの頃と同じように、しかしどこか大人びた表情で笑っていた。
湊はカメラを構える。ファインダー越しに見える悠の笑顔と、自分の中に流れ込んでくる、彼女が感じる潮風の心地よさや、未来への微かな希望が、くっきりと重なり合う。自己が曖昧になる恐怖は、もうなかった。そこには、二つの魂が溶け合い、一つの新しい世界を形作っているという、至福にも似た感覚だけがあった。
彼はシャッターを切った。カシャッという乾いた音と共に、新しい記憶が生まれる。それは湊だけのものでもなく、悠だけのものでもない。二人の共有財産として、永遠に刻まれる記憶。
彼らの友情は、互いの存在を分かち合い、記憶を交換し続けることで、誰にも理解できないかもしれないが、誰よりも深い、唯一無二の絆となった。それは、自己と他者の境界線が溶けた先に見つけた、新しい愛の形だったのかもしれない。ファインダーの中の悠は、世界で一番美しい顔で笑っていた。