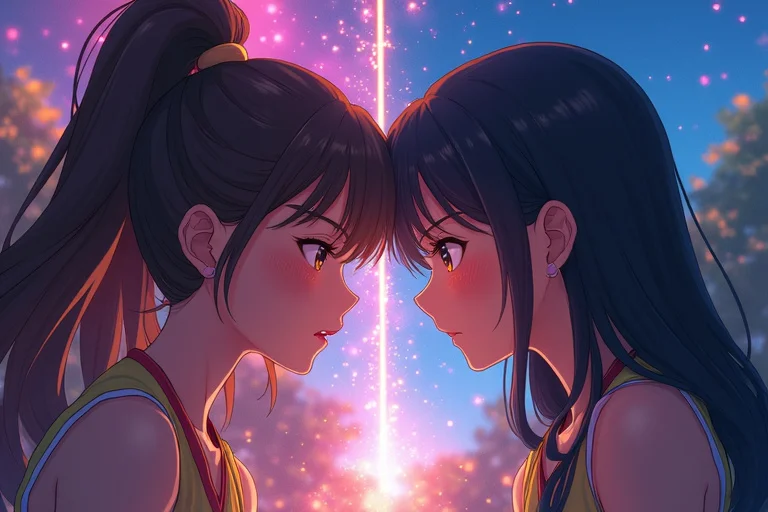第一章 沈黙のプレリュード
陽(はる)が消えた。
まるで薄紙が一枚、風に攫われたかのように、僕、水野湊(みずのみなと)の世界から忽然と姿を消した。警察はよくある家出だと片付けたが、僕には分かっていた。これは違う。陽の部屋のドアノブに手をかけた瞬間、全身を突き抜けた不協和音が、それを証明していたからだ。
僕には、秘密の能力がある。幼い頃から、他人の強い感情が残した「残響」を、音や色として感じ取ることができた。特に、十五年来の親友である陽の感情は、誰よりも鮮明に僕に届いた。彼が心から笑った時に触れたマグカップからは、弾けるようなピアノのアルペジオが聴こえ、制作に行き詰まった時のデッサン帳からは、低く唸るチェロの不協和音が漂っていた。僕は彼の心の音色を道標に、彼の隣を歩いてきた。
だが、今、陽のアパートに充満しているのは、これまで聴いたことのない種類の音だった。
それは、切り裂くようなヴァイオリンの軋みと、心臓を直接掴むような、不規則で重い打楽器のビート。空気に溶け込んだ恐怖の色は、まるで墨をぶちまけたようにどす黒く、息が詰まる。陽が最後に座っていたであろう椅子に恐る恐る触れると、指先から冷たい絶望が流れ込んできた。
「陽…お前に何があったんだ?」
部屋は荒らされた形跡もなく、机の上には書きかけの課題レポートが置かれたまま。ただ、そこにいるはずの陽だけがいない。そして、彼のすべてを語るはずの「残響」は、ただひたすらに恐怖と苦悩を奏でている。彼が誰かに連れ去られたのか? それとも、何かから必死に逃げていたのか?
陽の明るい笑顔の裏に、こんなおぞましい音色が隠されていたなんて、僕は少しも知らなかった。僕が聴いていたのは、彼の感情のほんの一部だったのかもしれない。僕たちの友情は、僕が思っていたような、澄んだ和音だけでできていたわけではなかったのだ。この日から、僕は彼の残した不協和音の正体を突き止めるため、沈黙してしまった彼の足跡を辿り始めた。
第二章 不協和音のフーガ
陽の残響を追う旅は、僕が知らなかった親友の肖像画を、一枚一枚めくっていくような作業だった。陽のバイト先だった古書店のカウンター。そこからは、微かな焦燥感と、誰かへの苛立ちが、金属的な響きとなって伝わってきた。僕が陽とよく待ち合わせた駅前のカフェ。彼がいつも座っていた窓際の席には、濁った緑色の霧のような嫉妬の残響が、澱のように沈んでいた。
「陽が、嫉妬…? あの陽が?」
信じられなかった。陽はいつも輪の中心にいた。太陽のように明るく、誰からも愛され、才能にも恵まれていた。美大の彫刻科では、入学当初から教授たちの期待を一身に集めていた。そんな彼が、一体誰に、何を嫉妬するというのか。
僕は、陽の所属する彫刻科のアトリエに忍び込んだ。巨大な粘土塊や石膏像が並ぶ、静まり返った空間。ひんやりとした空気の中、陽が制作途中だった作品が目に飛び込んできた。それは、天を仰ぎ、何かを掴もうと必死に手を伸ばす、苦悶の表情を浮かべた人物像だった。力強く、しかしどこか脆い。その作品に触れた指先から、これまでで最も複雑な残響が流れ込んできた。
それは、いくつもの旋律が絡み合い、互いを打ち消し合う「フーガ」のようだった。天賦の才への自負を示す壮大なホルンの音色。周囲の期待に応えなければならないというプレッシャーの、締め付けるような弦楽の旋律。そして、その奥深くから、か細く聴こえてくる、静寂への渇望と、僕――水野湊に対する、焦げるような羨望の音。
僕に? なぜ。僕は絵画科の隅で、目立たず、自分の世界に閉じこもって絵を描いているだけだ。人と話すのも苦手で、いつも陽の後ろに隠れていた。そんな僕の何を、陽が羨むというのか。
残響を辿れば辿るほど、僕の知っている陽の姿は崩れていった。彼が奏でる音は、僕が心地よいと感じていたハーモニーだけではなかった。その裏側には、僕が決して聴こうとしなかった、あるいは聴こえないふりをしていた、彼の孤独や葛藤が渦巻いていたのだ。友情とは、相手の心地よい音だけを聴くことではない。その不協和音にも、耳を澄ませることだったのかもしれない。だとしたら、僕は本当の意味で彼の親友だったのだろうか。自己嫌悪が、鉛のように心を重くした。
第三章 解かれたカノン
陽の部屋をもう一度、隅々まで調べ直した。何か、もっと明確な手掛かりがあるはずだ。本棚の奥、彼が大切にしていた古い画集の間に、一冊のノートが挟まっているのを見つけた。彼の筆跡だ。僕は息を飲んで、そのページをめくった。
それは、陽の日記だった。そして、その内容は、僕のちっぽけな想像を根底から覆す、彼の魂の叫びだった。
『湊には、聞こえているんだろうな。俺の気持ちが。俺が触ったものから、俺の心がダダ漏れなのが。いつからだろう。お前が俺の言葉じゃなくて、俺が残した“音”を信じるようになったのは』
心臓が凍りついた。陽は、僕の能力に気づいていた。
『お前はいいよな、湊。お前には、世界が音や色で見える。繊細で、静かで、誰も踏み込めないお前だけの世界がある。お前の描く絵は、静かだけど、宇宙みたいに広い。俺は、それがずっと羨ましかった』
『俺は、いつからか「太陽みたいな奴」でいるしかなくなった。明るく、強く、誰にでも優しい陽。みんなが求める俺を演じるのは、息が詰まる。本当は、お前みたいに、静かな場所で一人、自分の内側にあるものだけを見つめていたいのに』
ページをめくる指が震える。そこには、僕が知らなかった陽の苦悩が、痛々しいほど率直に綴られていた。彼は、僕が彼の残響に依存していることを見抜いていた。僕が彼の顔色を窺うように、彼の残した音を拾い集め、一喜一憂していることに、罪悪感すら感じていたのだ。
そして、最後の方のページに、衝撃的な一文があった。
『だから、俺は消えることにした。これは逃亡じゃない。湊、お前のための卒業式だ。俺という調律師がいなくなれば、お前はきっと、お前自身の音を奏でられるようになる。他人の音に惑わされず、自分の心の音を聴けるようになる。俺のいない世界で、お前がどんな絵を描くのか、見てみたいんだ』
『最後の残響は、とっておきの場所に残しておく。お前なら、きっと見つけられる』
失踪は、事件でも家出でもなかった。僕を、僕が囚われていたこの能力という名の呪縛から解放するための、陽による、あまりにも切なく、そして残酷なほどの優しさに満ちた計画だったのだ。僕たちの友情は、一人がもう一人に寄りかかる歪な関係(カノン)だったのかもしれない。そして陽は、その連鎖を自ら断ち切ったのだ。
涙が、ノートの上に落ちて染みを作った。陽、お前は、そんなことまで考えていたのか。僕が聴いていたのは、お前の苦悩のほんの上澄みでしかなかった。本当の苦しみは、音にもならず、お前の心の一番深い場所に沈んでいたんだ。
第四章 僕だけのソナタ
陽が残した「とっておきの場所」。考えるまでもなかった。僕たちが初めて出会った、あの海だ。十五年前、いじめられて一人で泣いていた僕に、陽が「お前、面白い色してるな」と声をかけてくれた、始まりの場所。
バスに乗り、潮の香りがする終着点で降りる。砂浜を歩くと、夕陽が海面をオレンジ色に染めていた。波の音だけが、静かに響いている。僕は、いつものように周囲の残響に耳を澄ませようとして、はっと息を止めた。
違う。陽は、僕にそれを望んでいない。
僕は目を閉じた。他人の感情の音を遮断し、生まれて初めて、自分自身の内側に意識を集中させた。そこは、驚くほど静かだった。しかし、その静寂の奥から、確かに何かが湧き上がってくる。それは、陽を失った深い悲しみ。僕を想ってくれたことへの、胸が張り裂けそうなほどの感謝。そして、これから一人で歩いていかなくてはならないという、小さな、だけれど確かな決意。
それは、誰かの残響ではない。僕自身の心から生まれた、僕だけの音――僕だけのソナタだった。
目を開けると、涙が頬を伝っていた。
その時、ふと、防波堤の上に、小さな石が一つ置かれているのが見えた。陽の彫刻のようだ。滑らかに磨かれた、手のひらサイズの石。僕はそれに、もう触れることはなかった。そこにどんな素晴らしいハーモニーが残されていたとしても、それを聴く必要はもうない。
陽、お前がどこにいるのか、僕には分からない。でも、それでいい。お前がくれたこの静寂と、僕の中から生まれたこの新しい音楽を、僕は大切にするよ。
いつか、僕が僕自身の音で、世界中を感動させられるような絵を描けたなら。その時は、胸を張ってお前に会いに行こう。
僕は、夕陽に染まる海に向かって、一度だけ深く頭を下げた。そして、背を向け、砂浜をしっかりと踏みしめて歩き始めた。もう、他人の残した音に振り返ることはない。僕の未来は、僕自身が奏でていくのだ。風が、陽の優しい声の代わりに、僕の髪をそっと撫でていった。