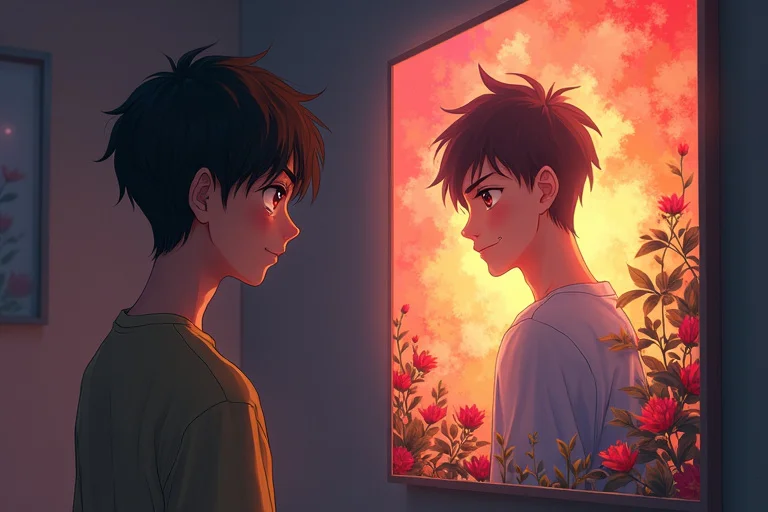第一章 さよならの形見
海斗が死んで、一年が経った。アスファルトに刻まれた夏の名残が、じりじりと足の裏から僕の心を焦がす。一周忌の帰り道、僕は慣れない黒いスーツの襟元を緩めながら、人気のない公園のベンチに腰を下ろした。空は、まるで何もなかったかのように、残酷なほど青い。
親友だった。僕にとって、世界の半分だったと言っても過言ではない。内向的で、いつも本の世界に逃げ込んでいた僕を、外の世界へと引っ張り出してくれたのが海斗だった。太陽みたいな笑顔と、どんな壁でも壊してしまいそうな真っ直ぐな瞳。彼が隣にいるだけで、僕のモノクロの世界は鮮やかな色彩を帯びた。
「……馬鹿だよ、お前は」
ぽつりと呟いた言葉は、乾いた空気に吸い込まれて消える。なぜ、あんな無茶な運転をするトラックの前に飛び出したんだ。なぜ、僕を置いて一人で逝ってしまったんだ。答えのない問いが、蝉時雨に混じって頭の中で反響する。
俯いた視線の先、コンクリートの地面に伸びる僕自身の影が、濃く、静かに横たわっていた。孤独の象徴。一人きりになったという、紛れもない事実の証明。目を閉じて、海斗の笑い声を思い出そうとした、その時だった。
ふと、自分の影の隣に、もう一つの影が寄り添うように現れたのに気づいた。
「え……?」
心臓が跳ねる。見間違いか。公園には僕以外誰もいない。街灯が灯るにはまだ早い時間だ。なのに、そこには確かにもう一つ、僕の影と同じくらいの背丈の人影があった。それは僕の影の肩に、馴れ馴れしく腕を回すような形をしている。生前の海斗がよくやっていた、あの仕草とそっくりだった。
恐怖よりも先に、懐かしさが胸を締め付けた。瞬きをしても、その影は消えない。それどころか、まるで「よっ」とでも言うように、手の形をした部分をひらひらと動かしたのだ。ありえない。影は物体の形を写すだけの、光の抜け殻のはずだ。意思を持つことなど、絶対にない。
僕はゆっくりと立ち上がった。僕が動くと、僕自身の影も当然のように動く。そして――その隣の影も、ぴったりとついてきた。僕が歩けば歩き、止まれば止まる。まるで、僕の体に二人分の魂が宿っているかのように。
それは、海斗の影だった。
僕にしか見えない、親友の形見だった。
第二章 二人だけの秘密
その日から、僕と「海斗の影」との奇妙な共同生活が始まった。影は言葉を話さない。声も、温度も、重さもない。ただ、黒いシルエットとして僕の足元に存在し続けるだけだ。しかし、それは単なる影ではなかった。
朝、僕が目を覚ますと、壁に映った影はコーヒーカップの形になり、キッチンの方を指し示している。僕がため息をつきながら古本を開けば、影の手が伸びて、まるでページをめくるのを手伝うかのようにゆらめく。僕が悲しい映画を観て涙を流すと、僕の頬を撫でるように、その影は優しく形を変えた。
僕たちは、言葉のいらない対話を続けた。海斗の影は、僕を笑わせようと必死だった。道端で猫を見つければ猫の形に、ショーウィンドウのマネキンを見れば同じポーズをとってふざけてみせる。そのたびに、僕は一年ぶりに心の底から笑った。孤独だった部屋は、影との二人だけの空間になり、色褪せていた日常が、少しずつ彩りを取り戻していくのを感じた。
「なあ、海斗。お前、ずっとそこにいてくれるのか」
問いかけても、影は答えない。ただ、僕の足元で、ぎゅっと僕の影を抱きしめるような形になるだけだ。それで十分だった。彼がここにいる。それだけで、僕は満たされていた。
しかし、その安らぎは、同時に僕を現実から遠ざける甘い毒でもあった。大学の友人からの誘いを断り、新しい人間関係を築くことを恐れ、僕はますます自分の殻に閉じこもるようになった。だって、僕には海斗がいる。たとえそれが実体のない影だとしても、他の誰にも代えがたい存在だったからだ。僕の世界は、僕と海斗の影だけで完結していた。失った世界の半分を取り戻した気になっていたが、それは残された半分までをも侵食する、静かな幻だったのかもしれない。
第三章 影が囁く真実
季節が巡り、再び夏が近づいてきたある日のことだった。海斗の影の様子がおかしくなった。いつものようにふざけるでもなく、ただ一点を、玄関のドアの方を必死に指し示している。その動きには、これまで感じたことのない切迫感があった。
「どうしたんだよ、海斗」
僕が尋ねても、影はドアを指し示すばかり。その指先は震えているように見えた。僕は不審に思いながらも、影に促されるままにアパートを出た。影は僕の前を先行するように地面を滑り、ある方向へと導いていく。それは、僕が一年間、ずっと避けてきた場所だった。海斗が命を落とした、あの交差点だ。
強い日差しが照りつける交差点。けたたましいクラクションと、信号の電子音。僕は足がすくんだ。あの日の光景がフラッシュバックする。ブレーキ音、悲鳴、そして、僕の名前を呼んだ、海斗のかすれた声――。
「嫌だ、行きたくない」
僕が後ずさると、海斗の影は僕の前に回り込み、両腕を広げて道を塞ぐような形になった。そして、何度も、何度も、交差点の向こう側を指し示す。その必死な姿に、僕は何かを見落としているような気がしてならなかった。これはただの感傷じゃない。海斗は、何かを伝えようとしている。
僕は覚悟を決めて、交差点の近くにある小さな花屋に入った。店番をしていた初老の女性は、僕の顔を見て何かを察したようだった。
「あの日も、暑い日だったわねぇ」
僕は震える声で、一年前の事故について何か知らないか尋ねた。女性は少しだけ目を伏せると、静かに語り始めた。
「あそこに飛び出した小さな男の子がいたのよ。ボールを追いかけてね。そこへトラックが…。あのお兄さん、その子を突き飛ばして、自分が身代わりに…」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。海斗は、無謀な運転で死んだのではなかった。見ず知らずの子供を、命を懸けて守ったのだ。僕が知っていたのは、無惨な結果だけ。その裏にあった、彼の勇気と優しさを、僕は何も知らなかった。
呆然と立ち尽くす僕の足元で、海斗の影がゆっくりと形を変えた。今度は、交差点ではなく、僕自身の影を指し示していた。そして、僕の影の胸のあたりを、そっと撫でるような仕草をした。
その瞬間、雷に打たれたように、すべてを理解した。
海斗の影がここにいたのは、僕を慰めるためだけじゃない。事故の真相を伝えたかっただけでもない。彼はずっと、僕に言いたかったのだ。
『お前は、前に進め』と。
僕が彼の死の本当の意味を知り、悲しみを乗り越え、自分の足で再び人生を歩き出すまで、彼は僕の側を離れられなかったのだ。この影は、海斗の未練であると同時に、僕自身の弱さが作り出した、甘い停滞の象徴だった。
「…そうか。お前、ずっと、それを言いたかったのか」
涙が溢れて止まらなかった。それはもう、悲しみだけの涙ではなかった。親友への誇りと、感謝と、そして、彼を縛り付けていた自分への申し訳なさがないまぜになった、熱い滴だった。
第四章 夜明けのアンダンテ
数日後、僕はあの花屋で教わった住所を訪ねた。小さなアパートのドアを開けてくれたのは、幼い男の子を抱いた若い母親だった。僕が海斗の友人だと名乗ると、彼女は堰を切ったように泣きながら、何度も頭を下げた。
僕は静かに首を横に振った。「あいつは、そういう奴なんです。きっと、後悔なんてしてませんから」。そう言うのが精一杯だった。男の子は、僕の後ろを不思議そうに見ている。きっと彼の目には、僕の足元に寄り添う、もう一つの影は見えていないのだろう。
帰り道、僕たちは夜明けの公園を歩いていた。東の空が白み始め、世界が新しい一日の始まりを告げている。僕はベンチに座り、足元の影に語りかけた。
「海斗。ありがとうな。お前のこと、誇りに思うよ」
影は何も言わない。ただ、僕の隣で静かに揺れている。
「もう、大丈夫だから。僕はもう、一人で歩ける。だから、お前も、もう行っていいよ」
それが、僕にできる最大限の友情の示し方だった。別れは辛い。でも、彼の魂を過去に縛り付けておくことの方が、もっと辛い。
僕の言葉に応えるように、海斗の影はゆっくりと立ち上がった。そして、生前の彼がよく見せた、あの太陽みたいな笑顔の形に、その輪郭がふわりと歪んだ。影は僕に一度だけ手を振ると、昇り始めた朝日の、優しい光の中へと歩き出す。その黒いシルエットは、光に触れるたびに薄くなり、輪郭が溶けて、最後には完全に光と一つになった。
あたりが、まばゆい光で満たされる。
目を開けると、僕の足元には、僕自身の影だけが、くっきりと、力強く地面に落ちていた。もう、隣にあの馴れ馴れしい相棒はいない。胸にぽっかりと穴が空いたような寂しさはある。でも、その穴からは、悲しみではなく、温かい光が差し込んでいるような気がした。
僕は空を見上げた。残酷なほど青かった空が、今はどこまでも優しく見えた。
さよなら、僕の世界の半分。
そして、ありがとう。
僕は立ち上がり、未来へと続く道を、今度は自分の足で、確かに一歩、踏み出した。