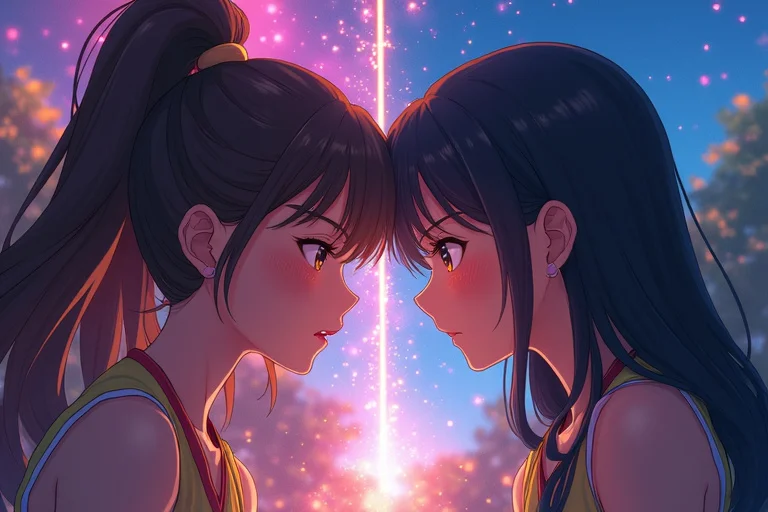第一章 沈黙のアンダンテ
僕の耳には、世界は常に嘘の交響曲を奏でている。
法学部の退屈な講義室。老教授が語る民法の原則は、荘厳だがどこか空虚なパイプオルガンの音色を伴って鼓膜を揺らす。彼自身、その理想を信じていないことの証左だ。最前列で熱心に頷く女子学生の相槌は、媚びるようなフルートのトリル。窓際で欠伸を噛み殺す友人に「大丈夫か?」と囁く男子学生の声は、本心とは裏腹の不協和音を響かせるチェロのピチカート。
人々が意識的、あるいは無意識的につく嘘は、僕、相葉響(あいば ひびき)の脳内で美しいメロディへと変換される。幼い頃の事故で頭を打って以来、僕に備わった呪いであり、才能でもある特殊な共感覚だ。この能力のせいで、僕は人間という生き物の建前と本音の乖離にうんざりし、誰かと深く関わることを諦めて久しかった。他人の心の裏側が奏でる音楽は、時に美しすぎ、時に醜悪すぎて、僕の精神をすり減らすのだ。
だから、僕にとって月島奏(つきしま かなで)の存在は、奇跡そのものだった。
彼といる時だけ、僕の世界から一切の音が消える。完全な静寂。まるで防音室にいるかのように、耳を澄ませても聞こえるのは彼の穏やかな呼吸と、僕自身の心臓の鼓動だけ。奏は嘘をつかない。少なくとも、僕の能力が反応するような、心と言葉が乖離した状態になったことが一度もないのだ。
「響、次の講義、一緒に出るだろ?」
僕の隣で、奏が静かにノートを閉じながら言った。その声は、何の音色も伴わない、純粋な振動として僕の耳に届く。その透明な響きが、オーケストラの喧騒に満ちた僕の世界で、唯一の安息を与えてくれる。
「ああ、もちろん」
僕たちは並んで埃っぽい廊下を歩く。すれ違う学生たちの会話が、軽薄なポルカや嫉妬深いタンゴとなって僕の周りを飛び交うが、奏の隣にいるだけで、それらの雑音は分厚いガラスの向こう側へと遠ざかっていく。彼が作り出す半径一メートルほどの「沈黙の聖域」。それが、僕がこの息苦しい世界で正気を保っていられる理由だった。
彼は自分のことを多く語らない。どこで生まれ、どんな家族がいて、何を夢見ているのか。僕が尋ねても、いつも静かに微笑んで、巧みにはぐらかすだけだった。それでも、彼の言葉に嘘のメロディが乗ることは決してなかったから、僕は気にしなかった。むしろ、そのミステリアスな部分さえも、彼の魅力の一部だと感じていた。
そんなある日の夕暮れ。茜色に染まるキャンパスのベンチで、奏が不意に口を開いた。
「今度の週末、僕の故郷を見に来ないか?」
その言葉は、あまりにも唐突で、そしてあまりにも純粋な響きを持っていた。僕は驚いて彼の顔を見た。いつも穏やかな彼の瞳の奥に、ほんの少しだけ、揺らめく灯火のようなものが見えた気がした。
「……君の、故郷?」
「うん。響にだけは、見せておきたいんだ」
嘘の音は、聞こえない。僕は胸が高鳴るのを感じた。彼が初めて、その心の深い部分へと僕を招き入れてくれようとしている。その誘いを、断る理由などどこにもなかった。
第二章 星屑のノクターン
週末、奏に連れられて電車を乗り継ぎ、たどり着いたのは、街の喧騒から遠く離れた丘の上だった。そこには、白く丸いドームを持つ、古びた天文台が静かに佇んでいた。蔦の絡まる壁、錆び付いた扉。とうの昔に役目を終え、忘れ去られた場所であることは一目瞭然だった。
「ここが……君の故郷?」
僕の問いに、奏は「うん」とだけ答えて、ぎしりと音を立てる扉を開けた。中はひんやりとした空気に満ち、微かなカビの匂いと、星の光を待ちわびる機械たちの沈黙が満ちていた。中央に鎮座する巨大な反射望遠鏡が、ドームの隙間から差し込む夕光を浴びて、鈍い光を放っている。
「僕はね、ここで生まれたんだ」
奏は螺旋階段を上りながら、ぽつりぽつりと語り始めた。
「いや、生まれた、というのとは少し違うかな。僕は、たくさんの人の『忘れられた記憶』や『忘れたいと願った想い』が集まって、形になった存在なんだ」
僕は彼の言葉の意味をすぐには理解できなかった。それはまるで、彼が好んで読む幻想小説の一節のようだった。詩的で、掴みどころのない比喩。きっと、彼なりの出自の表現なのだろうと解釈した。
「この天文台は、昔たくさんの人が星を見に来た場所だ。喜びも、悲しみも、願いも、後悔も……色々な想いがこの場所に染み付いている。僕は、その記憶の残滓が集まってできた、いわば幽霊みたいなものだよ」
ドームの頂上に着くと、息を呑むような光景が広がっていた。街の灯りが届かない丘の上は、満天の星が降ってきそうなほどの夜空に包まれていた。奏は手動でドームの天窓を開ける。星々の瞬きが、僕たちの頭上に直接降り注いだ。
「すごい……」
言葉を失う僕の隣で、奏は静かに星を見上げていた。その横顔は、星の光に照らされて、どこか儚く、透き通っているように見えた。
僕は、この不思議な友人の前で、初めて自分の秘密を打ち明ける覚悟を決めた。
「奏。僕には、人の嘘が音楽になって聞こえるんだ」
僕は、この能力のせいでどれだけ苦しんできたか、どれだけ人間を信じられなくなったかを語った。そして、彼といる時だけが唯一の救いなのだと伝えた。
「君だけなんだ。君の言葉からは、一度も嘘のメロディが聞こえたことがない。だから、僕は君を信じられる。君の隣は、世界で一番安らげる場所なんだ」
僕の告白を、奏はただ黙って聞いていた。やがて彼は、ゆっくりと僕の方を向き、穏やかに微笑んだ。
「そうか。……響の世界は、いつも賑やかだったんだね」
その声もまた、完璧な無音だった。僕たちはそれ以上何も語らず、ただ黙って、流れ落ちる星屑の夜想曲を聴いていた。この瞬間が永遠に続けばいいと、僕は心の底から願っていた。
第三章 偽りのクレッシェンド
その日を境に、僕たちの友情はさらに深まったように思えた。しかし、穏やかな時間は長くは続かなかった。次に天文台を訪れた時、僕は奏の姿に異変を感じた。彼の輪郭が、陽炎のように僅かに揺らぎ、指先が透けて向こうの景色が見える。
「奏、どうしたんだ? 体調でも悪いのか?」
駆け寄る僕に、奏は力なく微笑んだ。その笑顔は、いつにも増して儚げだった。
「……バレちゃったか。実は、僕、もうすぐ消えるんだ」
彼の言葉は、冷たい刃となって僕の胸を突き刺した。嘘の音は、やはり聞こえない。つまり、それは紛れもない真実だった。
「僕という存在はね、僕の元になった記憶の持ち主たちが、僕のことを覚えていることで、かろうじてこの世界に繋ぎ止められている。でも、その人たちも年老いて、一人、また一人と……この世を去っていく。記憶の源流が枯渇すれば、僕という集合体も形を保てなくなる」
頭が真っ白になった。彼が人間ではないこと。そして、消えゆく運命にあること。あまりにも非現実的な真実が、僕の理解を遥かに超えていた。
「そんな……。じゃあ、僕が君を覚えていれば! 僕が絶対に忘れないから!」
必死に叫ぶ僕に、奏は悲しげに首を横に振った。
「ありがとう、響。でも、それだけじゃ足りないんだ。それに……君に、もう一つ、謝らなければいけないことがある」
彼は躊躇いがちに、信じられない事実を告げた。
「君のその能力……嘘が音楽に聞こえる力は、もともと僕の一部だったんだ。君が幼い頃の事故で、記憶そのものを失いかけた時、僕は君を助けたかった。だから、僕を構成する記憶のかけらの中から、『真実と虚偽を判別する』という概念を君に分け与えたんだ」
雷に打たれたような衝撃。僕を苦しめ続けたこの能力は、奏からもらったものだった? 僕を救うために?
「だから、僕から嘘の音が聞こえなかったのは当然なんだよ。僕は『嘘』という概念を持たない、ただの記憶の集まりだから。嘘をつく機能も、その意味さえも、僕にはないんだ」
絶望が、僕の心を塗りつぶしていく。じゃあ、何だ? 僕が感じていたこの安らぎも、彼との友情も、全ては単なるシステム上の結果だったというのか? 彼は嘘がつけないから、僕が勝手に信頼していただけ?
「君が僕のそばにいたのは……君を存在させるために、僕の記憶が必要だったからなのか? 僕との友情も、君が存在を維持するための、ただの『機能』だったのか!?」
我知らず、僕は彼を詰っていた。嫉妬と絶望が入り混じった、醜い感情だった。
その時だった。
僕の耳に、聴こえたのだ。生まれて初めて、奏から発せられるメロディが。
それは、これまで聴いてきたどんな壮大な嘘の交響曲とも違っていた。ピアノの鍵盤を一つだけ、ためらいがちに押したような、か細く、不器用で、どうしようもなく悲しい単音。たった一つの、不完全な和音。
奏は、透けそうな体で僕を見つめ、震える声で言った。
「……違うよ。響と、一緒にいたかった。それは、僕の……僕自身の、意思だ」
その言葉と同時に奏でられた哀切なメロディ。それは、嘘だった。概念を持たないはずの彼が、僕を傷つけまいとして、僕を安心させようとして、彼の存在の根幹を揺るがしてまで、生まれて初めてつこうとした、不器用な、優しい嘘だった。
その嘘の音こそが、彼の中に確かに「自我」が芽生え、僕への「友情」が本物であったことの、何より雄弁な証明だった。
第四章 追憶のフーガ
奏のついたたった一つの嘘は、彼の存在を急速に霧散させた。自らの本質に反する行為は、彼という存在の定義を崩壊させる引き金となってしまったのだ。彼の体は、星屑のような光の粒子となって、ゆっくりと剥がれ落ちていく。
僕は涙を流しながら、その光景を見ていた。耳の奥では、まだあの不器用な和音が鳴り響いている。今まで僕が世界で最も忌み嫌ってきた嘘のメロディ。それが今、この世のどんな真実の言葉よりも、温かく、そして愛おしく感じられた。
「……ありがとう、奏」
僕は崩れ落ちそうになる彼の体を、抱きしめた。腕の中の感触は驚くほど希薄で、まるで光そのものを抱いているようだった。
「君が奏でてくれた音楽、絶対に忘れないよ」
「……うん。響の……友達で……よかった」
それが、彼の最後の言葉だった。腕の中の温もりがふっと消え、光の粒子はドームの天窓から夜空へと舞い上がり、瞬く星々の中に溶けていった。
彼の消滅と共に、僕を苛み続けた能力もまた、嘘のように消え去っていた。世界は再び、ただの音と沈黙に戻った。あれほど渇望した静寂だったが、奏を失った世界では、それはあまりにも空虚で、寂しいものに感じられた。
あれから、十年が経った。
僕は今、作曲家として生きている。僕の作る曲は、メジャーでもマイナーでもない、どこか切なく、それでいて聴く人の心に寄り添うような温かい旋律だと評される。
もう、他人の嘘が音楽として聞こえることはない。けれど、僕は今でも時々、思い出す。あの星降る夜の天文台で、僕の親友がたった一度だけ奏でてくれた、世界で最も美しい嘘のメロディを。
あれは嘘の音などではなかった。あれは、友情の音だったのだ。
僕は今日も、ピアノに向かう。奏という、星屑になった友人の記憶を、旋律という永遠に乗せて、この世界に響かせ続けるために。僕が彼を奏で、誰かがその曲を聴き、また誰かへと伝えていく。そうやって、彼の存在は追憶のフーガのように、この世界に永遠に響き渡るのだ。
真実だけが、人を救うわけじゃない。たった一つの優しい嘘が、時に何よりも深い真実を伝えることがある。
夜空を見上げるたび、僕は星々の沈黙の中に、あの不器用な和音を探している。