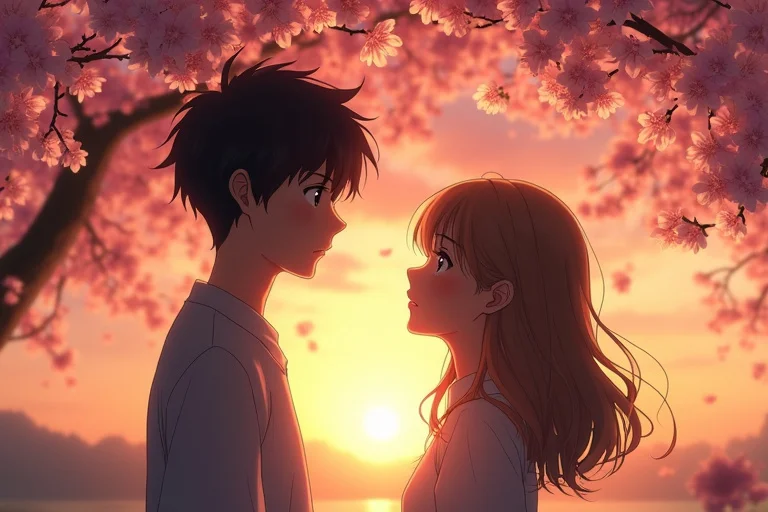第一章 影のない午後
柏木湊の住むこの街では、週に一度、奇妙で美しい時間が訪れる。毎週水曜の午後三時からきっかり一時間。全ての影が、その持ち主から離れて自由になるのだ。人々はそれを「影の散歩」と呼んでいた。
アスファルトに張り付いていた影たちが、するりと起き上がり、まるで黒い絹の布のように風にそよぐ。子供たちの影は手をつないで輪になり、老人の影は昔を懐かしむようにゆっくりと馴染みの店の壁を撫でる。恋人たちの影は、本人たちよりも大胆に絡み合い、街灯の柱をくるくると昇っていく。それは幻想的で、どこか滑稽で、そして当たり前の日常の光景だった。古書店「揺り籠文庫」の店主である湊も、窓辺の椅子に腰かけ、カウンターに落ちるはずの自分の影が、店内の本棚の間を気ままに散策するのを眺めるのが好きだった。それは、思考の澱が洗い流されるような、静かで穏やかな時間だった。
午後四時の鐘が鳴ると、魔法は解ける。影たちは一斉に我に返り、慌てたようにそれぞれの持ち主の足元へと駆け戻っていく。するり、するりと、まるで定位置に戻る磁石のように。それがいつもの約束事だった。
しかし、その日は違った。
四時の鐘が鳴り終わり、街が元の落ち着きを取り戻しても、湊の足元は空っぽのままだった。店の中を見渡しても、本棚の間をすり抜けていたはずの、あのひょろりとした黒い人型が見当たらない。外に出て、陽光が白く照らす歩道に立ってみても、そこにいるのは湊本人だけで、彼の存在を証明するはずの影はどこにもなかった。
まるで自分の半分が、予告もなく家出してしまったかのような、奇妙な喪失感。通行人たちが、影を連れていない湊に奇異の視線を向ける。ざわりと肌を撫でる風が、やけに心許なかった。湊の平穏な日常に、音もなく、しかし決定的な亀裂が入った瞬間だった。
第二章 空っぽの足元
影のない生活は、想像以上に不便で、そして不安なものだった。まず、物の距離感が掴みにくい。カップにコーヒーを注ごうとして縁からこぼし、階段を踏み外しそうになる。自分の身体の輪郭が曖昧になったようで、世界との間に一枚、薄い膜ができたような感覚が付きまとった。
だが、物理的な不便さよりも堪えたのは、精神的な侵食だった。人々は影のない湊を遠巻きにした。「影に見捨てられた男」と囁く声も聞こえた。影は魂の写し身だと言われている。その影が逃げ出すというのは、よほどその魂が歪んでいるか、空っぽであるかのどちらかだと、この街の人間は信じていた。湊自身、鏡に映る自分を見ても、どこか実在感のない、幽霊のような姿に思えてならなかった。穏やかで変化のない日常こそが、彼にとっての唯一の砦だったのに、その土台が足元から崩れ去っていくようだった。
藁にもすがる思いで、湊は街の外れにある「影探し屋」を訪ねた。煤けた看板を掲げた小さな店で、老婆が一人、煙管をふかしていた。
「影が戻らない。そういう相談は、たまにあるよ」
老婆は紫煙を吐き出しながら、こともなげに言った。
「影ってのはね、ただの光の遮蔽物じゃない。持ち主が捨てた感情や、忘れたい記憶を、全部引き受けてくれるゴミ箱みたいなもんなのさ。大抵の影は健気で、どんな重荷を背負わされても、時間になればちゃんと主人の元に帰ってくる。だがね、稀にいるんだよ。もうこれ以上は背負いきれない、と。あるいは、主人に気づいてほしくて、わざと遠くへ行く影がね」
「気づいてほしい…?何にです?」
湊の問いに、老婆は意味ありげに目を細めた。
「あんたさん自身が、一番よく知ってるはずさ。あんたが自分の影に、何を押し付けてきたのかをね。影は言葉を話さない。だが、行動で示す。あんたの影は、あんたをどこかに導こうとしてるのかもしれないよ。あんたが忘れてしまった、大切な場所へね」
老婆の言葉は、湊の心に小さな棘のように突き刺さった。自分が影に押し付けてきたもの。平穏な日常を維持するために、見て見ぬふりをしてきた感情。考えないように、心の奥底に沈めてきた記憶。空っぽになった足元を見つめながら、湊は途方もない旅の始まりを予感していた。それは、失くした影を追う旅であり、同時に、失くした自分自身を探す旅でもあった。
第三章 影がささやく記憶
湊は自分の過去を辿り始めた。幼い頃に住んでいた家、よく遊んだ公園、通っていた小学校。記憶の糸を手繰り寄せるように、街を歩いた。しかし、これといった手がかりは見つからない。影は一体、何を伝えたかったのか。焦りと無力感が募るばかりだった。
そんなある夜、湊は古いアルバムを開いていた。そこに、一枚の写真があった。ひまわり畑で、自分より少し小さな女の子の手を引いて笑う、幼い自分の姿。妹の、海(うみ)だ。病弱で、入退院を繰り返していたが、笑顔の絶えない、太陽のような子だった。湊が十歳の夏、海はあっけなく逝ってしまった。ひまわりのように、短い夏を駆け抜けるように。
その写真を見た瞬間、脳裏に閃光が走った。忘れていた光景が、堰を切ったように溢れ出す。
あの日も、今日のように暑い午後だった。病院を一時退院した海を連れて、二人で秘密にしていた丘の上のひまわり畑へ行った。医者からは安静にするように言われていたのに、海が「お兄ちゃんと、本物の太陽を見に行きたい」とせがむから。
「見て、お兄ちゃん!影が追いかけっこしてる!」
海がはしゃいで、自分の影と湊の影が重なり合うのを指さして笑った。その笑顔が、真夏の太陽よりも眩しかった。
だが、その帰り道、海は倒れた。小さな身体はすぐに冷たくなり、二度と目を開けることはなかった。
「僕のせいだ」
あの日から、湊は自分を責め続けた。僕が無理に連れ出さなければ。僕があの時、海を止めていれば。その罪悪感は、鉛のように彼の心に沈殿した。悲しみ、後悔、自分への怒り。それらの感情は、穏やかな日常を送るにはあまりにも重すぎた。だから湊は、無意識のうちにそれら全てに蓋をした。感じないように、思い出さないように。そして、その重荷の全てを、黙って寄り添う自分の影に押し付けていたのだ。
老婆の言葉が蘇る。『あんたが自分の影に、何を押し付けてきたのか』。
そうだ。僕の影は、僕が捨てた悲しみの塊だったんだ。海の記憶そのものだったんだ。
影は、僕に見捨てられたんじゃない。僕に、忘れないでと、叫んでいたんだ。もうこれ以上、一人で悲しみを背負うのは嫌だと、ストライキを起こしたのだ。
湊はアルバムを閉じ、立ち上がった。涙が頬を伝っていたが、もう迷いはなかった。行かなければならない場所が、たった一つだけあった。影が待っているであろう、あの約束の場所へ。
第四章 ただいま、僕の半分
丘の上のひまわり畑は、昔と変わらず、夕陽を浴びて黄金色に輝いていた。夏の終わりの風が、重くこうべを垂れたひまわりたちを揺らしている。その中央に、ぽつんと、一つの人影が佇んでいた。夕陽に長く引き伸ばされた、見慣れた自分の影だった。
湊はゆっくりと、一歩ずつ、影に近づいた。影は逃げなかった。まるで、ずっとここで彼を待っていたかのように、静かに揺らめいていた。
「…ごめんな」
湊の声は、風に震えていた。
「ずっと、押し付けてばかりで。辛かったよな。悲しかったよな。俺は、お前のこと、海のことも…忘れたふりをしてた。そうしないと、生きていけない気がして」
言葉にすると、堰き止められていた感情が奔流となって溢れ出した。妹を守れなかった後悔。一人で逝かせてしまった寂しさ。そして、そんな自分を許せないまま、長い年月を過ごしてきた虚しさ。湊はその場に崩れ落ち、子供のように泣いた。声を上げて、嗚咽しながら、心の奥底にしまい込んでいた全ての悲しみを吐き出した。
どれくらいの時間が経っただろうか。涙が枯れ果て、心が静かな凪を取り戻した時、湊はふと、足元に温かい気配を感じた。見ると、家出していたはずの影が、そっと彼の足元に寄り添い、一体化しようとしていた。それは、まるで「もういいんだよ」と、彼を慰撫するようだった。するり、と最後の隙間が埋まり、湊と影は再び一つになった。
足元に戻ってきた影は、以前よりも少しだけ濃く、そして輪郭が穏やかになったように見えた。それは、湊が自分の悲しみを受け入れた証だったのかもしれない。影を失ったことで、彼は初めて自分自身と向き合うことができたのだ。
翌週の水曜日、午後三時。湊は「揺り籠文庫」の窓辺で、いつものように「影の散歩」を迎えた。彼の足元から、するりと離れていく影。それは本棚の間を抜け、店の外へ出て、楽しそうに街灯の周りを踊り始めた。
湊は、その姿を穏やかな微笑みで見送った。以前のような、ただの傍観者としてではない。かけがえのない半身を送り出すような、温かい気持ちで。
「いってらっしゃい」
湊は小さく呟いた。
「また後でな」
その声は、影に届いただろうか。いや、きっと届いている。影は魂の写し身なのだから。平穏だった日常は、一度壊れて、そして新しい形で再構築された。悲しみを抱えたまま、それでも前を向いて生きていく。影と共に歩むその道は、きっと以前よりも豊かで、確かなものになるだろう。湊は、窓から差し込む西陽の中で、自分の手元に落ちる濃い影を、愛おしそうに見つめていた。