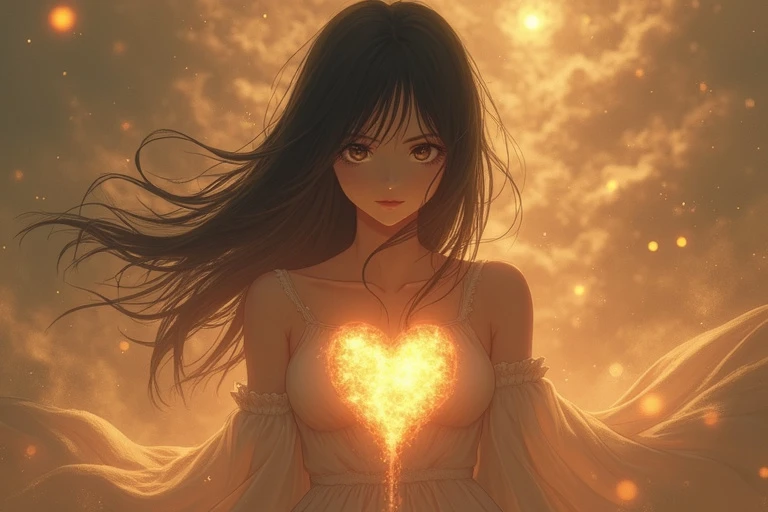古びた真鍮のドアノブが回されると、カランコロンと乾いた音が店内に響いた。
その音は、まるで水底に沈んだ小石が転がるような、寂しげで、それでいてどこか懐かしい余韻を残した。店の主、六角堂弦之介(ろっかくどう・げんのすけ)は、作業台の上のルーペを目に当てたまま、顔を上げずに言った。
「いらっしゃい。生憎の天気ですが」
外は篠突く雨だった。窓ガラスを叩く雨粒が、街のネオンを滲ませて、色とりどりの光の雫に変えている。都会の片隅、忘れ去られたような路地裏にあるこの『六角堂時計店』には、時折、こうした雨に紛れて迷い込んでくる客がいる。
「あの……ここ、時計の修理をお願いできると聞いて」
濡れた傘を閉じる音がして、若い女性の声がした。弦之介はようやく手を止めた。ピンセットの先には、米粒よりも小さな歯車が摘ままれている。彼はそれを慎重にシャーレに戻すと、ルーペを額へと押し上げた。
入り口に立っていたのは、二十代半ばほどの女性だった。亜麻色のコートの肩が黒く濡れている。その手には、色褪せたビロードの小箱が大切そうに握りしめられていた。
「どんな時計ですか」
「父の……形見なんです」
彼女はカウンターに近づき、震える手で箱を開けた。そこに鎮座していたのは、銀色の懐中時計だった。蓋の細工は見事な唐草模様で、使い込まれた銀特有の鈍い光沢を放っている。弦之介は白手袋をはめた手で、恭しくそれを手に取った。
ずしり、とした重み。それは金属の質量であると同時に、そこに刻まれた時間の重みでもあった。
「動かないのですか」
「はい。父が亡くなったその瞬間に、止まってしまったんです。それから一度も、動きません」
彼女――名を沙織といった――の話によれば、父親は厳格な職人だったという。家族との会話も少なかったが、この時計だけは肌身離さず持っていた。彼が息を引き取ったのは一ヶ月前の午後四時三十二分。そして、この時計の針もまた、四時三十二分を指して凍り付いていた。
「まるで、父の魂がそこに入り込んでしまったみたいで……。直していいものか迷ったんですが、どうしても、時間が止まったままの気がして」
弦之介は黙って頷き、裏蓋を開けるための器具を手に取った。カチリ、と微かな音がして、時計の心臓部が露わになる。
美しい景色だった。大小様々な歯車が複雑に噛み合い、テンプやアンクルが精緻な宇宙を構成している。だが、その宇宙は死んでいた。テンプは揺れず、歯車は沈黙を守っている。
弦之介はルーペを目に戻し、深淵を覗き込むように内部を凝視した。油の匂い、金属の匂い、そして微かに残る煙草の香り。それらが彼の鼻腔をくすぐり、時計が記憶している風景を脳裏に再生させる。
時計師とは、医者であり、また探偵でもある。
なぜ止まったのか。どこが痛んでいるのか。それを探ることは、持ち主の人生を遡ることに等しい。
数分後、弦之介は「ふむ」と小さく声を漏らした。
「何か、わかりましたか?」
「ええ。原因はこれです」
弦之介はピンセットを深く差し込み、香箱車(こうばこぐるま)と呼ばれる動力源の隙間から、何かを摘み出した。
それは、微細な、しかし確かに異物である破片だった。
「これは……?」
「桜の、花びらの欠片ですね。完全に乾燥して、石のようになっていますが」
沙織は目を見開いた。
「桜……?」
「この時計は防水ではありません。おそらく、裏蓋を開けて調整をしている最中か、あるいは風防が割れた際に紛れ込んだのでしょう。この小さな花びらが、長い時間をかけて油を吸い、硬化し、ついには歯車の間に挟まって、時計の息の根を止めた。……奇跡的な確率です」
沙織はハッとして口元を押さえた。その瞳に涙が膜を張る。
「四時三十二分……」
「何か心当たりが?」
「父が倒れる前日……私、父と喧嘩したんです。私の結婚のことで。父は頑固で、どうしても認めてくれなくて。私は家を飛び出して、翌日、父が倒れたと連絡を受けました」
彼女はカウンターに手をつき、嗚咽を漏らした。
「でも、思い出したんです。子供の頃、父とよく行った公園のこと。そこには大きな桜の木があって……父は毎年、その木の下で時計の手入れをしていました。『春の空気を吸わせるんだ』って言って。……四時三十二分。それは、私が生まれた時間です」
弦之介は静かに、摘み出した花びらの欠片を小さなガラス瓶に入れた。
「お父様は、亡くなる直前まで、この時計を見ていたのかもしれませんね。あるいは、もっと前から、この時計はあなたとの思い出を抱え込んで、限界まで動いていた。そして、お父様の鼓動が止まるのと呼応するように、この花びらがついに歯車を止めた」
それは偶然かもしれない。単なる物理現象の結果かもしれない。だが、時計修理の現場では、時として科学では説明のつかない「意思」のようなものを感じることがある。
「直りますか?」
沙織が涙を拭って尋ねた。
「もちろんです。花びらを取り除き、分解掃除(オーバーホール)をして、新しい油を差せば、また元気に時を刻み始めますよ」
「お願いします。……時間を、進めたいんです」
「承知しました」
弦之介は作業に取り掛かった。店内に流れるのは、雨音と、彼が使う工具の金属音だけ。まるで儀式のように、一つ一つの部品が洗浄され、磨かれ、再び組み上げられていく。
一時間ほどが経過しただろうか。全ての部品があるべき場所に戻された。
弦之介が竜頭(りゅうず)を巻き上げる。カリ、カリ、カリ、と指先に確かな手応えが伝わる。ゼンマイという名の筋肉に力が蓄えられる。
そして、彼が軽く時計を振ると、チチチチチ……と、軽やかな音が響き始めた。
それは蘇生の産声だった。止まっていた四時三十二分から、秒針が滑らかに動き出す。
「動いた……」
沙織の声が震えた。弦之介は時計を彼女に手渡した。
掌の中で脈打つ、父の生きた証。規則正しいリズムは、まるで「大丈夫だ」と語りかけているようだった。
「お父様は、時間を止めたかったのではなく、あなたにこの時間を託したかったのかもしれませんね」
弦之介の言葉に、沙織は深く頷いた。その表情からは、先ほどまでの陰鬱な影が消え、雨上がりの空のような晴れやかさが覗いていた。
「ありがとうございます。本当に……ありがとうございます」
代金を受け取り、彼女を見送る頃には、外の雨は小雨になっていた。ドアが開くと、湿った風と共に、夜の街の匂いが流れ込んでくる。
「お幸せに」
弦之介の言葉が届いたかどうかはわからない。だが、彼女の足取りは来た時よりもずっと軽く、前を向いていた。
再び静寂が戻った店内で、弦之介は淹れたてのコーヒーを一口啜った。壁に掛けられた数多の古時計たちが、それぞれのテンポで時を刻んでいる。
チクタク、チクタク。
その不揃いな合唱は、まるで人生そのもののようだ、と彼は思う。
時には止まり、時には進み、そして誰かの手によってまた動き出す。
弦之介は再び作業台に向かった。次の時計が、次の物語を抱えて、彼の手を待っているからだ。
雨はいつしか止み、雲の切れ間からは、洗われたばかりの月が、静かに街を見下ろしていた。