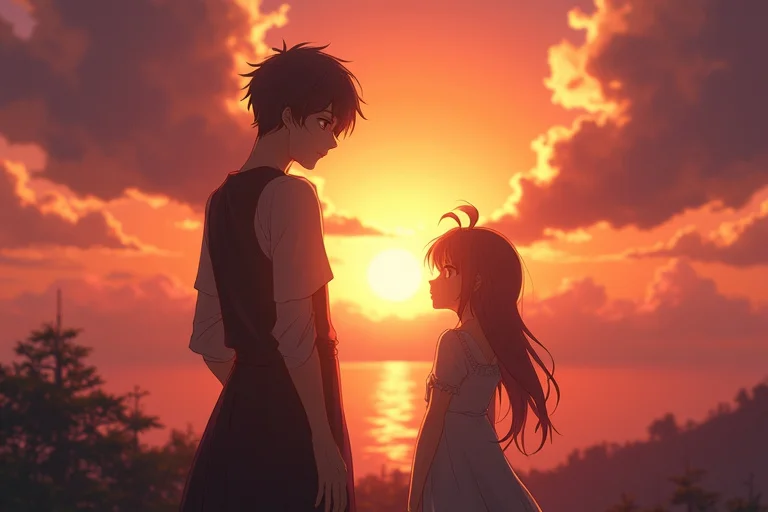第一章 静寂の鐘
リラの世界から、鳥のさえずりが消えたのは、彼女が生まれるずっと前のことだった。川のせせらぎも、風が木々の葉を揺らす音も、遠い神話の中の出来事。この世界では、魔法を使うたびに、その代償として何かしらの「音」が一つ、永遠に失われるのだ。かつて大いなる厄災を退けるため、古の賢者たちが禁断の魔法を幾度となく行使した結果、世界は深淵のような沈黙に包まれた。
それでも、リラの住む谷間の村「セレニタ」には、たった一つだけ残された音があった。一日に二度、朝と夕に鳴り響く、古い教会の「鐘の音」だ。それは魔法によるものではなく、人の手で撞かれる物理的な音。ゴォン、と腹の底に響く厳かな音色は、沈黙に慣れた村人たちの肌を震わせ、心に時間の流れを刻みつける唯一の道標だった。リラは調律師の見習いとして、その鐘を誰よりも愛していた。音を知らない彼女にとって、あの振動こそが「音楽」のすべてだった。
その日の夕暮れも、リラは教会の見える丘の上に座り、その時を待っていた。茜色の光が空を染め上げ、影が長く伸びる。定刻。村人たちが皆、無意識に仕事の手を止め、空を見上げる。しかし、待てど暮らせど、あの荘厳な響きは訪れなかった。
一秒が永遠のように感じられる。ざわめきすら起こらない。音のない世界では、人々の不安は表情と視線の交錯だけで伝播していく。誰もが息を殺し、耳を澄ます。だが、そこにあるのは完全な、底なしの静寂だけだった。
リラは丘を駆け下りた。心臓が嫌な音を立てている、と彼女は思った。いや、音などしない。ただ、激しい鼓動が胸郭を打つ感触があるだけだ。教会にたどり着くと、鐘楼守の老人が呆然と立ち尽くしていた。
「……鳴らないんだ」老人はかすれた声で言った。「何度、綱を引いても。ただ、虚しく揺れるだけで……音が、しない」
リラは震える足で鐘楼を上った。そこには、見慣れた巨大な青銅の鐘が鎮座している。見た目には何の変化もない。だが、彼女がそっと指で触れても、かつて感じた微かな残響の気配すらなかった。まるで、ただの冷たい鉄の塊。鐘から「音」という魂が、綺麗に抜き取られてしまったかのようだった。
誰かが、魔法を使ったのだ。この村に残された最後の宝物を代償にして。
絶望が霧のように村を覆い尽くす中、リラの心には、小さな怒りの炎が灯った。誰が、何のために。失われた音は二度と戻らない。それがこの世界の絶対的な理だ。しかし、本当にそうなのか? リラは祖父の遺した古文書に、失われた音を「記録」し、いつか世界に還すことを目指した「調律師」の話が書かれていたのを思い出していた。
皆が諦観に沈むなら、私が行く。この静寂を終わらせるために。リラは固く拳を握りしめた。鐘の音を奪った者を見つけ出し、そして、もし可能なら、この沈黙の世界に、もう一度、音を取り戻す旅に出ることを、たった一人、心に誓ったのだった。
第二章 音の記憶を紡ぐ者
音のない旅は、孤独との戦いだった。リラは風の感触からその強さを知り、地面の振動で獣の接近を察知した。五感は研ぎ澄まされていったが、心の隙間を埋めるものは何もない。かつて豊かな音色を奏でていたであろう森も川も、今はただの動く風景画に過ぎなかった。歩きながら、リラは想像する。本の記述にあった「サラサラ」という小川のせせらぎを、「ザワザワ」という木々の葉ずれを。だが、想像はすぐに虚しい沈黙に吸い込まれて消えてしまう。
旅を始めて十日目のこと。リラは打ち捨てられた廃墟で、一人の青年に出会った。彼は焚き火の前で、奇妙な踊りをしていた。手をひらひらさせ、唇を震わせ、喉を動かす。しかし、そこから発せられる音は一つもない。ただ、彼の表情は恍惚としており、まるで壮大な交響曲を聴いているかのようだった。
リラが声をかけると、青年は驚いて動きを止め、警戒の色を浮かべた。名をカイと名乗った彼は、旅の理由を尋ねるリラに、初めは何も答えようとしなかった。しかし、リラがセレニタ村の鐘が消えたこと、音を取り戻すために旅をしていることを話すと、彼の険しい表情がわずかに和らいだ。
「あんたも、か」カイは呟いた。「俺の一族は、『音の記憶』を守ってきた。魔法で失われる音を、その瞬間に立ち会い、魂に刻み込む。そして、決して忘れぬよう、こうして体で、心で、反芻し続けるんだ」
カイは、先ほどの奇妙な踊りが、かつて存在した「嵐の音」を再現していたのだと説明した。轟く雷鳴、叩きつける雨、唸る風。彼はその全てを、音のない世界でたった一人、体現していたのだ。リラは息を呑んだ。目の前にいるのは、生きた音の図書館だった。
「セレニタの鐘の音も……覚えている」カイは目を伏せた。「あれを代償にした魔法の気配を追って、俺も旅をしている。おそらく、北の『霧降り山』の方向だ」
二人の旅が始まった。カイはリラに、失われた音の話をたくさん聞かせてくれた。カッコウの鳴き声、夏の夜の虫の羽音、賑やかな市場の喧騒。彼はその音を、身振り手振りと、声にならない口の動きで必死に伝えようとした。リラは目を閉じ、彼の表現に全神経を集中させる。すると、不思議なことに、心の中に微かな響きが生まれるのを感じた。それは本当の音ではないかもしれない。けれど、冷たい沈黙に覆われた彼女の世界に、初めて生まれた温かい色彩だった。
カイと共にいると、リラの絶望は少しずつ薄れていった。音のない世界をただ嘆くのではなく、カイのように、その記憶を慈しみ、心の中で奏でる生き方もあるのだと知った。それでも、鐘の音を奪った者への怒りは消えない。何故なら、カイが記憶している音は、全て過去のもの。鐘の音は、今を生きる村人たちの希望だったのだから。
霧降り山の麓に近づくにつれ、魔法の残滓は強くなっていった。犯人は近い。リラとカイは、互いの存在を支えに、深く立ち込める霧の中へと足を踏み入れた。
第三章 沈黙の代償
霧降り山の山頂には、古びた石造りの小屋がひっそりと佇んでいた。魔法の気配は、そこから漏れ出ている。リラは心臓の鼓動を抑え、カイと共に慎重に扉を開けた。そこにいたのは、杖を手にやつれ果てた姿で座り込む、見知った顔だった。
「……長老」
リラの唇から、かすれた声が漏れた。セレニタ村の長老の一人、賢明で誰からも尊敬されていたエリオットその人だった。彼の傍らには、薬草をすり潰す道具と、何枚もの羊皮紙が散らばっている。
「リラか……それに、音の記憶を紡ぐ一族の子も一緒か。やはり、ここまで来たのだな」エリオットは静かに顔を上げた。その目には、罪悪感と、そして諦めにも似た深い疲労が滲んでいた。
「なぜです! なぜ鐘の音を!」リラは声を荒らげた。怒りと裏切られた想いが、彼女を突き動かす。「あの音は、村の……皆の心だったのに!」
エリオットはゆっくりと立ち上がり、窓の外を指さした。霧に覆われた麓の村の方角だ。「見て分からないか。この山から吹き下ろす風が、何を含んでいるのかを」
彼は語り始めた。数ヶ月前から、村では原因不明の咳病が流行り始めていた。初めは些細なものだったが、次第に悪化し、特に子供や老人が衰弱していった。それは、この霧降り山に巣食う、古代の瘴気が原因だった。通常の薬では効果がない。瘴気を浄化するには、強力な魔法に頼るしかなかった。
「私には、選ぶことしかできなかった」エリオットの声は、懺悔のように響いた。「村人たちの命か、それとも村の心の支えである鐘の音か。魔法の代償は、術者が最も大切に思うものから奪われるという。私は……誰よりもあの鐘の音を愛していた。だからこそ、代償として選ばれてしまったのだ。私が皆の命を救いたいと、強く願えば願うほど、最も大きな音を差し出すしかなかった……」
衝撃の事実に、リラは言葉を失った。彼女が追い求めてきた犯人は、私利私欲に駆られた悪人ではなかった。村を、人々を救うために、誰よりも苦しい決断を下した一人の人間だったのだ。鐘の音を奪った憎むべき行為は、同時に、多くの命を救った崇高な犠牲でもあった。
正義とは何か。悪とは何か。リラの信じてきた単純な二元論が、ガラガラと音を立てて崩れていく。音のない世界は死んだ世界だと思っていた。しかし、命がなければ、音があっても意味がないではないか。
隣で話を聞いていたカイもまた、複雑な表情で立ち尽くしていた。彼の一族は、魔法の使用を絶対悪とし、音を奪う者を追うことを使命としてきた。だが、目の前の現実は、その使命に根源的な問いを突きつけていた。
リラは、エリオットのやつれた顔と、彼の足元に散らばる治療法の研究の跡を見た。彼の苦悩と愛情が、痛いほどに伝わってくる。彼女は、この人を断罪することなど、到底できないと悟った。同時に、自分の旅の目的が、深い霧の中に消えてしまったような感覚に襲われた。失われた音は戻らない。そして、その喪失には、守られた命という、あまりにも重い意味があったのだ。
第四章 新たなる律べ
リラとカイは、エリオットを連れて村には戻らなかった。彼を糾弾することは、村を二つに引き裂くだけだと分かっていたからだ。三人は山頂の小屋に残り、静かな時を過ごした。エリオットは瘴気を完全に封じるための最後の仕上げを行い、リラとカイはそれを手伝った。
憎しみも怒りも消え、リラの心には虚無感が広がっていた。音を取り戻すという夢は破れた。だが、エリオットの自己犠牲と、カイが紡いできた音の記憶に触れ、彼女の中で何かが変わり始めていた。失われたものを追い求めるだけが、道ではないのではないか。
ある風の強い日、リラは小屋の外で、風に煽られてカタカタと揺れる木の枝をじっと見つめていた。音はしない。だが、その規則正しい揺れは、まるでリズムを刻んでいるかのようだった。その時、彼女の心に、一つの光が差し込んだ。
「……創ればいいんだ」
リラは呟いた。カイが驚いて彼女を見る。
「失われた音を取り戻すことはできない。魔法を使えば、また新たな沈黙が生まれるだけ。でも、今ここにあるものから、新しい音を創り出すことはできるかもしれない」
彼女は行動を開始した。森に入り、硬さや形の違う木々を選び、薄く削る。洞窟から持ち帰った石を磨き、大きさの違うものを並べる。川辺で見つけた葦の茎に、小さな穴を開ける。魔法ではない。太古の昔、人々が初めて楽器を生み出した時のような、素朴で根源的な試みだった。
カイは、初めは戸惑いながらも、やがて彼女のやろうとしていることを理解し、熱心に手伝い始めた。彼は記憶の中にある楽器の構造をリラに教え、リラは調律師としての知識を活かして、それを形にしていく。エリオットもまた、衰弱した体で、彼らに知恵を貸した。
数週間後。山頂の小屋の前に、奇妙なオブジェが出来上がっていた。様々な長さの木片や竹筒が吊るされ、磨かれた石が並べられている。それは風の力で揺れ、互いに触れ合うことで音を奏でる、原始的なウィンドチャイムだった。
そして、その瞬間は訪れた。
山頂を吹き抜ける一陣の風が、オブジェを優しく揺らした。
カラン……コロン……
か細く、不揃いだが、間違いなくそれは「音」だった。魔法の代償ではない、世界に新しく生まれた音。リラとカイ、そしてエリオットは、息を止めてその音に聴き入った。
リラの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、鐘を失った時の絶望の涙ではなかった。失われた鳥のさえずりでも、川のせせらぎでもない。けれど、これは紛れもなく、自分たちの手で生み出した、希望の音だった。
世界から失われた音は、もう戻らないだろう。沈黙が完全に消える日も来ないかもしれない。しかし、リラはもう絶望していなかった。彼女は調律師として、失われた音を修復するのではなく、静寂と調和する新たな音を世界に「調律」していく道を見つけたのだ。
リラは、麓の村を見下ろした。いつか、この新しい音を村へ届けよう。そして、皆で一緒に、もっとたくさんの音を創り出していこう。静寂の中に、一つ、また一つと、小さな音楽を灯していくのだ。
風が再び吹き、カラン、と澄んだ音が響いた。それは、沈黙の世界の終わりを告げる鐘ではなく、新しい世界の始まりを告げる、ささやかで、しかしどこまでも力強い産声のように、三人の心に深く、長く、響き渡った。