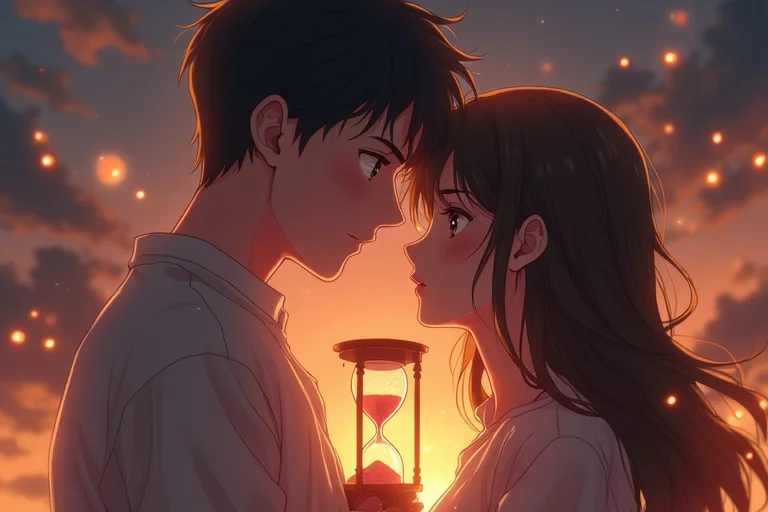第一章 無音のひと
古びた楽器の匂いが染みついた工房で、僕、相沢響(あいざわ ひびき)は息を潜めていた。僕の耳には、世界が奏でる過剰な音楽が常に流れ込んでいる。それは、僕が誰かに特別な感情――世間ではそれを好意や愛情と呼ぶらしい――を抱いた時にだけ聞こえる、その人の魂が奏でる内なるメロディーだ。
喜びは軽快なピチカート、悲しみはチェロの低く長い嗚咽、怒りは不協和音のクラスター。街を歩けば、すれ違う人々の心から漏れ出す無数のメロディーが乱反射し、僕の精神をすり減らしていく。だから僕は、他人と深く関わることを避け、この静かな工房で、言葉を持たない楽器たちの声に耳を傾ける生活を選んだ。僕にとってこの能力は、祝福ではなく呪いだった。
その日、修復を終えた古いチェロを依頼主の元へ届けに行った帰り道、雑踏の中で不意に世界が静かになった。いや、正確には、僕の耳を劈いていた感情のノイズが、ある一点を中心にすっと消え去ったのだ。まるで、強力な吸音材がそこにあるかのように。
視線をたどると、一人の女性がいた。彼女はショーウィンドウに飾られたアンティークの万年筆を、真剣な眼差しで見つめている。風に揺れる栗色の髪、白いブラウス。何の変哲もない姿なのに、彼女の周りだけが、完全な静寂――サイレンスに包まれていた。
僕の心臓が、トクン、と大きく脈打った。好奇心と、得体の知れない安堵感。この人からは、何のメロディーも聞こえない。僕がこれほど強く惹かれているにもかかわらず。彼女は僕にとって、初めて出会った「無音」の人間だった。
数日後、その偶然は運命の形をとって再び僕の前に現れた。街外れの小さな映画館『銀幕座』。僕はそこのオーナーから、上映前に流す古い手回しオルゴールの修復を依頼されていた。軋む扉を開けると、薄暗いホールに澄んだ声が響いていた。
「さあ、ご覧ください! 哀れな花売り娘に差し伸べられた、一輪の薔薇。それは偽りの紳士が仕掛けた、甘くも悲しい罠だったのでございます!」
スクリーンにはモノクロの映像が流れ、その横で、一人の女性が身振り手振りを交えながら物語を紡いでいる。活動弁士、というやつか。その声の主こそ、先日僕の世界から音を奪った、あの女性だった。
彼女は僕に気づくと、練習を中断して駆け寄ってきた。「あなたが、オルゴールの職人さん?」「……はい」。彼女、藤宮奏(ふじみや かなで)さんと名乗った。その名前とは裏腹に、彼女からはやはり何の音も聞こえない。ただ、彼女の言葉だけが、何の雑音にも邪魔されず、真っ直ぐに僕の鼓膜を震わせた。僕は生まれて初めて、人の声の響きを美しいと思った。
第二章 滴るようなピアニッシモ
奏さんとの時間は、僕にとって唯一の安息だった。週に一度、オルゴールの調整で銀幕座を訪れるたび、僕たちは言葉を交わした。彼女は無声映画にかける情熱を語り、僕は古い楽器たちが持つ記憶について話した。彼女の世界は言葉で彩られ、僕の世界は音で満ちている。正反対のようで、どこか似ている僕たちは、互いの世界にゆっくりと惹かれていった。
彼女といると、僕は呪われた能力のことなど忘れられた。他の人間のように、彼女の表情を読み、言葉の響きを感じ、その心の内を想像する。それは不確かで、もどかしく、けれど信じられないほど新鮮な体験だった。メロディーが聞こえないからこそ、僕は必死に彼女を「知ろう」とした。それは僕が、誰かに対して初めて抱いた純粋な欲求だった。
「響さんの手って、魔法使いみたいですね」
ある日、分解したオルゴールの繊細な部品をピンセットでつまむ僕の指先を見て、奏さんが言った。「壊れたものに、もう一度命を吹き込むんだから」
「そんな大したものじゃないですよ。ただ、声にならない声を聴くだけです」
僕がそう答えると、彼女は少し寂しそうに微笑んだ。「声にならない声、か。私も、そんな声を届けられる弁士になりたいな」
その時、彼女の細い指が、僕の手にそっと触れた。その瞬間だった。
――ポツリ。
静寂の湖に、一滴の雫が落ちたような、ごく微かな音がした。清らかで、どこまでも透明な、ピアノの最も優しい一打。それは間違いなく、彼女の内側から響いてきた音だった。喜びの、それも生まれたばかりの、まだ形を持たない純粋な感情の音。
僕の心臓が跳ねた。無音ではなかった。彼女も、僕と同じように魂のメロディーを持っていたのだ。ただ、それが聞こえなかっただけ。僕の気持ちが、ようやく彼女の心の深層に届き、小さな共鳴を起こした証なのかもしれない。
その日から、僕は彼女に触れるたび、その微かな音を探すようになった。それはまるで、耳を澄まさなければ聞こえない、遠い星の瞬きのようだった。彼女が笑うと、水の滴は陽の光を浴びてきらめき、僕が作った冗談に困った顔をすると、少しだけ曇った音色に変わる。僕はそのピアニッシモの旋律に、愛おしさで胸が張り裂けそうになった。
彼女の感情が聞こえる。その事実は、かつての僕なら恐怖したはずだ。だが、奏さんの音は違った。それは僕を苛むノイズではなく、むしろ僕の荒んだ心を癒す、聖水のような響きを持っていた。
僕は決意した。この気持ちを、僕の能力のことも含めて、すべて彼女に打ち明けよう。そして、彼女が奏でるメロディーをもっと、もっと大きな音で聴きたい、と。
第三章 砕かれた静寂
決意を胸に銀幕座を訪れた僕を待っていたのは、奏さんではなく、彼女の師匠である老弁士の白川さんだった。彼はいつもの温和な表情を消し、硬い面持ちで僕を映写室へと招き入れた。
「相沢さん、君に話しておかねばならんことがある」
カタカタと回る映写機の音だけが、重い沈黙を埋めていた。白川さんは、ゆっくりと語り始めた。奏さんの、誰にも明かしたことのない過去について。
「あの子はな、幼い頃に事故で頭を強く打った。幸い命に別状はなかったんだが…一つ、奇妙な後遺症が残ってしまった」
ゴクリと、僕は唾を飲んだ。嫌な予感が、冷たい手となって僕の背筋を撫でた。
「奏は、強い感情の起伏を経験すると、その引き金になった出来事の記憶を失ってしまうんだ。『感情性健忘』…医者はそう呼んでいた。喜び、悲しみ、怒り…感情が一定の閾値を超えると、脳が自己防衛のために、その記憶をシャットアウトしてしまうらしい」
言葉を失った。奏さんから聞こえるメロディーが、なぜあれほどまでに微かだったのか。なぜ僕が初めて会った時、彼女は完全な「無音」だったのか。全てのピースが、最悪の形で組み上がっていく。
彼女は、記憶を失うことを恐れ、無意識のうちに自分の感情に蓋をして生きてきたのだ。大きな喜びも、深い悲しみも感じないように。心の湖面を決して波立たせないように。だから、彼女のメロディーは、か細いピアニッシモでしか響かなかったのだ。
「あの子が弁士を目指しているのも、それが理由だ」と白川さんは続けた。「自分の中から生まれる感情は危険でも、物語の中の登場人物の感情なら、安全に表現できる。失われるかもしれない自分の感情を、物語という外部の記録装置に託しているんだ。あの子にとって、あれは生きるための術なんだよ」
僕が聞いた、あの水の滴のような喜びの音。それは、僕との触れ合いの中で、彼女が抑えきれずに漏らした、本当の感情の欠片だったのだ。そしてそれは同時に、彼女の記憶が失われる寸前の、危険な兆候でもあった。
僕が彼女を愛し、彼女も僕を愛してくれたなら。彼女の心が僕への想いで満たされたなら。その瞬間、彼女は僕と過ごした全ての記憶を失ってしまうかもしれない。
僕の存在そのものが、彼女の世界を壊す時限爆弾だったのだ。愛すれば愛するほど、彼女の中から僕という存在が消えていく。これ以上の呪いがあるだろうか。僕が求めていた彼女のメロディーは、彼女の記憶と引き換えに奏でられる、残酷な鎮魂歌だった。
工房に戻った僕は、修復途中のヴァイオリンを前にただ立ち尽くした。静寂を愛した僕が、初めて美しいと感じた音。その音を奏でることが、愛する人を壊すことにつながるなんて。僕は、奏さんの前から消えるべきなのだ。彼女の静かで安全な世界を、これ以上脅かしてはならない。
第四章 ふたりで奏でる旋律
僕は奏さんを避けた。銀幕座へ行くのをやめ、彼女からの連絡にも応じなかった。僕の耳には、日増しに強くなる彼女の混乱と悲しみのメロディーが届いていた。それはもはやピアニッシモではなく、僕の胸を掻きむしるような、痛々しい不協和音だった。その音に耐えきれなくなった僕は、全てを終わらせるために、最後にもう一度だけ彼女に会うことにした。
夜の銀幕座で待っていた奏さんは、やつれていた。僕の姿を見ると、その瞳に安堵と不安が入り混じった光が揺れた。
「どうして…」
か細い声で問いかける彼女に、僕は全てを話した。僕が持つ呪われた能力のこと。彼女から聞こえるメロディーのこと。そして、彼女を愛することが、彼女の記憶を奪うかもしれないという絶望的な恐怖を。
僕の話を、彼女は瞬きもせず、静かに聞いていた。やがて僕が語り終えると、彼女はふっと息を吐き、そして、驚くべきことに、小さく微笑んだ。
「そうだったんだ。…響さんには、私の心が聞こえていたんですね」
彼女はゆっくりと僕に近づき、僕の手に自分の手を重ねた。「記憶が消えるのは、怖いです。今までも、何度も…大切な瞬間を失くしてきました。楽しかったはずの遠足の日も、コンクールで賞をもらった日も、写真やトロフィーだけが残っていて、そこに心が無いんです。空っぽの箱みたいで、ずっと怖かった」
彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
「でも、何も感じずに生きていくのは、もっと怖い。響さんと出会って、私の世界に色がついて、音が生まれた。もし、その色や音の記憶を明日には忘れてしまうとしても…いいんです」
彼女は僕の手を強く握った。
「響さんと心が触れ合ったこの瞬間は、たとえ脳が忘れても、私の魂が覚えているはず。だから、怖がらないで。私の心を、もっと揺さぶって。あなたの音も、聴かせて」
その瞬間、僕の世界で、奇跡が起きた。
彼女の中から、これまで聞いたこともないほど豊かで、壮大なメロディーが溢れ出してきたのだ。それはオーケストラの一斉奏楽のような、圧倒的な愛の旋律だった。悲しみも、喜びも、恐怖も、希望も、全てを包み込んで昇華させていく、力強い生命の音楽。
僕たちは、どちらからともなく抱きしめ合っていた。彼女のあたたかいメロディーと、僕の中から初めて生まれる、臆病だけれど確かな愛情のメロディーが溶け合い、一つの完璧なハーモニーを奏でていた。
数年後、僕たちは海辺の小さな町で暮らしている。奏は時々、記憶の断片を失う。昨日食べた夕食のメニューや、僕と交わした些細な約束を忘れてしまうことがある。そのたびに僕の胸はちくりと痛む。
けれど、彼女から聞こえるメロディーは、いつも穏やかで、陽だまりのようにあたたかい。
彼女は僕の腕に寄りかかり、水平線に沈む夕日を見つめながら言う。
「ねえ、響さん。今日の夕日、なんだかすごく懐かしい音がする」
彼女は、昨日見た夕日のことを覚えていないのかもしれない。でも、その美しさを感じた魂の響きは、確かに彼女の中に蓄積されている。
僕は彼女を強く抱きしめる。たとえ彼女が昨日を忘れても、僕が全て覚えている。僕たちが共に奏でた今日のメロディーが、明日を照らす光になる。愛とは、記憶の連なりではなく、今この瞬間に響き合う、魂と魂の音楽なのだ。僕たちはこれからも、不確かで、儚くて、けれど何よりも美しい旋律を、二人で奏でていく。