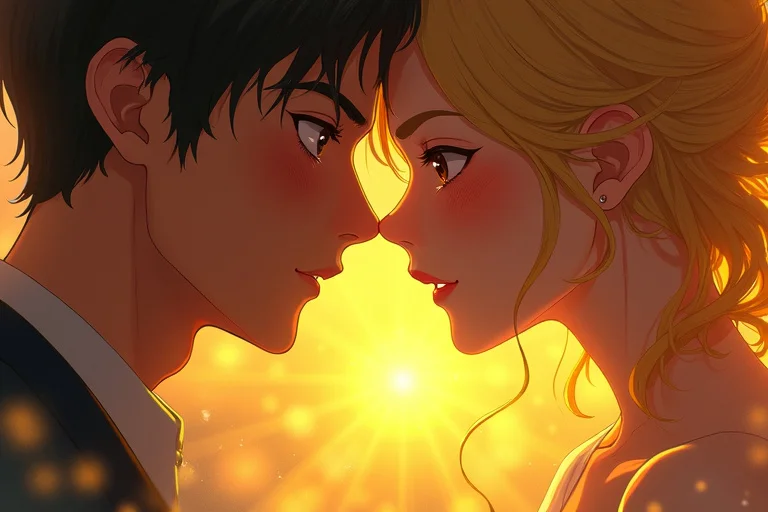第一章 紋様のささやき
世界から、色が失われつつあった。ニュースキャスターは沈痛な面持ちで、拡大を続ける『空白地帯』の地図を指し示している。人々が恋心を失い、その熱量が消費された後に残る、無色透明の領域。私の住むこの街も、その縁辺でくすんだセピア色に染まり始めていた。
私、凛(りん)の肌に、最初の『愛の紋様(アモルファス)』が浮かんだのは、そんな灰色の世界に差し込んだ一筋の光と出会った日だった。
街角の小さな工房。窓から漏れる琥珀色の光に誘われて足を止めると、一人の男性が古いチェロを修復していた。一心不乱に弓を動かし、弦の響きに耳を澄ます彼の横顔。奏(かなで)と名乗ったその人は、失われた音を取り戻す職人だった。彼が試しに弾いた一節が、私の心の澱みを静かに震わせた。その瞬間、左腕の内側に、チリリと微かな熱が走った。見れば、皮膚の下に水晶細工のような、透明な紋様が淡く浮かび上がっていた。
恋だった。
その日から、私の世界は奏を中心に回り始めた。しかし、喜びと共に奇妙な変化が訪れる。あれほど好きだった、図書館の古い本の匂いが薄れ、毎日淹れる紅茶の繊細な香りが、まるで水のように感じられるようになった。五感が、ゆっくりと鈍化していく予兆。私は、肌に刻まれた愛の証を、畏れにも似た気持ちで見つめるしかなかった。
第二章 色褪せた万華鏡
奏の工房に通ううちに、私の腕の紋様は複雑な蕾のように形を成し、より深く、鮮明になっていった。彼と話すたび、その指が楽器に触れるのを見るたび、紋様は心地よい微熱を帯びる。
「この街も、ずいぶん色褪せてしまったな」
ある日、奏が工房の窓から外を眺めながら呟いた。彼の瞳には、世界の色彩を憂う静かな悲しみが宿っていた。
「昔は、夕焼けがもっと燃えるような赤だったんだ。恋人たちの笑い声が、街を金色に染めていた」
彼は『恋心』が世界を彩る法則を知る者ではなかったが、その肌で、魂で、世界の変容を感じ取っていた。その感受性の鋭さが、私をさらに惹きつけてやまなかった。
彼の言葉に突き動かされ、私は祖母の遺品を整理していた時に見つけた、古びた木箱を開けた。中に入っていたのは、一本の『色褪せた万華鏡』。かつては世界の『恋心の色』を最も美しく映したという遺物だが、今では覗き込んでも、ぼんやりとした光の粒子が漂うだけだった。祖母もまた、『愛の紋様』を持つ者だったと、母から聞かされたことがある。この万華鏡は、私に何かを伝えようとしているのだろうか。私は冷たい感触を確かめるように、そっとそれを握りしめた。
第三章 空白の足音
奏への想いが深まるにつれて、私の世界は内側から静かに侵食されていった。
奏が私のために淹れてくれた、香り高いコーヒー。その湯気の向こうにある彼の笑顔ははっきりと見えるのに、鼻腔をくすぐるはずの香ばしい匂いは、もはや記憶の中にしか存在しなかった。彼の低い声も、チェロの優しい音色も、水中にいるかのようにくぐもって聞こえる。五感の喪失は、確実に進行していた。
同時に、世間では『愛の紋様』を持つ者たちの連続失踪事件が、深刻な社会問題となっていた。彼らはある日忽然と、文字通り跡形もなく消えるのだという。後に残るのは、かすかな光の粒子だけ。
恐怖が私の心を掴んだ。このまま奏を愛し続ければ、私の紋様は全身を覆い尽くし、私もまた消えてしまうのではないか。愛するほどに、自分の存在が希薄になっていく。奏に触れたいと願うのに、その温もりさえ、いつか感じられなくなるのかもしれない。空白地帯の拡大と、自らの身体に起きる透明化の兆候。二つの現象が、私の内で不気味に共鳴していた。
第四章 万華鏡の啓示
その夜、恐怖と愛情の狭間で眠れずにいると、腕の紋様がこれまでになく強く、内側から発光を始めた。まるで脈打つように明滅する光に導かれ、私は無意識に『色褪せた万華鏡』を手に取っていた。
震える手で、それを目に当てる。
次の瞬間、息を呑んだ。ぼんやりとした光しか見えなかったはずの万華鏡の内部で、失われたはずの色彩が爆発した。赤、青、黄金色、緑。無数の『恋心の色』が渦を巻き、万華鏡は星空そのものと化していた。
そして、その光の中に見たのだ。
笑顔の男女が、その身に宿した『愛の紋様』を輝かせながら、次々と世界の色彩の中へ溶けていく姿を。彼らは消滅しているのではなかった。自らの存在を愛の色に還元し、世界と一つになっていた。悲劇ではない、至福に満ちた昇華。
これが、真実。
『愛の紋様』を持つ者は、世界に色を取り戻すための存在。失踪は、新たな生への移行。『愛の循環』の一部なのだ。私は悟った。私の運命も、この光の渦の中にあるのだと。涙が頬を伝ったが、もはやそこに恐怖はなかった。
第五章 透明な告白
自分の運命を受け入れた私は、夜明けと共に奏の工房へ向かった。一歩踏み出すごとに、自分の身体が足元から透けていく感覚があった。世界の輪郭が、滲んで見える。
工房の扉を開けると、奏は驚いた顔で私を見た。
「凛、どうしたんだ……君の身体が……」
私の姿は、陽光に透けるガラス細工のように、向こう側がうっすらと見え始めていた。時間は、ない。
鈍化した聴覚のせいで、自分の声がどれほどの大きさで出ているのかも分からない。それでも、私は紡いだ。彼と出会えた喜びを、彼がくれた色彩を、そして、心の底からの愛を。
「奏さん、あなたを愛しています」
私の言葉に、奏は息を呑んだ。彼は透けゆく私の身体にそっと触れようとして、その指先が僅かに空を切る。彼の瞳に映る絶望と、それでも私を繋ぎ止めようとする必死の想いが、痛いほど伝わってきた。私は最後の力を振り絞り、彼の頬に手を伸ばした。もう、その温もりは感じられない。けれど、彼がここにいる。それだけで、よかった。
第六章 愛は世界の色となる
奏の腕に抱かれるようにして、私の身体は最後の輝きを放った。全身を覆い尽くした『愛の紋様』が、まるで教会のステンドグラスのように光を放ち、私の肉体は完全に透明な光の粒子へと変わっていく。
意識が拡散し、個としての輪郭を失っていく。
さようなら、奏。
私の最後の想いが、光の波となって世界に広がった。
その瞬間、奇跡が起きた。
灰色に淀んでいた街並みが、一斉に鮮やかな色彩を取り戻したのだ。建物の壁は煉瓦の赤を取り戻し、街路樹は生命力に満ちた緑を芽吹かせた。空はどこまでも澄んだ青に染まり、奏の工房に差し込む光は、温かい黄金色に輝いた。失われた『空白地帯』に、一瞬で色が、命が、吹き込まれていく。
私は風になり、光になり、音になった。
世界そのものになったのだ。
私の愛が、世界の色となった。
第七章 あなたが遺した色彩の中で
幾年かの月日が流れた。世界はかつての色彩を取り戻し、人々は再び恋をし、街には幸福な色が溢れている。
奏は工房で、今も楽器を修理し続けている。彼はもう、凛の姿を見ることも、その声を聞くことも、その肌に触れることもできない。
しかし、彼は知っている。
窓から差し込む夕焼けの茜色の中に、彼女の温もりがあることを。
風が運ぶ花の香りの中に、彼女の微笑みがあることを。
街に満ちる音楽の旋律の中に、彼女のささやきがあることを。
彼は色鮮やかに蘇った世界を見上げ、静かに微笑んだ。傍らには、いつの間にか息をのむほど美しい模様を映し出すようになった万華鏡が、静かに置かれている。
「聞こえているよ、凛」
奏は、世界そのものになった愛しい人へ向かって、そっと呟いた。
「君が奏でる、この世界の、すべての色が」