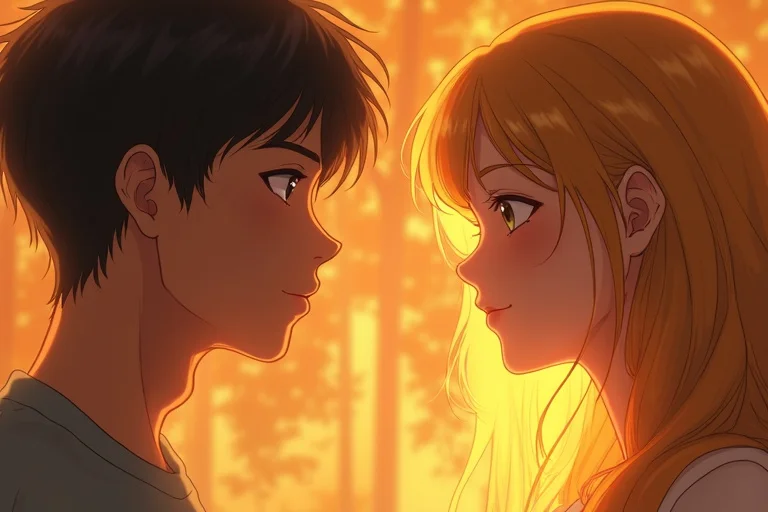第一章 心音の在り処
俺の頭の中では、常に誰かの心臓が鳴っている。
トクン、トクン、トクン……。それは、メトロノームのように正確で、ほとんど乱れることのない穏やかなリズム。この音が聞こえ始めたのは、三年前のあの事故以来だ。鉄骨の落下音と悲鳴が渦巻く中で意識を失い、次に病院のベッドで目覚めた時、この心音はすでに俺の一部になっていた。
医者は心的外傷による幻聴の一種だと診断したが、俺には分かっていた。これは幻聴などではない。生々しく、温かく、確かな生命の律動。世界中のどこかにいる、たった一人の人間の心臓の音だ。
俺、音無響(おとなしひびき)は、神保町の路地裏にひっそりと佇む古書店『時紡ぎ堂』で働いている。埃とインクの匂いが混じり合う静寂なこの場所は、世界の喧騒から耳を塞ぎたい俺にとって、唯一の聖域だった。そして、この心音が誰のものなのか、俺はとうの昔に答えに辿り着いている――と、信じていた。
週に三度、決まった曜日の午後に店を訪れる女性、朝比奈栞(あさひなしおり)さん。彼女が店の古びたドアベルを鳴らした瞬間から、俺の世界は色づく。陽だまりのような微笑みを浮かべ、背筋を伸ばして書架の間を歩く姿は、まるで古い物語から抜け出してきた登場人物のようだ。
彼女がそこにいるだけで、頭の中の心音は、その存在を肯定するように、より一層澄み渡って聞こえる。彼女の穏やかな物腰、静かな佇まい、そのすべてが、この安定したリズムと完璧に調和しているように思えた。だから、これは彼女の心音に違いない。そう確信していた。
「こんにちは、音無さん」
彼女のか細くも芯のある声が、本のページをめくる乾いた音に混じる。俺は「いらっしゃいませ」と返すのが精一杯で、すぐに視線を足元の床板に落としてしまう。彼女と話したい。もっと知りたい。けれど、コミュニケーションが極端に苦手な俺には、それが途方もなく高い壁に感じられた。
今日も彼女は、美術書のコーナーで一冊の本を手に取り、静かにページを繰っている。俺はカウンターの奥から、その姿を盗み見る。彼女が微笑むと、俺の胸が締め付けられる。頭の中のリズムは、変わらず穏やかだ。
この音は、俺にとって呪いであり、同時に救いでもあった。常に誰かと繋がっているという感覚は、孤独な俺を苛む枷でありながら、栞さんという存在を身近に感じさせてくれる唯一の絆だったのだ。いつか、この音の正体を彼女に打ち明け、そして俺の想いも伝えられたなら――。
そんな叶わぬ夢を抱きながら、俺は今日も、彼女の心音だと信じるその音に、静かに耳を澄ましていた。
第二章 不協和音の予感
季節が秋から冬へと移ろう頃、俺と栞さんの間には、ささやかな変化が訪れていた。きっかけは、一冊の古い詩集だった。彼女が探していたその本が、たまたま倉庫の奥から見つかったのだ。
「ずっと探していたんです。ありがとうございます、音無さん」
そう言って微笑んだ彼女の顔は、今まで見たどんな表情よりも輝いて見えた。その日から、彼女はカウンター越しに、俺に話しかけてくれるようになった。好きな作家のこと、最近読んだ小説の感想、街で見かけた猫の話。他愛のない会話だったが、俺にとっては宝物のような時間だった。
彼女と話している間、頭の中の心音は、ほんの少しだけテンポを速める。トクン、トク、トクン、と。それは心地よい高揚感となって、俺の全身に広がっていく。彼女も、俺と同じ気持ちでいてくれているのかもしれない。その小さな変化が、俺に淡い期待を抱かせた。
「音無さんは、どうしてここで働いているんですか?」
ある日、彼女が不意に尋ねた。
「……本が好きだから、です。あと、ここが、静かだから」
「静か、ですか」
栞さんは少し意外そうな顔をして、店内を見回した。「確かに。でも、本の声が聞こえてきませんか?一冊一冊が、誰かに読まれるのを待っているような、そんな囁きが」
彼女の言葉に、俺は息を呑んだ。本の声。そんな詩的な表現を、彼女はごく自然に口にする。頭の中のリズムが、また少しだけ速くなるのを感じた。俺はこの人を、もっと深く知りたい。そう強く思った。
しかし、その数日後。俺の中で何かが軋むような出来事が起きた。
その日、栞さんはいつもより少し顔色が悪く見えた。彼女が書架から本を取ろうと手を伸ばした瞬間、ふらりと身体が傾いだのだ。
「危ない!」
俺は咄嗟にカウンターを飛び出し、彼女の腕を支えた。触れた腕は、驚くほどに細く、冷たかった。
「大丈夫ですか、栞さん」
「……すみません、少し眩暈が」
彼女はそう言って弱々しく微笑んだが、その顔は紙のように白い。俺は動揺し、彼女を椅子に座らせた。心配で心臓が張り裂けそうだった。俺自身の心臓は、警鐘のように激しく脈打っている。
だが、その時だった。俺は気づいてしまった。
頭の中に響く、あの“心音”は――驚くほどに、穏やかなままなのだ。
トクン、トクン、トクン……。
まるで何事もなかったかのように、いつもの静かなリズムを刻み続けている。目の前で、その音の主であるはずの女性が苦しんでいるというのに。
ありえない。どうしてだ?
俺の全身を、冷たい汗が伝った。目の前の現実と、頭の中の音との間に生まれた、決定的な不協和音。それは、俺が築き上げてきたささやかな世界の土台を、静かに、しかし確実に揺るがし始めていた。
第三章 沈黙する心臓と、叫ぶ鼓動
違和感は日に日に増していった。栞さんと会話を交わす喜びの中に、常に一抹の疑念が付きまとうようになった。この音は、本当に彼女のものなのだろうか。だとしたら、なぜあの時、音は平然としていたのか。
俺は確かめなければならないと思った。この曖昧な関係と、自分自身の呪縛に、決着をつけるために。
雪がちらつき始めた十二月の夜。俺は栞さんを、店の閉店後、近くの公園に呼び出した。イルミネーションが煌めく木々の下で、彼女は白い息を吐きながら、静かに俺を待っていた。
「……来てくれて、ありがとうございます」
「いえ。大切なお話って、なんですか?」
彼女は不思議そうに小首を傾げる。その仕草に胸が痛んだ。
俺は、震える声で全てを話した。三年前の事故のこと。それ以来、頭の中に特定の心音が響き続けていること。そして、その音は、あなたの心音だと信じてきたことを。
「だから……俺は、あなたのことが……」
好きだ、と続けようとした言葉は、彼女の悲しげな表情に遮られた。彼女はゆっくりと首を横に振った。
「ごめんなさい、音無さん。それは、私の音じゃありません」
彼女はコートの胸元にそっと手を当てた。「私……生まれつき心臓が弱くて、ずっと昔に手術をしたんです。私の心臓は、ペースメーカーで動いています。だから、感情でドキドキしたり、鼓動が速くなったりすることは、もうないんです」
沈黙。世界の音が、消えた。
ペースメーカー……?じゃあ、俺が聞いてきたこの三年間は、一体何だったんだ?俺が恋い焦がれ、安らぎを感じていたこの音は、誰のものなんだ?
頭が真っ白になり、足元から崩れ落ちそうになった。俺が信じていた世界が、音を立てて砕けていく。
その時だった。
「栞!」
切羽詰まった声と共に、誰かが公園に駆け込んできた。息を切らし、肩で呼吸をしながら俺たちを睨みつけている。見覚えのある姿だった。
『時紡ぎ堂』で働く、俺の同僚。いつも無愛想で、必要最低限の会話しかしない、影山澪(かげやまみお)。栞さんとは幼馴染だと、前に一度だけ聞いたことがあった。
彼女が、栞さんを庇うように俺の前に立った、その瞬間。
ドクンッ、ドクンッ、ドクンッ、ドクンッ!!
頭の中の心音が、爆発したかのように激しく、速く、力強く脈打ち始めた。今まで経験したことのない、嵐のような鼓動。それは恐怖か、怒りか、あるいは――。
俺は、凍り付いたように影山を見つめた。彼女は、唇をきつく結び、その瞳で真っ直ぐに俺を射抜いている。その瞳の奥に、俺は見た。長年隠されてきたであろう、激情の渦を。
理解が、雷のように全身を貫いた。
そうか。
栞さんと話している時に心拍が上がったのは、それを見ている影山の心が揺れていたから。
栞さんが倒れそうになった時に心拍が穏やかだったのは、幼馴染の容態を冷静に見極めようと、影山が必死に感情を抑えていたから。
そして今、俺が栞さんに告白しようとしたことで、彼女の心臓は、悲鳴のような鼓動を上げている。
俺が三年間、ずっと聴き続けてきた音。
俺が恋の証だと信じていたリズム。
その在り処は、ずっと、灯台下暗しというにはあまりにも近い、すぐ隣にあったのだ。
第四章 君という名の律動
公園のベンチに、俺と影山は並んで座っていた。栞さんは、心配する影山に促され、先に帰宅した。イルミネーションの光が、二人の間に気まずい沈黙を落とす。
先に口を開いたのは、影山だった。
「……ごめん。ずっと、わかってた」
ぽつりと呟かれた言葉に、俺は顔を上げた。
「君が、栞のことを見てるのも。……君の頭の中で、音が聞こえてるって話も。前に一度、店長が話してるのを、偶然聞いちゃったから」
彼女は俯いたまま、続けた。「栞は、昔から身体が弱くて、私が守らなきゃって思ってた。だから、君が栞に近づいていくのが、怖かった。でも……羨ましかった。君が栞に向けるその優しい眼差しが、本当は、私に向けられたものだったらいいのにって、何度も思った」
彼女の言葉の一つ一つが、俺の胸に突き刺さる。俺はなんて愚かだったんだろう。言葉や表情という、目に見えるものばかりに囚われ、最も雄弁に語りかけてきていた“音”の意味を、完全に取り違えていた。
俺は、影山澪という人間を、何も見ていなかった。無愛想な同僚、というレッテルを貼り、その内側にある繊細で、不器用で、深い優しさに気づこうともしなかった。それなのに、俺の身体は、彼女の心の叫びを、三年間ずっと聴き続けていたのだ。
「影山さん」
俺は彼女の名前を呼んだ。彼女がびくりと肩を震わせる。
頭の中では、まだ少し速いリズムが続いている。だがそれはもう、嵐のような激しさではない。緊張と、期待と、不安が入り混じった、繊細な律動だった。
「俺は、君のことを何も知らなかった。知ろうともしなかった。ごめんなさい」
深く、頭を下げる。
「でも、これだけは信じてほしい。俺がこの三年間、安らぎを感じていたのは、君の心臓の音だったんだ。君が穏やかな気持ちでいる時、俺は救われていた。君が、栞さんのことで心を痛めている時、俺も無意識に、それを感じ取っていたんだと思う」
顔を上げると、影山の瞳から、大粒の涙が零れ落ちていた。
「……ばか」
それは、今まで聞いた彼女の声の中で、最もか弱く、愛おしい響きを持っていた。
それから、俺たちはたくさん話した。彼女が、俺が働き始めた日から、ずっと俺を見ていたこと。不器用な俺を、もどかしく、そして愛おしく思っていたこと。俺は、初めて「心拍」というフィルターを通さずに、影山澪という一人の人間と向き合っていた。
頭の中の音は、もう呪いではない。
それは、言葉よりもずっと正直に、彼女の心を伝えてくれる、かけがえのない絆だ。俺は、この音と共に生きていく。いや、この音の主である、君と共に生きていきたい。
帰り道、俺たちはどちらからともなく、そっと手を繋いだ。冷たい夜気の中で、彼女の手は驚くほど温かかった。頭の中に響く、穏やかで力強いリズム。それは、世界で最も美しい音楽のように、俺の内なる世界を満たしていく。
言葉にしなくても、伝わる想いはある。
俺たちは、心臓の音で恋をした。世界中の誰にも真似できない、二人だけのやり方で。
隣を歩く君の心音が、トクン、トクンと、確かな愛の律動を刻んでいる。もう、その在り処を間違うことはない。