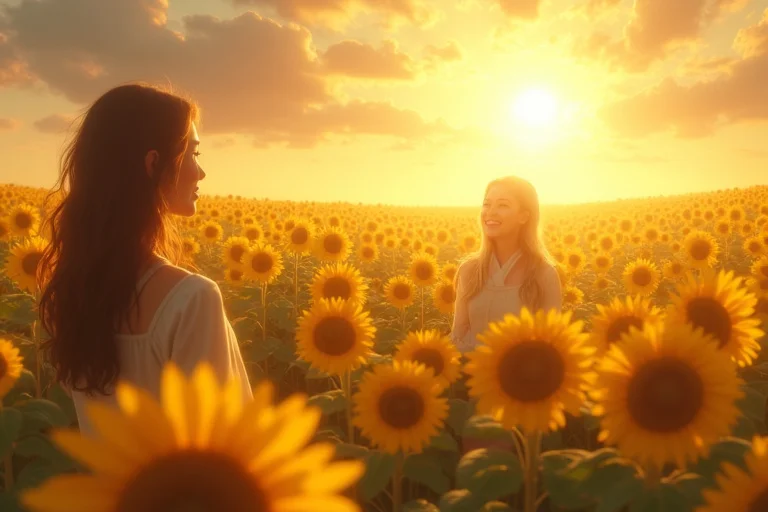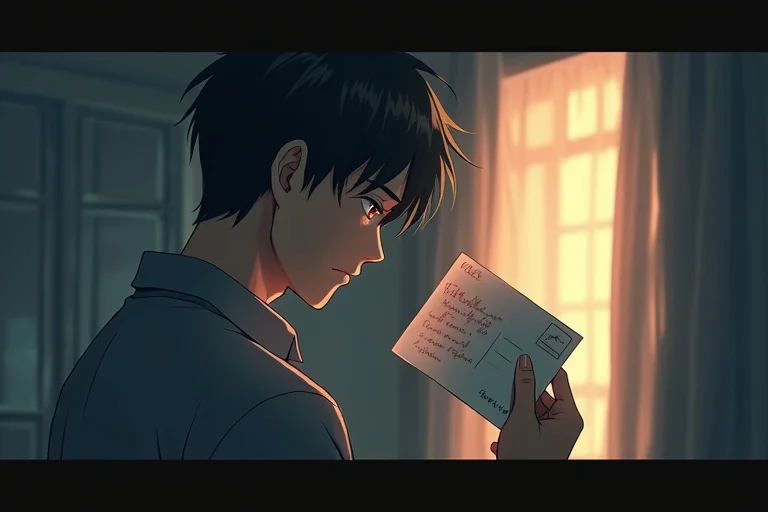第一章 結晶の指先
僕、アキトの指先は、かつて人々の心を映す鏡だった。他人の肌にそっと触れるだけで、その魂が抱える最も深い後悔、すなわち『未練』が、僕の指先に小さな結晶となって析出する。海の青さを湛えた八面体は叶わぬ恋の痛み。煤けた黒曜石の鋭い欠片は、拭えぬ裏切りへの怒り。僕はそれを集め、持ち主の物語を聞き、慰めることで生計を立てていた。それは、他人の心の澱に触れる、静かで孤独な仕事だった。
だが、今ではその指が何かを結晶にすることは二度とない。
世界から『未練』が消え失せて、もう一年になる。人々は過去を悔いなくなった。その代わり、誰もが顔のどこかに、美しい花を咲かせている。頬に咲くのは可憐な勿忘草、眉間に寄り添うのは気高い薔薇。嘘をつくたびに体に花が咲く、というこの世界の法則は昔からあったが、これほどまでに誰もが、顔という隠しようのない場所に、大輪の花を誇らしげに咲かせる時代はなかった。
街は静かだ。色とりどりの花々が風に揺れる光景は、一見すると楽園のように美しい。しかし、その花の下にある人々の瞳からは、感情の光が失われていた。誰も泣かず、誰も怒らず、そして誰も、心から笑うことがなかった。まるで精巧に作られた人形たちのパレードを見ているようで、僕はその不気味なほどの静寂に、いつも息を詰まらせていた。
第二章 夜明けの鳥は嘘を啼く
異変は、ある朝、唐突に訪れた。
いつものように老婆の皺だらけの手に触れた瞬間、僕は気づいた。何も感じない。いつもなら伝わってくるはずの、亡き夫への尽きせぬ想いの温もりが、指先を素通りしていく。何度試しても、僕の指はただ空を切るだけだった。その日を境に、世界から未練という概念そのものが蒸発した。
時を同じくして、街の中央広場に、それが出現した。天を突くほど巨大な、一輪の花。オパールのように虹色に輝く花弁を持ち、夜明けと共に、鳥のさえずりを模した清らかな音色を奏で始める。人々はそれを『夜明けの花』と名付け、神聖な奇跡だと崇めた。
だが、僕は知っていた。あの鳥の鳴き声は、本物ではない。本物の鳥たちは、あの花が現れてから、ぴたりと鳴くのをやめてしまったのだ。偽りのさえずりが街を支配し、人々はそれに安堵し、過去を振り返ることをやめた。後悔しないことは、確かに楽だろう。だが、それは本当に「救い」なのだろうか。僕の指先には、異変が起きる直前に触れた、最後の結晶が一つだけ残されている。それは、亡き妹の手から生まれた、小さな涙滴型の水晶。その冷たい感触だけが、失われた感情の在り処を僕に教えていた。
第三章 匂いのない街
僕は街外れの古い温室に住む、盲目の老婆リリアを訪ねた。彼女の顔には、嘘の花が一つも咲いていない。目が見えない彼女にとって、世界は匂いと音、そして肌で感じるもので構成されており、そこに偽りを挟む余地がなかったからだ。
「アキトかい。お前の足音は、いつも少しだけ迷っているね」
リリアは土をいじる手を止めずに言った。彼女の温室だけが、昔と変わらない植物の匂いに満ちていた。
「リリアさん。街の様子をどう感じますか?」
「匂いがしないのさ」彼女はきっぱりと言った。「以前は、街を歩けば色々な匂いがしたもんだった。喜びの甘い香り、悲しみの湿った匂い、そして後悔の、あの少し錆びついた鉄のような匂い。それが混じり合って、人の営みの匂いになっていた。でも今は、あの大きな花の、甘ったるい匂いだけさ。みんな、心の匂いを失くしちまったんだよ」
心の匂い。その言葉が、僕の胸に突き刺さった。僕はポケットから、妹の未練の結晶を取り出した。ひんやりとした感触が指に伝わる。「ごめんね」と、消え入りそうな声で僕に託された、最後の言葉の結晶。守れなかった後悔が、そこには詰まっていた。この痛みが、このどうしようもない後悔こそが、僕が妹を愛していた証なのだ。人々は、痛みと共に、愛した記憶の証拠さえも手放してしまったのだろうか。
第四章 甘美なる毒の麓
僕は決意を固め、『夜明けの花』へと向かった。近づくにつれて、偽りの鳥のさえずりは脳に直接響くような圧力を伴い、花の放つ甘い香りが思考を鈍らせる。まるで、抵抗する意志そのものを奪う毒のようだ。
花の麓には、多くの人々が祈るように集っていた。彼らの顔の花は、これまで見たこともないほどに色鮮やかに咲き誇り、その表情は恍惚としている。誰もが「これでいいのだ」「私たちは満たされている」という、静かな狂気に満ちていた。
僕は巨大な花の茎に、そっと手を伸ばした。
触れる直前、見えない壁に弾かれるような衝撃が走る。同時に、僕の心の中に押し殺していた小さな嘘が、鋭く疼いた。「妹の死は、もう乗り越えた」。そう自分に言い聞かせていた偽りが、花の力によって暴かれ、僕の頬に小さな菫の蕾を咲かせようとする。
「…っ!」
僕は慌てて手を引いた。やはりだ。この花は、嘘を糧にしている。そして、人々の心から未練を奪い、それを「過去は変えられないのだから後悔しても無駄だ」という、世界で最も巨大で、最も心地よい『嘘』に変換しているのだ。未練とは、過去を変えたいと願う心。その願いそのものを否定することが、この花の正体だった。
第五章 結晶が暴いた真実
もう一度、僕は花に向き直る。今度は、ポケットの中で妹の結晶を固く、固く握りしめて。あの冷たい痛みだけが、甘い毒の中で僕を正気に保ってくれる。
震える指で、結晶の先端を花の茎に押し当てた。
瞬間、世界が砕け散るような衝撃。結晶と花が激しく共鳴し、僕の脳裏に、おぞましい真実の光景が流れ込んできた。それは、声の洪水だった。世界中の人々の、無数の後悔の声。「愛していると伝えればよかった」「あの時、謝っていれば」「なぜ、助けられなかったのか」。その悲痛な叫びが、やがて『夜明けの花』から響く鳥のさえずりにかき消されていく。声は、「後悔など無意味だ」という一つの巨大な肯定の音に飲み込まれ、人々は安堵し、魂を明け渡していく。
花は、人々の未練を『嘘』として喰らう寄生生物だったのだ。後悔から解放された人々は、その代償として感情の機微を失い、笑顔を忘れた。顔の花は、巨大な嘘のシステムに繋がれた、美しき隷属の証。
絶望的な光景の中で、僕はたった一つの可能性を見た。この花の動力源が人々の嘘と未練なら、それを上回るほどの『真実』をぶつければ、このシステムを破壊できるかもしれない。だが、それは人々に、忘れていたすべての後悔と痛みを、一度に叩き返すことを意味する。偽りの楽園を壊し、地獄のような真実を突きつける権利が、僕にあるのだろうか。
第六章 ただ一つの真実
世界か、笑顔か。
僕は街を見下ろした。花を咲かせた無表情な人々が、静かに行き交っている。彼らは苦しみから解放された。僕がやろうとしていることは、彼らの平穏を乱す、ただのエゴイズムではないのか。
迷う僕の指先で、妹の結晶が、まるで心臓のように微かに脈打った気がした。
そうだ。僕はずっと、この結晶を手放せずにいた。この痛みこそが、僕が僕であるための最後の砦だったからだ。妹への愛を、後悔という形で抱きしめ続けてきたのだ。
笑顔とは、きっと悲しみを知っているからこそ、美しく咲く花なのだ。後悔を知っているからこそ、人は優しくなれるのだ。
僕は踵を返し、再び花の麓に戻った。今度はもう、迷いはなかった。僕は妹の結晶を、自らの胸、心臓の真上に強く押し当てた。
「ごめん、守れなかった。でも、お前を愛していたこの気持ちだけは、絶対に嘘にしない」
それが、僕の、僕だけの『真実』だった。
第七章 真実の白い花
結晶が、ガラスが砕けるような音を立てて僕の体に吸い込まれていく。直後、凄まじい奔流が僕の全身を貫いた。『夜明けの花』に囚われていた世界中の嘘と未練が、僕という一点を目指して殺到してきたのだ。
「ぐ…あああああっ!」
僕の体は内側から発光し、ガラス細工のように透き通り始める。人々の顔の花が急速に色を失い、枯れていくのが見えた。同時に、天を突いていた巨大な『夜明けの花』も、虹色の輝きを失い、砂のように崩れ落ちていく。偽りの鳥のさえずりが、止んだ。
世界に、本当の静寂が戻る。
人々が、呆然と空を見上げていた。彼らの瞳に、ゆっくりと感情の光が戻りつつあった。忘れていた後悔が、痛みと共に蘇り、誰かが静かに涙を流し始めた。それは、やがて嗚咽となり、伝染していく。
僕の体はもう、人の形を保ってはいなかった。僕が立っていた場所には、世界で初めて咲いた、巨大な一輪の『真実の白い花』が、月光を浴びて静かに佇んでいた。
その花から、ふわりと優しい香りが放たれる。それは雨上がりの土の匂いと、どこか懐かしい焼きたてのパンのような、温かい記憶の香りだった。香りが街に満ちていく。涙に濡れた人々が、顔を上げた。そして、一人の少女が、母親の顔を見上げて、くしゃりと顔を歪ませた。それは、泣き顔のようで、それでいて、誰もが忘れかけていた、紛れもない『笑顔』だった。
後悔を知り、痛みを知り、それでも人はまた笑う。僕は白い花となり、その愛おしい世界を、永遠に見守り続ける。