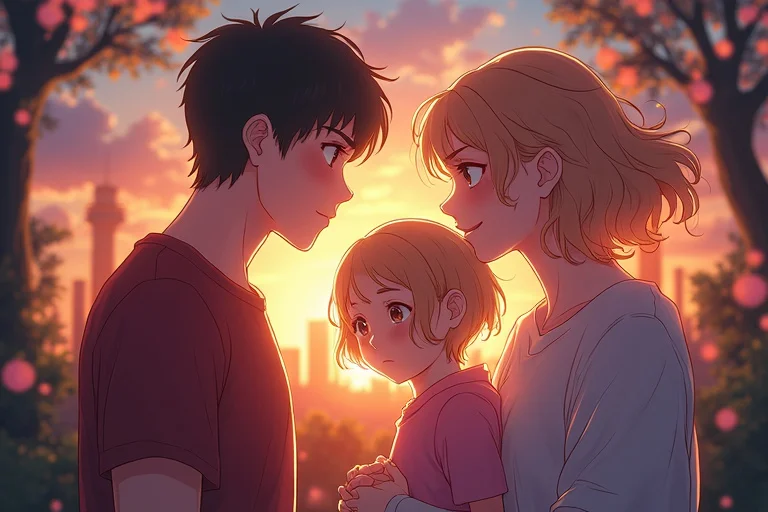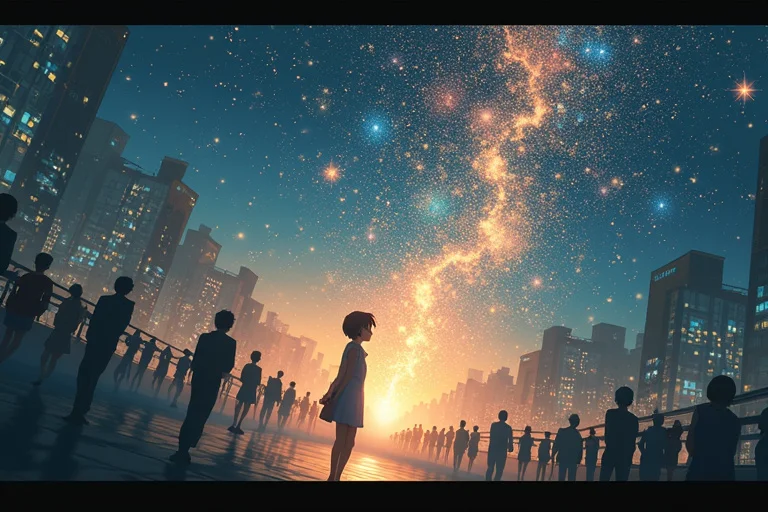第一章 鼻栓と図書館の不協和音
灰谷奏(はいたに かなで)にとって、世界は耐え難いほど香ばしい場所だった。それは比喩ではない。文字通り、物理的に、彼は他人の「本音」を、その人物が最も愛する食べ物の匂いとして嗅ぎ取ってしまうのだ。この奇妙で迷惑千万な体質、彼が内心で『共嗅覚(きょうきゅうかく)』と名付けた呪いは、静寂を愛する図書館司書の彼にとって、地獄のフルコースに他ならなかった。
奏が勤める市立図書館は、表向きは静謐な知識の聖域だ。しかし彼の鼻腔にとっては、欲望と本音が渦巻く巨大なフードコートだった。カウンターの向かいに座る同僚の田中さんは、にこやかな笑顔の裏で、常に「焼き立てのクロワッサン」の匂いをさせている。そのバターリッチで香ばしいアロマが意味するのは『ああ、もう帰りたい。カフェでサボりたい』という強烈な現実逃避願望だ。児童書コーナーで絵本を読む親子連れからは、子供の純粋なワクワク感が「綿あめ」の甘い匂いとして、母親の『今夜の献立どうしよう』という悩みが「生姜焼き」の醤油が焦げる匂いとして、混じり合って漂ってくる。
「灰谷さん、これの在庫、調べてもらえる?」
新人のアルバイトが、分厚い専門書を抱えてやってきた。彼女から漂うのは、ピリッとスパイシーな「グリーンカレー」の香り。『この先輩、いつも気だるげで話しかけづらいんだよな…』という本音が、ココナッツミルクのまろやかさの奥で舌を刺す。奏は無言で頷くと、キーボードを叩いた。口を開けば、余計な匂いを吸い込んで吐きそうになるからだ。
だから奏の日常に、医療用の高性能な鼻栓は欠かせない。同僚たちからは「重度の花粉症」だと思われているが、それでいい。人々の本音という名の暴力的な匂いの洪水から身を守るには、物理的に鼻腔を塞ぐしかなかった。ネガティブな感情は、さらにタチが悪い。嫉妬は腐った魚、退屈は湿気た段ボール、怒りは焦げ付いた鍋の匂いとなって、彼の嗅覚神経を直接殴りつけてくるのだ。
そんな奏にとって、唯一の安息は、図書館の片隅に現れる一人の老人だった。古賀と名乗るその老人は、毎日午後二時きっかりにやってきては、西日の差す窓際の席で静かに哲学書を広げる。彼が奏にとって特別なのは、その存在から一切の「匂い」がしないからだ。まるで無味無臭の蒸留水。感情の起伏がないのか、それとも、この鼻がとうとうイカれてしまったのか。奏は、鼻栓の奥で息を殺しながら、謎めいたその老人の、静かな背中を眺めるのが日課になっていた。その静寂は、騒々しい匂いの世界に生きる彼にとって、唯一の救いのように感じられた。
第二章 無臭の哲学者と混線するアロマ
匂いのしない男、古賀さんへの興味は、日増しに奏の中で膨らんでいった。彼は本当に無感情なのだろうか。それとも、彼もまた奏と同じような特殊能力者で、匂いを完全に遮断する術を心得ているのだろうか。後者である可能性を考えると、胸が少しざわついた。この呪いを共有する人間が、他にいるのかもしれない。
ある日の午後、奏は意を決して古賀さんの席へ向かった。手に持ったのは、彼が読んでいたニーチェの関連書籍だ。
「お客様、もしよろしければ、こちらの本もご興味があるかと」
古賀さんはゆっくりと顔を上げた。深く刻まれた皺が、穏やかな表情の中で揺れる。
「おや、これはご親切に。ありがとう」
古賀さんの声は、乾いた落ち葉を踏むような、心地よい音がした。しかし、やはり匂いはない。感謝も、驚きも、何の感情のフレーバーも感じ取れない。奏は内心の落胆を隠し、作り笑いを浮かべてカウンターに戻った。まるで厚いガラス壁の向こう側にいる人と話しているような、奇妙な隔絶感だけが残った。
その日の図書館は、いつにも増して騒がしかった。恋愛相談に訪れた女子高生二人組が、ヒソヒソ声で話し込んでいる。片方からは『彼って最高!』という熱烈な想いが「とろけるフォンダンショコラ」の甘美な香りを放ち、もう片方からは『いや、絶対そいつ浮気してるって…』という辛辣な本音が「激辛麻婆豆腐」の痺れるような匂いとなって、奏の鼻を襲った。甘さと辛さが無遠慮に混ざり合い、脳がバグを起こしそうだ。奏は鼻栓をぐっと押し込み、めまいをこらえた。
つくづく嫌になる。人の言葉は嘘で塗り固められていても、本音の匂いは隠せない。この能力は、世界の欺瞞を暴き立てる。だが、真実を知ったところで何になるというのか。他人の心の中を土足で歩き回るような不快感と、どうしようもない孤独感が募るだけだ。田中さんのクロワッサンも、女子高生のフォンダンショコラも、奏にとっては食欲をそそるご馳走ではなく、ただただ処理すべき情報量の多いデータに過ぎない。
だからこそ、古賀さんの「無臭」は際立っていた。それは、この匂いに満ちた世界で唯一、奏が安心して呼吸できる場所だった。奏は、彼が読み終えて棚に戻した哲学書を、そっと手に取った。そこには、何の匂いも残っていなかった。まるで、最初から誰も触れていなかったかのように。その完璧な無は、奏にとって、次第に恐怖にも似た感情を抱かせるようになっていた。
第三章 嵐の夜と卵焼きの香り
その日は、空が不機嫌に唸りを上げる、荒れた天気の日だった。夕方になると雨は豪雨へと変わり、雷鳴が図書館のガラス窓を震わせた。閉館時間を知らせるチャイムが鳴り響く頃には、館内に残っているのは奏と、窓際で本を読んでいた古賀さんだけになっていた。
「お客様、閉館の時間です。お足元、お気をつけて」
奏が声をかけると、古賀さんは静かに本を閉じ、立ち上がった。その瞬間だった。世界が、音もなく暗転した。ゴォッという風の音と、窓を叩く雨音だけが、絶対的な暗闇の中で存在を主張している。落雷による停電だった。
「うわっ!」
突然の闇に、奏は思わず声を上げた。心臓が嫌な音を立てて跳ねる。パニックになりかけた奏の鼻腔に、信じられない匂いが、ふわりと流れ込んできた。
甘くて、香ばしくて、どこか懐かしい。醤油が少し焦げた、あの匂い。
それは、奏が幼い頃に亡くなった母が、毎朝お弁当に入れてくれた、少し甘めの「卵焼き」の香りだった。
なぜ? どうして今、この匂いが?
混乱する奏のすぐ側で、暗闇に慣れた古賀さんの静かな声がした。
「奏くん、落ち着きなさい」
その声と共に、卵焼きの香りは一層濃くなった。それは、恐怖に震える奏の心を、温かい手で包み込むような、優しさに満ちた匂いだった。古賀さんからだ。この匂いは、間違いなく古賀さんから発せられている。
「どうして…その匂いを…あなたは…」
「驚かせてすまない。君を刺激しないよう、ずっと私の『匂い』を閉ざしていたんだよ」
古賀さんは、暗闇の中でゆっくりと語り始めた。彼の正体は、奏の母親、灰谷美咲の古い友人だった。そして、奏の母親もまた、同じ『共嗅覚』の能力者だったというのだ。
「美咲くんはね、君と同じように、この力にずっと苦しんでいた。人の感情が、あまりにも無防備に流れ込んでくるからと。彼女は亡くなる前に、私に頼んだんだ。『もし、あの子が私と同じ力に目覚めたら、どうかそばにいて、その力の使い方を教えてあげてほしい』と」
古賀さんもまた、特殊な能力者だった。ただし彼の能力は、奏とは逆の「匂いを遮断し、コントロールする力」。だから奏の前では、自身の感情の匂いを完全に消し去ることができたのだ。彼が奏に抱いていた感情、それは心配と、親愛と、そして亡き友人への約束を果たすという静かな決意。その温かい想いが、彼の好きな食べ物である「卵焼き」の香りとなって、今、奏の心を優しく満たしていた。
「君のお母さんが作る卵焼きは、絶品だった。私も大好きでね。だからかな、私の一番好きな食べ物も、これなんだ」
暗闇の中、奏の頬を、熱い雫が伝っていった。それは、呪いだと思っていたものが、母との繋がりを示す唯一の絆だったと知った、安堵の涙だった。
第四章 香り立つ世界の優しい処方箋
非常電源が作動し、薄暗いオレンジ色の光が図書館を照らし出した時、奏は自分が泣いていることに改めて気づいた。古賀さんは、何も言わずにハンカチを差し出してくれた。そのハンカチからは、何の匂いもしなかった。彼が、奏のために再び匂いを閉ざしてくれたのだとわかった。
その日を境に、奏の世界は少しずつ変わり始めた。古賀さんは、閉館後の図書館で、奏に能力のコントロール方法を教え始めた。
「いいかい、奏くん。この力は、一方的に受信するだけのラジオじゃない。君自身がチューナーなんだ。チャンネルを合わせ、ボリュームを調整することができる」
古賀さんの指導は、具体的かつ的確だった。まずは、自分の周りに薄い膜があることをイメージし、入ってくる匂いの量を制限する訓練。次に、特定の人物の匂いだけに意識を集中させる訓練。それはまるで、長年垂れ流しだった蛇口に、初めて栓を取り付ける作業のようだった。
数週間が経った。奏はまだ完璧ではないものの、日常のほとんどの場面で、不快な匂いの洪水をシャットアウトできるようになった。鼻栓を外して街を歩ける日が来るなんて、夢にも思わなかった。世界は、奏が思っていたよりもずっと静かで、穏やかだった。
ある日の午後、同僚の田中さんが、疲れきった顔でカウンターに寄りかかった。彼女からは、いつもの「焼き立てクロワッサン(早く帰りたい)」の匂いが、微かに漂ってくる。以前の奏なら、『またか』と心の中で毒づいて終わりだっただろう。しかし、今の彼は違った。奏は、意識して匂いのボリュームを少しだけ上げた。すると、クロワッサンの香りの奥に、微かな「ミルク粥」の優しい匂いが隠れていることに気づいた。それはおそらく、彼女の幼い息子への愛情の香りだ。仕事で疲れていても、息子のために早く帰って温かいものを作ってあげたい。その想いが、ミルク粥の匂いとなっているのだ。
奏は静かに立ち上がると、自動販売機で温かい缶コーヒーを買い、田中さんのデスクにそっと置いた。
「お疲れ様です。これでも飲んで、一息ついてください」
「え…灰谷さん? あ、ありがとうございます…!」
驚きと感謝の入り混じった表情を浮かべる田中さん。その瞬間、彼女から漂うクロワッサンとミルク粥の香りに、ふわりと「溶けたバター」の温かい香りが加わったのを、奏は確かに感じ取った。
呪いだと思っていた力は、呪いではなかったのかもしれない。人の本音を覗き見るための能力ではなく、その裏側にある、言葉にならない想いをそっと掬い上げるための、小さなきっかけ。世界は相変わらず、様々な感情の匂いで満ちている。でもそれはもう、奏にとって不快な不協和音ではなかった。むしろ、それぞれが懸命に生きる人々が奏でる、少し滑稽で、不器用で、だけれど愛おしいシンフォニーのように聞こえた。
奏は図書館の窓から、夕日に染まる街を眺めた。家路につく人々から、カレーや、味噌汁や、オムライスといった、無数の温かい生活の匂いが立ち上っている。彼はもう一度、鼻栓のない世界で、深く息を吸い込んだ。香ばしくて、騒がしくて、どうしようもなく人間臭いこの世界を、ほんの少しだけ、好きになれそうな気がした。