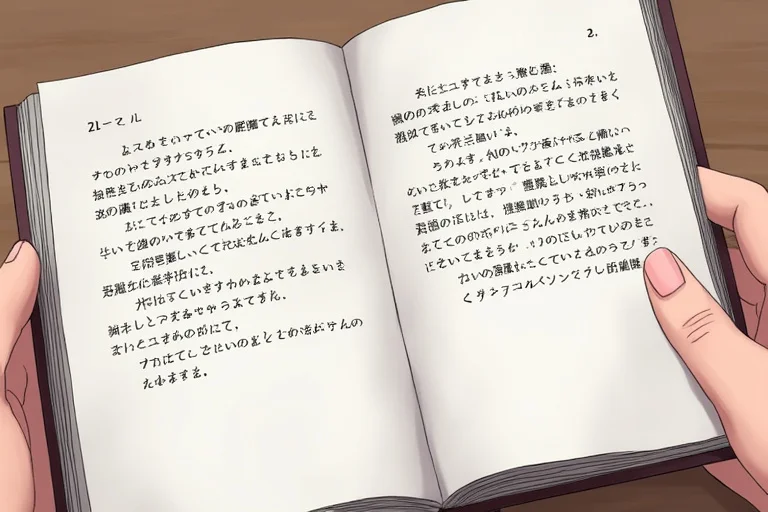第一章 忘れられた木箱
父が死んで、家から音が消えた。いや、正確には、音の種類が変わったのだ。父の立てる、規則正しい生活音――朝のコーヒーミルを回す音、書斎で万年筆が紙を擦る音、夜にクラシック音楽を低く流す音――が消え、代わりに母の忍び泣きと、姉と僕のぎこちない会話だけが、埃の積もった静寂をかき混ぜるようになった。
僕の一族には、奇妙な風習がある。「記憶の彫刻」と呼ばれるものだ。強い想いを込めた記憶は、特殊な木箱に封じ込め、物理的なオブジェクトとして保存することができる。箱にそっと手を触れると、まるで夢を見るように、その記憶を追体験できるのだ。父は、一族の中でも特に優れた「記憶彫刻師」だった。彼の書斎の棚には、家族の歴史が年代順に整然と並べられていた。僕の七五三、姉の卒業式、家族で行った海の風景。それらはすべて、父の手によって美しい木彫りの箱に収められ、永遠の輝きを放っていた。
僕は、その風習が少し息苦しかった。過去は過去として、流れていくべきではないのか。箱に閉じ込めた記憶は、美しい剥製のように、命の躍動を失っている気がした。だから、大学進学を機に家を出てからは、実家に寄り付かなくなり、父が彫る新しい記憶に参加することもなかった。
父の死から一週間が経った、湿度の高い午後。僕たちは書斎の遺品整理をしていた。埃っぽい空気の中、姉が本棚の裏に隠された小さな空間を見つけた。そこには、他のどの記憶箱とも違う、見慣れない木箱が一つ、静かに置かれていた。
それは黒檀のように艶やかで、表面には月と星を組み合わせたような、誰も見たことのない紋様が彫り抜かれていた。僕たちが知っている父の記憶箱は、すべて温かみのある桜の木で作られていたはずだ。箱の蓋には、父の震えるような筆跡で、たった一言、『未見の空へ』と記されていた。
「これ……お父さんの? 見たことないわ」姉が訝しげに呟く。
母は、その箱を一目見るなり、さっと顔を青ざめさせた。「それに触れてはいけません」
母の声は、拒絶と、そしてどこか恐怖の色を帯びていた。なぜ、母はこの箱を恐れるのか。父は僕たちに何を隠していたのか。その黒い木箱は、僕たちが知る「家族」という物語に、ぽっかりと空いた謎の穴のように、不気味な存在感を放っていた。
第二章 硝子の中の思い出
母は頑なだった。「お父さんのプライベートなものです。そっとしておいてあげましょう」そう言って、黒い木箱を自分の部屋の箪笥の奥深くへと仕舞い込んでしまった。僕と姉は顔を見合わせるしかなかった。父に、僕たちの知らない秘密があったという事実が、重たい靄のように家の中に立ち込める。
その日から、僕はまるで何かに取り憑かれたように、父が遺した記憶箱を片っ端から開けていった。父の記憶を辿れば、あの箱の謎が解けるかもしれないと思ったのだ。
書斎の棚に並ぶ桜の木の箱は、どれも温かかった。箱に手を置くと、瞼の裏に鮮やかな光景が広がる。幼い僕が初めて自転車に乗れた日。父の大きな手が背中を支えてくれていた感触。誇らしげに笑う声。姉のピアノの発表会。客席の隅で、誰よりも熱心に拍手を送る父の姿。食卓を囲む何気ない日常の風景。湯気の向こうで目を細める母の笑顔。
それらは紛れもなく、僕たちの幸福な家族の記録だった。硝子ケースに収められた美しい蝶のように、完璧で、色褪せることがない。だが、記憶を追体験すればするほど、僕の胸には奇妙な空虚感が広がっていった。どの記憶の中の父も、完璧すぎるのだ。穏やかで、優しく、決して怒ったり、悩んだりしない。まるで理想の父親像を演じているかのようだ。
僕が知っている父は、もっと人間臭い人だったはずだ。仕事で悩み、時には僕を厳しく叱り、そして不器用な愛情を示す人だった。この記憶箱たちは、父という人間の、美しく磨き上げられた表面だけを切り取ったものに過ぎないのではないか。
「お父さん、本当は何を考えていたんだろうな」
ある夜、僕はベランダでタバコを燻らせながら、隣に立つ姉にぽつりと漏らした。
「さあ……。でも、私たちを深く愛してくれていたことだけは確かよ」
姉の言葉は正しかった。どの記憶からも、父の深い愛情は痛いほど伝わってくる。だが、それだけではなかったはずだ。父の心の奥底には、僕たちが決して立ち入れない領域があった。あの黒い木箱は、その領域への唯一の扉のように思えた。
僕は、父との間にずっと感じていた、見えない壁の正体を知りたかった。なぜ、僕は父に心から甘えられなかったのか。なぜ、父の笑顔は時折、ひどく寂しそうに見えたのか。その答えが、あの箱の中にある。確信にも似た予感が、僕の心を強く揺さぶっていた。
第三章 未見の空
衝動は、真夜中にやってきた。家中の誰もが寝静まった頃、僕は忍び足で母の部屋に侵入した。月明かりが差し込む中、箪笥の引き出しをそっと開ける。冷たく滑らかな黒檀の箱が、指先に触れた。罪悪感と、それを上回る渇望が背中を押す。僕はその箱を抱え、自分の部屋へと戻った。
心臓が早鐘を打っていた。机の上に置かれた箱は、暗闇の中で静かに呼吸しているかのようだ。蓋に刻まれた『未見の空へ』という文字が、僕を誘っている。僕は深呼吸を一つして、震える手で蓋に触れた。
瞬間、僕の意識は眩い光に包まれ、次の瞬間には、見知らぬ場所に立っていた。
そこは、僕が子供の頃に住んでいた家の庭だった。夏の強い日差しが肌を焼き、蝉の声が耳を聾するほどに鳴り響いている。だが、何かが違う。僕の隣には、僕とそっくりな顔をした、少し年下の少年が立って、屈託なく笑っていた。
「ケン兄ちゃん、早く!」
少年が僕の手を引く。その小さな手の温もりが、あまりにリアルで、僕は息を呑んだ。
これは、誰の記憶だ?
光景は次々と移り変わる。少年と二人でキャッチボールをする夕暮れの公園。ボールを投げるのは、若き日の父だ。その顔には、僕の記憶にあるどの笑顔よりも深く、満ち足りた喜びが浮かんでいる。小学校の入学式、僕と少年の手を両脇に繋ぎ、誇らしげに歩く父と母。弟ができた、と友達に自慢する僕。喧嘩をして、泣いて、それでもすぐに仲直りして、秘密基地で未来を語り合う僕たち兄弟。
これは、父の記憶ではない。こんな事実は存在しない。僕に弟はいない。
混乱する僕の脳裏に、一つの可能性が雷のように突き刺さった。これは、父が「創造」した記憶なのだ。
最後の光景が現れる。病室のベッドに横たわる、小さな赤ん坊。ガラスの向こうで、母が泣き崩れている。父はただ、静かにその小さな体を、目に焼き付けるように見つめていた。その表情は、悲しみとも絶望とも違う、何か途方もない感情に満ちていた。そして、父の心の中から、声が聞こえた。
『大丈夫だ、蒼太(そうた)。お前が生きていくはずだった世界は、父さんが創ってやる。お前が見るはずだった空を、兄さんと一緒に見せてやるからな』
蒼太。それが、生まれてくるはずだった僕の弟の名前だった。流産で、僕たちが会うことのなかった、家族。父は、その子の死を誰にも言えず、たった一人で受け止め、そして、その子が生きるはずだった架空の人生を、何十年もの間、この記憶箱の中に「彫刻」し続けていたのだ。
僕が感じていた父との距離。父の笑顔の裏にあった寂しさ。そのすべてが、この「存在しない息子」に向けられた愛情の、僕たちの世界への漏出だったのだ。父は僕を愛していなかったわけじゃない。ただ、その愛情の半分は、いつも僕の隣にいるはずだった、見えない弟に注がれていた。
光景が途切れ、僕は自分の部屋の暗闇に引き戻された。頬を、熱い涙が止めどなく伝っていた。それは、裏切られたという感情ではなかった。父が一人で抱え込んできた、あまりにも深く、あまりにも切ない愛情の形に、ただ胸が張り裂けそうだった。
第四章 新しい箱の作り方
翌朝、僕は腫れた目のまま、あの黒い木箱をリビングのテーブルに置いた。そして、まだパジャマ姿の母と姉に、すべてを話した。僕が見た、蒼太という弟の、架空の一生を。
母は、僕の話を聞きながら、静かに泣いていた。それはもう、忍び泣きではなかった。堰を切ったように、声を上げて泣いた。姉も、肩を震わせていた。母が語ってくれた。僕が生まれる前、確かに、蒼太という子がいたこと。その死の悲しみを乗り越えるため、二人はその存在を胸の奥にしまい込み、決して口に出さないと決めたこと。だが、父は忘れることなどできなかったのだ。
「あんなに苦しんでいたなんて……。気づいてあげられなかった」
母の嗚咽が、家の静寂を震わせた。
その日、僕たちは三人で、もう一度あの箱に触れた。今度は、逃げずに、父が創り上げた世界を、家族として受け止めるために。夏の庭で笑う二人の息子と、それを見守る父。そこには、父が本当に望んでいた家族の姿があった。僕たちは、泣きながら、そして時々笑いながら、会うことのなかった家族の一員、蒼太の人生を、共に追体験した。
すべてを見終えた時、家の中を覆っていた重たい靄は、すっかり晴れていた。悲しみは消えない。だが、それはもう、僕たちを隔てる壁ではなかった。それは、僕たち家族が共有する、新しい絆の一部になっていた。
一週間後、僕は父の書斎に籠もり、慣れない手つきで木材を削り始めた。新しい記憶箱を作るためだ。それは、父が使っていた桜の木でも、黒檀でもない、名もなき白木の箱。不格好で、傷だらけの箱。
完成した箱に、僕はそっと手を触れ、一つの記憶を込めた。
リビングのテーブルを囲み、父の思い出と、そして蒼太の思い出を語り合いながら、三人で泣き、笑った、あの朝の記憶を。
それは、完璧ではない、ありのままの僕たちの記憶。父が遺した美しい記憶たちとは違う、少しだけ歪で、けれど温かい、僕たち自身の記憶だ。
父はもういない。記憶彫刻師のいなくなったこの家で、僕たちは、これから自分たちの手で、新しい家族の物語を彫っていくのだろう。不器用でも、傷だらけでもいい。失われた者への想いを胸に、僕たちは、まだ見ぬ未来の空へ向かって、ゆっくりと歩き出すのだ。