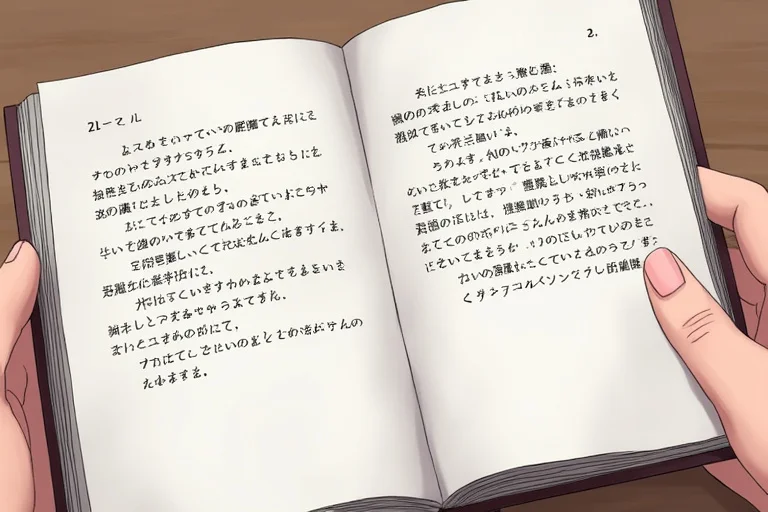第一章 浮遊する身体と褪せる記憶
僕の身体は、秋の枯葉のように軽かった。少し強い風が窓の隙間から吹き込むだけで、踵がふわりと床を離れる。その度に、僕は必死で家具の縁に指をかけ、この世界に繋ぎ止められようと足掻いた。父さん、母さん、リナ。心の中で家族の名を呼ぶ。その重みが、僕を辛うじて地面に引き留める最後の錨だった。
かつて、僕たち一家は「彩の守り人」と呼ばれていた。父の深紅、母の瑠璃、妹リナの向日葵色。それぞれの存在が放つ鮮やかな色は、互いの絆を映し出す鏡であり、僕の世界そのものだった。強い絆は僕の身体に心地よい重みを与え、地に足を着けているという確かな実感をもたらしてくれた。だが、それも今は遠い記憶の欠片だ。
書斎の机に置かれた「彩の砂時計」が、静かに時の終わりを告げていた。くびれたガラスの中を、色褪せた砂がサラサラと絶え間なく流れ落ちていく。かつては家族それぞれの色が混じり合い、虹のようにきらめいていたはずの砂は、今や灰色に近い濁った色をしていた。その流れは異常に速く、まるで家族の記憶が、存在が、この世界から急速に洗い流されていくようだった。
家の中は、色が失われ、輪郭がぼやけている。壁に飾られた家族写真も、今では誰が写っているのか判別できないほどに淡い。父の笑い声も、母の優しい歌声も、リナの駆け回る足音も、もう聞こえない。このままでは、僕も、僕たち家族も、誰にも認識されない"透明"な存在になってしまう。
僕は砂時計をそっと手に取った。ひやりとしたガラスの感触だけが、今の僕がここにいる唯一の証だった。この砂がすべて落ちきる前に、見つけなければならない。僕たちの色を奪った原因と、それを取り戻す方法を。僕がまだ完全に透明にならず、この世界に留まれている理由を。軽すぎる身体を引きずるように、僕は色を失った扉を開けた。
第二章 灰色の街と忘れられた人々
一歩外に出ると、世界は音のないモノクロ映画のようだった。人々は俯き、互いに視線を合わせることなく、影のように街路を彷徨っている。彼らの纏う色もまた、僕の家族と同じように極限まで薄まっていた。すれ違う男は、隣を歩く妻の存在に気づいていない。公園のベンチに座る老婆は、膝の上で眠る猫の温もりを忘れてしまったかのように、虚空を見つめていた。
「ねえ、あなた、誰だったかしら」
「さあ……覚えていないんだ」
すぐ側で交わされる会話は、霧のように実体がない。家族の絆が薄れ、存在の色を失った人々は、互いを認識できなくなっていた。愛する人の顔を忘れ、交わした言葉を忘れ、共に過ごした温かな時間さえも忘れていく。世界は、静かな孤独という病に侵されていた。
風が吹く。僕は咄嗟に街灯の柱にしがみついた。身体が風船のように持ち上がり、危うく空へと攫われそうになる。この軽さは、僕と家族を繋ぐ糸が、もう切れかかっている証拠だ。街行く人々は、宙に浮きかけた僕の姿を見ても、何も反応しない。彼らの瞳には、もう僕の姿は映っていないのかもしれない。
焦りが胸を焼く。僕は、かつて父が話してくれた「始まりの聖域」を目指すことにした。そこには、世界の色の理を記した古文書が眠っているという。僕は風に抗い、一歩一歩、地面を踏みしめるように進んだ。足の裏に伝わる硬いアスファルトの感触だけが、僕をこの灰色の現実世界に繋ぎ止めていた。
第三章 彩の守り人の伝説
「始まりの聖域」は、時の流れから取り残されたかのように静かな場所に佇んでいた。巨大な石造りの図書館は埃の匂いが立ち込め、差し込む光が空気中の塵をきらきらと照らし出している。僕は震える手で古文書のページをめくった。そこには、「彩の守り人」に関する断片的な記述が残されていた。
『彩の守り人は、世界の色彩を司る。その絆は大地を重くし、その色は世界を鮮やかに灯す。絆が尽きる時、世界は色を失い、静寂に包まれるだろう』
書かれているのは、僕が知っていることばかりだった。なぜ僕たちの色が薄れ始めたのか、どうすればそれを取り戻せるのか。答えは見つからない。諦めかけたその時、古文書の隅に描かれた小さな挿絵に目が留まった。それは、僕が持つものとよく似た「彩の砂時計」の絵だった。そして、その下にはこう記されていた。
『砂が終わりを告げる時、守り人は「世界の心臓」へ還るべし。そこは終焉の地にして、新たな始まりの揺りかごなり』
世界の心臓。聞いたことのない場所だ。しかし、その文字を見つめた瞬間、僕が懐に忍ばせていた砂時計が、微かに、温かい光を放った。ガラスの中の濁った砂が、一瞬だけ、淡い虹色に輝いたのだ。そして、その光は、図書館のさらに奥深く、地下へと続く螺旋階段を指し示していた。まるで、砂時計自身が道を知っているかのように。僕は光に導かれるまま、冷たい石の階段を一歩ずつ下りていった。
第四章 世界の心臓
螺旋階段の先には、巨大な地下洞窟が広がっていた。壁一面に自発光する苔が群生し、幻想的な青白い光で空間を照らしている。洞窟の中心には、静かな地底湖があり、その湖畔には、数え切れないほどの「彩の砂時計」が安置されていた。どれも砂は落ちきり、ガラスは静かに冷え切っている。ここは、かつて存在した無数の家族たちの、記憶の墓標だった。
「ようこそ、最後の守り人」
声がした。振り返ると、そこにいたのは、完全に色が抜け落ち、輪郭さえもぼやけた老人の姿だった。透明なはずのその存在は、しかし、不思議な圧を放っていた。彼は色を失ったのではない。洞窟の光、地底湖の揺らめき、空気の震え、その全てが彼自身であるかのように、世界そのものと一体化していた。
「あなたは……?」
「私は、最初の守り人。そして、この世界の理を見守る者」
老人は静かに語り始めた。僕が悲劇だと思っていた「色の喪失」は、実はこの世界の生命を繋ぐ、穏やかな循環システムの一部なのだと。
「家族という物語には、始まりもあれば終わりもある。一つの家族がその役割を終える時、彼らの存在の色は世界へと還るのだ。その色は、悲しみや喪失ではない。それは、大地を潤す雨となり、新たな生命を育む光となる。そして、やがて生まれる新しい家族に、その彩りは受け継がれていく」
彼の言葉は、僕の心を激しく揺さぶった。では、僕たち家族の色が薄れたのは、誰かに奪われたからではなく、僕たちの物語が、終わりを迎えようとしていたからだというのか。
「彩の守り人とは、世界の色を維持する者ではない。その役目が終わる家族が、穏やかに世界へ還れるよう、その愛を最後まで見届ける『渡し守』なのだ。君の家族の色が急速に薄れたのは、世界中で多くの家族が同時に還る時を迎えたから。その大きな循環を導くため、最も強い彩りを持つ君たち一家が、その先導役として選ばれた」
衝撃の真実に、僕は言葉を失った。悲劇ではなかった。これは、別れと誕生を繰り返す、世界の優しい営みだったのだ。
第五章 選択の刻
「なぜ、僕だけがまだここに?」僕はかろうじて声を絞り出した。
「君は、家族の絆の集積体だからだ」と老人は答えた。「父の強さ、母の優しさ、妹の明るさ。その全ての色を受け継いだ君は、家族の愛そのものだ。君がその愛を手放す決断をするまで、君という存在は消えはしない。最後の渡し守として、この循環を見届けるために」
老人は僕の前に、二つの道を示した。この世界の理に抗い、家族の記憶と共に、色褪せながらも存在し続ける道。あるいは、循環を受け入れ、家族の愛を未来へ手渡す道。
僕は目を閉じた。脳裏に、鮮やかな日々が蘇る。力強い深紅で僕を抱きしめてくれた父。穏やかな瑠璃色の瞳で僕を見守ってくれた母。向日葵のような笑顔で僕の名を呼んだ妹のリナ。僕の身体にずっしりと心地よい重みを与えてくれた、かけがえのない絆。それを手放すことは、僕自身を失うことにも等しかった。
しかし、同時に理解した。僕たちがいたから、僕たちが愛し合ったから、その色が世界に満ち、またどこかで新しい誰かが愛し合うことができる。僕たちの終わりは、絶望ではない。未来への贈り物なのだ。
僕は懐から、僕たち家族の「彩の砂時計」を取り出した。流れ落ちる砂は、もはや濁った灰色ではなかった。父の赤、母の青、妹の黄色、そして僕の色が混じり合った、温かく、そしてどこか切ない薄紫の色をしていた。これが、僕たち家族が生きた証。僕たち家族の愛の形。
「ありがとう」
僕は砂時計に、そして遠い記憶の中にいる家族に、そっと囁いた。
第六章 世界に還る色
僕は静かに歩み寄り、地底湖のほとりにある祭壇に、僕たちの砂時計を置いた。その瞬間、サラサラと音を立てていた砂が、堰を切ったように流れ落ち、ガラス容器の底を満たした。
最後の一粒が落ちきった時、砂時計は眩いばかりの虹色の光を放った。父の赤が、母の青が、妹の黄色が、僕の中で溶け合い、そして洞窟全体を満たしていく。それは悲しい光ではなかった。温かく、すべてを包み込むような、優しい愛の光だった。
僕の身体は、完全に重力から解放された。もう、どこにも繋ぎ止めるものはない。足がゆっくりと地面を離れ、僕は光の中へと溶けていく。消滅する恐怖はなかった。むしろ、世界と一つになるような、穏やかで満たされた感覚が僕を包み込んでいた。
薄れゆく意識の中、僕は見た。僕たち家族から放たれた色が、地上へと昇っていき、灰色の世界に降り注ぐのを。遠くの街で、一組の男女がはっと顔を見合わせ、互いの瞳に映る微かな色に気づき、涙を流すのが見えた。どこかの家で、生まれたばかりの赤ん坊の頬に、淡い桜色の光が灯るのが見えた。
僕たちの物語は終わった。けれど、僕たちの愛は、形を変え、こうして新しい物語を紡ぎ始めていく。身体が完全に透明になり、僕という個が消え去る直前、風に乗って、赤ん坊の朗らかな産声が聞こえた気がした。それは、世界が奏でる、新しい始まりの詩だった。