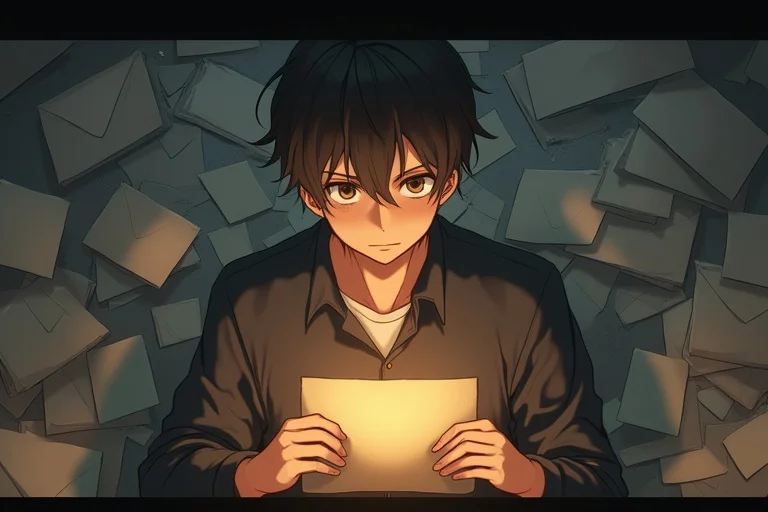第一章 揺らめく炎と孤独な影
僕の目には、他人の寿命が映る。それはまるで、その人の胸の内に灯る蝋燭の炎のようだった。生まれたばかりの赤子は力強く燃え盛る巨大な篝火のように、老人は今にも消えそうな頼りない火花のように。僕は、その光の揺らめきで、その人がどれほどの時をこの世に許されているのかを、嫌でも理解してしまう。
だから、僕は他人と深く関わることを避けて生きてきた。図書館の古書の匂いだけが、僕の孤独を慰めてくれる友人だった。静まり返った書架の間を歩きながら、僕は本に宿る物語にだけ心を許した。そこには、残酷な寿命の可視化は存在しないからだ。
ある秋風が吹き始めた日の午後、その少女は僕の前に現れた。図書館の前の公園で、一人寂しげにブランコを揺らしていた。リナ、と名乗った彼女の胸の内に灯る炎は、あまりにも小さく、儚かった。風が吹けば、ふっとかき消えてしまいそうな、小さな豆電球ほどの光。長くはないだろう。そう直感した僕は、無意識に彼女から視線を逸らした。関わってはいけない。心の奥で警鐘が鳴り響く。情が移れば、必ず訪れる別れが僕の心を焼き尽くすだろう。
しかし、リナは僕のそんな思いを知る由もなく、僕を見つけると、ぱあっと顔を輝かせた。「お兄さん、図書館の人? あのね、すっごく高いところにある絵本が読みたいの!」
無垢な笑顔だった。その笑顔は、僕が築いてきた心の壁をいとも容易くすり抜けて、僕の内に差し込んだ。僕は抵抗できずに、彼女を図書館へ招き入れた。それが、僕の灰色だった世界に、最初で最後の色彩がもたらされた瞬間だった。
リナはそれから毎日のように図書館へやって来た。僕は彼女に様々な絵本を読んで聞かせた。竜と戦う勇敢な王子の話、星の海を渡る猫の話。物語に聞き入る彼女の瞳はきらきらと輝き、その時だけは、胸の内の炎も少しだけ強く燃えているように見えた。
だが、現実は非情だ。彼女の咳は日に日に増え、そのたびに、胸の炎が大きく揺らめいた。僕は祈るような気持ちで、その小さな光を見つめることしかできなかった。自分の無力さに歯噛みしながら、ただ、彼女と過ごす一日一日を、記憶に刻みつけるように大切に生きた。僕自身の蝋燭の炎がどうなっているのか、僕には見えなかった。生まれた時から、自分の寿命だけは、僕の目には映らなかったのだ。
第二章 ささやかな日々と小さな奇跡
リナと過ごす時間は、僕にとって温かな陽だまりだった。彼女は僕を「カイ兄ちゃん」と呼び、公園のベンチで、僕が読んで聞かせる物語の世界に夢中になった。彼女は僕が紡ぐ言葉の一つ一つを、宝物のように大切に受け取ってくれた。
「カイ兄ちゃんは、魔法使いみたいだね」
ある日、リナが不意にそんなことを言った。「だって、カイ兄ちゃんが読んでくれると、ただの絵本が本当に動き出すみたいに見えるんだもん」
僕は苦笑するしかなかった。僕が使える魔法なんて、人の死期を予見するという、呪いのようなものだけだ。もし本当に魔法が使えるのなら、今すぐにでも、君の胸に燃え盛る炎を灯してあげるのに。そんな叶わぬ願いが、喉まで出かかった。
そんな日々が続いていたある雨の夜、僕は仕事の帰り道で、翼を折られ、路上に蹲る一羽のツバメを見つけた。その小さな胸には、風前の灯火という言葉がぴったりの、チリチリと頼りなく燃える光が見えた。もう助からないだろう。いつもなら、僕は目を伏せて通り過ぎていたはずだった。
だが、その夜の僕は違った。ツバメの小さな炎が、リナのそれと重なって見えたのだ。僕は衝動的にその場に膝をつき、震えるツバメを両手でそっと包み込んだ。
「生きてくれ」
心の底から、そう願った。僕の温もりが、少しでもこの命を繋ぎとめてくれるのなら。そう強く念じた瞬間、信じられないことが起きた。僕の手のひらから、淡い光が溢れ出し、ツバメの身体に吸い込まれていったのだ。すると、あれほど弱々しかったツバメの胸の炎が、ふわりと一回り大きく、そして力強くなった。ツバメは驚いたように一度僕を見上げると、力強く羽ばたき、雨の夜空へと消えていった。
呆然と立ち尽くす僕。今の現象は一体何だったのか。自分の寿命を、分け与えた…? そんなことが可能なのか?
翌日、僕は公園で再びあのツバメを見つけた。翼の傷は癒え、元気に飛び回っている。僕は安堵し、そっと近づいた。しかし、ツバメは僕を見ると、他の人間に対するのと同じように、警戒してさっと飛び去ってしまった。僕が命を助けた個体であるはずなのに、僕に対する親しみの感情は、そこには微塵も感じられなかった。
まるで、僕という存在が、初めからその記憶になかったかのように。
その時、僕の胸に一つの予感が芽生えた。これは奇跡ではない。何かを得るためには、何かを失う。それが世界の法則だ。僕が得たこの力には、きっと、重い代償があるに違いない。
第三章 決断の代償
その日は、突然やってきた。リナが図書館に現れなかったのだ。胸騒ぎを覚え、彼女の家を訪ねると、青ざめた顔の母親が、リナが病院に緊急搬送されたと告げた。
僕は無我夢中で病院へ走った。ガラス張りの集中治療室。いくつもの管に繋がれたリナの身体は、シーツの海に沈む小舟のように小さく見えた。そして、彼女の胸の炎は、もうほとんど見えなかった。今にも消えそうな線香花火の最後の火花のように、かろうじて存在を主張しているだけだった。
医師は、絶望的な言葉を並べた。もう、医学的にできることは何もない、と。
僕はガラスに額を押し付け、リナを見つめた。僕と過ごしたあの日々が、走馬灯のように蘇る。彼女の笑顔、笑い声、僕を呼ぶ声。それら全てが、この世界から消えてしまう。そんなこと、あってはならない。
僕には、できることがある。あの夜のツバメが、脳裏をよぎる。代償が何であろうと、構わない。リナが生きてくれるのなら。彼女がこれからも、たくさんの物語に出会い、笑い、泣き、そして誰かを愛することができるのなら。僕の存在など、安いものだ。
僕は静かにリナの病室に入り、彼女の小さな手を握った。そして、目を閉じ、強く、強く念じた。僕の全てを、君にあげよう。僕の持てる時間を、君の未来のために。
僕の身体から、今まで感じたことのないほどの眩い光が溢れ出し、奔流となってリナの身体へと注ぎ込まれていく。彼女の胸で消えかけていた炎が、みるみるうちに勢いを増し、やがては力強く、安定した美しい光を放ち始めた。呼吸器のモニターが示す数値が、正常へと戻っていくのが見えた。
安堵したのも束の間、僕は自らの身体に起きた異変に気づいた。僕の手が、光に透け始めていたのだ。足元から、自分の存在が砂のように崩れていく感覚。これは、ただ寿命が縮むのとは違う。僕という存在そのものが、この世界から希薄になっていく。
そして、その時、僕は悟った。
代償は、忘れられること。僕が命を分け与えた相手の記憶から、カイという人間が存在したという事実そのものが、完全に消去されるのだ。ツバメが僕を覚えていなかったのは、そういうことだったのか。
さらに、もう一つの衝撃的な真実が、雷のように僕の脳天を貫いた。
なぜ、僕は自分の寿命の炎が見えなかったのか。それは、僕に炎がなかったからではない。僕自身が、そもそも誰かの「忘却」と引き換えに、この世に生を受けた「灯火」だったからだ。僕という存在は、かつて誰かが、僕のために全てを捧げてくれた、その愛の結晶だったのだ。僕の知らない誰かが、僕の記憶から消えることを代償に、僕に命を繋いでくれたのだ。
ああ、そうか。僕は、独りではなかった。生まれてからずっと、誰かの温かい愛に抱かれて生きてきたんだ。その愛を、今度は僕が、リナに繋ぐ番だったんだ。
第四章 忘却の灯火
僕の意識は、穏やかな光の中に溶けていくようだった。身体の感覚はもうない。ただ、不思議なほどの充足感と、温かな感謝の気持ちだけが、僕の全てを満たしていた。僕に命をくれた名も知らぬ誰かへ。そして、僕に生きる意味を教えてくれたリナへ。ありがとう。
僕の視界の端で、リナがゆっくりと目を開けた。彼女の瞳は力強く、その頬には血の気が戻っている。彼女は不思議そうに辺りを見回し、そして、僕がいた空間を、何も映さない瞳で通り過ぎた。彼女の記憶から、「カイ兄ちゃん」はもういない。
それで良かった。心から、そう思った。
僕の役目は、終わったのだ。
それから、五年が過ぎた。
秋晴れの公園のベンチに、一人の少女が座ってスケッチブックを広げている。すっかり健康になったリナだった。彼女は楽しそうに、公園の風景を描いている。その手元には、少し古びた一冊の絵本が置かれていた。『星の海を渡る猫』。彼女が一番好きだった物語だ。
リナはふと、クレヨンを止め、何かを思い出すように遠くを見つめた。そして、スケッチブックの隅に、おぼろげな青年の姿を描き始めた。優しそうな目をした、名前も知らない誰か。
「誰だったかな……」
彼女は小さく呟いた。
「思い出せないや。でも……なんだか、すごく温かい人だった気がする」
その言葉は、秋風に溶けて消えた。リナは首を傾げた後、また楽しそうに絵の続きを描き始めた。彼女が描く空の色は、まるで誰かの瞳のように、どこまでも澄み渡っていた。
僕という個人の存在は、この世界から完全に消え去った。誰の記憶にも残らず、記録にも留まらない。しかし、僕が繋いだ命は、僕が与えた温もりは、確かにここに在る。リナの中で、彼女の未来として、生き続けている。
忘れられても、愛は残る。
名もなき灯火は、そう信じながら、静かに、世界に溶けていった。