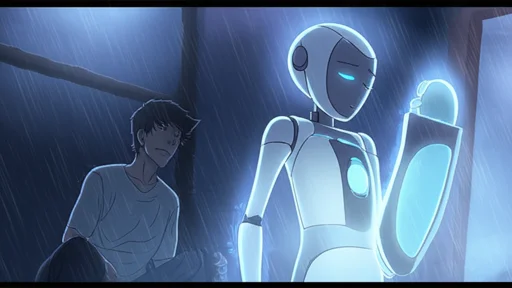男の名はカイ。銀河を駆ける宇宙郵便配達人だ。相棒の小型宇宙船「シルフ号」と共に、彼は今日も手紙を運ぶ。データ通信が主流のこの時代に、インクと紙で綴られた想いを届けるのが彼の仕事であり、誇りだった。
ある日、カイは中央郵便局の片隅で、忘れられたように埃を被る一通の手紙を見つけた。羊皮紙を思わせる古風な封筒。宛先は「惑星アクアマリンの灯台守様」とだけある。消印は、三百年前。
「アクアマリンだと?」
上司は眉をひそめた。公式記録では、その星は二百年以上前に小惑星の衝突で消滅したことになっている。「記録上存在しない星に手紙は届けられん。破棄しろ」
だが、カイにはできなかった。その手紙からは、まるで微かな鼓動のような温もりが伝わってくる気がしたのだ。「どんな手紙にも、届けられるべき理由があるはずです」。カイは固い決意を瞳に宿し、自らの休暇を全て使い、たった一通の手紙を届けるための、無謀な旅に出ることを決めた。
「マスター、正気かい? 生存確率は0.013%以下だよ」シルフ号の合成音声が心配そうに告げる。
「ゼロじゃないなら、十分だ」
カイは古い星図の断片と、好事家たちが囁く伝説だけを頼りに、シルフ号を未開拓宙域へと向けた。
最初の難関は、無数の残骸が高速で飛び交う「亡霊のアステロイドベルト」。カイは歴戦の勘と技で、死のダンスを踊るように岩塊の隙間を縫っていく。レーダーが悲鳴を上げ、船体が軋む。だが、そのスリルこそが、カイの心を奮い立たせた。まるで、この手紙が彼を試しているかのようだった。
次に待ち受けていたのは、時空が歪む紫色の宇宙嵐「クロノス・テンペスト」。嵐に呑まれたシルフ号の窓の外に、若き日の自分の幻影が映った。なぜこの仕事を選んだのか。デジタルの奔流の中で、失われゆく人の温もりを繋ぎ止めたかった、あの頃の情熱が蘇る。手の中の手紙が、一層熱を帯びたように感じられた。
幾多の困難を乗り越え、旅も終わりに近づいた頃。絶望的な静寂の中、シルフ号のセンサーが微かなエネルギー反応を捉えた。星図には存在しない座標。そこに、星はあった。巨大な蒼い水の惑星が、まるで宇宙に浮かぶサファイアのように、静かに輝いていたのだ。星全体が不可視のフィールドに覆われ、自ら姿を隠していたのである。
「アクアマリン……本当に、あったんだ」
カイは息を呑んだ。惑星に降り立つと、そこには広大な海の真ん中に、古びた灯台が一つだけ、天を突くように建っていた。
灯台の扉を開けると、深い皺を刻んだ老人が、カイを待っていたかのように穏やかな笑みで迎えた。
「お待ちしておりました、郵便配達人殿」
カイは驚きながらも、旅の目的だった手紙を差し出した。老人は震える手でそれを受け取ると、一筋の涙を頬に伝わせた。
「これは、三百年前、この星に最初に来た私の先祖からの手紙です」
老人が語り始めた。アクアマリンは小惑星の衝突を予見し、特殊なフィールドで身を守ったのだと。そして、なぜ姿を隠し続けたのか。老人が開いた手紙を、カイは隣で読ませてもらった。
『未来の同胞へ。もし、果てしない宇宙で人類が道に迷い、故郷の温もりを忘れそうになったなら、この星が道標とならんことを。我らはここで宇宙の海を照らす灯台守となろう。この手紙がいつか、心ある誰かの手に渡り、我らの想いが届きますように』
灯台の光は、ただの光ではなかった。宇宙で遭難した船を導くための、救難信号だったのだ。彼らの一族は三百年もの間、誰にも知られることなく、宇宙の片隅で道に迷った人々を救う「最後の希望」として、この灯りを守り続けていた。
カイは言葉を失った。自分が届けたのは、単なる紙切れではなかった。三百年という時を超えて受け継がれた、人類愛そのものだったのだ。
帰り道、カイはシルフ号の窓から、遠ざかるアクアマリンを見つめていた。その青い光は、これまで見たどんな恒星よりも温かく、そして力強く輝いていた。
「シルフ、次の配達先はどこだ?」
「セクター9の開拓惑星です。五歳の女の子から、遠い星にいるお婆ちゃんへの、絵手紙だよ」
カイは深く、満足げに頷いた。この広い宇宙で、彼にしか届けられない想いがある。彼の旅は、まだ終わらない。星屑の海を駆ける彼の心には、アクアマリンの灯が、新たな道標として確かに灯っていた。