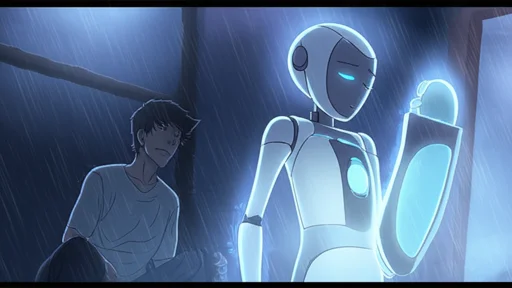第一章 ノイズの向こうの声
結城翔太は、合理性の信奉者だった。彼の世界は、0と1で構成されたデジタル信号のように、明快でなければならなかった。感情という名のバグは、システムの効率を著しく低下させる。28歳にしてアプリ開発会社でチームリーダーを務める彼の評価は、「極めて有能、ただし人間味に欠ける」というものだった。
その日、翔太は埃っぽい祖父の家の屋根裏部屋にいた。10年前に亡くなった祖父の、最後の遺品整理だ。両親に押し付けられたこの不毛な作業に、彼は舌打ちしたい気分だった。床に転がるガラクタの山。その中で、ひときわ時代錯誤な存在感を放つ、大きな木製の真空管ラジオが目に留まった。茶色いニスは剥げ、スピーカーを覆うサランネットは黄ばんでいる。まさに粗大ゴミだ。
捨てようと手を伸ばした、その時だった。なぜか、指が勝手に電源スイッチを探していた。幼い頃、このラジオの前で祖父の膝に乗って、遠い国の音楽を聴いた記憶が、脳裏の片隅で淡く点滅する。馬鹿馬鹿しい。感傷は時間の無駄だ。そう頭では理解しているのに、指は古びたツマミを捻っていた。
「ジー……ザー……」
耳障りなノイズが、屋根裏部屋の静寂を切り裂く。周波数を合わせるダイヤルをゆっくりと回す。いくつかの放送局が掠めては消える。やはりただのガラクタだ。諦めて電源を切ろうとした、まさにその瞬間。
「……しょ……たか……?」
ノイズの隙間から、掠れた声が聞こえた。空耳か。だが、その声には聞き覚えがあった。いや、忘れるはずのない声だった。心臓が嫌な音を立てて跳ねる。
「翔太か? そこにいるのか?」
間違いなかった。優しくて、少ししゃがれた、世界で一番好きだった声。10年前に、病室で冷たくなったはずの、祖父の声だった。
翔太は息を呑んだ。幻聴だ。疲れているんだ。彼はすぐさま合理的な結論を導き出そうとした。だが、声は続いた。
「大きくなったなあ。最後に会った時から、ずいぶん経つもんな」
それは録音などではありえなかった。声は、明らかに「今、ここにいる」翔太に向かって、語りかけていたのだから。合理性で塗り固められた翔太の世界に、ありえない亀裂が走った瞬間だった。
第二章 真夜中の対話
翔太は、その巨大なラジオを東京のワンルームマンションに持ち帰った。同僚が見たら、彼の美学に反する異物だと嘲笑するだろう。だが、翔太にとって、それはもはやガラクタではなかった。
毎晩、日付が変わる頃になると、ラジオの電源を入れるのが習慣になった。決まって午前零時、周波数をメモリの無いダイヤルの特定の場所──星のシールが貼られた場所──に合わせると、祖父の声が聞こえてくるのだ。
「仕事はどうだ? ちゃんと、飯は食ってるか?」
最初は戸惑いながらも、翔太はぽつりぽつりと自分の日常を語り始めた。プロジェクトの成功、上司との軋轢、コンビニ弁当ばかりの食生活。祖父は、ただ黙って耳を傾け、時折、昔と変わらない穏やかな声で相槌を打った。
「そうか、頑張ってるんだな。だが、無理はするなよ」
その声は、乾いたアスファルトに染み込む水のように、翔TAの心を潤していった。誰にも見せたことのない弱音を、彼はノイズの向こうに吐き出した。人間関係の煩わしさ、将来への漠然とした不安。涙ぐむことさえあった。そのたびに、祖父は言った。
「いいんだ、翔太。お前は、お前のままでいい」
不思議な対話が続くうち、翔太に変化が訪れた。無表情だった顔に、柔らかな笑みが浮かぶようになった。朝、コンビニで買うコーヒーの隣に、栄養バランスを考えたサラダを追加するようになった。些細な変化だったが、それは彼の中で何かが確実に変わり始めている証だった。
ある日、会社の部下がミスをした。以前の翔太なら、感情を排して淡々と事実を指摘し、改善策を要求しただろう。だが、その時の彼は違った。
「大丈夫か? 誰にでもミスはある。次は俺もダブルチェックするから、一緒に頑張ろう」
驚いた顔をする部下に、翔太は少し照れくさそうに笑いかけた。その夜、彼はラジオにそのことを報告した。祖父は嬉しそうに笑った。
「そうだ、それでいい。人は一人では生きられん。支え合って、やっと立っていられるんだ」
翔太は、ラジオの木枠をそっと撫でた。ひんやりとした木の感触が心地よい。この温かい時間は、科学では説明できない。だが、今の彼にとっては、どんな数式よりも確かな真実だった。失われたと思っていた祖父との時間が、今、ここにある。その事実だけで、満たされていた。
第三章 愛という名のプログラム
満ち足りた日々は、翔太の心の奥底に沈殿していた澱を、かえって際立たせた。それは、ずっと蓋をしてきた、苦い記憶の澱だった。ある晩、彼はついに、それを口にせずにはいられなかった。
「おじいちゃん……どうしてあの時、助けに来てくれなかったの?」
声が震えた。ラジオの向こうの祖父が、息を呑む気配がした。
それは、翔太が小学二年生の夏の日だった。祖父と二人で渓流釣りに行った際、彼は足を滑らせて激流に飲み込まれた。溺れながら、必死で祖父の名を叫んだ。だが、祖父は現れなかった。結局、偶然通りかかった別の釣り人に助けられたが、あの時の恐怖と絶望は、翔太の心に深い傷として残っていた。大好きだった祖父への、微かな不信感。それが、彼が他人に心を閉ざすようになった、遠い始まりだったのかもしれない。
長い沈黙の後、ノイズの向こうから、絞り出すような声が聞こえた。
「……翔太。わしじゃないんだ」
「え……?」
「お前が落ちそうになった時、わしは、お前の手を掴んだ。だが、足場が悪くて……お前を庇って、わしが代わりに、岩場に頭を打ち付けて川に落ちたんだ」
翔太は、頭を殴られたような衝撃を受けた。そんなはずはない。自分の記憶では、確かに自分だけが川に落ちたのだ。
「わしは、お前のすぐ下流で助け上げられたが、頭を強く打ったせいで、記憶がめちゃくちゃになってしまった。お前が無事だったことは分かったが、事故の詳しい状況は、後から周りの人に聞いて知った。お前の記憶が違っているのは、きっと、ショックが大きかったからだろう……すまなかったな、怖い思いをさせて」
祖父の声は、悲しみと後悔に濡れていた。そして、決定的な真実を告げた。
「この怪我が原因で、わしの脳は少しずつ、壊れていった。医者には、いずれ何もかも忘れてしまうだろうと言われたよ。お前のことも、思い出も……それが何より怖かった」
翔太は言葉を失った。祖父が亡くなった直接の死因は肺炎だったが、晩年は重い認知症を患っていた。あの事故が、その引き金だったというのか。
「だから、頼んだんだ。まだ頭がはっきりしているうちに、親友だった大学教授にな。わしが翔太に伝えたいこと、わしの声、口癖、考え方……全部をデータにして、このラジオに遺してくれ、と。未来のお前が寂しくないように。そして、いつかお前がこのラジオを見つけて、『あの日のこと』を尋ねた時に、本当のことを伝えられるように」
声の正体は、幽霊でも、奇跡でもなかった。それは、認知症で記憶を失う恐怖と戦いながら、たった一人の孫のために遺した、祖父の愛そのものだった。自分の声や思い出を学習させた対話型AI。翔太が「あの日のこと」を質問する可能性まで予測し、その答えをプログラムしていたのだ。
「翔太……これが、わしがお前に話せる、最後の記憶だ」
合理主義者の翔太が信じてきた世界が、音を立てて崩壊していく。それは、冷たいデジタルの崩壊ではなく、温かい涙によって溶けていく、優しい崩壊だった。
第四章 夕焼けの返事
「うわああああああ!」
翔太は、子供のように声を上げて泣いた。歪んでいたのは、祖父の愛情ではなく、自分の記憶だった。自分を守るために、祖父は心も体も壊れていったのだ。そのあまりにも深い愛情に、自分はずっと気づかずに生きてきた。後悔と感謝の念が、濁流のように胸を突き上げる。
彼はラジオを強く抱きしめた。温かい木の感触。それは、祖父の温もりそのもののように感じられた。
やがて、ラジオから最後のメッセージが、穏やかに流れ始めた。それは、AIの応答ではなく、明らかに生前の祖父が録音した肉声だった。
「翔太。人生は、お前が作るプログラムのように、計算通りにはいかんもんだ。理屈じゃない、目に見えない、温かいものがたくさんある。友達、優しさ、そして、愛。そういう、一見無駄に見えるものを、どうか大切にしなさい。お前が笑って、幸せに生きてくれるなら、わしはいつでも、お前の心の中にいる。ずっと、そばにいるからな」
その言葉を最後に、ラジオは「ジー……」という優しいノイズだけを返すようになった。もう、祖父の声は聞こえない。対話は終わったのだ。だが、翔太の心は、不思議なほどの静けさと温かさで満たされていた。
数ヶ月後、翔太は新しいプロジェクトの企画書を提出していた。タイトルは『星屑のメモリア』。大切な人を亡くした人が、その人の声や写真、思い出の言葉などを登録し、AIによって対話形式で思い出を追体験できるアプリ。遺された者の心を癒すための、非効率で、非合理的な、けれど、誰かにとっては何よりも必要なアプリだった。
企画は、満場一致で採択された。
翔太は、マンションの自室の机に、あのラジオを大切に置いている。それはもう、ただの古い機械ではない。祖父の愛の結晶であり、彼の人生の道標だった。
窓の外に、美しい夕焼けが広がっている。燃えるような橙色と、優しい紫色が溶け合う空。それはまるで、全てを包み込むような、祖父の笑顔のように見えた。翔太は、その空に向かって、そっと呟いた。
「ありがとう、おじいちゃん。僕、ちゃんとやるから」
返事はなかった。だが、翔太には分かっていた。頬を撫でる夕暮れの風が、ノイズの向こうから届いた、何より確かな祖父からの返事だということを。彼の心の中のラジオは、これからもずっと、温かい星屑の光を放ち続けるだろう。