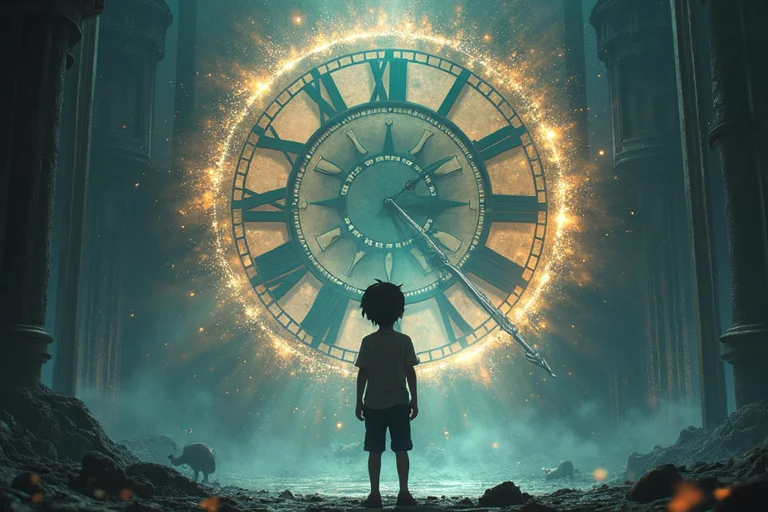第一章 色を失くした奏鳴曲(ソナタ)
相田奏(あいだ かなで)が意識を取り戻した時、頬を撫でる風は、湿った腐葉土と、嗅いだことのない甘い花の香りを運んでいた。最新鋭のスタジオでミキシング卓に向かっていたはずの記憶は、鋭い金属音と全身を貫くような振動を最後に途切れている。目を開けると、視界を埋め尽くしたのは、天を突くような巨木が織りなす深い緑の天蓋だった。
「……どこだ、ここ」
掠れた声は、静寂に吸い込まれた。立ち上がろうとして、奏は息をのむ。彼女の数メートル先で、一匹の兎のような小動物が茂みから顔を出した。その瞬間、周囲の下草がさざ波のように一斉に震え、恐怖に呼応するかのように青白く発光した。小動物が跳ねて去ると、草の震えと光は嘘のように消える。
あり得ない。幻覚か? 奏は音響技師として、常に冷静で論理的な思考を信条としてきた。あらゆる事象は、物理法則とデータで説明できるはずだった。しかし、目の前で起きている現象は、彼女が知る世界のどの法則にも当てはまらない。
ふと、背後で歌うような声がした。
「あら、珍しい。色のない人」
振り返ると、そこに少女が立っていた。亜麻色の髪を三つ編みにし、草花で編んだ簡素な服をまとっている。彼女が微笑むと、足元の地面から小さな蕾が顔を出し、瞬く間に鮮やかな黄色の花を咲かせた。
「あなたは……?」
「わたしはリラ。この森の番人。あなたは?」
「相田奏……。ここは、日本じゃないのか?」
リラは不思議そうに首を傾げた。「にほん? 聞いたことない名前ね。ここは『心象界(しんしょうかい)』。想いが世界を彩る場所よ」
リラの言葉は、奏の理解を超えていた。だが、彼女の周りで起こる奇妙な現象が、その言葉を裏付けているようだった。リラが楽しそうに笑うと、木漏れ日がきらきらと舞い、蝶のような光の粒が集まってくる。逆に、奏の混乱した表情を見て少し不安になると、辺りにすっと冷たい霧が立ち込めた。
「あなたの周りだけ、何も起こらない。まるで音がしないみたいに、静かね」
リラは奏をじっと見つめて言った。「普通、人は心に色を持っているものよ。喜びは赤や黄、悲しみは青、怒りは黒い嵐を呼ぶ。でも、あなたは……透明だ」
奏は自分の内側を探った。混乱と警戒心はある。だが、それは激しい感情の奔流とは程遠い、制御された思考の産物だ。パニックに陥ることも、絶望に泣き叫ぶこともない。常に物事を客観的に分析し、最適解を探す。それが、彼女が長年培ってきた生き方だった。
「感情が……世界を動かす?」
「そうよ。だから、強い想いがないと、ここでは生きていくのも大変なの」
リラはそう言うと、目の前の小川に手を差し伸べた。彼女が「喉が渇いたな」と純粋に願うと、水面から一筋の水が生き物のように立ち上り、彼女の手の中に収まって球体となった。
奏は愕然とした。この世界では、論理も、技術も、知識も、ほとんど無力なのかもしれない。生きるために必要なのは、奏が最も苦手とし、意識的に遠ざけてきた、制御不能な「感情」そのものだというのか。空っぽの心を持つ彼女は、この色彩豊かな世界で、ただ一人の異物だった。
第二章 不協和音の共鳴
リラとの奇妙な共同生活が始まった。奏は元の世界へ帰る方法を探すため、リラはこの「色のない」異邦人に興味を抱き、行動を共にすることになった。
奏は、自分の「無感情」が、この世界では特異な盾となることに気づいた。ある日、森の奥で巨大な猪が縄張りを荒らされた怒りに燃えていた。その感情は黒い稲妻となり、周囲の木々をなぎ倒すほどの嵐を巻き起こしていた。リラは恐怖で顔を青くし、その感情がさらに嵐を強めてしまう。しかし、奏はその嵐の中心にいても、ほとんど影響を受けなかった。彼女の心が凪いでいるため、世界の荒波が素通りしていくのだ。
「すごい……。奏は、怒りの嵐の中でも平気なのね」
「感情という波長に、私の心が共鳴しないだけだ」
奏は冷静に分析した。音響技師の知識が、意外な形で役に立った。彼女は感情が引き起こす現象を「周波数」や「波形」として捉え、危険を予測し、回避することができた。
だが、生きるためにはそれだけでは足りなかった。食料を得るには、獲物への渇望や、果実への感謝の念が必要だった。硬い岩の道を行くには、道を切り拓こうとする強い意志が、岩を動かす力となる。奏は、必死に感情を模倣しようとした。喜びを思い浮かべ、感謝を口にし、意志を奮い立たせようとした。しかし、それは空虚な演技でしかなかった。世界は、彼女のうわべだけの言葉に全く反応を示さない。
「だめ……。奏の想いは、響いてこない」
リラが悲しそうに言うと、彼女の焼いた木の実が少しだけしんなりと萎びた。
奏は、日に日に自分の無力さと内面の空虚さに苛まれた。論理で満たされていたはずの心は、この世界ではただの「無」だった。感情豊かなリラの隣にいると、自分がまるで出来損ないの機械のように思えてくる。リラの純粋な喜びが花を咲かせ、彼女のささやかな悲しみが露を降らせる。その一つ一つが、奏にとっては眩しすぎた。
「どうして、私には何もないんだろう」
ある夜、月明かりの下で奏はぽつりと呟いた。
「そんなことないわ」リラは静かに答えた。「奏は、いつも静か。でも、その静けさが、嵐の中にいるわたしを安心させてくれる。それは、奏にしか作れない、特別な『音』だと思う」
リラの言葉は、奏の心に小さな波紋を広げた。だが、その波紋の意味を、彼女はまだ理解できなかった。そんな中、リラの村から急報が届く。世界の中心にあるという「沈黙の核(サイレント・コア)」の力が強まり、世界各地で感情が消え去る「虚無化」が広がっているというのだ。リラの故郷も、その危機に瀕していた。
第三章 心象のフーガ
「沈黙の核」。それは、あらゆる感情が吸い込まれ、世界が「無」に還る場所。リラの一族は、代々その核の浸食から心象界を守る役目を担ってきたという。
「虚無化が村にまで……。このままでは、世界からすべての色が消えてしまう」
リラの顔から血の気が引いていた。彼女の強い不安に呼応し、周囲の空気が鉛のように重くなる。
奏は、その言葉に奇妙な符合を感じた。「感情が消える」現象。それは、自分自身の在り方に酷似している。
「その核は、誰かが作ったものなのか?」
「ううん、遥か昔からある、世界の『傷』のようなものだって聞いているわ」
奏は一つの仮説を立てた。もし、自分と同じように元の世界から迷い込んだ人間が過去にいたとしたら?その人物が、自分と同じ「無感情」な人間だったとしたら?その存在が、この世界の理と反発し、巨大な「無」の溜まり場……すなわち「沈黙の核」を生み出したのではないか。もしそうなら、核の正体を理解できるのは自分だけかもしれない。
「リラ、その核へ案内してくれ。私なら、何か分かるかもしれない」
リラの案内で、二人は世界の中心を目指した。進むにつれて、世界の色彩は急速に失われていく。鳥のさえずりは喜びの響きを失い、風はただ空虚に吹き抜けるだけ。やがて、二人は巨大な盆地の縁にたどり着いた。
眼下に広がる光景に、奏は絶句した。そこは、完全な「無」だった。色も、音も、匂いも、あらゆる感覚情報が欠落した空間が、まるで黒い穴のように口を開けている。そして、その中心で、結晶化した巨大な樹木が静かに佇んでいた。
「あれが……核……」
リラが震える声で言った。その時、リラの一族に伝わる古い記憶が、彼女の心を通して奏の心にも流れ込んできた。それは、世界の真実だった。
驚くべき事実***が、津波のように奏の思考を打ち砕いた。「沈黙の核」は、誰かが作った傷ではなかった。あれこそが、この心象界の原初の姿、「基底状態」だったのだ。感情こそが、この無のキャンバスに、後から描かれた色彩豊かな異常現象だったのである。
そして、リラの一族は、世界を守る守護者などではなかった。彼らは、代々その身に宿す強大な感情のエネルギーを核に捧げることで、「無」の侵食を押しとどめてきた「生贄」だった。彼らの喜び、愛、希望が、この世界の彩りを辛うじて維持していたのだ。そして、リラもまた、いずれその役目を担い、自らの感情のすべてを捧げて「無」に還る運命にあった。
奏は全身が凍りつくのを感じた。自分が異端だと思っていた「無感情」こそが、この世界の本来の姿。そして、自分が焦がれたリラの感情の豊かさは、いずれ世界のために消費される運命にある、儚い輝き。論理も、理屈も、善悪さえも通用しない。世界の根源的な矛盾を前に、彼女の心は激しく揺さぶられた。守るべきだと思っていた秩序が、実は巨大な犠牲の上に成り立つ、脆い幻想だったのだ。
第四章 静寂に響くアンダンテ
「私が、行かなきゃ」
リラは覚悟を決めた顔で、核へと一歩踏み出した。「これが、私の役目だから」
彼女の身体から、眩いほどの光が溢れ出す。それは、彼女が持つ愛情、希望、喜び、すべての感情の奔流だった。世界を維持するため、自らを犠牲にする。その崇高な自己犠牲を前に、奏は何も言えなかった。論理的に考えれば、それがこの世界にとっての「最適解」なのかもしれない。一人の犠牲で、世界が救われるのなら。
だが。
奏の胸の奥深く、これまで感じたことのない熱い何かが込み上げた。それは、論理ではない。計算でもない。ただ一つの、純粋な叫びだった。
『リラを、失いたくない』
それは恐怖であり、慈しみであり、友情を超えた何かだった。生まれて初めて、彼女の空っぽだった心に、他者を想うという確かな「感情」が灯ったのだ。それは、リラのように世界を彩るほどの強い光ではなかった。しかし、決して消えることのない、静かで、しかし揺るぎない響きを持っていた。
「待ってくれ、リラ!」
奏は叫んだ。彼女の声に、ほんのわずかだが、力が宿っていた。足元の小石が、ぴくりと震える。
「感情が世界に影響を与える波だというなら……その波は、調律できるはずだ!」
奏は音響技師だった。音を重ね、干渉させ、一つのハーモニーを創り出すプロフェッショナル。彼女は、自分の内に芽生えたこの微かな感情の波を「基音(ルート)」にすることを決意した。リラの強すぎる感情の波(世界を彩る高周波)と、核が放つ絶対的な沈黙の波(すべてを吸収する低周波)。二つの極端な波を、自分の心の音で繋ぎ、調律する。破壊し合う不協和音を、新たな共鳴へと導くのだ。
奏は目を閉じ、全神経を集中させた。リラへの想いを、ただひたすらに響かせる。それは祈りにも似ていた。彼女の純粋な響きは、リラの激しい光の奔流に触れ、その指向性を変えた。さらに、その波は核の「無」へと届き、沈黙の淵にささやかな振動を生み出した。
破壊的な衝突ではない。吸収でもない。それは、静かな「共存」の始まりだった。リラの感情は核に捧げられることなく、核の沈黙は世界を侵食することなく、互いが互いを補い合うような、新たな均衡が生まれた。
世界は救われた。だが、それは以前の世界とは違っていた。鮮やかな感情が爆発するような色彩は影を潜め、代わりに、静けさの中に微かな感情の機微が灯るような、穏やかで、少しだけ寂寥感を帯びた世界へと変貌していた。
リラは奏の隣で、呆然と変わり果てた世界を見つめていた。彼女は犠牲にならずに済んだ。しかし、かつての鮮やかな世界はもうない。
「奏……」
「これでよかったのか、私には分からない」奏は静かに言った。「でも、君がいない世界なんて、私には意味がないと思った。それだけだ」
奏は、元の世界へ帰る選択肢を捨てた。論理と理屈だけの灰色の世界には、もう彼女の居場所はなかった。空っぽだった彼女に、初めての「音」をくれたのは、この世界と、リラという存在だったからだ。
二人は、静かになった世界を並んで歩いていた。空は淡い水彩画のように、どこか物憂げだ。だが、吹き抜ける風の中に、奏はリラの穏やかな喜びの響きを感じ取ることができた。そして、それに呼応するように、奏自身の心にも、温かい何かがじんわりと広がっていく。それは世界を動かすほどの力はないが、彼女の内面を豊かに彩る、かけがえのない宝物だった。
奏は空を見上げ、そっと呟いた。
「空っぽだった私に、音をくれたのは、この世界だった」
感情の豊かさだけが幸福ではない。完全な沈黙だけが安らぎでもない。その狭間にある、ささやかな心の響きに耳を澄ませること。奏は、無響の世界で、自分だけの音楽を見つけたのだ。