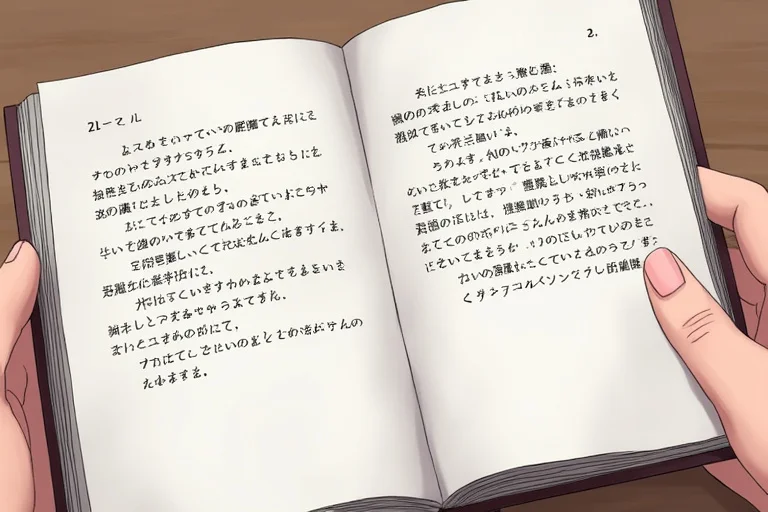第一章 錆びついた帰郷
「お父様が、亡くなりました」
受話器の向こうから聞こえてきたのは、事務的でいて、どこか遠い世界の響きを伴った声だった。俺、水野健太は、高層ビルのオフィスでコーヒーを啜っていた。窓の外には、幾何学模様のように広がる灰色の都市。父とは、もう十年以上、まともに顔を合わせていなかった。母が亡くなって以来、父と俺の間には、修復不可能なほど冷たく、深い溝が横たわっていた。
「そうですか」と短く応え、電話を切る。涙は一滴も出なかった。ただ、胸の奥に小さな石ころが投げ込まれたような、鈍い波紋が広がっただけだ。合理的に、感傷を排して、俺は数日後の週末、遺品整理のために新幹線のチケットを取った。
埃とカビの匂いが混じり合った空気が、玄関の扉を開けた途端に俺の肺を満たした。そこは、俺の記憶の中にある実家とは似ても似つかぬ、時の止まった廃墟のようだった。床には読みかけの新聞が散乱し、壁には蜘蛛の巣がアートのように張り巡らされている。だが、俺の足を止めたのは、その荒廃した光景ではなかった。
リビングの真ん中に、見知らぬ若い女が立っていたのだ。年の頃は二十代後半だろうか。陽だまりのような柔らかな色のセーターを着て、俺をまっすぐに見つめていた。
「どちら様ですか」
警戒心を最大にして、俺は尋ねた。不法侵入か、あるいは父の金を狙った手の込んだ詐欺師か。
女は、ふわりと微笑んだ。その笑顔は、この家の澱んだ空気にはあまりに不釣り合いだった。
「初めまして。私、ひかりと申します。あなたがお父様の息子の、健太さんですね」
「ええ、そうですが」
「お父様の、最後の家族です」
最後の、家族? 意味が分からなかった。父に再婚したという話は聞いていない。ひかりと名乗る女は、俺の混乱を意に介さず、静かに続けた。
「どうぞ、上がってください。お茶を淹れます」
彼女に促されるままリビングに足を踏み入れた俺は、再び絶句した。部屋の至る所に、奇妙なオブジェが飾られていたのだ。空き缶と針金で作られた不格好なロボット、色褪せたビー玉を埋め込んだ粘土の塊、折れた定規と洗濯ばさみで組み立てられた謎の飛行物体。それらはガラクタにしか見えなかったが、一つ一つをよく見ると、俺の脳裏に既視感が閃光のように走った。
あのロボットは、俺が五歳の時に欲しがったおもちゃだ。あのビー玉は、夏祭りの夜に父と二人で集めた宝物。あの飛行物体は、小学生の自由研究で父に手伝ってもらいながら作った――いや、ほとんど父が作った代物だ。
俺の幼い頃の記憶が、錆びついたガラクタの姿を借りて、部屋中に溢れかえっていた。なぜ父は、こんなものを。そして、目の前の女は、一体何者なんだ。俺の知らない父の「最後の家族」と、俺の記憶の残骸。その二つの謎が、俺をこの薄暗い家に縛り付けていた。
第二章 歪な食卓
ひかりとの奇妙な共同生活は、その日から始まった。遺品整理には数日かかると判断した俺は、実家に泊まり込むことにした。ひかりを追い出すことも考えたが、彼女が語る父の姿と、このオブジェの謎を解き明かすまでは、そうすることもできなかった。
「健太さんは、トマトがお嫌いでしたよね」
初日の夜、ひかりはそう言って、食卓に湯気の立つ肉じゃがを置いた。驚いたことに、そこには俺が子供の頃から苦手だった人参が、星形にくり抜かれて入っていた。母がよくやってくれた、俺に野菜を食べさせるためのささやかな工夫だ。
「……なぜ、それを」
「お父様から、よく聞いていましたから。健太さんの好きだったもの、嫌いだったもの。全部」
ひかりが作る料理は、どれも父が好きだったものばかりだった。そして、その味付けは、驚くほど母の味に似ていた。俺がとうの昔に胃袋の底に忘れ去ってしまった、懐かしい味。一口食べるごとに、錆びついた記憶の扉が、ぎしりと音を立てて開いていく。
「お父様は、よく健太さんの話をされていましたよ。小学校の運動会で一等賞を取ったこと、初めて自転車に乗れた日には二人で町内を一周したこと……」
ひかりは、まるで見てきたかのように語る。それは確かに俺の記憶にある出来事だったが、彼女の口から語られると、まるで他人の物語を聞いているような奇妙な感覚に陥った。
俺は、彼女をまだ疑っていた。父の孤独に付け込み、財産を奪おうとしているのではないか。しかし、彼女の瞳はあまりに澄んでいて、その言葉には嘘の匂いがしなかった。
日中、俺は黙々と遺品を整理し、ひかりはそんな俺の傍らで、オブジェの埃を丁寧に拭っていた。
「これは、健太さんが七歳の夏休みに作った秘密基地だそうです。この木片は、お父様が拾ってきた桜の枝なんですよ」
彼女は、オブジェの一つ一つにまつわる物語を知っていた。俺自身でさえ忘れかけていた、些細な、けれど当時は世界の全てだった思い出の数々を。
俺は冷たく突き放した。
「あんたに何が分かる。ただのガラクタだ。親父の自己満足に付き合わされて、迷惑だったんじゃないのか」
ひかりは、少しだけ悲しそうに目を伏せたが、すぐに顔を上げた。
「いいえ。とても、大切な時間でした。私にとっても……お父様にとっても」
その夜、俺は眠れずに、リビングで一人、酒を飲んでいた。月明かりが、オブジェたちの歪な輪郭を照らし出している。針金のロボットの、ぎこちない腕。それはまるで、何かを掴もうとして、掴みきれずにいる不器用な父の姿そのもののように見えた。俺は一体、この十数年、父の何を分かっていたというのだろう。
第三章 父の告白
転機は、三日目の午後に訪れた。父の書斎を整理していた俺は、鍵のかかった引き出しを見つけた。工具で無理やりこじ開けると、中から出てきたのは、数冊の古びた大学ノートと、一通の厚い封筒だった。
ノートの表紙には、父の震えるような字で『記憶のための覚書』と記されていた。ページをめくった俺は、息を飲んだ。
『九月十日。健太の好物、ハンバーグ。玉ねぎは多め。ケチャップとソースを混ぜる。これを忘れるな』
『九月十五日。健太が生まれた日。病院の廊下で夜を明かした。ガラス越しの小さな顔。一生守ると誓った。なぜ、この記憶が薄れる?』
『十月三日。今日、ヘルパーのひかりさんが来た。俺の記憶の語り部になってもらう。俺が忘れた健太を、彼女に語ってもらう。情けないが、これしか方法がない』
そこには、若年性アルツハイマー病と診断された父が、日に日に失われていく「息子との記憶」と必死に闘っていた記録が、克明に綴られていた。オブジェは、彼が記憶を形として繋ぎ止めるための、必死の抵抗だったのだ。運動会の記憶、自転車の記憶、夏祭りの記憶。言葉や文章だけでは留めておけない感情の欠片を、彼はガラクタに託していた。
そして、ひかりは、父が雇ったヘルパーだった。日記は続く。
『ひかりさんは、俺の話を辛抱強く聞いてくれる。俺が何度も同じ話をしても、初めて聞くように相槌を打ってくれる。俺が忘れた健太の思い出を、彼女が代わりに覚えていてくれる。彼女は、俺の記憶の金庫だ。俺にとって、最後の、大切な家族だ』
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。俺が詐欺師だと疑っていた女は、父の尊厳と記憶を守るために雇われた、最後の砦だったのだ。歪な食卓も、思い出話も、すべては父が「健太を忘れないため」の、悲しくも愛おしい儀式だった。
震える手で、封筒を開ける。中には、父の字で書かれた、たった一枚の便箋が入っていた。
『健太へ。
もしお前がこれを読んでいる時、俺はもう俺ではないだろう。
たくさんのことを忘れてしまった。お前の母さんの顔も、声も、おぼろげだ。
だが、これだけは、最後まで忘れたくなかった。
お前が生まれた日、俺は世界で一番幸せな男だった。
不器用な父で、すまなかった。
お前を、忘れたくなかった。』
インクが滲んだ最後の数文字に、俺は声を上げて泣いた。疎遠だったのではない。冷たい溝があったわけでもない。父は、病という巨大な壁の向こう側で、たった一人、俺の記憶を抱きしめて闘っていたのだ。俺は、その闘いから目を背け、父を孤独の中に置き去りにしていた。後悔と、今更になって溢れ出す父への愛情で、胸が張り裂けそうだった。
第四章 明日へのオブジェ
リビングに戻ると、ひかりが静かに立っていた。俺の泣き腫らした顔を見ても、彼女は何も言わず、ただ温かいお茶を差し出してくれた。
「……ごめん」
俺は、絞り出すように言った。
「何も知らずに、ひどい態度をとった。本当に、すまなかった」
ひかりは、静かに首を横に振った。
「健太さんが、お父様の想いを知ってくださった。それが、何よりです。それが、私の役目でしたから」
その夜、俺たちは初めて、本当の意味で向かい合って食卓を囲んだ。ひかりが語る父の最後の数年間は、病との闘いであると同時に、ユーモアと愛情に満ちた日々でもあった。オブジェ作りに失敗して悔しがったり、俺の子供の頃の悪戯を思い出して、一人で声を立てて笑ったり。俺の知らない父の姿が、ひかりの言葉を通して、鮮やかに蘇ってきた。
遺品整理は、中断した。いや、やめたのだ。この家は、もはやただの古い家ではない。父の記憶と愛情が詰まった、巨大なオブジェそのものだ。ガラクタに見えた一つ一つが、俺にとってはかけがえのない宝物に変わっていた。
書斎の隅に、作りかけの木彫りのオブジェが残されているのを見つけた。それは、スーツを着た、大人の男の姿をしていた。顔の部分はまだ荒削りで、表情は分からない。だが俺には分かった。これは、父が最後に作ろうとしていた、大人になった俺の姿なのだ。
俺は、父が使っていた彫刻刀を手に取った。
「ひかりさん。手伝ってくれないか」
ひかりは、こくりと頷いた。
二人で、その木彫りを完成させた。俺は父から聞いたひかりの記憶を頼りに、ひかりは俺の今の顔を見ながら。出来上がったのは、決して上手いとは言えない、けれどどこか温かい表情をした男の像だった。それは、過去の記憶と、今の俺と、未来への希望が混じり合った、新しいオブジェだった。
数日後、ひかりが「私の役目は終わりましたから」と、荷物をまとめて出ていこうとした。俺は、玄関で彼女を呼び止めた。
「まだ、聞きたい話がたくさんあるんだ。俺の知らない、親父の話を」
俺は、作りかけのオブジェを指差した。
「それに、まだ完成してないオブジェもある。手伝ってほしい」
ひかりは驚いたように目を見開いたが、やがて、出会った時と同じように、ふわりと微笑んだ。その笑顔は、もはやこの家の空気に馴染んでいた。
血の繋がりはない。だが、一人の人間の大切な記憶を共有し、共に未来へ繋いでいこうとする俺たちは、父が言った「最後の家族」の、その先にある新しい形なのかもしれない。
俺は、父が残した針金のロボットを、そっと手に取った。冷たい金属のはずなのに、確かな温もりが、指先から心へと伝わってくる。父さん、聞こえるか。俺は、あんたを忘れない。あんたの記憶と一緒に、生きていくよ。空っぽだったはずのこの家は、今、世界で一番豊かな場所に思えた。