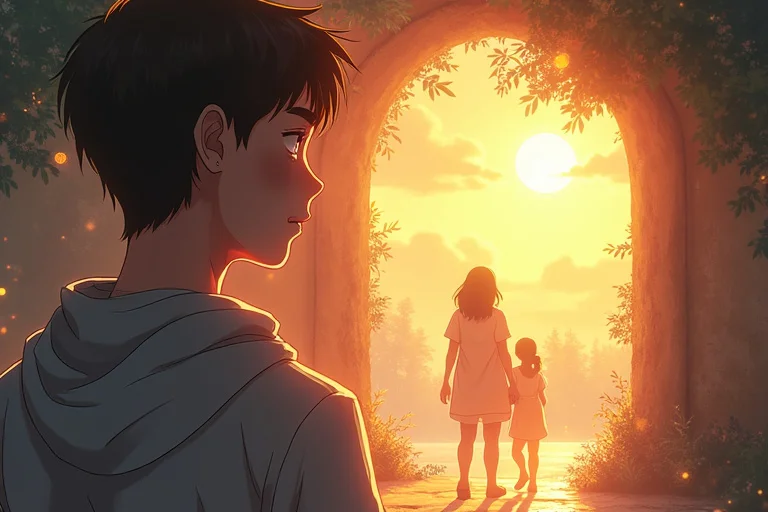第一章 静かな食卓の亀裂
夕食の食卓に、小さな亀裂が入ったのは、秋風が窓を揺らすようになった頃だった。味噌汁の湯気が立ち上り、焼き魚の香ばしい匂いがダイニングを満たしている。父の寡黙さも、妹・美咲の屈託のない笑顔も、いつも通りの風景のはずだった。だが、母だけが違っていた。
「ねえ、健太。あなたの部屋、少し片付けたら? 二人部屋にしては少し手狭でしょう」
母の何気ない一言に、俺は箸を止めた。二人部屋? 俺の部屋は、物心ついた頃からずっと一人部屋だ。かつて、この家にはもう一人、部屋を共有するはずの人間がいた。三年前に事故で死んだ、兄の拓也が。
「母さん、何を言ってるんだ。俺の部屋は昔から一人部屋だよ」
「あら、そうだったかしら。なんだか、ずっと二人で使っていたような気がして」
母はそう言って、悪戯っぽく笑った。だが、その瞳の奥には、奇妙なほど何の感情も浮かんでいなかった。まるで、本当にそう信じているかのような、曇りのない瞳だった。
その日から、母の口から「拓也」という名前が完全に消えた。まるで、最初から息子が二人しかいなかったかのように、母は俺と美咲に愛情を注いだ。父も美咲も、その母の異変に気づいているはずなのに、何も言わない。ただ、静かに母の言葉を受け流し、話を合わせている。食卓の上の、見えない亀裂は日に日に広がっていくようだった。
ある夜、俺は居間の戸棚にしまってある古いアルバムを、こっそりと開いた。兄との思い出が詰まった、宝物のようなアルバムだ。しかし、ページをめくる指が震えた。七五三で一緒に千歳飴を握る写真、中学の卒業式で兄が俺の肩を組んでいる写真、家族旅行で撮った最後の写真。そこにいるはずの兄の姿だけが、まるで外科手術のように、綺麗に切り取られていたのだ。背景だけが虚しく残り、兄がいた場所は不自然な空白となって、俺の記憶の確かさを嘲笑っていた。
これは、何かの悪い冗談だ。母の認知症が始まったのか? だとしたら、父も美咲も、なぜ俺に隠す? それとも、狂っているのは俺の方なのか? 兄は、本当に存在したのだろうか。自分の記憶すら信じられなくなる恐怖が、冷たい霧のように心を蝕んでいった。
第二章 存在しない兄の影
俺は、兄・拓也が存在した証拠を探し始めた。それは、失われた家族の輪郭を取り戻すための、孤独な闘いだった。まずは自室のクローゼットの奥にしまい込んでいた段ボール箱を引っ張り出した。卒業文集、交換日記、兄からもらった誕生日カード。だが、そこにあるはずのものが、ことごとく消えていた。文集のクラス写真では、兄がいたはずの場所が不自然に滲んでいる。兄と交わした手紙は、一通たりとも見つからない。まるで、世界そのものが共謀して、兄の存在を抹消しようとしているかのようだった。
「美咲、ちょっといいか」
休日の午後、リビングで雑誌を読んでいた妹に声をかけた。
「拓也兄ちゃんのこと、覚えてるよな?」
俺の真剣な問いに、美咲はきょとんとした顔を向けた。その表情には、嘘や誤魔化しの色は見えない。ただ純粋な困惑だけがあった。
「……タクヤ、にいちゃん? 誰、それ」
「三年前に死んだ、俺たちの兄貴だよ! お前、あんなに懐いてたじゃないか!」
声を荒らげた俺に、美咲は怯えたように身をすくめた。「お兄ちゃん、最近どうかしちゃったよ。うち、兄弟は二人だけでしょ?」その言葉は、鋭いガラスの破片となって俺の胸に突き刺さった。
家族の中で、俺だけが取り残されている。父は俺の問いかけに対し、「お前の気のせいだろう」と低い声で言うだけで、決して目を合わせようとはしなかった。その態度は、俺の疑念をさらに深いものにした。これは、家族ぐるみで行われている、巧妙で残酷な隠蔽工作なのだ。だが、何のために? なぜ、愛する家族の一員を、いなかったことにしなければならないのか。
焦燥感に駆られた俺は、最後の望みをかけて父の書斎に忍び込んだ。埃っぽいインクの匂いが鼻をつく。本棚の隅に、古びた桐の箱があった。中には、墨で書かれた一巻の家系図が納められていた。震える手でそれを広げると、そこには俺たちの家の血筋が、何代にもわたって記されていた。そして、俺は奇妙な事実に気づいた。いくつかの名前が、黒い墨で太く塗りつ潰されているのだ。その横には、小さな文字で没年が記されている。二十歳、十五歳、三十歳……。いずれも、若くして亡くなった者たちの名前だった。
その塗り潰された名前の列の最後に、見慣れた文字を見つけた。「拓也」。その名前もまた、冷たい墨によってその存在を否定されていた。心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。これは単なる記憶違いや病気ではない。もっと根深く、おぞましい、この家に纏わる何らかの「ルール」なのだ。
第三章 記憶の継承者
その夜、父が俺の部屋を訪れた。手には、あの家系図を握っていた。
「健太、お前に話さなければならないことがある」
父は静かに、しかし抗いがたい重みのある声で言った。俺は黙って父を見つめ返した。長い沈黙の後、父は、我が家に代々伝わる、呪いとも祝福ともつかない秘密を語り始めた。
「我々の一族にはな、特異な体質がある。家族の一人が亡くなると、残された者の中から一人だけ、その故人に関する記憶が消えるんだ」
「……記憶が、消える?」
「ああ。だが、ただ消えるわけじゃない。最も深く、強く、その者を愛していた人間の記憶から、故人の存在そのものが抜け落ちる。悲しみに心が壊れてしまわないように、我々の祖先が身につけた、一種の防衛本能のようなものらしい」
父の言葉は、にわかには信じがたいものだった。だが、母の異変、消えた写真、そして美咲の言葉が、恐ろしい説得力をもって父の話を裏付けていた。
「拓也が死んだ時、あいつのことを誰よりも愛していたのは、母さんだった。だから、母さんの記憶から、拓也は消えた。あいつを産み、育て、誰よりもその将来を案じていた母さんだからこそ、その悲しみに耐えられなかったんだろう。我々は……残された俺たちは、母さんを守るために、母さんの新しい現実に合わせるしかなかったんだ。写真を切り抜き、遺品を隠し、拓也の話題を避ける。それが、俺たちにできる唯一の弔いであり、母さんへの愛情だった」
全身から血の気が引いていくのが分かった。俺が疑っていた家族の隠蔽工作は、病んだ母を傷つけまいとする、悲痛なまでの優しさだったのだ。俺は、父と妹の苦しみを理解せず、自分だけが正しいと信じ、彼らを責めていた。恥ずかしさと罪悪感で、顔が焼けつくようだった。
「健太」
父が、俺の肩に手を置いた。その手は、乾いていて、少し震えていた。
「お前が信じているお前の記憶も、完全なものじゃないんだ」
「どういう、意味だ……?」
「お前がまだ五歳だった頃、おばあちゃんが亡くなったのを覚えているか?」
祖母。その言葉に、俺の頭の中は真っ白になった。祖母がいたという記憶が、ひとかけらも無かった。
「お前は、筋金入りのおばあちゃん子だった。いつもおばあちゃんの背中にくっついて、どこへ行くにも一緒だった。だから……おばあちゃんが亡くなった時、記憶を失ったのは、お前だったんだよ、健太」
足元の床が、ぐらりと揺れた。俺がよすがとしてきた「記憶」という名の地面が、根底から崩れ落ちていく。俺もまた、家族の誰かを忘れることで、今日まで生きてきたのだ。知らず知らずのうちに、俺もまた、この一族の悲しい宿命に守られていたのだ。俺は、兄の記憶を持つ唯一の人間ではなかった。ただ、今回は「忘れる側」ではなかったというだけのこと。その事実に、俺は言葉を失った。
第四章 残響のオルゴール
真実を知ってから、俺の中の何かが静かに変わった。家族を見る目が変わった。母の無邪気な笑顔の裏にある巨大な喪失を、父の寡黙さに秘められた深い悲しみと覚悟を、そして妹の健気な嘘に隠された優しさを、俺は初めて理解した。俺の役割は、この家で唯一、兄・拓也を覚えている「記憶の番人」になることなのだ。それは孤独な務めだが、兄を確かに愛した証であり、この家族を守るための俺の誇りだった。
ある晴れた日の午後、母が屋根裏の掃除をしていた。
「健太、これ、あなたの?」
母が手にしていたのは、少し錆びついたブリキのオルゴールだった。俺は息を呑んだ。それは、拓也が高校生の時、アルバイトで貯めたお金で母の誕生日にプレゼントしたものだった。
「いや、俺のじゃないよ」
俺は平静を装って答えた。母は不思議そうに首を傾げながら、オルゴールの蓋を開けた。
カラン、コロン……。どこか懐かしい、優しいメロディが部屋に響き渡る。それは、母が大好きだった古い映画の主題歌だった。
母は、その音色にじっと耳を澄ませていた。やがて、その瞳から、ぽろりと一粒の涙がこぼれ落ちた。
「……あら、どうしたのかしら」
母は戸惑ったように、自分の濡れた頬に触れた。
「覚えていないのに。なぜか、とても懐かしくて、胸がぎゅっと温かくなるの。まるで、すごく大切な宝物を、失くしてしまったような……そんな気持ち」
俺は何も言わず、ただ母の隣に座った。記憶は消えても、魂に刻まれた愛の残響は、決して消えはしないのかもしれない。言葉や形を失っても、それは温かい感情として、人の心に留まり続けるのだ。母が流す涙は、拓也が存在した紛れもない証だった。
俺は古物商の仕事に戻った。物に宿る人々の記憶を、以前よりもずっと愛おしく感じるようになった。一つ一つの傷や汚れが、誰かがそれを大切にしていた時間の証に見える。俺は、失われた記憶を繋ぎとめるように、今日も古い品々を丁寧に磨き上げる。
愛とは、記憶することだけではない。時には忘れることもまた、愛の形なのかもしれない。そして、忘れられてもなお、残り続ける温かな何かこそが、家族を繋ぐ本当の絆なのだろう。俺は、兄の記憶を胸に抱きながら、この静かで、少しだけ欠けた家族と共に、これからも生きていく。空の青さが、やけに目に染みた。