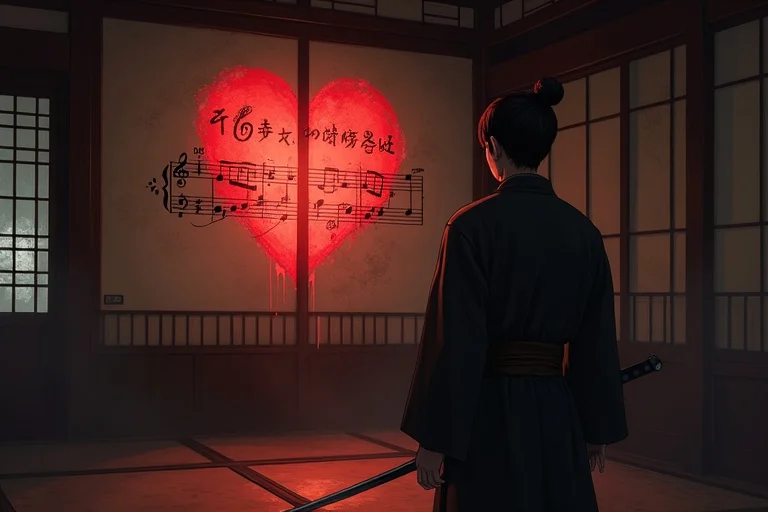第一章 偽りの墨痕
橘右近(たちばな うこん)の世界は、常に滲んでいた。人の言葉が偽りである時、その口元から黒い靄が墨を水に落としたようにゆらりと立ち上る。それは呪いであり、彼を孤独の淵に追いやる特異な病であった。
かつては城下の誰しもが認める実直な若侍だった。だが三年前、親友に裏切られ、家伝の刀を騙し取られたあの日から、右近の眼は人の心の闇を形として捉えるようになった。以来、彼は人を避けた。上役への返答は常に靄に曇り、同輩の世辞は黒煙を吐いた。人の言葉を信じられぬ侍に、忠義も交友もあったものではない。彼は禄を食むだけの抜け殻となり、屋敷の奥でひっそりと息を潜めていた。
その静寂を破ったのは、初夏の蒸し暑い昼下がりだった。藩主の嫡男、松若君が急逝したという報せが城下を駆け巡った。病弱ではあったが、あまりに突然の死。やがて毒殺の疑いが持ち上がり、城内は蜂の巣をつついたような騒ぎとなった。
そして、右近の心を凍らせる報せが届く。容疑者として捕縛されたのは、松若君の傅役(もりやく)であった老臣、伊東頼母(いとう たのも)。その名を聞いた瞬間、右近の喉がひゅっと鳴った。伊東頼母は、右近がまだ人の言葉を信じられた頃、剣の道と人の道を説いてくれた唯一の恩師だったのだ。
「そんなはずがない」
右近はいてもたってもいられず、白州へ引き出される伊東の姿を一目見ようと人垣に紛れた。縄を打たれ、やつれた姿の恩師。しかしその背筋は、昔と変わらず凛と伸びている。
奉行が厳しい声で罪状を読み上げ、伊東に問うた。
「頼母、申し開きはあるか」
伊東は固く目を閉じ、一度大きく息を吸い込むと、張りのある声で答えた。
「某、天に誓って身に覚えのないこと。若君を手に掛けるなど、断じてありませぬ」
その瞬間、右近は息を呑んだ。伊東の言葉と共に、彼の口元から濃く、どす黒い靄が立ち上った。それは右近がこれまで見た中でも、最も深く、底知れない闇の色をしていた。
恩師の言葉は、嘘だった。
確かな証拠を眼前に突きつけられ、右近の世界から最後の光が消えた。ぐらりと揺らいだ視界の中で、人々の喧騒が遠のいていく。信じていた最後の砦が、音を立てて崩れ落ちた。右近は人垣から抜け出すと、逃げるようにその場を後にした。降り始めた雨が、彼の絶望を洗い流すかのように、冷たく頬を濡らした。
第二章 無垢なる瞳
伊東頼母が捕らえられて三日後、右近の荒れた屋敷に、思いがけない客が訪れた。伊東の一人娘、沙耶(さや)だった。雨に濡れた小袖を纏い、戸口に立つ彼女の姿は、まるで雨中の白百合のように儚げだった。
「橘様。どうか、父の無実を証明してくださいませ」
畳に両手をつき、深く頭を下げる沙耶の声は、震えながらも芯が通っていた。右近は目を伏せ、その言葉を聞いていた。彼女の口元からは、一片の靄も立ち上ってはいなかった。一点の曇りもない、真実の言葉。だが、それが右近を一層苦しめた。この娘の信じる心は本物だ。しかし、自分が見た父の嘘もまた、本物なのだ。
「……お引き取り願いたい。某にできることは何もない」
冷たく突き放す右近に、沙耶は顔を上げた。その濡れた瞳が、真っ直ぐに彼を射抜く。
「いいえ、橘様にならできます。父は常々、あなたのことを申しておりました。『右近は、誰よりも人の心の機微に敏い。その真っ直ぐすぎる目が、いつか己を苦しめるのではないかと案じている』と。その眼で、真実を見抜いてはいただけませぬか」
恩師の言葉が、錆びついた右近の心を軋ませた。この無垢な瞳を前にして、己が見た醜い真実を告げることなどできるはずもない。右近は重い沈黙の末、短く「分かった」とだけ答えた。それは沙耶のためというより、己の中で燻る疑念に決着をつけるための、苦い決断だった。
右近は事件の調査を始めた。城へ上がり、関係者から話を聞いて回る。しかし、行く先々で彼の眼は、うんざりするほどの靄に満たされた。
松若君の死を嘆く側室の言葉は、薄紫の靄となって消えた。悲しみの裏に、安堵か、あるいは別の感情が隠されている。
事件の調査を指揮する家老の言葉は、粘つくような灰色の靄を伴った。何かを隠し、体面を取り繕おうとする役人の嘘だ。
誰もが何かを偽り、何かを隠している。人の世とは、かくも偽りに満ちたものなのか。右近は調査を進めるほどに、人間そのものへの嫌悪を募らせていった。
そんな彼の心を唯一凪がせたのは、沙耶の存在だった。彼女は毎日、調査の進捗を尋ねに右近の屋敷を訪れた。彼女が持ってくる素朴な握り飯を二人で食べながら、他愛もない話をする時間だけが、右近にとって靄のない、澄んだ世界だった。
「橘様のお顔、少し和らがれましたね」
ある日、縁側で茶をすすりながら沙耶が言った。彼女の言葉に、右近は我に返る。いつの間にか、この偽りのない言葉と時間に、自分が救われていたことに気づいた。そして同時に、激しい罪悪感に襲われた。彼女の信じる父が、最も濃い嘘をついたという事実から、目を逸らしている自分に。
第三章 靄の向こう側
調査は難航を極めたが、一つの光明が見えてきた。松若君の侍医であった玄庵(げんあん)という男の存在だ。彼は松若君に、病弱な体を強壮にするという秘薬を処方していた。右近は城下の薬種問屋を回り、その秘薬が、少量ずつ与え続ければ人を緩やかに死に至らしめる毒草を含んでいることを突き止めた。
右近は玄庵の屋敷へ乗り込んだ。庭先で薬草を干していた玄庵は、右近の姿を認めると、動じることなく静かに招き入れた。
「若君の件ですな。いずれ、どなたかがお見えになると思っておりました」
茶を淹れながら、玄庵はこともなげに言った。
「貴殿が、若君を手に掛けたのか」
右近の問いに、玄庵は穏やかに頷いた。
「いかにも。あれは、この藩のために必要なことでございました。病弱な若君では、いずれこの藩は立ち行かなくなる。聡明であられる側室様のお子、菊千代君こそが次代の主にふさわしい。某は、藩の未来のために、大義を果たしたまで」
その言葉を聞きながら、右近は全身が粟立つのを感じた。驚愕すべきは、その告白の内容ではない。玄庵の口元から、一片の靄も立ち上っていないことだった。彼は自分の行いを微塵も嘘だと思っていない。心の底から、藩のためを思った「正義」の行いだと信じきっているのだ。
雷に打たれたような衝撃が、右近の脳を貫いた。
まさか。この眼は、「嘘」そのものを見ているのではないのでは?
人が言葉を発する時、その言葉と内心が食い違っている、その矛盾。本人が「これは嘘だ」と自覚している心の揺らぎだけを、靄として捉えているのではないか?
だとしたら、恩師・伊東頼母の、あのどす黒い靄は一体何だったのだ。
「無実だ」という言葉の裏に隠された、彼の内心の「嘘」とは?
「伊東殿は、実に気の毒なことよ」
玄庵が嘲るように呟いた。「あの御仁は、某の薬に早くから気づいておられた。だが、事を荒立てるのを恐れ、強く若君をお諫めすることができなかった。己の不明を恥じ、責め苦に苛まれておられたわ。おかげで、捕縛された時も、実に都合の良い罪人となってくださった」
右近は、すべてを悟った。彼は礼も言わずに玄庵の屋敷を飛び出し、伊東が囚われている牢へと走った。雨上がりのぬかるみが、草鞋に絡みつくのも構わなかった。
第四章 心の在り処
湿っぽく黴臭い牢の中で、伊東頼母は静かに座していた。以前よりさらに痩せたように見える。格子越しに右近の姿を認めると、彼は驚いたように目を見開いた。
「右近か。なぜ、ここに」
「先生。もう一度だけ、お聞かせください。あなたは、無実なのですね」
右近の真に迫る眼差しに、伊東はふっと寂しげに微笑んだ。
「ああ。わしは若君を毒殺してはおらぬ。それは真じゃ」
彼の言葉からは、やはり靄は出ていない。
「では、なぜ白州でのお言葉は……」
伊東は静かに語り始めた。
「わしは、己の無力さを恥じておった。玄庵の怪しい薬に気づきながら、藩内の力関係を恐れ、強く進言できなかった。傅役でありながら、若君を守ることができなかったのだ。わしがもっと早く動いていれば、若君は死なずに済んだ……。その罪悪感が、わしの心を苛んでいた」
彼は一度言葉を切り、格子を握る右近の手をじっと見つめた。
「だから、捕らえられた時、『無実だ』と叫びながらも、心の底ではこう思っていた。『わしには若君を守れなかった責任がある。このまま死んで償うべきだ』と。口にする言葉と、心の奥底にある罪の意識。その大きな隔たりが……お主には、黒い靄として見えたのだろう」
法的には無実。だが、彼の武士としての、人としての良心が、自らを「有罪だ」と断じていた。それこそが、右近が見た最も濃い「嘘」の正体だった。右近は、格子の向こうで静かに涙を流す恩師の姿に、言葉を失った。人の心とは、なんと複雑で、悲しく、そして気高いものなのだろう。
右近は、玄庵の自白と伊東の告白のすべてを、藩の上層部に報告した。真相は明らかになり、玄庵と彼に与した側室は裁かれ、伊東頼母は無罪放免となった。
数日後、右近は伊東の屋敷を訪れた。すっかり元気を取り戻した恩師は、縁側で穏やかに庭を眺めていた。
「お主のその眼は、呪いかもしれぬな」
伊東は、隣に座る右近に静かに語りかけた。
「だが、それは人の心の弱さをも映す鏡じゃ。そして、真の強さとは、己の弱さ、人の弱さから目を逸らさぬことやもしれぬ」
その言葉は、靄に苛まれ続けた右近の心に、深く染み渡った。
帰り際、門前で沙耶が待っていた。
「橘様。本当に、ありがとうございました」
彼女の曇りのない瞳が、右近を映す。その言葉からは、もちろん一片の靄も出ていない。右近は初めて、靄のない言葉の温かさを、心の底から感じることができた。
第五章 灰色世界の夜明け
橘右近の世界は、今も滲んでいる。彼の眼に見える景色は、あの日と何も変わらない。人の言葉は相変わらず、大小さまざまな色の靄を伴って立ち上っては消えていく。
だが、右近の心は変わった。
彼はもう、靄に絶望しない。靄の向こう側にある、人の心の複雑さを見つめようと決めたからだ。
靄は、必ずしも悪意の証ではない。それは見栄であり、臆病であり、後悔であり、時には誰かを守るための、悲しい偽りでもある。その一つ一つに、人の営みのどうしようもない愛おしさが詰まっている。
夕暮れの城下町を、右近は一人歩いていた。すれ違う商人たちの威勢の良い声も、娘たちの楽しげな囁きも、淡い靄を纏っている。かつて彼を孤独にした灰色の世界は、今や無数の人間の感情が織りなす、物悲しくも美しいタペストリーのように見えた。
彼の眼は呪いであり続けるだろう。だが、それは同時に、人の弱さと、その中に灯る僅かな誠実さを見出すための、導きの光にもなり得るのかもしれない。
右近は、ゆっくりと顔を上げた。西の空が、燃えるような茜色に染まっている。その確かな色彩を胸に刻み、彼は靄の滲む世界の中を、迷わずに歩き続けた。