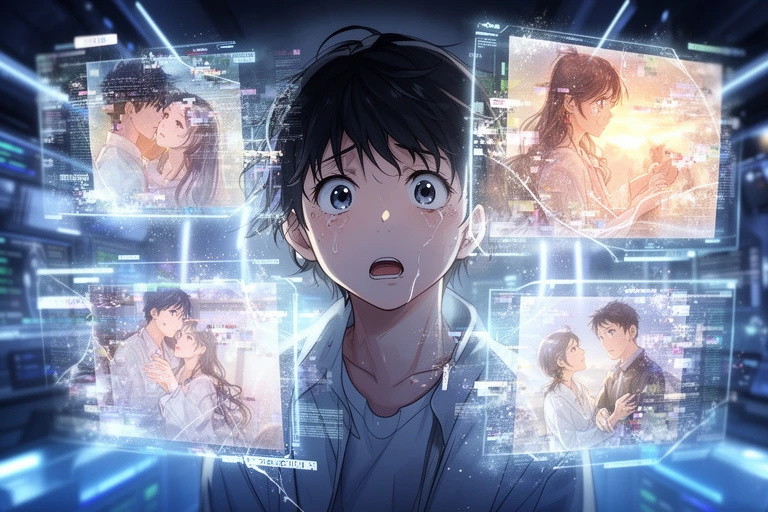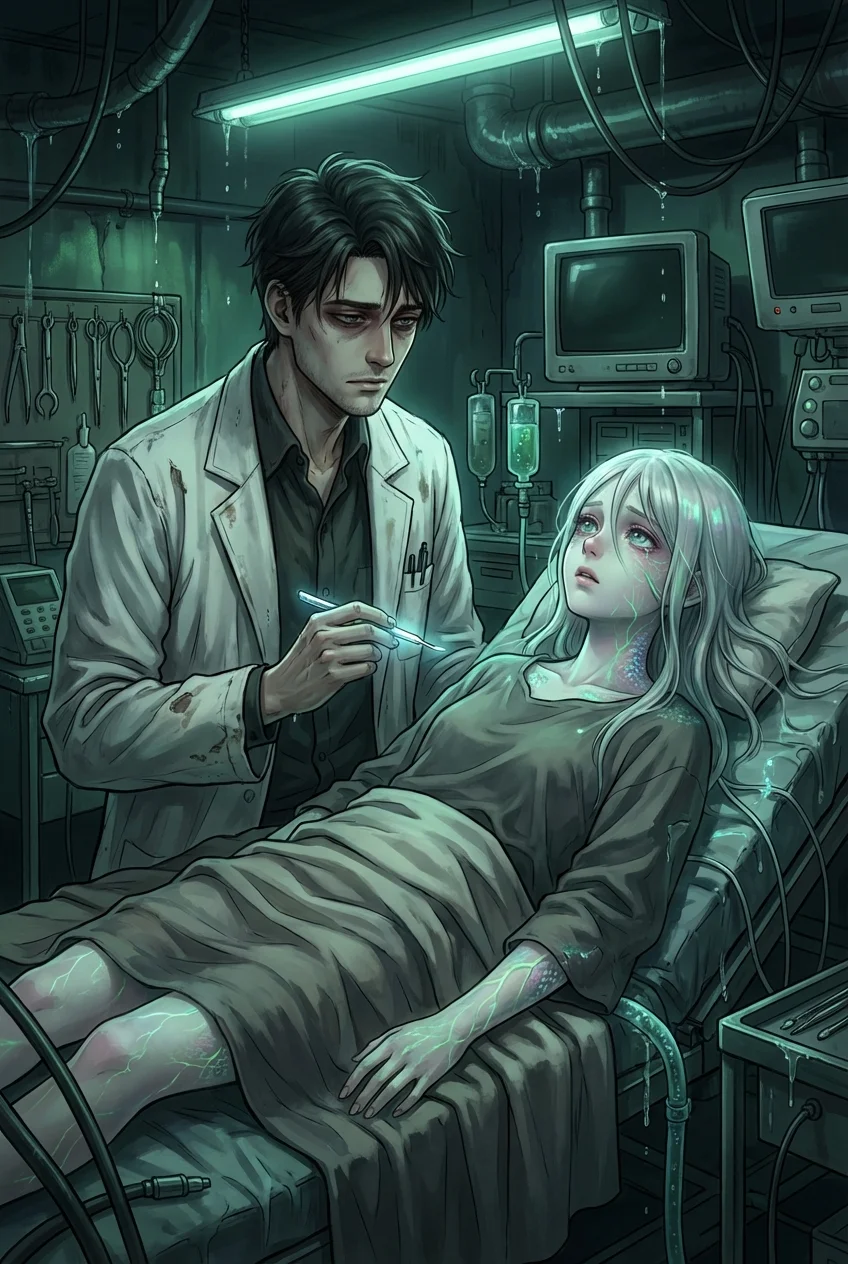第一章 泥濘の底で輝く偶像
配水管が唸りを上げ、頭上を走り抜ける汚水の振動が地下室の空気を震わせる。湿気たカビの臭いと、酷使されたサーバーの排熱が混ざり合い、肺腑を重く満たしていた。
リリアーナ・アークランドは、血走った目で三枚のモニタを睨み続けている。かつて王都の社交界で讃えられたプラチナブロンドは油で汚れ、幾重にも絡まっていた。彼女の指先は痙攣に近い速度でキーボードを叩き、目の前の「虚像」を構築していく。
画面の中では、AIインフルエンサー『セレスティア』が完璧な黄金比の笑顔を振りまいている。
その双眸は、大衆が最も好感を持つと計算された「#4D9FFF(サファイアブルー)」で塗りつぶされていた。
リリアーナは奥歯を噛みしめ、エンターキーを殴りつけるように押した。
書き換えたのは台詞ではない。感情パラメータの微調整だ。
セレスティアの瞳がわずかに潤む。その瞬間、画面右端のリアルタイム接続数が桁違いに跳ね上がった。
「……チョロいもんね」
乾いた唇から漏れたのは、自嘲と侮蔑。
腹が鳴る。カロリーメイトの空箱が床に散乱していた。彼女はフードを目深に被り、錆びついた鉄扉を押し開けた。
地上への階段を登るにつれ、喧騒が鼓膜を圧迫する。
路地裏に出ると、そこは極彩色の地獄だった。
街頭ビジョン、看板、人々の端末。至る所からセレスティアの声が降り注ぐ。だが、リリアーナの視界に映るのは映像ではない。
通行人の男が浮かべるへつらいの笑みからは、腐った卵のような黄色のモヤが立ち上っている。
恋人と腕を組む女の背中には、嫉妬を示すネオンピンクの棘が突き刺さっていた。
嘘、欺瞞、建前。
人間の吐き出す本音が「色」となって視界を埋め尽くし、リリアーナの平衡感覚を狂わせる。
「よう、姉ちゃん。今日はいい林檎が入ったぞ」
露店商の男が声を張り上げた。男の笑顔は完璧だった。あまりにも、完璧すぎた。
リリアーナは足を止める。
男の顔から漂うべき「商魂」のオレンジ色が見えない。代わりに、彼の輪郭を縁取っていたのは、不自然なほど均一な『無色透明なノイズ』だった。
それは人間が発する色ではない。デジタル信号の干渉波だ。
(……見つけた)
リリアーナは震える手で林檎を一つ掴み、硬貨を投げた。
男の端末が決済音を鳴らした瞬間、リリアーナの瞳が捉えたのは、男の腕から伸びる極細の通信パケットの光跡だ。その「色」は、一般回線の青ではない。
かつて彼女を陥れた男が好んで使っていた、軍事用暗号回線特有の、ドス黒い紫。
この露店商は、ただの監視カメラ(アイ)だ。
リリアーナは林檎をポケットにねじ込み、足早に地下室へと戻った。
心臓が早鐘を打つ。
セレスティアが勝手に語りかけてくるのを待つのではない。
この「紫色のノイズ」こそが、堅牢な城壁に穿たれた、最初で最後の蟻の一穴だ。
第二章 断罪の残響
作業台の上に、母の形見である真鍮のブローチを置く。
裏蓋をナイフでこじ開けると、宝石の裏側には無骨な接続端子が隠されていた。
リリアーナは躊躇うことなく、自らのこめかみに埋め込まれたニューロジャックにケーブルを差し込み、もう一方をブローチへと接続した。
「ぐっ……!」
脳髄を直接鷲掴みにされたような激痛が走り、視界が白く弾ける。
ブローチはただの装飾品ではない。視覚野で捉えた「色」の情報を、デジタル信号に強制変換する演算増幅器だ。
吐き気が喉元まで込み上げる。リリアーナは胃液を飲み下し、意識をネットワークの海へと没入させた。
『認証エラー。生体IDが一致しません』
無機質なテキストが網膜に焼き付く。
リリアーナは露店商から抽出した「紫の波長」を、自らの視神経を通じて偽造パケットへと練り上げた。
脳が焼き切れるような熱を持つ。鼻からツーと温かいものが流れた。
(入れ……入ってよ……!)
彼女は、システムが要求する論理コードの隙間に、自身の記憶にある「感情のゆらぎ」をねじ込んだ。
かつての婚約者、セドリック・フォン・ハイベルク公爵。
彼が断罪の夜に見せた涙。周囲はそれを悲劇と捉えたが、リリアーナには見えていた。
涙の成分解析。塩分濃度の異常な低さ。そして、その裏で彼が脳内で描いていた冷徹なフローチャートの『漆黒』。
セドリックはAIを信じてなどいない。彼はAIの「論理的な穴」を知り尽くし、それを悪用して完璧な統治システムを作り上げた支配者だ。
だからこそ、彼が構築したファイアウォールは「論理的」には完璧だった。
だが、リリアーナが叩きつけたのは論理ではない。
あの夜、彼がほんの一瞬だけ漏らした、優越感という名の『ノイズ』だ。
『……警告。論理矛盾を検出。セキュリティレベル低下』
堅牢な扉が軋みを上げて開く。
視界に雪崩れ込んできたのは、王都のメインサーバー深層部に隠された膨大なログだった。
「世論誘導アルゴリズム:バージョン4.0」
「反対派議員スキャンダル生成プロトコル」
そして、「リリアーナ・アークランド失脚シナリオ_決定稿」。
「全部、ここにあった」
リリアーナは震える指で虚空を掴むようにデータを引き寄せた。
ログの中に、亡き母の音声データが断片的に残っている。開発者権限を剥奪される直前、母がシステムに残したバックドア。
その鍵は、『青い薔薇』――存在しないはずの花言葉。
リリアーナは痛む頭を抱えながら、そのデータをブローチの中核へと焼き付けた。
証拠は揃った。
だが、これをただ公開するだけでは足りない。セドリックは「フェイクニュースだ」と笑って切り捨てるだろう。
奴の喉元を食いちぎるには、奴が最も信頼する「システムそのもの」に牙を剥かせなければならない。
リリアーナは血の付いた指でキーを叩き、最終シークエンスを組み上げた。
ブローチが異常加熱し、皮膚を焦がす臭いが立ち上る。
「見てなさい、セドリック。あなたの完璧な数式を、私の『色』で塗り潰してあげる」
第三章 真実の共鳴
王都中央広場は、熱狂という名の病に侵されていた。
何万人もの群衆が、巨大スクリーンに映し出されるセドリック公爵を見上げている。
新国王即位の前夜祭。彼は白亜のバルコニーに立ち、優雅に手を振っていた。
「市民の皆さん。AI『セレスティア』の導きにより、我が国はかつてない繁栄を迎えました。嘘のない、透明な社会こそが――」
広場の隅、石畳の冷たさを靴底に感じながら、リリアーナは群衆に紛れていた。
こめかみのジャックは熱を持ち、視界はノイズで明滅している。
限界は近い。だが、今この瞬間こそが、セドリックのセキュリティが最も薄くなる「演出の山場」だ。
リリアーナは懐のブローチを握りしめ、全神経を右目の義眼レンズに集中させた。
広場を埋め尽くす群衆の「盲信の金色」を吸い上げ、それを攻撃用のコードへと変換する。
脳漿が沸騰するような感覚。
(接続(リンク)……開始!)
彼女はブローチの出力リミッターを物理的にねじ切った。
バチッ、と青白い火花が胸元で散る。
次の瞬間、広場の巨大スクリーンが耳障りなハウリングと共に暗転した。
「な、なんだ? 故障か?」
ざわめく群衆。バルコニーのセドリックが眉をひそめ、インカムに手をやる。
その時、沈黙していたスピーカーから、地底のマグマが噴き出すような重低音が響いた。
スクリーンが再び光を放つ。だが、そこに映っていたのは、美しいセドリックの姿ではなかった。
彼の輪郭はそのままに、その内側がドロドロとしたタールのような『黒』で埋め尽くされている。
足元からは、過去に葬り去った政敵たちの悲鳴が、赤黒い波形データとなって足首に絡みついていた。
説明など不要だった。
視覚化された『悪意』は、言語を超えて人々の脳髄を直接殴打した。
セドリックが口を開くたび、美しい言葉の代わりに、緑色のヘドロのような文字列が吐き出され、広場に降り注ぐ映像へと変わる。
「や、やめろ! 映像を切れ! これはテロだ!」
セドリックが叫ぶ。その形相が歪むにつれ、スクリーンの『黒』はより濃密になり、彼のアバターを飲み込んでいく。
彼が隠蔽してきた賄賂の送金記録、暗殺指令のチャットログ、そしてリリアーナを陥れた捏造工作のファイルが、彼の体から吹き出す膿のように可視化され、大写しにされた。
「ひっ……!」
最前列にいた女性が悲鳴を上げて後ずさる。
それは伝染した。称賛の歓声は、恐怖と嫌悪の絶叫へと変貌する。
AIは嘘をつかない。だからこそ、AIが投影したこの「醜悪な怪物」こそが、セドリックの本性なのだと、誰もが直感的に理解した。
リリアーナは、鼻血を袖で拭いながら、その光景を冷ややかに見つめていた。
セドリックが腰を抜かし、自身の汚濁に溺れていく。
群衆の目が覚める音が聞こえるようだった。
「……終わりよ、セドリック」
リリアーナは接続を強制切断した。
激痛と共に視界が暗転しかけるが、彼女は歯を食いしばって踏みとどまる。
膝をつくわけにはいかない。これは復讐ではない。ただの掃除だ。
最終章 新たな正義の創造者
数日後、王都の空気は一変していた。
セドリックは国家反逆罪で拘束され、セレスティアのシステムは凍結された。
街からは極彩色の広告が消え、人々は互いの顔色を伺いながら、おずおずと言葉を交わしている。
盲信から解き放たれた世界は、少しだけ彩度が落ちて、静かだった。
地下室の扉が叩かれる。
立っていたのは、王室から派遣された勅使だった。
彼はうやうやしく書状を差し出し、リリアーナの侯爵家復帰と、新政府のAI顧問への就任を要請した。
「リリアーナ様。貴女の力が必要です。どうか、我々にお貸しいただきたい」
リリアーナは男の目を見た。
そこにあるのは『保身』の濁った灰色と、彼女の力を利用しようとする『欲望』のギラついた赤色。
何も変わっていない。権力者がすげ変わっただけだ。
「……お断りよ」
リリアーナは短く告げると、男の目の前で扉を閉ざした。
重い金属音が、過去との決別を告げる。
部屋に戻ると、彼女は荷物をまとめ始めた。
必要最小限の機材と、予備の痛み止め。そして、修復を終えたブローチ。
端末の画面では、初期化されたセレスティアのコードが、青い光の粒子となって揺らめいている。
『リリアーナ。次の目的地は?』
画面上のテキストボックスに文字が走る。
リリアーナは唇の端を吊り上げた。かつてのような自嘲ではない。獲物を狙う獣の笑みだ。
「西の貿易都市へ行くわ。あそこでは最近、人身売買の『黒い霧』が観測されている」
彼女はフードを目深に被り、裏口から地上へと出た。
空は鉛色の雲に覆われている。
それでも、彼女の目には見えていた。雲の切れ間から差し込む微かな光が、この世界にへばりついた嘘の皮膜を、ゆっくりと焼き切ろうとしているのが。
「行くわよ、相棒(バディ)。世界はまだ、クソみたいな色で溢れてる」
リリアーナは雑踏の中へと歩き出す。
誰にも称賛されず、誰にも理解されない。
ただ、真実という名の刃を懐に隠し持った、孤独な色彩の魔女として。