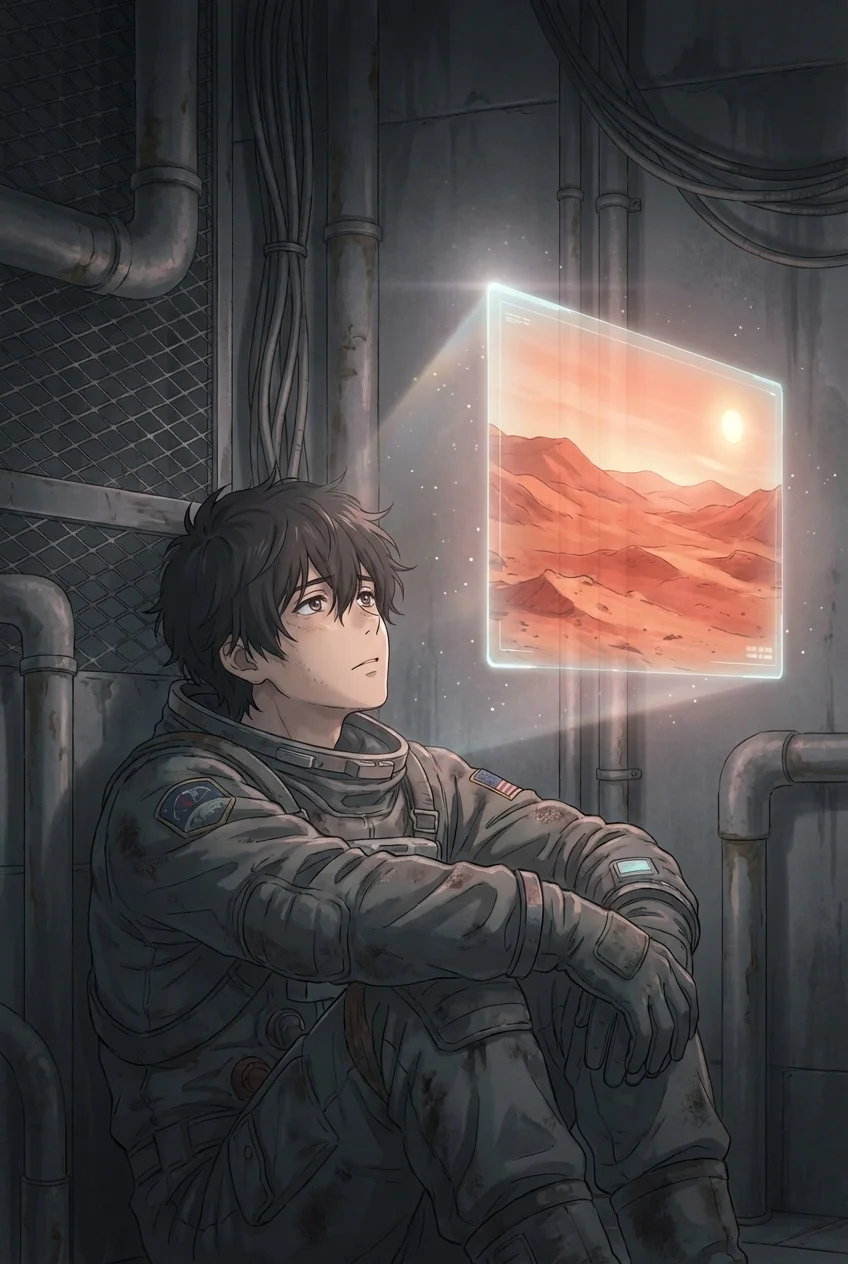第一章 路地裏の未公開株
王都の裏路地。腐った野菜とドブネズミの死骸が浮く泥水の中で、僕は息を潜めていた。
冷たい雨が、不定形の身体(ゼリー)を叩く。
「……おい、そこのゲル状資産」
頭上から降ってきたのは、革靴の足音と、ひどく理知的な響きを持つ男の声だった。
見上げると、泥はね一つないスーツを着た男が立っている。
レイモンド。王都の投資家たちが「狂犬」と呼ぶ男だ。
「聞こえてるだろ。這い出てこい」
僕は身体を縮こまらせた。
無理だ。僕はただの落ちこぼれスライム。
魔王軍からは「知能も攻撃力もゼロ」と解雇され、人間からは害獣として石を投げられる。
僕の視界には、常にノイズのように『数字』が走っている。
レイモンドを見上げた瞬間、その頭上に青白い文字列が浮かんだ。
現在資産:金貨50枚(流動性危機)
負債総額:金貨2億枚
信用格付:D-(破綻懸念)
彼は終わっている。
だというのに、その瞳は獲物を狙う獣のようにギラついていた。
「ポテト、お前には『本当の値段』が見えるんだろ?」
レイモンドは懐から、薄汚れた石ころを取り出した。
道端に転がる灰色の石。魔力も感じない。市場価値はゼロ。
誰もがゴミだと断じる代物だ。
だが、僕の目は焼けるような光を捉えていた。
「っ……!」
石から溢れ出すのは、黄金のキャッシュフロー。
数値が桁を超えてスパークする。
潜在的時価総額:金貨500億枚
成長率:∞(測定不能)
「……『無価値の魔石(ダストストーン)』……」
「そうだ。先週、お前がゴミ捨て場でこの石を見て震えているのを俺は見た」
レイモンドは膝を折り、僕の目の高さに合わせて石を掲げた。
「俺は全財産と、ありったけの借金で、この石の採掘権を独占契約した」
「き、狂ってる……! そんなの、ただの産業廃棄物ですよ……!」
「世間にとってはな。だが、お前には違うものが見えている」
彼が手を伸ばす。
人間がスライムに触れれば、酸で火傷するかもしれないのに、彼は躊躇わなかった。
「俺は賭けたんだ。この石と、それを見出したお前の『目』にな」
冷え切った僕のコアに、熱が伝わる。
レイモンドの頭上の数字が、激しく明滅していた。
破綻懸念の文字の裏に隠された、圧倒的な***勝率***。
「立て、ポテト。俺とお前で、この腐った市場(マーケット)を教育してやる」
第二章 空売りの包囲網
一ヶ月後。
王都証券取引所の大会議室は、嘲笑と野次で埋め尽くされていた。
「おい見ろよ、ゴミ拾いのレイモンドだ!」
「産業廃棄物の山を担保に金を借りたって? 正気か?」
壇上に立った僕たちの視界には、脂ぎった商会員たちの顔が並ぶ。
彼らの頭上には、赤黒い数値が浮かんでいた。
ポジション:空売り(ショート)
レバレッジ:最大
彼らはレイモンドの破産に賭けている。
僕たちが保有する『ダストストーン』の価値がゼロであることに、全財産を賭けているのだ。
「ひぃ……レイモンドさん、みんな笑ってます……」
僕はレイモンドの肩の上で、小さく震えた。
怖くてたまらない。
もし失敗すれば、レイモンドは路頭に迷い、僕は実験動物として解剖されるだろう。
「笑わせておけ。奴らは自分の首に縄がかかっていることにも気づいていない」
レイモンドは不敵に笑い、演台に置いたダストストーンに手を触れた。
「諸君。君たちはこれを、魔力を生まないゴミだと言ったな」
「当たり前だ! 魔力伝導率ゼロの石ころなんぞ、道路の舗装にも使えん!」
最大手商会の会頭が、腹を揺らして叫んだ。
会場がドッと沸く。
「ポテト」
レイモンドが短く呼んだ。
「は、はい……!」
「『情報』を開示しろ」
僕は震える身体を奮い立たせ、自身の粘液をダストストーンに垂らした。
僕の体液は、特殊な触媒になる。
それは、この一ヶ月の研究で分かったことだ。
「……見せてあげます。あなたたちが捨てたものの価値を」
ジュッ、と音がして、石が反応を始めた。
くすんだ灰色が剥がれ落ち、内部から目が眩むほどの青白い光が噴出する。
会場の気温が一気に下がった。
「な、なんだ!?」
「魔力じゃない……これは……『冷却』か?」
レイモンドがマイクを握りしめ、冷徹な声で告げる。
「そうだ。この石は魔力を生まない。だが、周囲の熱を吸収し、純粋な魔力に変換して保存する『吸熱魔石』だ」
静まり返る会場。
蒸気機関や魔導具の排熱問題に悩むこの世界において、その性質が何を意味するか。
ここにいる強欲な投資家たちが、理解できないはずがない。
「排熱ゼロの永久機関。その独占採掘権は、現在すべて私の手元にある」
僕の目には見えていた。
商会員たちの頭上の数値が、一斉に崩壊(クラッシュ)していく様が。
第三章 マーケット・メーカー
「ば、馬鹿な……あり得ない……!」
会頭が顔面蒼白で立ち上がった。
含み損:測定不能
マージンコール(追証):発生中
「そ、そんな石の価値、認めんぞ! 誰が買うものか!」
「おや、買わなくていいのか?」
レイモンドは愉しげに、手元の書類をひらつかせた。
「君たちは私の会社に対して、大量の『空売り』を仕掛けていたな? つまり、市場から株を買い戻して返済しなきゃならない」
「あ……」
「だが、市場にはもう株がない。私が99%を保有しているからな」
レイモンドの目が、冷酷な狩人のそれになる。
「さあ、買い戻したまえ。価格(ねだん)は私が決める。言い値で買うか、破産して牢屋に行くか。選ぶ権利をやろう」
「う、うわあああああ!!」
怒号は悲鳴に変わった。
買い注文が殺到する。
株価ボードの数字が、垂直に跳ね上がっていく。
僕の視界にあるレイモンドの資産残高が、ものすごい勢いでカウントアップされていく。
億、十億、百億……。
それは魔法のような奇跡じゃない。
情報の非対称性と、敵の欲望を利用した、完璧な『嵌め込み(ショートスクイズ)』だった。
騒乱の会議室を背に、レイモンドは僕を肩に乗せたまま出口へと歩き出す。
「見たか、ポテト。これがバブルの弾ける音だ」
「……性格が悪すぎますよ、レイモンドさん」
「褒め言葉だな」
外に出ると、雨は上がっていた。
雲の切れ間から差す光が、泥だらけの路地を照らしている。
レイモンドは懐から葉巻を取り出し、火をつけた。
そして、煙と共に小さな呟きを漏らす。
「俺たちの仕事は、世界を救うことじゃない。世界が見落とした価値を拾い上げ、適正価格をつけさせる。ただそれだけだ」
彼は僕を見た。
その頭上には、もう『破産寸前』の文字はない。
パートナー信頼度:プライスレス
そんな馬鹿げた文字列が見えて、僕は思わず吹き出した。
「次はどうします? 王都の地下下水道に、面白いカビが生えているのを見つけたんですけど」
「ほう? そいつの利回りは良さそうか?」
「ええ。最低でも金貨一万枚は堅いです」
レイモンドがニヤリと笑う。
「なら、買い占めに行くぞ。相場が過熱する前にな」
僕たちは歩き出した。
まだ誰も知らない、次の宝の山へ向かって。