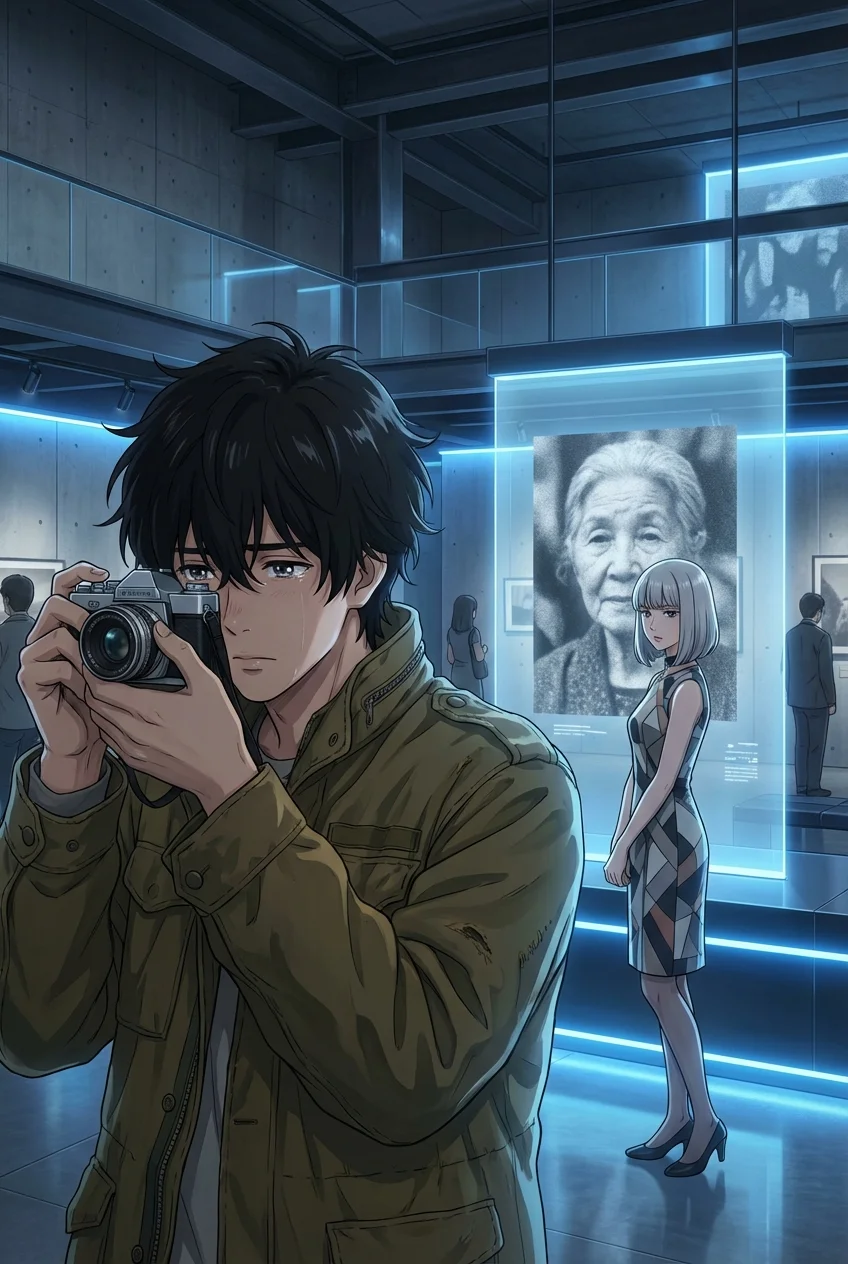第一章 誤字だらけの断罪劇
「エララ・フォン・ローゼンバーグ! 貴様との婚約をこの場で破棄する!」
セドリック王太子の声が、王宮の大広間に響き渡る。
シャンデリアの光を反射する彼の金髪は美しいが、唾を飛ばして叫ぶその姿は、三流芝居のようだった。
私は扇子で口元を隠し、冷めた目で彼を見下ろす。
「……殿下。文法が間違っておりますわ」
「は?」
「『破棄』ではなく『解消』が適切かと。それに、貴様のあとの『!』は一つで十分です。品がありません」
周囲の貴族たちがざわめく。
この女、何を言っているんだという視線。
隣で震えるふりをしているのは、男爵令嬢のリリア。
ピンクブロンドの髪、潤んだ瞳。
典型的なヒロイン。
ああ、またこれか。
私の視界には、現実の風景と共に『文字列』が浮かんでいる。
『セドリックは激昂し、エララを指差した』
『リリアは怯え、彼の腕にしがみつく』
この世界は物語だ。
そして私は、その物語の『文字』が見える。
前世で編集者として過労死した私が、悪役令嬢として転生した皮肉。
神様とやらは、私に安息を与える気がないらしい。
「ふざけるな! 貴様がリリアに嫌がらせをし、あまつさえ毒を盛ろうとしたことは明白なのだ!」
セドリックが合図をすると、近衛騎士が銀のトレイを持って進み出た。
そこには、怪しげな紫色の小瓶が乗っている。
「これが証拠だ! 貴様の部屋から見つかった、リリアを害するための猛毒『アコナイトの雫』!」
リリアが「きゃっ」と悲鳴を上げ、セドリックの胸に顔を埋める。
完璧なシナリオ。
誰もが私を軽蔑の眼差しで見ている。
普通なら、ここで絶望し、無実を訴え、それでも牢獄へ送られる。
それが『運命』という名の強制力。
けれど。
私は扇子を閉じ、パチンと音を立てた。
(……プロットが甘いのよ、この世界の作者は)
私の右目が熱を帯びる。
視界の『文字列』にノイズが走る。
私には特異な才能があった。
ただ文字を読むだけではない。
誤字脱字を、修正する力。
現実という名の原稿(テキスト)を、書き換える権限(アクセス権)。
「殿下、よくご覧になって」
私は心の中で、赤ペンを握る。
対象は、トレイの上の小瓶。
設定記述:『猛毒アコナイトの雫』。
その文字列を、私は視線だけで捕捉する。
脳が焼き切れそうな頭痛。
鼻から生温かいものが垂れる感覚。
それでも、私は笑った。
「それは毒などではありませんわ」
第二章 赤ペンは剣よりも強し
脳内でインクの匂いが弾ける。
『猛毒アコナイトの雫』
削除(デリート)。
そして、上書き(オーバーライト)。
『最高級ブルーベリーシロップ』
記述が確定した瞬間、世界がカチリと音を立てて歪んだ。
「何を往生際の悪い……!」
セドリックが小瓶を掴み上げ、蓋を開ける。
その瞬間、広間に漂ったのは、鼻を突く毒の臭気ではなく、甘酸っぱく芳醇な果実の香りだった。
「……は?」
セドリックが固まる。
リリアが鼻をひくつかせ、思わず顔を上げる。
「いい香り……」
誰かが呟いた。
「殿下、それは私がリリア様との親睦を深めるために用意した、パンケーキ用の特製シロップですわ。お茶会にお誘いしようと思っておりましたのに」
嘘だ。
ついさっきまで、それは確かに猛毒だった。
だが今、この世界の『事実』はシロップになった。
「ば、馬鹿な! 鑑定士! 鑑定士を呼べ!」
慌てて駆け寄った宮廷魔導師が、小瓶の中身を調べる。
彼は困惑した顔で、震える声を上げた。
「……こ、これは……北の森でしか採れない、希少な完熟ブルーベリーのエキスです。毒性は一切ありません。むしろ、目に良いかと」
会場が静まり返る。
断罪の空気は、一瞬にして「勘違いした王太子」への冷ややかな視線へと変わる。
「そ、そんなはずは……! だ、だが! これだけではない!」
セドリックは焦り、次のカードを切る。
「そうだ、手紙だ! 貴様が隣国の密偵と通じている証拠の手紙が見つかっている! これを見ても言い逃れができるか!」
彼は懐から、束になった手紙を取り出し、床にぶちまけた。
汚い。
資料の扱いが雑だ。
編集者として、紙を粗末にする人間は許せない。
床に散らばる手紙。
そこに書かれているのは、『国家転覆の計画』や『王族暗殺の手順』。
観衆が息を飲む。
これこそが決定的な証拠。
私はため息をつき、こめかみを指で押さえた。
(……文字数が多いわね。修正が面倒だわ)
再び、視界の文字を睨む。
ターゲット:『反逆の密書』。
全選択(Ctrl+A)。
内容を置換(リプレイス)。
流し込むテキストは――私の記憶にある、セドリックがリリアに送った『ポエム集』。
頭痛が激しさを増す。
視界が赤く染まる。
限界が近い。
けれど、この快感には代えられない。
「殿下。それは私の手紙ではありません」
「ふん、署名がなくとも筆跡で……」
拾い上げた騎士が、手紙の一枚を読み上げようとして、絶句した。
「……おい、読め! 皆に聞かせるのだ!」
「は、はい……」
騎士は顔を真っ赤にして、震える声で読み始めた。
『ああ、僕の子猫ちゃん。君の瞳はマロングラッセのように甘く、僕の心を溶かしてしまう……』
「……は?」
セドリックの声が裏返る。
騎士は続ける。
拷問を受けているかのような苦悶の表情で。
『君と出会って、僕は初めて知ったんだ。呼吸をする意味を。君は僕の酸素、僕のミトコンドリア……』
ぶふっ、と誰かが吹き出した。
それを皮切りに、会場のあちこちから堪えきれない笑い声が漏れる。
「な、なにを読んでいる! 貸せ!」
セドリックが手紙をひったくる。
その紙面には、確かに彼が夜な夜な書き連ねていた(そして恥ずかしいので燃やしたはずの)愛のポエムが、私の筆跡で書かれていた。
「『僕の愛は暴走機関車。ブレーキなんて壊してしまったのさ』……ぷっ」
私が読み上げると、セドリックはゆでダコのようになった。
「ち、ちがう! これは! なぜ貴様の字でこんなものが!」
「存じませんわ。ですが殿下、そのような熱烈な文章、私にはとても書けません。……文才がおありなんですね」
第三章 物語(シナリオ)からの退場
勝負はついた。
毒はシロップに。
密書は恥ずかしいポエムに。
断罪イベントは、王太子の奇行と勘違い、そして文学的センス(笑)の暴露大会へと書き換わった。
リリアが青ざめた顔でセドリックから離れていく。
「ミトコンドリア……」と呟きながら、ドン引きしているのが見える。
「こ、こんな……こんなことが……」
セドリックはその場に膝をついた。
もはや彼に、王太子の威厳はない。
私は鼻から垂れた血をハンカチで拭い、静かに彼に近づいた。
「殿下。婚約破棄、喜んでお受けいたします」
「……え?」
「このような素晴らしい感性をお持ちの方の隣に立つなど、凡人の私には荷が重すぎますので」
私は優雅にカーテシー(膝礼)をした。
「それと、リリア様」
私は呆然とするヒロインに向き直る。
「そのシロップ、本当に美味しいので差し上げます。パンケーキにかけて召し上がれ。……ただし、甘すぎると胸焼けしますから、程々に」
踵を返す。
大広間の扉が開く。
背後から「待て、エララ!」と呼ぶ声が聞こえた気がしたが、私は一度も振り返らなかった。
城を出た瞬間、夜風が熱を持った頬を撫でる。
視界の端に、物語の終わりを示す『END』の文字が浮かびかけていたが、私はそれを指先で弾き飛ばした。
まだ、終わりじゃない。
私の物語は、誰かに書かれるものじゃない。
私が書くのだ。
「さて……次はどの国のプロットを直しに行こうかしら」
夜空を見上げると、星々がインクの染みのように瞬いていた。
私は懐から愛用の万年筆を取り出し、月に向かって線を引く。
未定の未来。
白紙の明日。
最高の原稿用紙が、そこに広がっていた。