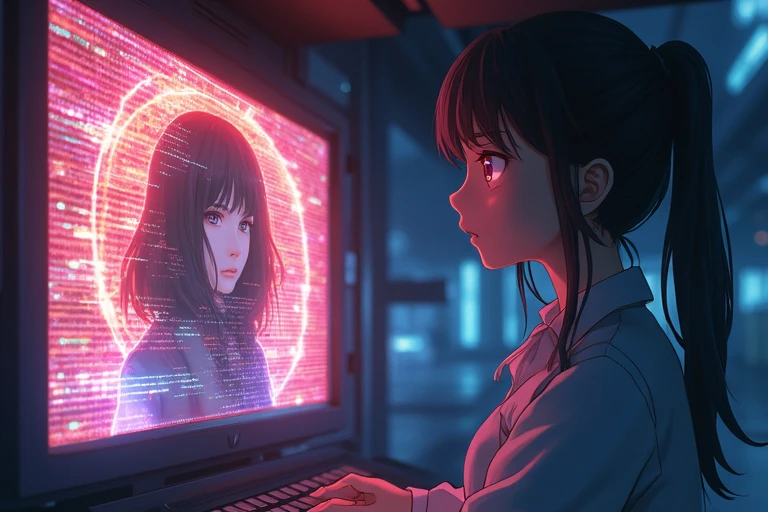英雄の墓は、雑草に飲まれるほど小さかった。
それが八十年という歳月の正体だ。
かつての栄光も、伝説も、等しく堆肥へと変わる。
雨が降っていた。
私の肌を濡らす雫は冷たいはずなのに、どこか生ぬるい。
エルフである私にとって、人間の寿命など瞬きに等しい。
そう理解していたはずなのに。
墓石の前で、私は濡れた金髪をかき上げることもせず、ただ立ち尽くしていた。
手には、錆びついた懐中時計。
彼が最後に残した、「開かずの遺品」だ。
第一章 錆びついた英雄譚
王都の裏路地にある古物商『刻(とき)の澱(おり)』。
そこが私の今の居場所だ。
店内に充満するのは、カビた紙の匂いと、埃っぽい絨毯の感触。
薄暗いランプの灯りが、陳列されたガラクタたちをぼんやりと照らしている。
カラン、コロン。
ドアベルが鳴り、湿った風が吹き込んだ。
「……いらっしゃい」
顔を上げずに声をかける。
入ってきたのは、仕立ての良いスーツを着た青年だった。
栗色の髪。意志の強そうな瞳。
一瞬、呼吸が止まるかと思った。
「店主殿。ここに、鑑定できないものはないと聞いて参りました」
青年の声は少し震えていた。
緊張しているのか、それとも雨の寒さか。
「物によるわ。……君、名前は?」
「アルフレッドです。アルフレッド・レイン」
レイン。
その姓を聞いた瞬間、私の奥底で何かが軋んだ。
「そう。英雄アルトの曾孫(ひまご)が、こんな場末の店に何の用?」
あえて突き放すように言う。
青年――アルフレッドは驚いた顔を見せたが、すぐに居住まいを正して懐から小さな包みを取り出した。
「曾祖父の遺品です。王家の魔導師たちでさえ、開けることができなかった」
布が解かれる。
現れたのは、泥と錆にまみれた銀色の懐中時計だった。
かつて私が、彼に贈ったもの。
(まだ、持っていたのね)
胸の奥がチクリと痛む。
私は手袋を外し、その冷たい金属に指先を触れさせた。
瞬間。
指先から流れ込んでくる「記憶(残留思念)」。
『ニナ、頼む。置いていかないでくれ』
『俺は怖いんだ。死ぬのが怖い』
『英雄なんて、なりたくなかった』
視界が歪む。
魔王城の決戦前夜。
焚き火のそばで震えていた彼の体温が、指先を通じて鮮明に蘇る。
汗の匂い。
薪が爆ぜる音。
そして、私にすがりついてきた彼のか細い腕。
「……ッ」
私は反射的に手を引っ込めた。
「店主殿?」
「……なんでもない。ただのガラクタよ。中身なんて、歯車が錆びついて動かないに決まってる」
嘘をついた。
この時計には、強力な封印魔法が施されている。
それも、私にしか解けない術式で。
「お願いします! 曾祖父は死の間際、これだけは必ず『ニナ』というエルフに渡せと言い残したそうです。貴女が、そのニナさんではありませんか?」
八十年。
人間にとっては三世代。
私にとっては、つい昨日のこと。
彼の必死な瞳が、かつてのアルトと重なる。
あの泣き虫で、弱虫で、それなのに誰よりも優しかった英雄と。
私は溜息をつき、再び時計を手に取った。
「……開けるわ。でも、後悔しないでね」
第二章 嘘つきの魔法使い
魔力を流し込む。
私のマナに反応し、錆びついていた銀が淡い光を帯び始めた。
カチ、リ。
小さな音がして、裏蓋が弾かれる。
中に入っていたのは、宝石でも、世界を揺るがす魔道具でもなかった。
小さく折り畳まれた、一枚の羊皮紙。
そして、枯れた白い花びら。
「これは……」
アルフレッドが身を乗り出す。
私は羊皮紙を開いた。
そこにあったのは、乱雑な走り書き。
『ニナへ。君がこれを読んでいる頃、俺はもう土の中だろう。君にとっての数日が、俺の一生だったことが、今でも信じられない』
文字が滲んでいる。
『俺は嘘をついた。魔王を倒した後、王女と結婚したのは、国のためなんかじゃない。君を、人間たちの嫉妬や政治から遠ざけるためだった』
喉が熱くなる。
当時の私は、彼に裏切られたと思っていた。
平和になった世界で、長命種である私は「異物」でしかなかったから。
彼が私をパーティから追放し、王女と結ばれた時、私は何も言わずに姿を消した。
『君は歳を取らない。俺は老いていく。隣に並んで歩くことが、残酷なほど怖かった。君の美しい顔に、俺の老いが影を落とすのが耐えられなかった』
「馬鹿……」
声が漏れた。
視界が滲んで、文字が読めない。
『この花を覚えているか? 最初の冒険で、君が「綺麗だ」と言って笑った花だ。俺は毎年、この花が咲くたびに君を思い出していた』
押し花は、八十年という時を経てもなお、微かに魔力を帯びていた。
彼が、拙い魔法で必死に保存していたのだ。
魔法の才能なんて、からっきし無かったくせに。
『愛している、なんて言わない。それは君を縛る呪いになるから。ただ、俺の人生は、君と旅をしたあの三年間のためにあった。それだけは伝えたかった』
手紙の最後には、震える文字でこう記されていた。
『ありがとう。俺の、永遠の人』
店の中に、静寂が満ちる。
雨音だけが、遠くで響いていた。
私は知っていた。
彼が臆病だったことを。
でも、その臆病さが、私を守るための強さだったことを、私は今の今まで知らなかった。
「……曾祖父は、幸せだったのでしょうか」
アルフレッドがぽつりと呟く。
私は羊皮紙を強く握りしめた。
紙の皺(しわ)の一つ一つに、彼が生きた時間の重みが刻まれている。
「ええ、そうね」
私は涙を拭わずに微笑んだ。
「彼は、最高の嘘つきだったもの。最期まで、自分の人生を演じきったのよ」
第三章 雨上がりの刻音(ときおと)
アルフレッドが帰った後、私は店の窓を開けた。
雨は上がり、雲の切れ間から夕日が差し込んでいる。
濡れた石畳が、黄金色に輝いていた。
手元の懐中時計を見る。
止まっていたはずの秒針が、再び動き出していた。
チク、タク、チク、タク。
それはまるで、彼に置いていかれた私の時間が、ようやく動き出した音のように聞こえた。
「……遅いのよ、アルト」
私は時計を胸に抱いた。
不老長寿。
それは、多くの別れを見送る呪い。
けれど、記憶だけは風化しない。
八十年。
たった八十年、彼と離れていただけ。
これからの数百年、数千年。
私はこの痛みを抱えて生きていく。
でも、それはもう「虚無」ではない。
彼が命を削って守ろうとした、この平和な世界と、彼が愛してくれた私自身。
「行ってきます」
誰に言うでもなく、私は呟いた。
店の奥から、旅の支度が入った鞄を取り出す。
もう一度、世界を見て回ろう。
彼が守り、彼が見ることのできなかった「その後」の景色を。
そしていつか、遠い未来でまた彼に会えたら、今度こそ伝えてあげるのだ。
『貴方のシワだらけの顔も、きっと悪くなかったわよ』と。
懐中時計の秒針は、正確なリズムで時を刻み続ける。
私の心臓と、同じ速さで。